複数辞典一括検索+![]()
![]()
え-かい  カイ 【懐海】🔗⭐🔉
カイ 【懐海】🔗⭐🔉
え-かい  カイ 【懐海】
⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海
カイ 【懐海】
⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海
 カイ 【懐海】
⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海
カイ 【懐海】
⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海
え-がい  ガヒ [1] 【絵貝】🔗⭐🔉
ガヒ [1] 【絵貝】🔗⭐🔉
え-がい  ガヒ [1] 【絵貝】
貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。
ガヒ [1] 【絵貝】
貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。
 ガヒ [1] 【絵貝】
貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。
ガヒ [1] 【絵貝】
貝合わせの一。貝の両片に分けて書いた名所などの絵と,それに関係ある和歌とを合わせて取る遊戯。天暦(947-957)の頃行われた。
え-がいき  ― [2] 【絵海気】🔗⭐🔉
― [2] 【絵海気】🔗⭐🔉
え-がいき  ― [2] 【絵海気】
文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。
→海気
― [2] 【絵海気】
文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。
→海気
 ― [2] 【絵海気】
文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。
→海気
― [2] 【絵海気】
文様を染めた糸を経(タテ)糸に用いて織った海気(カイキ)。
→海気
え-がお  ガホ [1] 【笑顔】🔗⭐🔉
ガホ [1] 【笑顔】🔗⭐🔉
え-がお  ガホ [1] 【笑顔】
にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」
ガホ [1] 【笑顔】
にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」
 ガホ [1] 【笑顔】
にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」
ガホ [1] 【笑顔】
にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」
え-かがみ [2] 【柄鏡】🔗⭐🔉
え-かがみ [2] 【柄鏡】
(紐鏡(ヒモカガミ)に対して)柄のついた鏡。中国宋代に盛行し,日本では室町以後に用いられるようになった。
柄鏡
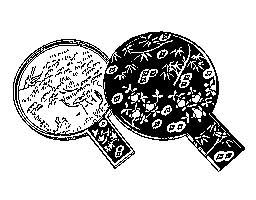 [図]
[図]
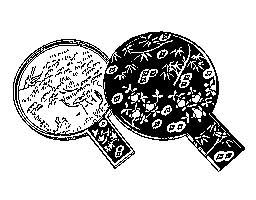 [図]
[図]
え-かがみ  ― [2] 【絵鑑】🔗⭐🔉
― [2] 【絵鑑】🔗⭐🔉
え-かがみ  ― [2] 【絵鑑】
鑑定用の古画帖。
― [2] 【絵鑑】
鑑定用の古画帖。
 ― [2] 【絵鑑】
鑑定用の古画帖。
― [2] 【絵鑑】
鑑定用の古画帖。
え-かき  ― [3] 【絵書き・絵描】🔗⭐🔉
― [3] 【絵書き・絵描】🔗⭐🔉
え-かき  ― [3] 【絵書き・絵描】
絵を描くことを職業にしている人。画家。
― [3] 【絵書き・絵描】
絵を描くことを職業にしている人。画家。
 ― [3] 【絵書き・絵描】
絵を描くことを職業にしている人。画家。
― [3] 【絵書き・絵描】
絵を描くことを職業にしている人。画家。
えかき-うた  ― [3] 【絵書き歌】🔗⭐🔉
― [3] 【絵書き歌】🔗⭐🔉
えかき-うた  ― [3] 【絵書き歌】
描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。
― [3] 【絵書き歌】
描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。
 ― [3] 【絵書き歌】
描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。
― [3] 【絵書き歌】
描く線や形を説明した歌詞を歌いながら一定の絵を完成する遊戯。また,その歌。
えかき-べ  ― [3] 【画部】🔗⭐🔉
― [3] 【画部】🔗⭐🔉
えかき-べ  ― [3] 【画部】
律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。
― [3] 【画部】
律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。
 ― [3] 【画部】
律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。
― [3] 【画部】
律令制で,中務省の画工司(エダクミノツカサ)に属し,絵画のことにたずさわった部。また,その人。
えがき-だ・す  ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
えがき-だ・す  ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])
(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」
(2)物事のありさまを想像する。
(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」
[可能] えがきだせる
ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])
(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」
(2)物事のありさまを想像する。
(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」
[可能] えがきだせる
 ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])
(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」
(2)物事のありさまを想像する。
(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」
[可能] えがきだせる
ガキ― [4] 【描き出す】 (動サ五[四])
(1)物の形やありさまを絵画や言葉で表現する。「下町の情緒を―・す」
(2)物事のありさまを想像する。
(3)物の動いた跡がある形を表す。「水面に波紋が―・された」
[可能] えがきだせる
えかく  カク 【慧鶴】🔗⭐🔉
カク 【慧鶴】🔗⭐🔉
えかく  カク 【慧鶴】
⇒白隠(ハクイン)
カク 【慧鶴】
⇒白隠(ハクイン)
 カク 【慧鶴】
⇒白隠(ハクイン)
カク 【慧鶴】
⇒白隠(ハクイン)
え-がく [1] 【依学】🔗⭐🔉
え-がく [1] 【依学】
仏教で,教義を信仰のためでなく学問として学ぶこと。
えがく-の-しゅう [1]-[1] 【依学の宗】🔗⭐🔉
えがく-の-しゅう [1]-[1] 【依学の宗】
依学を旨とする宗。倶舎(クシヤ)宗・成実(ジヨウジツ)宗など。寓宗。
え-が・く  ― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])🔗⭐🔉
― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])🔗⭐🔉
え-が・く  ― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])
〔「絵書く」の意〕
(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」
(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」
(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」
(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」
[可能] えがける
― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])
〔「絵書く」の意〕
(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」
(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」
(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」
(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」
[可能] えがける
 ― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])
〔「絵書く」の意〕
(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」
(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」
(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」
(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」
[可能] えがける
― [2] 【描く・画く】 (動カ五[四])
〔「絵書く」の意〕
(1)物の形を絵や図にかき表す。絵や図をかく。「水彩で花を―・く」
(2)物の形状や物事のありさまを,文章や音楽などで表現する。「若い教師の生活を―・いた作品」
(3)(心の中に)思い浮かべる。想像してみる。「理想を―・く」「夢に―・く」
(4)物が動いた跡がある形を表す。「弧を―・く」「トンビが輪を―・いて飛ぶ」
[可能] えがける
大辞林 ページ 139660。