複数辞典一括検索+![]()
![]()
おおあみしらさと オホアミ― 【大網白里】🔗⭐🔉
おおあみしらさと オホアミ― 【大網白里】
千葉県中東部,山武郡の町。九十九里浜の中部に位置する交通の要衝。
おお-あめ オホ― [3] 【大雨】🔗⭐🔉
おお-あめ オホ― [3] 【大雨】
ある時間はげしく,多量に降る雨。
⇔小雨(コサメ)
「―注意報」
おお-あや オホ― 【大綾】🔗⭐🔉
おお-あや オホ― 【大綾】
大きな模様の綾織り。「色なつかしき紫の―の衣(キヌ)/万葉 3791」
おおあらい オホアラヒ 【大洗】🔗⭐🔉
おおあらい オホアラヒ 【大洗】
茨城県東部,鹿島灘に臨む町。古くからの漁港。海水浴場がある。民謡「磯節」で名高い。
おお-あらき オホ― 【大荒城・大殯】🔗⭐🔉
おお-あらき オホ― 【大荒城・大殯】
「あらき(荒城)」を敬っていう語。「―の時にはあらねど雲隠ります/万葉 441」
おおあらき-の-もり オホアラキ― 【大荒木の森】🔗⭐🔉
おおあらき-の-もり オホアラキ― 【大荒木の森】
京都市伏見区淀本町,与杼(ヨド)神社付近の森という。((歌枕))「―の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし/古今(雑上)」
〔もと,大殯(オオアラキ)を営む浮田(ウキタ)の森をいったが,平安以降,場所不詳のまま山城国の歌枕とされた〕
おお-あらめ オホ― [3] 【大荒目】🔗⭐🔉
おお-あらめ オホ― [3] 【大荒目】
鎧(ヨロイ)の縅(オドシ)の一。幅の広い札(サネ)を用い,太い糸で糸目を荒くつづるもの。また,その鎧。
おお-あり オホ― [0] 【大有り】🔗⭐🔉
おお-あり オホ― [0] 【大有り】
(1)非常にたくさんあること。
(2)「ある」ということを強めた言い方。もちろんあること。言うまでもなくあること。「不満は―だよ」
おお-ありくい オホアリクヒ [3][4] 【大蟻食】🔗⭐🔉
おお-ありくい オホアリクヒ [3][4] 【大蟻食】
アリクイの一種。体長は1.2メートル内外で,70センチメートルあまりの尾をもつ。全身黒灰色の長毛におおわれ,肩に広い白帯がある。歯は全くなく,長い舌でシロアリや甲虫の幼虫などを食べる。中南米の森林・草原にすむ。
大蟻食
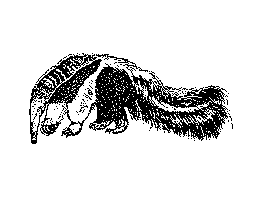 [図]
[図]
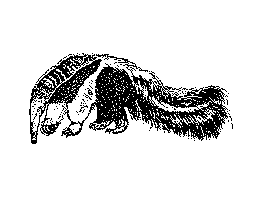 [図]
[図]
おお-あれ オホ― [0] 【大荒れ】 (名・形動)🔗⭐🔉
おお-あれ オホ― [0] 【大荒れ】 (名・形動)
(1)天気が悪くて,風・雨・波などがたいへん激しい・こと(さま)。「―の海」
(2)人の感情や動作が非常に乱暴になること。「酔って―に荒れる」
(3)試合・相場などで,予想しない結果が続くこと。混乱すること。「初日の土俵は―だった」
大辞林 ページ 139991。