複数辞典一括検索+![]()
![]()
――も畏(カシコ)き🔗⭐🔉
――も畏(カシコ)き
口に出して言うのもおそれ多い。「―君(=天皇)の御名を申すは/大鏡(序)」
かげまさ 【景正】🔗⭐🔉
かげまさ 【景正】
⇒加藤景正(カトウカゲマサ)
かげ-まち 【影待ち】🔗⭐🔉
かげ-まち 【影待ち】
「日待ち」に同じ。「五月十四日の夜はさだまつて―あそばしける/浮世草子・五人女 3」
かげ-まつり [3] 【陰祭(り)】🔗⭐🔉
かげ-まつり [3] 【陰祭(り)】
(1)例祭(本祭り)が隔年に行われる場合,その例祭のない年に行われる簡略な祭り。例えば神田祭など。[季]夏。
(2)歌舞伎で,曾我(ソガ)狂言を上演した興行の千秋楽のあと,楽屋で行う祭り。
→曾我祭
かけ-まと 【賭け的】🔗⭐🔉
かけ-まと 【賭け的】
物をかけて的を射ること。「かぶき踊,―,武士・民も入り乱れて/浮世草子・新可笑記 2」
かけ-まもり [3] 【懸(け)守り】🔗⭐🔉
かけ-まもり [3] 【懸(け)守り】
胸にかける筒形の守り袋。平安時代以降主に婦人が用いた。
懸け守り
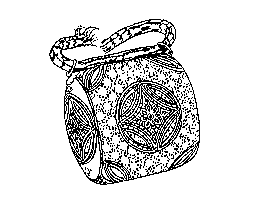 [図]
[図]
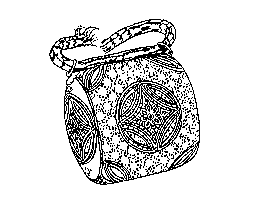 [図]
[図]
かけ-まわ・る ―マハル [0][4] 【駆(け)回る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉
かけ-まわ・る ―マハル [0][4] 【駆(け)回る】 (動ラ五[四])
(1)あちこち走りまわる。「子犬が庭を―・る」
(2)あちこち行き歩いて努力する。奔走する。「金策に一日中―・る」
[可能] かけまわれる
かげ-み 【影身】🔗⭐🔉
かげ-み 【影身】
影が身を離れることのないように,常に離れないこと。「―の如く馴れ馴れしに/謡曲・初雪」
――に添・う🔗⭐🔉
――に添・う
いつもその人の身辺を離れないでいる。
かげ-みせ 【陰見世・陰店】🔗⭐🔉
かげ-みせ 【陰見世・陰店】
遊女が往来に面した場所でなく,家の奥の方に並ぶこと。近世,宿駅の遊女屋など,公許でない店に多かった。うちみせ。
⇔張り見世(ミセ)
かけ-みち 【懸け道】🔗⭐🔉
かけ-みち 【懸け道】
「懸け路(ジ){(1)}」に同じ。「岩の―を伝ひつつ/平家(灌頂)」
がけ-みち [0] 【崖道・崖路】🔗⭐🔉
がけ-みち [0] 【崖道・崖路】
崖のふちを通る道。がけじ。
大辞林 ページ 141005。