複数辞典一括検索+![]()
![]()
こさく-まい [0] 【小作米】🔗⭐🔉
こさく-まい [0] 【小作米】
小作人が小作料として地主に納める米。
こさく-りょう ―レウ [3] 【小作料】🔗⭐🔉
こさく-りょう ―レウ [3] 【小作料】
小作地の使用料。古くは物納であったが,農地法により金納などの制約が定められている。
こ-さく [0] 【古作】🔗⭐🔉
こ-さく [0] 【古作】
古い時代の制作。古人の作品。
こ-さく [0] 【雇作】🔗⭐🔉
こ-さく [0] 【雇作】
やとわれて作業をすること。また,その人。
こ-ざくら [2] 【小桜】🔗⭐🔉
こ-ざくら [2] 【小桜】
(1)花の小さな桜。
(2)小さな桜の花の紋様。多く染め革に用いられる。
こざくら-おどし ―ヲドシ [5] 【小桜縅】🔗⭐🔉
こざくら-おどし ―ヲドシ [5] 【小桜縅】
鎧(ヨロイ)の縅の一。小桜革でしんを包んだ緒で縅したもの。桜縅。
小桜縅
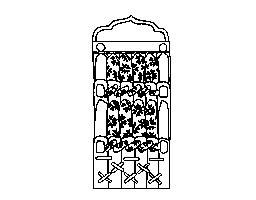 [図]
[図]
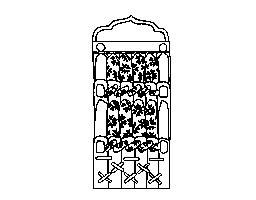 [図]
[図]
こざくら-がわ ―ガハ [4] 【小桜革】🔗⭐🔉
こざくら-がわ ―ガハ [4] 【小桜革】
染め革の一。藍(アイ)染めの地に,白で小さく桜花の模様を染め出したものが多い。多く鎧(ヨロイ)の縅に用いる。
ごさくらまち-てんのう ―テンワウ 【後桜町天皇】🔗⭐🔉
ごさくらまち-てんのう ―テンワウ 【後桜町天皇】
(1740-1813) 第一一七代天皇(在位 1762-1770)。名は智子(トシコ)。桜町天皇の第二皇女。和歌をよくし,一千数百首の御製(ギヨセイ)がある。
こ-ざけ 【醴】🔗⭐🔉
こ-ざけ 【醴】
〔「こさけ」とも。濃い酒の意〕
昔,米・麹(コウジ)・酒をまぜ,一夜で醸造した酒。現在の甘酒のようなもの。
こざ-こざ [1]🔗⭐🔉
こざ-こざ [1]
■一■ (副)スル
こまごまとしたものが入り交じっているさま。「―した切れを入れた行李/発展(泡鳴)」
■二■ (名)
こまごまと入り交じっていること。細かいこと。「米屋が弐両弐分,此外に―が惣〆で三両/滑稽本・一盃綺言」
こ-ざさ [1][0] 【小笹】🔗⭐🔉
こ-ざさ [1][0] 【小笹】
背の低い小さい笹。おざさ。
こ-さじ [0] 【小匙】🔗⭐🔉
こ-さじ [0] 【小匙】
(1)茶匙など小形のさじ。
(2)調理用の計量スプーン。容量は普通5ミリリットル。
こ-ざしき [2] 【小座敷】🔗⭐🔉
こ-ざしき [2] 【小座敷】
(1)小さい座敷。小座。
(2)母屋(オモヤ)につづけて外へ建て出した部屋。放ち出(イ)で。
(3)茶道で,四畳半以下の座敷の呼び名。また,広間に対する草庵茶室の称。小間(コマ)。
大辞林 ページ 144200。