複数辞典一括検索+![]()
![]()
すみよし-づくり [5] 【住吉造り】🔗⭐🔉
すみよし-づくり [5] 【住吉造り】
神社本殿様式の一。屋根は反りのない切妻造りで,棟に千木と堅魚木(カツオギ)を置く。妻を正面とする前後に細長い建築で,内部は内陣と外陣の二室に分かれている。大阪住吉大社本殿はこの代表例。
住吉造り
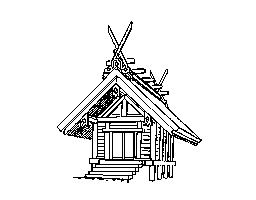 [図]
[図]
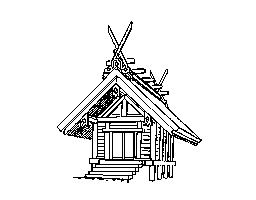 [図]
[図]
すみよし-どりい ― [5] 【住吉鳥居】🔗⭐🔉
[5] 【住吉鳥居】🔗⭐🔉
すみよし-どりい ― [5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
[5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
 [5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
[5] 【住吉鳥居】
住吉大社などに用いた鳥居で,中山鳥居の柱が四角となったもの。
すみよし-にんぎょう ―ギヤウ [5] 【住吉人形】🔗⭐🔉
すみよし-にんぎょう ―ギヤウ [5] 【住吉人形】
住吉でつくった土製の人形。
すみよし-の-かみ 【住吉の神】🔗⭐🔉
すみよし-の-かみ 【住吉の神】
⇒住吉神(スミノエノカミ)
すみよし 【住吉】🔗⭐🔉
すみよし 【住吉】
姓氏の一。
すみよし-ぐけい 【住吉具慶】🔗⭐🔉
すみよし-ぐけい 【住吉具慶】
(1631-1705) 江戸前期の大和絵画家。如慶の長男。幕府の奥絵師となり大和絵を江戸に広め,住吉派隆盛の礎を築いた。
すみよし-じょけい 【住吉如慶】🔗⭐🔉
すみよし-じょけい 【住吉如慶】
(1599-1670) 江戸前期の大和絵画家。土佐光吉の弟子。後水尾天皇の勅により住吉絵所を再興,土佐派から分かれて住吉派を興した。
すみよし-は 【住吉派】🔗⭐🔉
すみよし-は 【住吉派】
大和絵の一派。如慶が土佐派から分かれて一派をなしたもの。京の土佐家に対し,江戸での大和絵の中心をなし,狩野家と並んで幕末まで幕府の御用絵師を務めた。
すみよしものがたり 【住吉物語】🔗⭐🔉
すみよしものがたり 【住吉物語】
物語。二巻。作者・成立年代とも未詳。平安前期の同名の物語を改作したものらしく,異本がきわめて多い。継子いじめ譚(タン)に長谷観音の利生(リシヨウ)説話を交える。
す-みるちゃ 【素海松茶】🔗⭐🔉
す-みるちゃ 【素海松茶】
江戸時代の染め色の名。暗緑褐色。みるちゃ。「―の袖口かけし/浮世草子・禁短気」
大辞林 ページ 147442。