複数辞典一括検索+![]()
![]()
つき-ゆき-はな [2][2]-[2]-[2] 【月雪花】🔗⭐🔉
つき-ゆき-はな [2][2]-[2]-[2] 【月雪花】
⇒雪月花(セツゲツカ)
つき-ゆび [0] 【突(き)指】 (名)スル🔗⭐🔉
つき-ゆび [0] 【突(き)指】 (名)スル
指先に強く物が当たって,指の関節を痛めること。
つき-ゆみ 【槻弓】🔗⭐🔉
つき-ゆみ 【槻弓】
槻の木(ケヤキ)で作った丸木の弓。つくゆみ。「梓弓ま弓―年をへて/伊勢 24」
つき-よ [2] 【月夜】🔗⭐🔉
つき-よ [2] 【月夜】
〔古くは「つくよ」〕
月の照る夜。月の明るい夜。[季]秋。
――に釜(カマ)を抜かれる🔗⭐🔉
――に釜(カマ)を抜かれる
月の明るい夜に釜を盗まれる。油断をして失敗することのたとえ。月夜に釜。
――に提灯(チヨウチン)🔗⭐🔉
――に提灯(チヨウチン)
無益なこと,不必要なことのたとえ。
――の蟹(カニ)🔗⭐🔉
――の蟹(カニ)
〔月夜には蟹は餌をあさらないので肉がないということから〕
やせて肉のない蟹。転じて,中身のないことのたとえ。
つきよ-がらす [4] 【月夜烏】🔗⭐🔉
つきよ-がらす [4] 【月夜烏】
月の明るい晩に浮かれて鳴き出す烏。「爰は山かげ,森の下,―はいつもなく/狂言・花子」
つきよ-たけ [3] 【月夜茸】🔗⭐🔉
つきよ-たけ [3] 【月夜茸】
担子菌類ハラタケ目のきのこ。傘は半円形で,長径10〜20センチメートル。表面は紫褐色で,ひだは白色。シイタケ・ハラタケなどに似るが毒性が強い。ひだは暗所で青白色の光を放つ。秋,ブナなどの倒木に群生する。
月夜茸
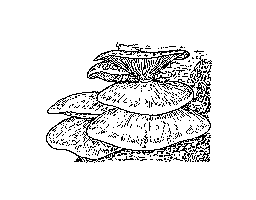 [図]
[図]
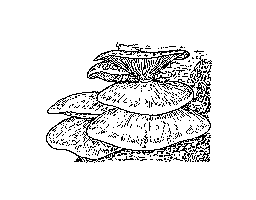 [図]
[図]
つき-よみ 【月夜見・月読み】🔗⭐🔉
つき-よみ 【月夜見・月読み】
⇒つくよみ(月夜見)
つきよみ-の-みや 【月夜見宮】🔗⭐🔉
つきよみ-の-みや 【月夜見宮】
伊勢市宮後(ミヤジリ)町にある,豊受大神宮の別宮。祭神は月夜見尊並びにその荒御魂(アラミタマ)。
つきよみ-の-みや 【月読宮】🔗⭐🔉
つきよみ-の-みや 【月読宮】
伊勢市北中村にある,皇大神宮の別宮。祭神は月読尊。
つぎ-ラウ [3] 【継ぎ―】🔗⭐🔉
つぎ-ラウ [3] 【継ぎ―】
継いで延長できるような構造になっているキセルのラウ。
→ラウ
つ・きる [2] 【尽きる】 (動カ上一)[文]カ上二 つ・く🔗⭐🔉
つ・きる [2] 【尽きる】 (動カ上一)[文]カ上二 つ・く
(1)次第に減っていって,全くなくなる。「体力が―・きる」「食糧が―・きる」
(2)終わる。はてる。「話は―・きない」「道が―・きる」
(3)(「…に尽きる」の形で)限度にまで達し,他には何も残らない。きわまる。「幸運の一語に―・きる」「楽しみはここに―・きる」「今日の試楽は,青海波に事皆―・きぬ/源氏(紅葉賀)」
〔「尽くす」に対する自動詞〕
[慣用] 愛想が―・刀折れ矢―・冥加に―・冥利に―
大辞林 ページ 149683。