複数辞典一括検索+![]()
![]()
どう-だい [0] 【同大】🔗⭐🔉
どう-だい [0] 【同大】
大きさが同じであること。「同型―」
とうだい-じ 【東大寺】🔗⭐🔉
とうだい-じ 【東大寺】
奈良市雑司町にある華厳宗の大本山。金光明四天王護国之寺・総国分寺・大華厳寺ともいう。南都七大寺の一。聖武天皇の発願により創建。行基を大勧進とし,良弁を開基とする。本尊は盧遮那仏(ルシヤナブツ)(いわゆる奈良の大仏)。752年に大仏開眼供養。唐僧鑑真(ガンジン)により,戒壇院を設立,三戒壇の一として奈良・平安時代を通じて興福寺と並ぶ大寺院となり,広大な荘園を有して栄えたが,中世以後衰えた。江戸時代再建の大仏殿(世界最大の木造建築物),創建以来の遺構である三月堂・正倉院のほか,南大門・鐘楼などがある。
とうだいじ-けんもつちょう ―チヤウ 【東大寺献物帳】🔗⭐🔉
とうだいじ-けんもつちょう ―チヤウ 【東大寺献物帳】
奈良時代に朝廷から東大寺に献納された宝物真蹟の目録。「国家珍宝帳」「種々薬帳」「屏風花帳」「大小王帳」「藤原公真蹟屏風帳」の五巻。正倉院に現存する。
とうだいじ-さんろんしゅうてん 【東大寺三論宗点】🔗⭐🔉
とうだいじ-さんろんしゅうてん 【東大寺三論宗点】
ヲコト点の一種。三論宗・華厳宗・真言宗の僧の間で用いられた訓点。左下・左中・左上の点を順に読むと「てには」となるのでテニハ点とも呼ばれた。東大寺点。三論宗点。
とうだいじ-ふじゅもんこう ―カウ 【東大寺諷誦文稿】🔗⭐🔉
とうだいじ-ふじゅもんこう ―カウ 【東大寺諷誦文稿】
片仮名まじり文で書かれた諷誦文の草案集。九世紀前半頃の成立。著者不明。
とうだいじ-ようろく ―エウ― 【東大寺要録】🔗⭐🔉
とうだいじ-ようろく ―エウ― 【東大寺要録】
東大寺およびその諸院・所領・末寺などに関する史料集。一二世紀初期の成立。一〇巻。観厳編。
とうだいわじょうとうせいでん タウダイワジヤウ― 【唐大和上東征伝】🔗⭐🔉
とうだいわじょうとうせいでん タウダイワジヤウ― 【唐大和上東征伝】
一巻。779年,淡海三船著。苦難の末に果たされた日本渡来の経緯を中心に,鑑真(ガンジン)の伝記を記したもの。
とう-たく 【董卓】🔗⭐🔉
とう-たく 【董卓】
(?-192) 中国,後漢末の群雄の一人。強力な軍隊を背景に少帝を廃して献帝を擁立し,一時政権を掌握したが,部下の呂布に殺された。
どう-たく [0] 【銅鐸】🔗⭐🔉
どう-たく [0] 【銅鐸】
弥生時代の青銅器。釣り鐘を扁平にした形の身(ミ)と,その両側の帯状の鰭(ヒレ),頭部の半円形の鈕(チユウ)からなる。高さは10〜140センチメートル。両面に各種の文様,原始絵画を施す。祭器として用いたと推定され,近畿地方を中心に分布。
銅鐸
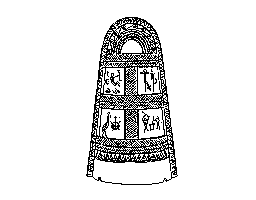 [図]
[図]
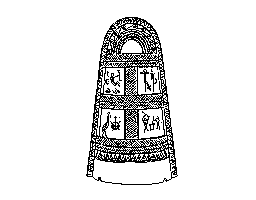 [図]
[図]
大辞林 ページ 150447。