複数辞典一括検索+![]()
![]()
ふしなわめ-おどし ―ナハメヲドシ [6] 【伏縄目縅】🔗⭐🔉
ふしなわめ-おどし ―ナハメヲドシ [6] 【伏縄目縅】
鎧(ヨロイ)の縅の一。白・浅葱(アサギ)・紺で斜めの (ダン)に染めた革緒で縅したもの。縄を並べたように見えるのでいう。
伏縄目縅
(ダン)に染めた革緒で縅したもの。縄を並べたように見えるのでいう。
伏縄目縅
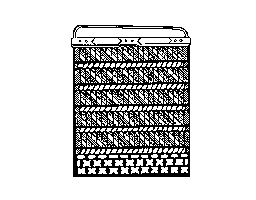 [図]
[図]
 (ダン)に染めた革緒で縅したもの。縄を並べたように見えるのでいう。
伏縄目縅
(ダン)に染めた革緒で縅したもの。縄を並べたように見えるのでいう。
伏縄目縅
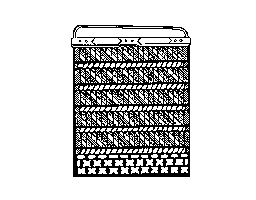 [図]
[図]
ふじ-なんど フヂ― [3] 【藤納戸】🔗⭐🔉
ふじ-なんど フヂ― [3] 【藤納戸】
藤色を帯びた納戸色。
ふじにたつかげ 【富士に立つ影】🔗⭐🔉
ふじにたつかげ 【富士に立つ影】
小説。白井喬二作。1924(大正13)〜27年(昭和2)「報知新聞」連載。富士の裾野の築城論議に始まる,熊木家と佐藤家の三代70年にわたる対立と和解を描く。
ふじ-ぬの フヂ― [0] 【藤布】🔗⭐🔉
ふじ-ぬの フヂ― [0] 【藤布】
藤蔓(フジヅル)の繊維で織った布。
ふじの フヂノ 【藤野】🔗⭐🔉
ふじの フヂノ 【藤野】
神奈川県北西部,津久井郡の町。中心の吉野は甲州街道の宿場町。相模湖・陣馬山がある。
ふし-の-き [3] 【五倍子の木】🔗⭐🔉
ふし-の-き [3] 【五倍子の木】
ヌルデの別名。
ふじのき-こふん フヂノキ― 【藤 木古墳】🔗⭐🔉
木古墳】🔗⭐🔉
ふじのき-こふん フヂノキ― 【藤 木古墳】
奈良県生駒郡斑鳩(イカルガ)町にある円墳。内部は横穴式石室で,巨石を使って築かれており,六世紀後半の築造と推定される。1985年(昭和60)には石室内から金銅製の鞍金具などの馬具類と家形石棺,88年には石棺内から金銅製の冠や沓,金・銀・金銅製の大刀などが発見された。
木古墳】
奈良県生駒郡斑鳩(イカルガ)町にある円墳。内部は横穴式石室で,巨石を使って築かれており,六世紀後半の築造と推定される。1985年(昭和60)には石室内から金銅製の鞍金具などの馬具類と家形石棺,88年には石棺内から金銅製の冠や沓,金・銀・金銅製の大刀などが発見された。
 木古墳】
奈良県生駒郡斑鳩(イカルガ)町にある円墳。内部は横穴式石室で,巨石を使って築かれており,六世紀後半の築造と推定される。1985年(昭和60)には石室内から金銅製の鞍金具などの馬具類と家形石棺,88年には石棺内から金銅製の冠や沓,金・銀・金銅製の大刀などが発見された。
木古墳】
奈良県生駒郡斑鳩(イカルガ)町にある円墳。内部は横穴式石室で,巨石を使って築かれており,六世紀後半の築造と推定される。1985年(昭和60)には石室内から金銅製の鞍金具などの馬具類と家形石棺,88年には石棺内から金銅製の冠や沓,金・銀・金銅製の大刀などが発見された。
ふし-の-こ [3] 【五倍子の粉】🔗⭐🔉
ふし-の-こ [3] 【五倍子の粉】
五倍子(フシ)を乾燥させて粉末にしたもの。
ふし-の-ま 【節の間】🔗⭐🔉
ふし-の-ま 【節の間】
〔節と節との間の意から〕
ほんのわずかな間。「―も惜しき命を/万葉 4211」
ふじ-の-まきがり 【富士の巻狩り】🔗⭐🔉
ふじ-の-まきがり 【富士の巻狩り】
1193年5月,源頼朝が富士の裾野で催した大規模な狩猟。この時,曾我兄弟の仇討ちが行われたので名高い。
ふじのみや 【富士宮】🔗⭐🔉
ふじのみや 【富士宮】
静岡県中東部,富士山南西麓にある市。浅間(センゲン)神社の門前町,富士山の表登山口として発展。製紙・フィルム・食品工業が盛ん。
大辞林 ページ 153472。