複数辞典一括検索+![]()
![]()
のろ【祝女】🔗⭐🔉
のろ [1] 【祝女】
沖縄で,村落の神事をつかさどる世襲の女神職。琉球王国時代には王府から辞令を受け,村の神女である根神(ネガミ)を従えて最高神女聞得大君(キコエオオギミ)に属し,役地が与えられていた。
のろ【鈍】🔗⭐🔉
のろ [1] 【鈍】 (名・形動)
動作や頭のはたらきなどがおそい・こと(さま)。そのような人。のろま。「此女房に使はれるは中々―では及付かぬ/いさなとり(露伴)」
のろ【 ・麕・
・麕・ 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
のろ [1] 【 ・麕・
・麕・ 】
シカ科の一種。肩高約75センチメートル。雄は長さ約20センチメートルの三本に枝分かれした角をもつ。夏毛は赤黄色,冬毛は灰褐色。ユーラシア大陸に分布。ノロジカ。
】
シカ科の一種。肩高約75センチメートル。雄は長さ約20センチメートルの三本に枝分かれした角をもつ。夏毛は赤黄色,冬毛は灰褐色。ユーラシア大陸に分布。ノロジカ。

 " src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_183220_1824_256_200.bmp" />
[図]
" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_183220_1824_256_200.bmp" />
[図]
 ・麕・
・麕・ 】
シカ科の一種。肩高約75センチメートル。雄は長さ約20センチメートルの三本に枝分かれした角をもつ。夏毛は赤黄色,冬毛は灰褐色。ユーラシア大陸に分布。ノロジカ。
】
シカ科の一種。肩高約75センチメートル。雄は長さ約20センチメートルの三本に枝分かれした角をもつ。夏毛は赤黄色,冬毛は灰褐色。ユーラシア大陸に分布。ノロジカ。

 " src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_183220_1824_256_200.bmp" />
[図]
" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_183220_1824_256_200.bmp" />
[図]
のろ【野呂】🔗⭐🔉
のろ 【野呂】
姓氏の一。
のろ-えいたろう【野呂栄太郎】🔗⭐🔉
のろ-えいたろう ―エイタラウ 【野呂栄太郎】
(1900-1934) 経済学者。北海道生まれ。慶大在学中から社会運動に参加。「日本資本主義発達史講座」の企画・編集者の一人として講座派を主導。のち,共産党を地下から指導,検挙されて警察署をたらい回しの末,死去。著「日本資本主義発達史」
のろ-かいせき【野呂介石】🔗⭐🔉
のろ-かいせき 【野呂介石】
(1747-1828) 江戸後期の南画家。紀伊の人。池大雅の門。紀伊藩御用絵師。
のろ-げんじょう【野呂元丈】🔗⭐🔉
のろ-げんじょう ―ゲンヂヤウ 【野呂元丈】
(1693-1761) 江戸中期の本草学者・蘭学者。伊勢の人。医学修業のかたわら,稲生(イノウ)若水らから本草学を学び,諸国を実地調査。江戸参府のオランダ商館員の協力を得て本草書を解読,「阿蘭陀本草和解(オランダホンゾウワゲ)」を著した。
のろい【呪い・詛い】🔗⭐🔉
のろい ノロヒ [0][3] 【呪い・詛い】
のろうこと。呪詛(ジユソ)。「―をかける」「―の言葉を吐く」
のろい-ごと【呪ひ言・呪ひ事】🔗⭐🔉
のろい-ごと ノロヒ― 【呪ひ言・呪ひ事】
相手を憎みのろう言葉。また,のろいを込めた仕業(シワザ)。「さて,その―せさせし人も,いくほどなくて殃(ワザワイ)にあひて死にけりとぞ/宇治拾遺 10」
のろ・い【鈍い】🔗⭐🔉
のろ・い [2] 【鈍い】 (形)[文]ク のろ・し
(1)動作や進行の速度がおそい。「足が―・い」「仕事が―・い」「この列車はひどく―・い」
(2)頭の働きがにぶい。愚鈍だ。「てめへなんぞはかうべが―・いぜ/西洋道中膝栗毛(魯文)」
(3)異性に甘い。異性の魅力に弱い。「なぜあの女に―・くなつたらう/滑稽本・浮世床(初)」
[派生] ――さ(名)
のろ・う【呪う・詛う】🔗⭐🔉
のろ・う ノロフ [2] 【呪う・詛う】 (動ワ五[ハ四])
〔「告(ノ)る」に継続の助動詞「ふ」の付いた「のらふ」の転〕
(1)恨みのある人などに不幸な事が起こるように神仏に祈る。また,そのようなことを心の中で願う。「人を―・う」「汝,牛を―・ひて殺せり/霊異記(上訓注)」
(2)強くうらむ。「世を―・う」「我が身の不運を―・う」
のろ-かじめ【野呂搗布】🔗⭐🔉
のろ-かじめ ―カヂメ [3] 【野呂搗布】
カジメの別名。
のろ-くさ【鈍臭】🔗⭐🔉
のろ-くさ [1] 【鈍臭】 (副)スル
動作がてきぱきしないさま。のろのろ。「なにをやらせても―(と)している」
のろ-くさ・い【鈍臭い】🔗⭐🔉
のろ-くさ・い [4] 【鈍臭い】 (形)[文]ク のろくさ・し
見ているほうがじれったくなるほどのろのろしている。のろい。「やることが―・いのでいらいらする」
[派生] ――さ(名)
のろ-け【惚気】🔗⭐🔉
のろ-け [0][3] 【惚気】
のろけること。また,その話。「―を聞かされる」
のろけ-ばなし【惚気話】🔗⭐🔉
のろけ-ばなし [4] 【惚気話】
のろけてする話。
のろ・ける【惚気る】🔗⭐🔉
のろ・ける [0][3] 【惚気る】 (動カ下一)
(1)自分の夫・妻・恋人との間のむつまじいことを得意になって人に話して聞かせる。「手ばなしで―・ける」
(2)女色にひかれる。色情にひかれて甘くなる。「なにつまらねえ,素人じみて,さう女に―・けもしますめえ/人情本・梅児誉美 3」
のろ-さく【鈍作】🔗⭐🔉
のろ-さく [0] 【鈍作】
のろまな人を人名めかしていった語。のろすけ。「彼(カノ)―が本妻にせんといひしは後日の妨げ/高橋阿伝夜叉譚(魯文)」
のろし【狼煙・狼烟・烽火】🔗⭐🔉
のろし [0] 【狼煙・狼烟・烽火】
(1)敵襲などの変事の急報のために,高く上げる煙や火。古くは草や薪を燃し,後には,火薬を用いた花火のようなものもあった。「―があがる」
〔中国で,狼の糞(フン)を加えると煙が直上するといわれた〕
(2)合図。信号。「新時代の到来を告げる―」
のろ-のろ【鈍鈍】🔗⭐🔉
のろ-のろ [1] 【鈍鈍】 (副)スル
動きがおそいさま。「疲れきって―(と)動く」「―(と)した歩み」「―運転」
のろのろ・し【呪呪し】🔗⭐🔉
のろのろ・し 【呪呪し】 (形シク)
のろわしい。いまいましい。恨めしい。「―・しき事ども多かり/栄花(花山)」
のろ-ま【鈍間・野呂松】🔗⭐🔉
のろ-ま [0] 【鈍間・野呂松】
■一■ (名・形動)
〔■二■の意から〕
(1)動作がにぶく,気がきかない・こと(さま)。そのような人にもいう。「―な男」
(2)「のろま色」の略。「銅杓子かして―にして返し/柳多留(初)」
■二■ (名)
「野呂松(ノロマ)人形」の略。
のろま-いろ【鈍間色】🔗⭐🔉
のろま-いろ 【鈍間色】
〔野呂松(ノロマ)人形の顔の色から〕
青黒い色。「板じめの―になつたほそおびをしめ/洒落本・青楼昼之世界錦之裏」
のろま-ざる【鈍間猿】🔗⭐🔉
のろま-ざる [4] 【鈍間猿】
⇒ロリス
のろま-づかい【野呂松遣い】🔗⭐🔉
のろま-づかい ―ヅカヒ [4] 【野呂松遣い】
野呂松人形を遣う人形遣い。寛文(1661-1673)・延宝(1673-1681)期の江戸和泉太夫芝居の野呂松勘兵衛や貞享(1684-1688)・元禄(1688-1704)期ののろま治兵衛が名高い。
のろま-にんぎょう【野呂松人形・野呂間人形】🔗⭐🔉
のろま-にんぎょう ―ギヤウ [4] 【野呂松人形・野呂間人形】
人形浄瑠璃の間(アイ)狂言として演じられた道化人形。頭が平たく顔の青黒い,卑しげな一人遣いの人形で,俗語を交えた狂言風の台詞(セリフ)で演じる。間狂言は1715年の「国性爺合戦」上演から除かれ,劇場からは脱落して現在は新潟県佐渡などにわずかに伝承されている。
→曾呂間(ソロマ)人形
野呂松人形
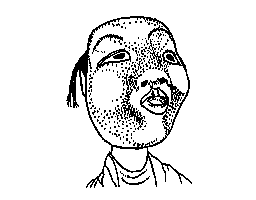 [図]
[図]
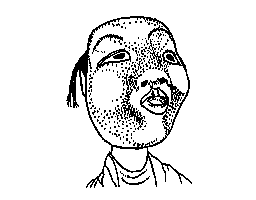 [図]
[図]
のろり🔗⭐🔉
のろり [2][3] (副)
(多く「と」を伴って)
(1)動作の鈍いさま。のろのろ。のんびり。「―と人の顔を見る/大内旅宿(虚子)」
(2)なんとなく。ふらりと。「ゆふべ―と帰つた所が,内へは這入られねえから/滑稽本・浮世風呂 3」
のろわし・い【呪わしい】🔗⭐🔉
のろわし・い ノロハシイ [4] 【呪わしい】 (形)[文]シク のろは・し
〔動詞「のろう」の形容詞化〕
のろいたい気持ちである。「―・い戦争の爪跡(ツメアト)」
[派生] ――げ(形動)――さ(名)
のろん-じ【呪師】🔗⭐🔉
のろん-じ 【呪師】
⇒じゅし(呪師)(3)
のろい【呪】(和英)🔗⭐🔉
のろい【呪】
a curse.→英和
のろい【鈍い】(和英)🔗⭐🔉
のろう【呪う】(和英)🔗⭐🔉
のろけ【惚気を言う】(和英)🔗⭐🔉
のろけ【惚気を言う】
talk (fondly) about one's sweetheart[wife,etc.].
のろし【狼煙(を上げる)】(和英)🔗⭐🔉
のろし【狼煙(を上げる)】
(light) a signal fire.
のろのろ(和英)🔗⭐🔉
のろのろ
〜(と) slowly;idly.
大辞林に「のろ」で始まるの検索結果 1-38。