複数辞典一括検索+![]()
![]()
うば【乳母】🔗⭐🔉
うば [1] 【乳母】
母親に代わって子供に乳を飲ませ,面倒をみる女性。めのと。
うば【姥・媼】🔗⭐🔉
うば [1] 【姥・媼】
(1)年をとった女。老女。老婆。おうな。
(2)能面の一。老女の顔にかたどったもの。老女物に用いるほか,「高砂(タカサゴ)」などでは神の化身にも用いる。
⇔尉(ジヨウ)
姥(2)
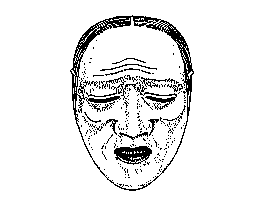 [図]
[図]
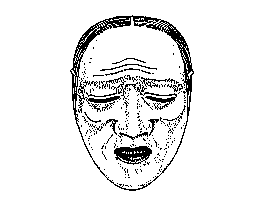 [図]
[図]
うば【祖母】🔗⭐🔉
うば 【祖母】
両親の母親。おおば。祖母(ソボ)。「―にて侍りし人の身まかりて/隆信集」
う-ば🔗⭐🔉
う-ば [1]
(1)酒などを醸造するとき,表面に浮き上がってくるあく。
(2)湯葉(ユバ)のこと。
ウバ Uva
Uva 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ウバ [1]  Uva
Uva スリランカ南東部の山岳地帯で産する紅茶の銘柄。高い香りと芳醇な味わいが特徴。
スリランカ南東部の山岳地帯で産する紅茶の銘柄。高い香りと芳醇な味わいが特徴。
 Uva
Uva スリランカ南東部の山岳地帯で産する紅茶の銘柄。高い香りと芳醇な味わいが特徴。
スリランカ南東部の山岳地帯で産する紅茶の銘柄。高い香りと芳醇な味わいが特徴。
う-ばい【烏梅】🔗⭐🔉
う-ばい [0][1] 【烏梅】
梅の未熟な実を干していぶしたもの。染料や下痢・腫(ハ)れ物などの薬料とする。ふすべうめ。
うばい【優婆夷】🔗⭐🔉
うばい-あ・う【奪い合う】🔗⭐🔉
うばい-あ・う ウバヒアフ [4][0] 【奪い合う】 (動ワ五[ハ四])
争って,数に限りのある物の取り合いをする。「席を―・う」
うば-いし【姥石】🔗⭐🔉
うば-いし [2] 【姥石】
女性に関する伝説をもつ石。母に別れた子に乳を与えた女性や,女人禁制を犯して登山した尼が化したなど,伝説の内容はさまざま。
ウバイド ‘Ubaid
‘Ubaid 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
うばい-と・る【奪い取る】🔗⭐🔉
うばい-と・る ウバヒ― [4][2] 【奪い取る】 (動ラ五[四])
他人の物を無理に取る。「力ずくで―・る」
[可能] うばいとれる
うば・う【奪う】🔗⭐🔉
うば・う ウバフ [2][0] 【奪う】 (動ワ五[ハ四])
(1)他人の所有するものを無理に取り上げて自分のものにする。(ア)力ずくで他人のものを自分のものにする。「金を―・う」(イ)ある人のもっていた権利・地位を失わせる。「選挙権を―・う」(ウ)ある行為によって相手がそれを持っていない状態にする。「生きる希望を―・う」「命を―・う」(エ)ある地位にいる人をやめさせ,かわって自分がその地位につく。「王位を―・う」
(2)性質や成分などを取り去る。「熱を―・う」「水分を―・う」
(3)心や注意などを強くひきつける。気持ちをとらえてしまう。「目を―・うあでやかさ」「景色に心が―・われる」
(4)競技などで,得点する。また,タイトルなどを獲得する。「一挙に五点を―・った」
〔中古以降「むばふ」「ばふ」とも表記される〕
[可能] うばえる
[慣用] お株を―・心を―・胆を―・人目を―・目を―
うば-がい【姥貝・雨波貝】🔗⭐🔉
うば-がい ―ガヒ [2] 【姥貝・雨波貝】
海産の二枚貝。殻はふくらんだ方円形で,殻長10センチメートルぐらい。殻表に褐色の皮をかぶる。浅海の砂底にすむ。肉は美味。千葉県銚子以北に分布。北寄貝(ホツキガイ)。
うばがね-もち🔗⭐🔉
うばがね-もち [4]
植物イズセンリョウの異名。
うば-が-ふち【姥ヶ淵】🔗⭐🔉
うば-が-ふち 【姥ヶ淵】
貴人の子を養育していた乳母が追いつめられてその子とともに水中に身を投じたという伝説。また,そのような伝説のある淵。
うば-がみ【姥髪】🔗⭐🔉
うば-がみ [0][2] 【姥髪】
能で,老女の扮装(フンソウ)に用いる白髪のまじった鬘(カツラ)。姥鬘(ウバカズラ)。
うば-が-もち【姥餅】🔗⭐🔉
うば-が-もち [3][1] 【姥餅】
近江国草津名産のあんころ餅。近江国の郷代官六角左京大夫が滅ぼされたとき,その遺児を養育するため,乳母が売り出したものという。
うば-かわ【姥皮】🔗⭐🔉
うば-かわ ―カハ [0] 【姥皮】
昔話で,着ると醜悪な老女となり,脱ぐとまたもとの姿になるという想像上の衣。
うば-ぐち【姥口】🔗⭐🔉
うば-ぐち [2][0] 【姥口】
(1)老女の歯のない口もとのように,口の周囲の盛り上がった香炉や茶釜など。
(2)物のふたなどがきちんとしまらず開いているさま。
うば-ぐるま【乳母車】🔗⭐🔉
うば-ぐるま [3] 【乳母車】
乳幼児を乗せて押して歩く小さな四輪車。明治初期に日本に伝わる。
うば-ざくら【姥桜】🔗⭐🔉
うば-ざくら [3] 【姥桜】
〔「葉(歯)なし」の意からという〕
(1)葉の出るよりも先に花の咲く種類のサクラの俗称。ヒガンザクラ・ウバヒガンなど。
(2)娘盛りの年頃を過ぎても,なお美しい器量を保っている女。
うば-ざめ【姥鮫】🔗⭐🔉
うば-ざめ [0][2] 【姥鮫】
ネズミザメ目の海魚。全長15メートルに達する大形のサメ。体は紡錘形で,鰓孔(サイコウ)は長く五対ある。目・歯ははなはだ小さい。プランクトンなどを食べ,人間を襲うことはない。卵胎生。温帯の海域に広く分布。バカザメ。ウトウザメ。テング。
うばすて-やま【姨捨山】🔗⭐🔉
うばすて-やま 【姨捨山】
⇒おばすてやま(姨捨山)
うばそく【優婆塞】🔗⭐🔉
うばそく [2] 【優婆塞】
〔梵 up saka〕
〔仏〕 三帰・五戒を受けて正式の仏教信者となった男子。また,在家のままで仏道修行にはげむ人。近事男(ゴンジナン)。
⇔優婆夷(ウバイ)
saka〕
〔仏〕 三帰・五戒を受けて正式の仏教信者となった男子。また,在家のままで仏道修行にはげむ人。近事男(ゴンジナン)。
⇔優婆夷(ウバイ)
 saka〕
〔仏〕 三帰・五戒を受けて正式の仏教信者となった男子。また,在家のままで仏道修行にはげむ人。近事男(ゴンジナン)。
⇔優婆夷(ウバイ)
saka〕
〔仏〕 三帰・五戒を受けて正式の仏教信者となった男子。また,在家のままで仏道修行にはげむ人。近事男(ゴンジナン)。
⇔優婆夷(ウバイ)
うばそく-の-みや【優婆塞の宮】🔗⭐🔉
うばそく-の-みや 【優婆塞の宮】
源氏物語の作中人物。桐壺院の第八皇子。光源氏の異母弟。大君(オオイギミ)・中君・浮舟の父。北の方と死別後宇治に隠棲(インセイ)し,優婆塞の生活をおくる。宇治の八の宮。
うば-たま【烏羽玉】🔗⭐🔉
うば-たま [0] 【烏羽玉】
(1)ヒオウギの種子。黒色で丸い。ぬばたま。
(2)求肥(ギユウヒ)に餡(アン)を包んで白砂糖をまぶした餅菓子。
(3)アメリカ合衆国南西部からメキシコにかけて分布する球形のサボテン。メスカリンを含む種がある。
うばたま-の【烏羽玉の】🔗⭐🔉
うばたま-の 【烏羽玉の】 (枕詞)
烏羽玉が黒いことから,「闇」「夜」「夢」などにかかる。ぬばたまの。「―夢になにかは慰さまむうつつにだにもあかぬ心を/古今(物名)」
う-はつ【有髪】🔗⭐🔉
う-はつ [0] 【有髪】
仏門にはいった人が僧形にならずに髪をそらないでいること。また,その人。「―の尼」
うはつ-そう【有髪僧】🔗⭐🔉
うはつ-そう [3] 【有髪僧】
(1)髪をそらないでいる僧。
(2)俗人で仏道を修行している人。
う-ばっか【右幕下】🔗⭐🔉
う-ばっか ―バクカ 【右幕下】
(1)右近衛大将の居所。
(2)右近衛大将。特に,源頼朝のこと。
うばめ-がし【姥芽 ・姥目樫】🔗⭐🔉
・姥目樫】🔗⭐🔉
うばめ-がし [3] 【姥芽 ・姥目樫】
ブナ科の常緑高木。高さ10メートルに達する。葉は厚く長楕円形。庭木・生け垣として利用する。材は堅く備長炭(ビンチヨウズミ)の原料となる。実は食べられる。イマメガシ。ウマメガシ。
・姥目樫】
ブナ科の常緑高木。高さ10メートルに達する。葉は厚く長楕円形。庭木・生け垣として利用する。材は堅く備長炭(ビンチヨウズミ)の原料となる。実は食べられる。イマメガシ。ウマメガシ。
 ・姥目樫】
ブナ科の常緑高木。高さ10メートルに達する。葉は厚く長楕円形。庭木・生け垣として利用する。材は堅く備長炭(ビンチヨウズミ)の原料となる。実は食べられる。イマメガシ。ウマメガシ。
・姥目樫】
ブナ科の常緑高木。高さ10メートルに達する。葉は厚く長楕円形。庭木・生け垣として利用する。材は堅く備長炭(ビンチヨウズミ)の原料となる。実は食べられる。イマメガシ。ウマメガシ。
うばやま-かいづか【姥山貝塚】🔗⭐🔉
うばやま-かいづか ―カヒヅカ 【姥山貝塚】
千葉県市川市にある縄文時代中期・後期の遺跡。竪穴住居跡・人骨などが多数発見されている。
うば-ゆり【姥百合】🔗⭐🔉
うば-ゆり [2] 【姥百合】
ユリ科の多年草。山林中に生える。葉は卵心形。花茎は高さ1メートルに達し,夏,茎頂に数個の筒形の緑色を帯びた白花を開く。
うばら【茨・荊棘】🔗⭐🔉
うばら 【茨・荊棘】
いばら。うまら。「からたちの―刈りそけ倉立てむ/万葉 3832」
うば-ら【姥等】🔗⭐🔉
うば-ら 【姥等】
近世,京都で歳末に白木綿で顔を隠し,赤前垂れをかけ,籠(カゴ)を持って各戸を訪ねて物乞(モノゴ)いをした女乞食。老女に多かった。
うばら-ぐつわ【
 轡】🔗⭐🔉
轡】🔗⭐🔉
うばら-ぐつわ 【
 轡】
唐鞍(カラクラ)に用いる轡。鏡板(カガミイタ)の左右が菱(ヒシ)状にとがっているもの。[和名抄]
轡】
唐鞍(カラクラ)に用いる轡。鏡板(カガミイタ)の左右が菱(ヒシ)状にとがっているもの。[和名抄]

 轡】
唐鞍(カラクラ)に用いる轡。鏡板(カガミイタ)の左右が菱(ヒシ)状にとがっているもの。[和名抄]
轡】
唐鞍(カラクラ)に用いる轡。鏡板(カガミイタ)の左右が菱(ヒシ)状にとがっているもの。[和名抄]
うばり【優波離】🔗⭐🔉
うばり 【優波離】
〔梵 Up li〕
紀元前六世紀頃のインドの僧。釈尊の十大弟子の一人。戒律に精通していることから持律第一といわれた。ウパーリ。
li〕
紀元前六世紀頃のインドの僧。釈尊の十大弟子の一人。戒律に精通していることから持律第一といわれた。ウパーリ。
 li〕
紀元前六世紀頃のインドの僧。釈尊の十大弟子の一人。戒律に精通していることから持律第一といわれた。ウパーリ。
li〕
紀元前六世紀頃のインドの僧。釈尊の十大弟子の一人。戒律に精通していることから持律第一といわれた。ウパーリ。
うば【乳母】(和英)🔗⭐🔉
うばう【奪う】(和英)🔗⭐🔉
うばざくら【姥桜】(和英)🔗⭐🔉
うばざくら【姥桜】
a faded beauty.
大辞林に「ウバ」で始まるの検索結果 1-40。