複数辞典一括検索+![]()
![]()
いたこ【潮来】🔗⭐🔉
いたこ 【潮来】
茨城県行方(ナメガタ)郡の町。霞ヶ浦と北浦とを結ぶ北利根川に面した水郷地帯の中心地。
いたこ-ぶし【潮来節】🔗⭐🔉
いたこ-ぶし 【潮来節】
俗謡。潮来の船唄に由来。江戸の花柳界から各地に広まり,盆踊り唄・お座敷唄・仕事唄などとして唄われた。
うしお【潮】🔗⭐🔉
うしお ウシホ [0] 【潮】
(1)満ち干(ヒ)する海水。しお。「―のごとく敵が押し寄せる」
(2)海の水。
(3)海水の流れ。潮流。
(4)潮汁(ウシオジル)のこと。
うしお-じる【潮汁】🔗⭐🔉
うしお-じる ウシホ― [4] 【潮汁】
魚介を実(ミ)とし,塩だけで味をつけた吸い物。うしお。うしおに。
うしお-ぞめ【潮染(め)】🔗⭐🔉
うしお-ぞめ ウシホ― [0] 【潮染(め)】
浴衣地などに,鮮やかな青色の合成染料を用いて型付け染めをしたもの。洗濯や日光にも褪(ア)せにくい。
うしお-に【潮煮】🔗⭐🔉
うしお-に ウシホ― [0] 【潮煮】
⇒潮汁(ウシオジル)
しお【潮・汐】🔗⭐🔉
しお シホ [2] 【潮・汐】
(1)月および太陽の引力によって,海水が周期的に満ちたり引いたりすること。うしお。「―が満ちる」「大―」
(2)物事をするのにちょうどよい時期。しおどき。「それを―に席を立つ」「之を―に…庭の方へ走出(ハセイズ)るに/鉄仮面(涙香)」
(3)愛嬌(アイキヨウ)。「尼崎とは海近く何故にそなたは―がない/浄瑠璃・五十年忌(下)」
(4)江戸時代,大坂新町の遊女の階級で,鹿恋(カコイ)の次,影の上の位。「三五以上の月の顔,さす―影の訳もよき/浄瑠璃・寿の門松」
〔「潮」は朝のしお,「汐」は夕べのしお〕
しお=がさ・す🔗⭐🔉
――がさ・す
潮が満ちてくる。上げ潮になる。
しお=が引・く🔗⭐🔉
――が引・く
(1)引き潮になる。
(2)(「潮が引くように」の形で)集まった人々がみるみる散っていく。
しお=ならぬ海(ウミ)🔗⭐🔉
――ならぬ海(ウミ)
淡水湖。特に琵琶湖をさす。
しお-あい【潮合(い)】🔗⭐🔉
しお-あい シホアヒ [0][3] 【潮合(い)】
(1)潮の満ち引きの度合。しおどき。
(2)ちょうどよい時機。しおどき。「つい起(タチ)そそくれて―を失ひ/浮雲(四迷)」
(3)潮流がぶつかりあう所。
しお-あし【潮足】🔗⭐🔉
しお-あし シホ― [0][2] 【潮足】
潮の満ち引きの速さ。
しお-いり【潮入り】🔗⭐🔉
しお-いり シホ― [0][4] 【潮入り】
川・沼などに海水が入りこむこと。また,その場所。
しお-うみ【潮海】🔗⭐🔉
しお-うみ シホ― 【潮海】
塩分を含んでいる海。海。淡海(アワウミ)に対していう。「―のほとりにてあざれあへり/土左」
しお-おけ【潮桶】🔗⭐🔉
しお-おけ シホヲケ [3] 【潮桶】
塩をつくるために海水をくむ桶。
しお-がかり【潮懸(か)り】🔗⭐🔉
しお-がかり シホ― [3] 【潮懸(か)り】
逆潮(船の進行方向と逆の潮の流れ)にあった船が,一時停泊し順潮を待つこと。櫓漕(ロコ)ぎ・帆走に依存した時代の重要な航海技術の一。潮待ち。
しお-がしら【潮頭】🔗⭐🔉
しお-がしら シホ― [3] 【潮頭】
さしてくる潮の波がしら。しおさき。
しお-かぜ【潮風】🔗⭐🔉
しお-かぜ シホ― [2] 【潮風】
潮けを含んだ海からの風。
しお-がみ【潮上】🔗⭐🔉
しお-がみ シホ― [0] 【潮上】
潮の干満の時,海水が流れ動いてくる方向。しおかみ。
しお-きり【潮切り】🔗⭐🔉
しお-きり シホ― [0][4] 【潮切り】
(1)和船の荷船で,波を避けるために,艪床(ロドコ)の外側につけるもの。浪(ナミ)切り。
(2)和船で,水押(ミヨシ)の水中にある部分。浪(ナミ)切り。
しお-くみ【潮汲み・汐汲み】🔗⭐🔉
しお-くみ シホ― [3][4] 【潮汲み・汐汲み】 (名)スル
塩をつくるために海水を汲むこと。また,その人。
しお-ぐもり【潮曇(り)】🔗⭐🔉
しお-ぐもり シホ― [3] 【潮曇(り)】
海上の潮けによって,空または海面がくもること。
しお-け【潮気】🔗⭐🔉
しお-け シホ― [3] 【潮気】
塩分を含んだ湿りけ。また,潮の香。
しお-けむり【潮煙】🔗⭐🔉
しお-けむり シホ― [3] 【潮煙】
海水が岩にくだけて飛び散るしぶき。しおけぶり。「岩の間から―が立つ」
しお-さい【潮騒】🔗⭐🔉
しお-さい シホサ [0] 【潮騒】
〔「しおざい」とも〕
潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。
[0] 【潮騒】
〔「しおざい」とも〕
潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。
 [0] 【潮騒】
〔「しおざい」とも〕
潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。
[0] 【潮騒】
〔「しおざい」とも〕
潮がさしてくる時の波の音。寄せ来る波が立てる音。
しおさい【潮騒】🔗⭐🔉
しおさい シホサ 【潮騒】
小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。
【潮騒】
小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。
 【潮騒】
小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。
【潮騒】
小説。三島由紀夫作。1954年(昭和29)刊。太陽あふれる歌島の,若く健康な肉体と精神を持つ男女の恋物語を,ギリシャ的様式美のうちに描く。
しお-ざかい【潮境】🔗⭐🔉
しお-ざかい シホザカヒ [3] 【潮境】
(1)異なる二つの海流が出合う所。しばしば潮目(シオメ)が生じる。
→潮目
(2)河水と海水の境目。
(3)物事の境目。「今が浮沈の―/浮雲(四迷)」
しお-さき【潮先】🔗⭐🔉
しお-さき シホ― [0][4] 【潮先】
(1)潮がさしてくる時。また,さしてくる潮の波先。しおがしら。
(2)物事の始まる時。しお。「いで此の―をかりてなさくじりそ/落窪 1」
しお-じ・む【潮染む】🔗⭐🔉
しお-じ・む シホ― 【潮染む】 (動マ四)
(1)海の水や潮の気がしみ込む。海のにおいがしみ付く。「世を海にここら―・む身となりて/源氏(明石)」
(2)慣れる。世慣れる。「この方に―・みたる人はいかなるも心やすげなり/浜松中納言 3」
しお-じる【潮汁・塩汁】🔗⭐🔉
しお-じる シホ― [3] 【潮汁・塩汁】
(1)塩で調味した汁。
(2)海水。また,塩水。
しお-せ【潮瀬】🔗⭐🔉
しお-せ シホ― 【潮瀬】
潮の流れるところ。潮流。「―のなをりを見れば,遊びくる鮪(シビ)がはたてに妻立てり見ゆ/古事記(下)」
しお-た・れる【潮垂れる】🔗⭐🔉
しお-た・れる シホ― [0][4] 【潮垂れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 しほた・る
(1)元気がなくなる。あわれな様子になる。「しよぼしよぼと―・れた姿で帰つて来る/田舎教師(花袋)」
(2)(海水にぬれて)しずくが垂れる。ぐっしょりぬれる。「髪も袴も―・れて/平家 9」
(3)涙にぬれる。また,嘆き沈む。「いと尊ければ皆人―・れ給ふ/源氏(鈴虫)」
しお-つなみ【潮津浪】🔗⭐🔉
しお-つなみ シホ― [3] 【潮津浪】
⇒海嘯(カイシヨウ)
しお-とうじ【潮湯治】🔗⭐🔉
しお-とうじ シホタウヂ [3] 【潮湯治】
病気の治療のために海水につかること。また,海水浴。しおゆあみ。
しお-どき【潮時】🔗⭐🔉
しお-どき シホ― [0] 【潮時】
(1)潮が満ちたり引いたりする時。「満潮の―にかかる」
(2)物事をするのにちょうどよい時。「―を見計らう」「物には―というものがある」
しお-ど・く【潮解く】🔗⭐🔉
しお-ど・く シホ― 【潮解く】 (動カ下二)
(1)びっしょりぬれる。「雨少しうち降りて田子の袂も―・けたり/栄花(御裳着)」
(2)涙にぬれる。「あはれにて―・け暮らし/栄花(月の宴)」
しお-どけ・し【潮解けし】🔗⭐🔉
しお-どけ・し シホ― 【潮解けし】 (形ク)
海水にぬれている。また,涙にぬれている。「よる浪にたちかさねたる旅ごろも,―・しとや人のいとはむ/源氏(明石)」
しお-どめ【潮止め】🔗⭐🔉
しお-どめ シホ― [0][4] 【潮止め】
干拓工事で,海水をせき止める堤防の開口部を締めきって,干拓地から海水を完全に遮断すること。「―口」
しお-なり【潮鳴り】🔗⭐🔉
しお-なり シホ― [0] 【潮鳴り】
遠くから聞こえる,寄せては返す波の音。
しお-な・る【潮馴る】🔗⭐🔉
しお-な・る シホ― 【潮馴る】 (動ラ下二)
潮けがしみてよれよれになる。「いかに伊勢をの海士(アマ)の―・れてや/源氏(空蝉)」
しお-なわ【潮泡・塩沫】🔗⭐🔉
しお-なわ シホ― 【潮泡・塩沫】
〔「しおのあわ」の転〕
海水のあわ。しおあわ。「―の留まる限り/祝詞(祈年祭)」
しお-の-みさき【潮岬】🔗⭐🔉
しお-の-みさき シホ― 【潮岬】
紀伊半島南端,太平洋に突出する本州最南端の岬。岬一帯は海抜40〜80メートルの平坦な隆起海食台地からなる陸繋(リクケイ)島。
しお-の-め【潮の目】🔗⭐🔉
しお-の-め シホ― [0] 【潮の目】
⇒潮目(シオメ)
しお-ひ【潮干】🔗⭐🔉
しお-ひ シホ― [3] 【潮干】
(1)潮が引くこと。また,潮が引いて現れた海浜。[季]春。《青柳の泥にしだるゝ―かな/芭蕉》
(2)「潮干狩り」の略。「―と桜こぎわける柳ばし/柳多留 93」[季]春。《―より今帰りたる隣かな/正岡子規》
しおひ-がた【潮干潟】🔗⭐🔉
しおひ-がた シホ― 【潮干潟】
海水が引いて現れた干潟。[季]春。「沖つ風吹上の浜の―/新千載(冬)」
しおひ-がり【潮干狩(り)】🔗⭐🔉
しおひ-がり シホ― [3] 【潮干狩(り)】
潮の引いた浜へ出て,アサリやハマグリなどの貝をとって遊ぶこと。春の大潮の時が好期で,かつては陰暦三月三日の行事でもあった。しおひ。[季]春。《ぬるき汐つめたき汐や―/富安風生》
しおひ-の-なごり【潮干の名残】🔗⭐🔉
しおひ-の-なごり シホ― 【潮干の名残】
潮が引いたあとに残った水たまり。「難波潟―よく見てむ/万葉 976」
しおひる-たま【潮干る珠】🔗⭐🔉
しおひる-たま シホヒル― 【潮干る珠】
⇒しおふるたま(潮干珠)
しお-ふき【潮吹き】🔗⭐🔉
しお-ふき シホ― [3][4][0] 【潮吹き】
(1)クジラの呼気。体内で温められ湿った空気が急激に体外へ吐き出され,水蒸気が水滴となり,同時に鼻孔周辺の海水も一緒に吹き上げられる。
(2)船の舵の羽板(ハイタ)に開けた穴。輪精(リンセイ)。
(3)「潮吹き面」の略。
(4)海産の二枚貝。殻長5センチメートル前後で,丸みのある三角形。殻表は黄褐色で細かい輪脈がある。内湾の潮間帯の砂泥にすむ。佃煮(ツクダニ)にする。しおふきがい。
しおふき-めん【潮吹き面】🔗⭐🔉
しおふき-めん シホ― [4] 【潮吹き面】
火男(ヒヨツトコ)の面。潮吹き。
しお-ぶね【潮舟】🔗⭐🔉
しお-ぶね シホ― 【潮舟】
海路を行く船。「―にま楫(カジ)しじ貫き我は帰り来む/万葉 4368」
しおぶね-の【潮舟の】🔗⭐🔉
しおぶね-の シホ― 【潮舟の】 (枕詞)
舟の並び行くさまや,浜に置かれたさまからいうか。「並ぶ」「置く」にかかる。「―並べて見れば/万葉 3450」
しおふる-たま【潮干る珠】🔗⭐🔉
しおふる-たま シホフル― 【潮干る珠】
潮を引かせる力をもつという珠。干珠(カンジユ)。しおひるたま。しおひるに。
⇔潮満つ珠
「若し其れ愁ひ請(マオ)さば―を出して活かし/古事記(上訓)」
しお-ぶろ【塩風呂・潮風呂】🔗⭐🔉
しお-ぶろ シホ― [0] 【塩風呂・潮風呂】
海水や塩水を沸かした風呂。塩湯。[日葡]
しお-ま【潮間】🔗⭐🔉
しお-ま シホ― [0][3] 【潮間】
潮が引いている間。
しお-まち【潮待ち】🔗⭐🔉
しお-まち シホ― [4] 【潮待ち】 (名)スル
(1)釣りで,潮が動き出すのを待つこと。
(2)好機を待つこと。「うら茶屋ばいりの―もたいぎだから/安愚楽鍋(魯文)」
(3)「潮懸かり」に同じ。
しお-まねき【潮招・望潮】🔗⭐🔉
しお-まねき シホ― [3] 【潮招・望潮】
海産のカニ。甲幅3センチメートル内外。砂泥地の干潟にすむ。雄は片方のはさみが著しく大きくなり,これを上下に振る動作が潮を招くように見えるのでこの名がある。砕いて塩辛にしたものを「蟹漬(ガンヅケ)」といい,有明海沿岸の名物。紀伊半島以南に広く分布。タウチガニ。[季]春。
潮招
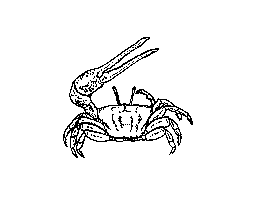 [図]
[図]
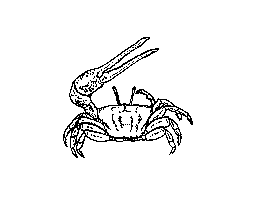 [図]
[図]
しお-まわり【潮回り】🔗⭐🔉
しお-まわり シホマハリ [3] 【潮回り】
約一五日周期の潮の変化。
しお-み【潮見】🔗⭐🔉
しお-み シホ― [3][0] 【潮見】
潮時・潮の具合を見ること。
しおみ-ばし【潮見橋】🔗⭐🔉
しおみ-ばし シホ― [3] 【潮見橋】
日本庭園で池尻の狭い場所などにかけ渡す橋。古船の底板を使って作る。
しお-みず【潮水】🔗⭐🔉
しお-みず シホミヅ [2] 【潮水】
海の水。うしお。
しおみつ-たま【潮満つ珠】🔗⭐🔉
しおみつ-たま シホミツ― 【潮満つ珠】
潮を満ちさせる力をもつという珠。満珠(マンジユ)。しおみつに。
⇔潮干(フ)る珠
「攻め戦はば,―を出して溺らし/古事記(上訓)」
しおみつ-に【潮満つ瓊】🔗⭐🔉
しおみつ-に シホミツ― 【潮満つ瓊】
「しおみつたま(潮満珠)」に同じ。「―を出せば則ち潮大きに溢(ミ)ちて/日本書紀(神代下訓)」
しお-むし【潮虫】🔗⭐🔉
しお-むし シホ― [2] 【潮虫】
甲殻綱等脚目の節足動物。体は平たい卵円形。体長15ミリメートルほど。背面は淡褐色で黒点が散在する。乾燥して養殖魚の餌(エサ)とする。北海道・千島の沿岸の砂泥底にすむ。
しお-め【潮目】🔗⭐🔉
しお-め シホ― [0][3] 【潮目】
異なる二つの潮流の接する海面に現れる帯状の筋。寒流と暖流の出合う付近などに見られ,しばしば好漁場となる。しおのめ。
しお-やけ【潮焼け】🔗⭐🔉
しお-やけ シホ― [0] 【潮焼け】 (名)スル
(1)皮膚が,潮風に吹かれ,日光を受けて,赤黒く焼けること。「―したたくましい顔」
(2)海上の水蒸気が日光を受け赤く映えること。
しお-ゆ【塩湯・潮湯】🔗⭐🔉
しお-ゆ シホ― [2] 【塩湯・潮湯】
(1)「塩風呂(シオブロ)」に同じ。
(2)塩分を含む温泉。
(3)食塩を加えた白湯(サユ)。
しお-ゆあみ【潮浴み】🔗⭐🔉
しお-ゆあみ シホ― 【潮浴み】
海水に浴すること。潮湯治(シオトウジ)。「播磨の明石といふ所に―にまかりて/後拾遺(羇旅詞)」
しょうさい-ふぐ【潮前河豚】🔗⭐🔉
しょうさい-ふぐ [5] 【潮前河豚】
フグ目の海魚。全長30センチメートルほど。やや小形のフグで,体表に明瞭なとげはない。背面は淡い青緑色に暗褐色の小斑が一面にあり,腹面と尻びれは白い。食用とされているが卵巣・肝臓は猛毒,肉は弱毒。本州以南の沿岸に広く分布。ナゴヤフグ。
ちょうあん【潮安】🔗⭐🔉
ちょうあん テウアン 【潮安】
(1)中国,もと広東省の県。現在は潮州市に合併。
(2)潮州市の旧称。チャオアン。
ちょう-い【潮位】🔗⭐🔉
ちょう-い テウ [1] 【潮位】
基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。
[1] 【潮位】
基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。
 [1] 【潮位】
基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。
[1] 【潮位】
基準面から測った海面の高さ。潮の満ち引きによって変化する。潮高。
ちょう-おん【潮音】🔗⭐🔉
ちょう-おん テウ― [0][1] 【潮音】
海の波の音。潮声。海潮音。
ちょう-かい【潮解】🔗⭐🔉
ちょう-かい テウ― [0] 【潮解】 (名)スル
空気中に放置された結晶が,空気中の水分を吸収して溶解すること。塩化マグネシウム・塩化カルシウムなどがこの性質を示す。
ちょう-がい【潮害】🔗⭐🔉
ちょう-がい テウ― [0] 【潮害】
⇒塩害(エンガイ)(1)
ちょうかん-たい【潮間帯】🔗⭐🔉
ちょうかん-たい テウカン― [0] 【潮間帯】
高潮線と低潮線との間の海岸。波と砂・礫(レキ)がつくった微地形や,波食棚が見られる。満潮時は海水に浸され,干潮時は空気にさらされるなど,生物にとっては厳しい環境となる。
ちょう-きょう【潮況】🔗⭐🔉
ちょう-きょう テウキヤウ [0] 【潮況】
潮流の状況。
ちょう-こう【潮高】🔗⭐🔉
ちょう-こう テウカウ [0] 【潮高】
⇒潮位(チヨウイ)
ちょう-さ【潮差】🔗⭐🔉
ちょう-さ テウ― [1] 【潮差】
ある地点における満潮と干潮との海面の高さの差。
ちょうしゅう【潮州】🔗⭐🔉
ちょうしゅう テウシウ 【潮州】
中国,広東省東部の都市。古くは潮安といわれた。韓江デルタの北端に位置し,夏布・彫刻・竹細工などの工芸品を産する。チャオチョウ。
ちょう-すい【潮水】🔗⭐🔉
ちょう-すい テウ― [0] 【潮水】
海の水。しおみず。うしお。
ちょう・する【潮する】🔗⭐🔉
ちょう・する テウ― [3] 【潮する】 (動サ変)[文]サ変 てう・す
おもてに表す。多く,「紅を潮する」の形で,顔が赤らむの意に用いる。「満面に紅(コウ)を―・す/花柳春話(純一郎)」
ちょう-せい【潮勢】🔗⭐🔉
ちょう-せい テウ― [0] 【潮勢】
(1)潮流の勢い。
(2)時勢のなりゆき。風潮。潮流。
ちょう-せき【潮汐】🔗⭐🔉
ちょう-せき テウ― [0] 【潮汐】
海面が周期的に昇降する現象。主に月および太陽の引力の作用による。特に,月の作用による太陰潮が大きな部分を占め,新月または満月の頃太陰潮と太陽潮が重なりあって大潮となり,上弦または下弦の頃小潮となる。ある地点での一日の干満は普通二回あり,平均一二時間二五分で次の干または満を迎え,毎日平均約五〇分の遅れを生じて現れる。
ちょうせき-はつでん【潮汐発電】🔗⭐🔉
ちょうせき-はつでん テウ― [5] 【潮汐発電】
「潮力(チヨウリヨク)発電」に同じ。
ちょうせき-ひょう【潮汐表】🔗⭐🔉
ちょうせき-ひょう テウ―ヘウ [0] 【潮汐表】
各地の潮汐の予報数値を記載した表。
ちょうせき-まさつ【潮汐摩擦】🔗⭐🔉
ちょうせき-まさつ テウ― [5] 【潮汐摩擦】
潮流と海底との摩擦。これにより地球の自転速度が遅くなる。
ちょう-りゅう【潮流】🔗⭐🔉
ちょう-りゅう テウリウ [0] 【潮流】
(1)潮の流れ。
(2)海の干満によっておこる海水の流れ。一日に二回ずつ,その流れの方向が逆になる。
(3)時勢の動き。時代の流れ。「時代の―に乗る」
うしお【潮】(和英)🔗⭐🔉
しおかぜ【潮風】(和英)🔗⭐🔉
しおかぜ【潮風】
a sea breeze.
しおさい【潮騒】(和英)🔗⭐🔉
しおさい【潮騒】
the sound of the sea.→英和
しおどき【潮時(を外す)】(和英)🔗⭐🔉
しおどき【潮時(を外す)】
(let slip) an opportunity.→英和
⇒機会.
しおひがり【潮干狩】(和英)🔗⭐🔉
しおひがり【潮干狩】
gathering shellfish at low tide.
ちょうかい【潮解】(和英)🔗⭐🔉
ちょうかい【潮解】
《化》deliquescence.〜する deliquesce.→英和
大辞林に「潮」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む