複数辞典一括検索+![]()
![]()
おこし‐ごめ【 =
= 米】🔗⭐🔉
米】🔗⭐🔉
おこし‐ごめ【 =
= 米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
 =
= 米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
米】
米に蜜(みつ)をまぜ合わせながら煎(い)った菓子。後世のおこしの原型。
おこし‐ずみ【×熾し炭】🔗⭐🔉
おこし‐ずみ【×熾し炭】
赤くおこした炭火。
おこし‐だね【 =
= 種】🔗⭐🔉
種】🔗⭐🔉
おこし‐だね【 =
= 種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
 =
= 種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
種】
おこしの材料とする、米や粟を蒸し、乾かして煎ったもの。
おこし‐び【×熾し火】🔗⭐🔉
おこし‐び【×熾し火】
真っ赤におこった炭火。
おこじょ🔗⭐🔉
おこじょ

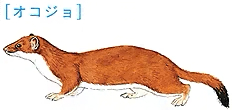 イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。
イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。

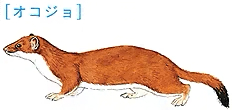 イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。
イタチ科の哺乳類。体長一八〜二九センチ、尾長六〜一二センチ。夏毛は背面が褐色、腹面は白色で、冬には尾端以外が白く変わる。ネズミやウサギを捕食。ユーラシア北部・北アメリカに分布し、日本では北海道・本州の山地にみられる。毛皮はヨーロッパではアーミンと呼ばれ、高級品。えぞいたち。やまいたち。
おこ・す【起(こ)す】🔗⭐🔉
おこ・す【起(こ)す】
[動サ五(四)] 横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」
横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」 目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」
目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」 今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」
今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」 新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
 自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」
自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」 平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」
平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」 静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」
静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」 ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」
ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」 表面に現れるようにする。
表面に現れるようにする。 土を掘り返す。「畑を―・す」
土を掘り返す。「畑を―・す」 へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」
へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」 伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。
伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。 隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」
隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」 速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
 横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」
横になっているものを立たせる。「からだを―・す」「倒木を―・す」「転んだ子を―・す」 目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」
目を覚まさせる。「寝入りばなを―・される」 今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」
今までなかったものを新たに生じさせる。「風力を利用して電気を―・す」「波を―・す」 新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
新しく物事を始める。興す。「事業を―・す」
 自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」
自然が働きや動きを示す。「噴火を―・す」「地滑りを―・す」 平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」
平常と異なる状態や、好ましくない事態を生じさせる。ひきおこす。「革命を―・す」「事故を―・す」 静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」
静かな状態を刺激して、ある影響をもたらす。「ブームを―・す」 ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」
ある感情・欲望を生じさせる。また、からだの働きがある状態を示す。「やる気を―・す」「里心を―・す」「拒絶反応を―・す」「食中毒を―・す」 表面に現れるようにする。
表面に現れるようにする。 土を掘り返す。「畑を―・す」
土を掘り返す。「畑を―・す」 へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」
へばりついている状態のものをはがす。「芝を―・す」「敷石を―・す」 伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。
伏せてあるカード・花札などをめくって表を出す。 隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」
隠されていた状態から表に出す。「伏せ字を―・す」 速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
速記や録音テープの音声などを文字化する。また、文章を書いたり文書を作ったりする。「講演の録音を原稿に―・す」「稿を―・す」「伝票を―・す」
[可能]おこせる
[下接句]願(がん)を起こす・事を起こす・甚助(じんすけ)を起こす・寝た子を起こす・身を起こす・虫を起こす
おこ・す【×熾す】🔗⭐🔉
おこ・す【×熾す】
[動サ五(四)]《「起こす」と同語源》炭火などの勢いを盛んにする。また、炭などに火をつける。「火吹き竹で火を―・す」
[可能]おこせる
大辞泉 ページ 2102。