複数辞典一括検索+![]()
![]()
かがみ‐は【鏡葉】🔗⭐🔉
かがみ‐は【鏡葉】
カシワなどの、表面が広くてつやのある葉。
かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡×匣・鏡×筥】🔗⭐🔉
かがみ‐ばこ【鏡箱・鏡×匣・鏡×筥】

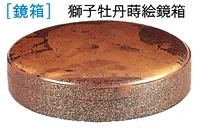 平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。
平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。

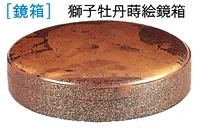 平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。
平安時代以後、寝殿に置いた調度の一。円形または八つ花形で脚のついた台の上にのせ、鏡・汗手拭(あせたなごい)・領巾(ひれ)などを入れた。
かがみ‐はだ【鏡肌】🔗⭐🔉
かがみ‐はだ【鏡肌】
断層面に沿って岩盤がずれ動いたときの摩擦で生じた、鏡のような光沢のある面。
かがみ‐ばり【鏡張り】🔗⭐🔉
かがみ‐ばり【鏡張り】
鏡板 を張ること。また、張ったもの。
を張ること。また、張ったもの。
 を張ること。また、張ったもの。
を張ること。また、張ったもの。
かがみ‐びらき【鏡開き】🔗⭐🔉
かがみ‐びらき【鏡開き】
《「開き」は「割り」の忌み詞》正月一一日(もと二〇日)に鏡餅(かがみもち)を下ろし、雑煮や汁粉にして食べること。武家では、男子は具足に、女子は鏡台に供えた鏡餅を手や槌(つち)で割り砕いた。町家でもこの風習をまねて行うようになった。鏡割り。《季 新年》「伊勢海老の―や具足櫃(ぐそくびつ)/許六」
かがみ‐ぶとん【鏡布団】🔗⭐🔉
かがみ‐ぶとん【鏡布団】
裏布を表の方に折り返して、額縁のように縫い上げた布団。鏡の形に似ているところからいう。
かがみ‐もじ【鏡文字】🔗⭐🔉
かがみ‐もじ【鏡文字】
鏡にうつったように、左右が逆になった文字。
かがみ‐もち【鏡×餅】🔗⭐🔉
かがみ‐もち【鏡×餅】
平たく円形に作った餅。大小二個をひと重ねにし、正月や祝いのとき、神仏に供える。おそなえ。おかがみ。《季 新年》「―暗きところに割れて坐す/三鬼」
かがみ‐もの【鏡物】🔗⭐🔉
かがみ‐もの【鏡物】
書名に「鏡」のつく、和文の歴史物語の総称。「大鏡」「今鏡」「水鏡」「増鏡」など。鏡類。
かがみ‐やま【鏡山】🔗⭐🔉
かがみ‐やま【鏡山】
 滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉
滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉 佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。
佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。 広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
 滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉
滋賀県南部、蒲生(がもう)郡竜王町と野洲(やす)郡野洲町との境にある山。標高三八五メートル。《歌枕》「―いざ立ちよりて見てゆかむ」〈古今・雑上〉 佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。
佐賀県唐津市と東の浜玉町との境にある山。唐津湾を望む。標高二八四メートル。松浦佐用姫(まつらさよひめ)の伝説の地。松浦山。領巾振(ひれふり)山。 広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
広島県東広島市にある山。戦国時代に大内氏の築いた西条城があり、尼子経久(あまこつねひさ)に攻められて落城。
大辞泉 ページ 2636。