複数辞典一括検索+![]()
![]()
こ‐ばん【小判】🔗⭐🔉
こ‐ばん【小判】
①天正(1573〜1592)頃から江戸末期まで行われた、薄い楕円形の金貨。その1枚は1両に相当。一両判。↔大判。
②紙などの判ばんが小さいこと。
⇒こばん‐いただき【小判頂き】
⇒こばん‐いち【小判市】
⇒こばん‐がた【小判形】
⇒こばん‐きん【小判金】
⇒こばん‐ぎん【小判銀】
⇒こばん‐ざめ【小判鮫】
⇒こばん‐じょろう【小判女郎】
⇒こばん‐そう【小判草】
⇒こばん‐づけ【小判漬】
⇒こばん‐なり【小判形】
⇒こばん‐ふん【小判粉】
こ‐ばん【小番】🔗⭐🔉
こ‐ばん【小番】
①中世、朝廷・門跡寺院・神社で、輪番で当直勤務すること。
②室町時代、武家の近習きんじゅ。小番衆。
⇒こばん‐しゅう【小番衆】
こ‐ばん【戸番】🔗⭐🔉
こ‐ばん【戸番】
番地・号など、住居や住戸を特定する番号。
こ‐ばん【火番】🔗⭐🔉
こ‐ばん【火番】
禅家で火を管理する役僧。禅寺の下男。
こ‐ばん【枯礬】🔗⭐🔉
こ‐ばん【枯礬】
(→)焼明礬やきみょうばんに同じ。
こばん‐いち【小判市】🔗⭐🔉
こばん‐いち【小判市】
小判金を銀貨または銭で売買する市。
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐がた【小判形】🔗⭐🔉
こばん‐がた【小判形】
小判の形。楕円形。こばんなり。
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐きん【小判金】🔗⭐🔉
こばん‐きん【小判金】
小判の金貨。
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐ぎん【小判銀】🔗⭐🔉
こばん‐ぎん【小判銀】
小判の銀貨。
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐ざめ【小判鮫】🔗⭐🔉
こばん‐ざめ【小判鮫】
①コバンザメ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。細長い頭頂に第1背びれの変形物である小判状の吸盤があり、これで回遊魚の皮膚や船の底に吸着して移動する。サメ類ではない。コバンイタダキ。アヤカシ。
こばんざめ
 マダラトビエイとコバンザメ
提供:東京動物園協会
マダラトビエイとコバンザメ
提供:東京動物園協会
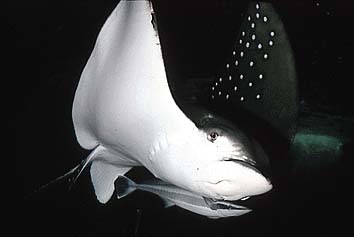 コバンザメ(吸盤)
提供:東京動物園協会
コバンザメ(吸盤)
提供:東京動物園協会
 ②コバンザメ科魚類の総称。
⇒こ‐ばん【小判】
②コバンザメ科魚類の総称。
⇒こ‐ばん【小判】
 マダラトビエイとコバンザメ
提供:東京動物園協会
マダラトビエイとコバンザメ
提供:東京動物園協会
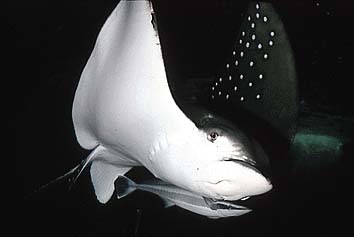 コバンザメ(吸盤)
提供:東京動物園協会
コバンザメ(吸盤)
提供:東京動物園協会
 ②コバンザメ科魚類の総称。
⇒こ‐ばん【小判】
②コバンザメ科魚類の総称。
⇒こ‐ばん【小判】
こ‐ばんし【小半紙】🔗⭐🔉
こ‐ばんし【小半紙】
小型の半紙。女の懐中紙に用いた。浄瑠璃、心中天の網島「一分―塵々紙で」
こばん‐しゅう【小番衆】🔗⭐🔉
こばん‐しゅう【小番衆】
小番を勤める者。また、近習。
⇒こ‐ばん【小番】
こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ🔗⭐🔉
こばん‐じょろう【小判女郎】‥ヂヨラウ
小判を女郎にたとえていう語。愛すべき意を示す。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「ほうほう、可愛らしい―」
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐そう【小判草】‥サウ🔗⭐🔉
こばん‐そう【小判草】‥サウ
イネ科の一年草。ヨーロッパ原産。牧草に混じって渡来。高さ30〜60センチメートルで群生する。葉は麦に似て細く、夏に小判型をした緑の花穂を垂らし、黄熟する。俵麦たわらむぎ。〈[季]夏〉
コバンソウ
撮影:関戸 勇
 ⇒こ‐ばん【小判】
⇒こ‐ばん【小判】
 ⇒こ‐ばん【小判】
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐づけ【小判漬】🔗⭐🔉
こばん‐づけ【小判漬】
(横に切ると、その中の卵が小判のように見えるからいう)鮎などの粕漬。
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐なり【小判形】🔗⭐🔉
こばん‐なり【小判形】
(→)「こばんがた」に同じ。
⇒こ‐ばん【小判】
こばん‐ふん【小判粉】🔗⭐🔉
こばん‐ふん【小判粉】
蒔絵まきえに用いる金粉。銀含量の多い金で作り、青みを帯びる。青金粉。
⇒こ‐ばん【小判】
広辞苑に「こばん」で始まるの検索結果 1-18。