複数辞典一括検索+![]()
![]()
まんざら【満更】🔗⭐🔉
○満更でもないまんざらでもない🔗⭐🔉
○満更でもないまんざらでもない
必ずしも悪くない。かなり気に入ったことを婉曲にいう語。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「なんと見れば見るほど満更でもねへあのお娘」
⇒まんざら【満更】
まん‐さん【満参】
宿願の日限に達すること。また、その日に参詣すること。
まん‐さん【蹣跚】
足もとがよろめいて、ひょろひょろと歩くさま。「酔歩―」
まん‐ざん【満山】
①山全体。全山。
②寺中の僧全体。寺中。平家物語2「―の大衆みな東坂本へおり下る」
まん‐し【慢詞】
中国の詞曲で、1首が60字以上のもの。
まん‐じ【卍・卐】
(万字の意)
①(梵語svastika ヴィシュヌなどの胸部にある旋毛)功徳くどく円満の意。仏像の胸に描き、吉祥万徳の相とするもの。右旋・左旋の両種があり、日本の仏教では主に左旋を用い、寺院の記号などにも用いる。
②1のような形。
③紋所の名。1にかたどったもの。左まんじ・右まんじ・角立まんじ・丸まんじなど。
卍
 ⇒まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】
⇒まんじ‐ともえ【卍巴】
まんじ【万治】‥ヂ
[史記]江戸前期、後西天皇朝の年号。明暦4年7月23日(1658年8月21日)改元、万治4年4月25日(1661年5月23日)寛文に改元。
まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】‥クヅシ‥
卍を崩した形を連続させた組子。法隆寺の金堂・中門・五重塔などの上層の高欄の地覆じふくと平桁との間にある。
卍崩し組子
⇒まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】
⇒まんじ‐ともえ【卍巴】
まんじ【万治】‥ヂ
[史記]江戸前期、後西天皇朝の年号。明暦4年7月23日(1658年8月21日)改元、万治4年4月25日(1661年5月23日)寛文に改元。
まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】‥クヅシ‥
卍を崩した形を連続させた組子。法隆寺の金堂・中門・五重塔などの上層の高欄の地覆じふくと平桁との間にある。
卍崩し組子
 ⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐くす・む【慢じくすむ】
〔自四〕
高慢顔ですましこむ。もっともらしい顔つきをする。醒睡笑「われとわが名を畠山の右兵衛佐とつき、―・み」
まん‐しつ【満室】
旅館やホテルなどで、全室がふさがっていること。
まんじ‐ともえ【卍巴】‥トモヱ
(マンジドモエとも)卍や巴の模様のように、追いかけあうように入り乱れるさま。
⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐まんざぶろう【万次万三郎】‥ラウ
磐次磐三郎ばんじばんざぶろうのこと。
まん‐しゃ【満車】
駐車場が車両でいっぱいでこれ以上駐車できる余地のないこと。
まんじゅ【万寿】
[詩経「万寿無疆」]平安中期、後一条天皇朝の年号。甲子革令により治安4年7月13日(1024年8月19日)改元、万寿5年7月25日(1028年8月18日)長元に改元。
まん‐じゅ【満珠】
(→)「しおみちのたま」に同じ。太平記39「竜宮城に宝とする干珠・―を借り召さる」↔干珠
まんしゅ‐いん【曼殊院】‥ヰン
(マンジュインとも)京都市左京区にある天台宗の門跡寺院。もと北野天満宮の別当寺。延暦(782〜806)年間最澄の創めた比叡山中の一宇に始まり、15世紀から宮門跡となり竹内門跡と称す。1656年(明暦2)現在地に移転。黄不動尊絵像や古典籍などを所蔵。
まんしゅう【満州・満洲】‥シウ
中国の東北一帯の俗称。もと民族名。行政上は東北三省(遼寧・吉林・黒竜江)と内モンゴル自治区の一部にわたり、中国では東北と呼ぶ。
⇒まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】
⇒まんしゅう‐ご【満州語】
⇒まんしゅう‐こく【満州国】
⇒まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】
⇒まんしゅう‐じへん【満州事変】
⇒まんしゅう‐ぞく【満州族】
⇒まんしゅう‐もじ【満州文字】
まん‐じゅう【饅頭】‥ヂユウ
(ジュウは唐音)
①小麦粉・米粉・そば粉などでつくった皮で餡あんを包んで蒸して作る菓子。暦応(1338〜1342)年間、中国から帰化した林浄因が奈良で始めた奈良饅頭を始めとする。狂言、栗焼「―羊羹などではござりませぬか」
②饅頭金物の略。
⇒まんじゅう‐がさ【饅頭笠】
⇒まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】
⇒まんじゅう‐がに【饅頭蟹】
⇒まんじゅう‐じころ【饅頭錏】
⇒まんじゅう‐はだ【饅頭肌】
⇒まんじゅう‐ぼん【饅頭本】
まんじゅう‐がさ【饅頭笠】‥ヂユウ‥
頂はまるく浅く、饅頭を横に半分に切ったような形につくったかぶり笠。
饅頭笠
⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐くす・む【慢じくすむ】
〔自四〕
高慢顔ですましこむ。もっともらしい顔つきをする。醒睡笑「われとわが名を畠山の右兵衛佐とつき、―・み」
まん‐しつ【満室】
旅館やホテルなどで、全室がふさがっていること。
まんじ‐ともえ【卍巴】‥トモヱ
(マンジドモエとも)卍や巴の模様のように、追いかけあうように入り乱れるさま。
⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐まんざぶろう【万次万三郎】‥ラウ
磐次磐三郎ばんじばんざぶろうのこと。
まん‐しゃ【満車】
駐車場が車両でいっぱいでこれ以上駐車できる余地のないこと。
まんじゅ【万寿】
[詩経「万寿無疆」]平安中期、後一条天皇朝の年号。甲子革令により治安4年7月13日(1024年8月19日)改元、万寿5年7月25日(1028年8月18日)長元に改元。
まん‐じゅ【満珠】
(→)「しおみちのたま」に同じ。太平記39「竜宮城に宝とする干珠・―を借り召さる」↔干珠
まんしゅ‐いん【曼殊院】‥ヰン
(マンジュインとも)京都市左京区にある天台宗の門跡寺院。もと北野天満宮の別当寺。延暦(782〜806)年間最澄の創めた比叡山中の一宇に始まり、15世紀から宮門跡となり竹内門跡と称す。1656年(明暦2)現在地に移転。黄不動尊絵像や古典籍などを所蔵。
まんしゅう【満州・満洲】‥シウ
中国の東北一帯の俗称。もと民族名。行政上は東北三省(遼寧・吉林・黒竜江)と内モンゴル自治区の一部にわたり、中国では東北と呼ぶ。
⇒まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】
⇒まんしゅう‐ご【満州語】
⇒まんしゅう‐こく【満州国】
⇒まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】
⇒まんしゅう‐じへん【満州事変】
⇒まんしゅう‐ぞく【満州族】
⇒まんしゅう‐もじ【満州文字】
まん‐じゅう【饅頭】‥ヂユウ
(ジュウは唐音)
①小麦粉・米粉・そば粉などでつくった皮で餡あんを包んで蒸して作る菓子。暦応(1338〜1342)年間、中国から帰化した林浄因が奈良で始めた奈良饅頭を始めとする。狂言、栗焼「―羊羹などではござりませぬか」
②饅頭金物の略。
⇒まんじゅう‐がさ【饅頭笠】
⇒まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】
⇒まんじゅう‐がに【饅頭蟹】
⇒まんじゅう‐じころ【饅頭錏】
⇒まんじゅう‐はだ【饅頭肌】
⇒まんじゅう‐ぼん【饅頭本】
まんじゅう‐がさ【饅頭笠】‥ヂユウ‥
頂はまるく浅く、饅頭を横に半分に切ったような形につくったかぶり笠。
饅頭笠
 ⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】‥ヂユウ‥
扉に打つ半球形の装飾金物。元来は釘の頭を隠すもの。乳金物ちかなもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐がに【饅頭蟹】‥ヂユウ‥
オウギガニ科マンジュウガニ属のカニの総称。甲は左右に長い楕円形で、歩脚は短く、全体にずんぐりした形。その一種スベスベマンジュウガニは房総半島以南の磯に普通。食うと有毒。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】‥シウ‥リウカウ
古来中国東北部(満州)に興亡した諸族および風俗・地理などに関する地誌。20巻。清の阿桂・于敏中らが奉勅撰。1778年成る。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ご【満州語】‥シウ‥
満州族の用いる言語。アルタイ語族ツングース語派に属する。特に17世紀後半以降、清朝の興隆とともに中国語の影響を受け、語彙および文法の面で変化。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐こく【満州国】‥シウ‥
日本が満州事変により、中国の東北三省および東部内モンゴル(熱河省)をもって作りあげた傀儡かいらい国家。1932年、もと清の宣統帝であった溥儀ふぎを執政として建国、34年に溥儀が皇帝に即位。首都は新京(長春)。45年日本の敗戦に伴い消滅。中国では偽満州国と称。
満州国建国
提供:NHK
→資料:日満議定書
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】‥シウ‥ケフ‥クワイ
満州国の住民を組織し動員するための官製団体。満州国や関東軍の高官を幹部として1932年(昭和7)発足。当初は宣撫工作を主としたが、36年住民動員組織に改組。満州国崩壊とともに解体。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうこわい【饅頭怖い】‥ヂユウコハイ
落語。若い連中が自分の怖いものを白状し合っていると、仲間内の嫌われ者が「饅頭が怖い」というので、皆で饅頭を与えるが、すっかり食われてしまう話。
まんじゅう‐じころ【饅頭錏】‥ヂユウ‥
兜かぶとの錏しころの一種。笠錏や日根野ひねの錏に対して、一の板から裾板すそいたまで勾配に曲線をつけて縅おどし下げたもの。江戸時代の復古的作品に多い。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐じへん【満州事変】‥シウ‥
1931年(昭和6)9月18日、奉天(今の瀋陽)北方の柳条湖の鉄道爆破事件を契機とする日本の中国東北侵略戦争。十五年戦争の第1段階。翌32年には、満州国を樹立。華北分離工作を経て、日中戦争へ発展。→柳条湖事件。
現場検証するリットン調査団
提供:毎日新聞社
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】‥ヂユウ‥
扉に打つ半球形の装飾金物。元来は釘の頭を隠すもの。乳金物ちかなもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐がに【饅頭蟹】‥ヂユウ‥
オウギガニ科マンジュウガニ属のカニの総称。甲は左右に長い楕円形で、歩脚は短く、全体にずんぐりした形。その一種スベスベマンジュウガニは房総半島以南の磯に普通。食うと有毒。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】‥シウ‥リウカウ
古来中国東北部(満州)に興亡した諸族および風俗・地理などに関する地誌。20巻。清の阿桂・于敏中らが奉勅撰。1778年成る。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ご【満州語】‥シウ‥
満州族の用いる言語。アルタイ語族ツングース語派に属する。特に17世紀後半以降、清朝の興隆とともに中国語の影響を受け、語彙および文法の面で変化。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐こく【満州国】‥シウ‥
日本が満州事変により、中国の東北三省および東部内モンゴル(熱河省)をもって作りあげた傀儡かいらい国家。1932年、もと清の宣統帝であった溥儀ふぎを執政として建国、34年に溥儀が皇帝に即位。首都は新京(長春)。45年日本の敗戦に伴い消滅。中国では偽満州国と称。
満州国建国
提供:NHK
→資料:日満議定書
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】‥シウ‥ケフ‥クワイ
満州国の住民を組織し動員するための官製団体。満州国や関東軍の高官を幹部として1932年(昭和7)発足。当初は宣撫工作を主としたが、36年住民動員組織に改組。満州国崩壊とともに解体。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうこわい【饅頭怖い】‥ヂユウコハイ
落語。若い連中が自分の怖いものを白状し合っていると、仲間内の嫌われ者が「饅頭が怖い」というので、皆で饅頭を与えるが、すっかり食われてしまう話。
まんじゅう‐じころ【饅頭錏】‥ヂユウ‥
兜かぶとの錏しころの一種。笠錏や日根野ひねの錏に対して、一の板から裾板すそいたまで勾配に曲線をつけて縅おどし下げたもの。江戸時代の復古的作品に多い。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐じへん【満州事変】‥シウ‥
1931年(昭和6)9月18日、奉天(今の瀋陽)北方の柳条湖の鉄道爆破事件を契機とする日本の中国東北侵略戦争。十五年戦争の第1段階。翌32年には、満州国を樹立。華北分離工作を経て、日中戦争へ発展。→柳条湖事件。
現場検証するリットン調査団
提供:毎日新聞社
 満州事変
提供:NHK
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ぞく【満州族】‥シウ‥
中国東北地方の東北部から南部一帯にかけて分布した民族。南方ツングース系で、渤海国を建てた靺鞨まっかつ、金を建てた女真、清を建てた女直はともにこれに属する。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅう‐はだ【饅頭肌】‥ヂユウ‥
饅頭のように滑らかにつやつやした肌。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐ぼん【饅頭本】‥ヂユウ‥
亡くなった人の遺した文章やその人を偲ぶ文章などを本にして、近親やゆかりの人々に配るもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐もじ【満州文字】‥シウ‥
満州語を表記するための文字。モンゴル文字を基本とし、点または圏を加えて満州語の音を示すに至ったもので、別にまた、字体を定めて中国語をも記し得るようになっている。1599年清の太祖ヌルハチの制定に始まり、太宗の時に成った。満州字。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうや‐ぼん【饅頭屋本】‥ヂユウ‥
室町末期、奈良の歌人・歌学者で菓子商(塩瀬の祖)の饅頭屋宗二(林逸1498〜1581)が刊行した本。饅頭屋本節用集のほか、漢籍がある。
まんじゅう‐らく【万秋楽】‥ジウ‥
⇒まんじゅらく
まんしゅうり【満洲里】‥シウ‥
⇒マンチュリ
まんじゅ‐ぎく【万寿菊】
マリーゴールドの和名。
まんじゅ‐さん【万寿山】
中国北京、頤和園いわえんにある山丘。清朝の離宮が残り、山水・楼閣の美に富む。
まんじゅ‐じ【万寿寺】
京都市東山区の東福寺内にある臨済宗の寺。京都五山の一つ。1097年(承徳1)白河上皇の御願により建立され六条御堂と称す。正嘉(1257〜1259)年中円爾えんにに帰依して禅宗となり、万寿禅寺と改称。天正(1573〜1592)年中現在地に移る。
まんじゅしゃげ【曼殊沙華・曼珠沙華】
①〔仏〕(梵語mañjūṣaka)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を柔軟にするという。
②〔植〕ヒガンバナの別称。〈[季]秋〉。日葡辞書「マンジュシャケ」
まんじゅ‐らく【万秋楽】
雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの大曲。六人または四人舞。736年(天平8)天竺僧仙那・林邑僧仏哲が来日して伝えたともいう。慈尊楽。まんずらく。まんじゅうらく。
まん‐しょ【万庶】
すべての人民。ばんしょ。
まん‐しょう【満床】‥シヤウ
病院で、入院患者用のベッドがすべてふさがっていること。
まん‐じょう【満場】‥ヂヤウ
その場所にいる人全体。会場全体。「―の諸君」
⇒まんじょう‐いっち【満場一致】
まんじょう‐いっち【満場一致】‥ヂヤウ‥
その場にいる全員の意見が一致すること。「―で可決する」
⇒まん‐じょう【満場】
まんじょう‐かんぼ【満城漢墓】‥ジヤウ‥
中国河北省満城県にある前漢代の墓。中山国初代の中山靖王劉勝とその妻の墓。遺骸を包んだ金縷玉衣きんるぎょくいなどで有名。
マンジョーカ【manjoca ポルトガル】
キャッサバのこと。ブラジルの日本移民が沖縄などにこの名で持ち帰った。
マンション【mansion】
(大邸宅の意)中高層の集合住宅。1960年代後半から急速に普及。
⇒マンション‐ほう【マンション法】
マンション‐ほう【マンション法】‥ハフ
建物区分所有法の通称。マンションの権利関係・管理・集会・建替えなどについて定める。
⇒マンション【mansion】
まんじり
〔副〕
①(多く、打消の語を伴う)ちょっと眠るさま。まどろむさま。「―ともせず一夜を明かす」
②じっと。まじまじと。「―と見る」
まん・じる【慢じる】
〔自上一〕
(→)「慢ずる」に同じ。
まん‐しん【満身】
からだじゅう。全身。「―の力をこめる」
⇒まんしん‐そうい【満身創痍】
まん‐しん【慢心】
おごりたかぶること。また、その心。
まんしん‐そうい【満身創痍】‥サウ‥
全身傷だらけであること。転じて、手ひどく痛めつけられていること。
⇒まん‐しん【満身】
まん・ず【満ず】
〔自サ変〕
①願い事が叶う。古今著聞集13「我願すでに―・ずとてぞ…をどりおりさせ給ひける」
②期限が満ちる。期限が来る。平家物語1「七日に―・ずる夜」
まん‐すい【満水】
水がいっぱいになること。河水などが増水して、あふれんばかりになること。
まん‐すう【満数】
定数に達すること。「―次第締切」
マンズー【Giacomo Manzù】
イタリア、現代具象派彫刻の代表者。素描家としても著名。(1908〜1991)
まん‐すじ【万筋】‥スヂ
2本ずつ色のちがった経糸たていとを配列した竪縞たてじま。→縞織物(図)
マンスフィールド【Katherine Mansfield】
イギリスの女性作家。ニュー‐ジーランド出身。繊細な感覚と優雅な文体で多くの短編小説を書いた。代表作「園遊会」。(1888〜1923)
マンスリー【monthly】
(「月ごと」の意)月刊雑誌。
まん・ずる【慢ずる】
〔自サ変〕[文]慢ず(サ変)
①あなどる。軽んじる。天草本伊曾保物語「この難に遇ふこと最も道理ぢや、…仇となるものを―・じた故ぢや」
②自慢する。ほこる。慢心する。日葡辞書「ワレ(我)トミ(身)ヲマンゼザレ」
まん‐せい【慢性】
①症状が激しくなく経過の長びくような病気の性質。↔急性。
②比喩的に、好ましくない現象・状態が長く続くこと。「―のインフレ」
⇒まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】
⇒まんせい‐しっかん【慢性疾患】
⇒まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
⇒まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】
⇒まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】
まん‐せい【蔓生】
茎が蔓つるとなって生えること。つるだち。
まん‐せい【蔓菁】
〔植〕カブラの漢名。
まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】‥シヤウ
感染してから発症するまでの時間が長く緩慢な経過をとる伝染性疾患の総称。エイズ・結核・ハンセン病など。慢性伝染病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせい‐しっかん【慢性疾患】‥クワン
徐々に発病し、または急性期から移行して長期間経過する病気。慢性病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんぜい‐しゃみ【満誓沙弥】
沙弥満誓さみまんぜいのこと。
まんせい‐しょくぶつ【蔓性植物】
(→)蔓つる植物に同じ。
まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
毒物が長時間持続的に作用することによって徐々に生理的機能に異常を生じること。麻薬など一部の薬品やアルコール飲料などの嗜好品では耐性と依存性を招く。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】‥ラウシヤウ‥
(chronic fatigue syndrome)健康に生活していた人に突然発症し、極度の疲労感が長く続いて活動能力が低下する状態。ウイルス病原説があるが原因不明。CFS
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】‥クワン
慢性の気道・肺の炎症のために肺胞組織が破壊され、呼吸困難・閉塞性換気障害を起こす病態。空気中の有害物質によると考えられ、患者は喫煙者が大多数を占める。
⇒まん‐せい【慢性】
マンセー【万歳】
(朝鮮語manse)祝いの意を表す語。ばんざい。
まん‐せき【満席】
乗物・劇場などで、すべての客席がふさがること。満員。
マンセル‐ひょうしょくけい【マンセル表色系】‥ヘウ‥
アメリカの画家マンセル(A. H. Munsell1858〜1918)が考案した色の表示体系。個々の色を色相・明度・彩度の3次元座標軸内の点として記述する。
まん‐せん【満線】
駅構内の線路に列車が停車中で、後続列車の入れない状態。
まん‐ぜん【万善】
あらゆる善行・善事。
まん‐ぜん【漫然】
心にとめて深く考えず、またはっきりとした目的や意識を持たないさま。とりとめのないさま。しまりのないさま。「―と日を過ごす」
まん‐そう【万草】‥サウ
よろずの草。すべての草。
まん‐そう【蔓草】‥サウ
茎が蔓つるとなって生える草。つるくさ。
まんぞう‐くじ【万雑公事】‥ザフ‥
荘園における種々の雑税や夫役。狂言、餅酒「―を御免なさるる」
マンゾーニ【Alessandro Manzoni】
イタリアのロマン主義の小説家・劇作家。大部の歴史小説「いいなずけ」で名声を得、晩年は歴史や言語への省察に傾いた。他に悲劇「カルマニョーラ伯爵」「アデルキ」など。(1785〜1873)
まん‐ぞく【満足】
①十分なこと。完全なこと。「挨拶も―にできない」
②望みが満ち足りて不平のないこと。今昔物語集6「霊幹りょうかん、其の上に坐して願ふ所―しぬと」。「予は―じゃ」「好奇心を―させる」
③〔数〕方程式の未知数に適当なある値を代入した時、等式が成立すれば、この値はこの方程式を満足する、あるいは満たすという。
⇒まんぞく‐かん【満足感】
まんぞく‐かん【満足感】
満ち足りたという感じ。
⇒まん‐ぞく【満足】
まんた【茨田】
河内国(大阪府)の旧郡名。
⇒まんた‐の‐いけ【茨田の池】
⇒まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
マンタ【manta】
イトマキエイ科の海産の軟骨魚。オニイトマキエイの別称。体盤長5メートル以上に達するものもある。頭の前端に一対の耳状の頭びれがある。全世界の熱帯海域に分布。マンタエイ。
マンタ
満州事変
提供:NHK
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ぞく【満州族】‥シウ‥
中国東北地方の東北部から南部一帯にかけて分布した民族。南方ツングース系で、渤海国を建てた靺鞨まっかつ、金を建てた女真、清を建てた女直はともにこれに属する。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅう‐はだ【饅頭肌】‥ヂユウ‥
饅頭のように滑らかにつやつやした肌。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐ぼん【饅頭本】‥ヂユウ‥
亡くなった人の遺した文章やその人を偲ぶ文章などを本にして、近親やゆかりの人々に配るもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐もじ【満州文字】‥シウ‥
満州語を表記するための文字。モンゴル文字を基本とし、点または圏を加えて満州語の音を示すに至ったもので、別にまた、字体を定めて中国語をも記し得るようになっている。1599年清の太祖ヌルハチの制定に始まり、太宗の時に成った。満州字。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうや‐ぼん【饅頭屋本】‥ヂユウ‥
室町末期、奈良の歌人・歌学者で菓子商(塩瀬の祖)の饅頭屋宗二(林逸1498〜1581)が刊行した本。饅頭屋本節用集のほか、漢籍がある。
まんじゅう‐らく【万秋楽】‥ジウ‥
⇒まんじゅらく
まんしゅうり【満洲里】‥シウ‥
⇒マンチュリ
まんじゅ‐ぎく【万寿菊】
マリーゴールドの和名。
まんじゅ‐さん【万寿山】
中国北京、頤和園いわえんにある山丘。清朝の離宮が残り、山水・楼閣の美に富む。
まんじゅ‐じ【万寿寺】
京都市東山区の東福寺内にある臨済宗の寺。京都五山の一つ。1097年(承徳1)白河上皇の御願により建立され六条御堂と称す。正嘉(1257〜1259)年中円爾えんにに帰依して禅宗となり、万寿禅寺と改称。天正(1573〜1592)年中現在地に移る。
まんじゅしゃげ【曼殊沙華・曼珠沙華】
①〔仏〕(梵語mañjūṣaka)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を柔軟にするという。
②〔植〕ヒガンバナの別称。〈[季]秋〉。日葡辞書「マンジュシャケ」
まんじゅ‐らく【万秋楽】
雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの大曲。六人または四人舞。736年(天平8)天竺僧仙那・林邑僧仏哲が来日して伝えたともいう。慈尊楽。まんずらく。まんじゅうらく。
まん‐しょ【万庶】
すべての人民。ばんしょ。
まん‐しょう【満床】‥シヤウ
病院で、入院患者用のベッドがすべてふさがっていること。
まん‐じょう【満場】‥ヂヤウ
その場所にいる人全体。会場全体。「―の諸君」
⇒まんじょう‐いっち【満場一致】
まんじょう‐いっち【満場一致】‥ヂヤウ‥
その場にいる全員の意見が一致すること。「―で可決する」
⇒まん‐じょう【満場】
まんじょう‐かんぼ【満城漢墓】‥ジヤウ‥
中国河北省満城県にある前漢代の墓。中山国初代の中山靖王劉勝とその妻の墓。遺骸を包んだ金縷玉衣きんるぎょくいなどで有名。
マンジョーカ【manjoca ポルトガル】
キャッサバのこと。ブラジルの日本移民が沖縄などにこの名で持ち帰った。
マンション【mansion】
(大邸宅の意)中高層の集合住宅。1960年代後半から急速に普及。
⇒マンション‐ほう【マンション法】
マンション‐ほう【マンション法】‥ハフ
建物区分所有法の通称。マンションの権利関係・管理・集会・建替えなどについて定める。
⇒マンション【mansion】
まんじり
〔副〕
①(多く、打消の語を伴う)ちょっと眠るさま。まどろむさま。「―ともせず一夜を明かす」
②じっと。まじまじと。「―と見る」
まん・じる【慢じる】
〔自上一〕
(→)「慢ずる」に同じ。
まん‐しん【満身】
からだじゅう。全身。「―の力をこめる」
⇒まんしん‐そうい【満身創痍】
まん‐しん【慢心】
おごりたかぶること。また、その心。
まんしん‐そうい【満身創痍】‥サウ‥
全身傷だらけであること。転じて、手ひどく痛めつけられていること。
⇒まん‐しん【満身】
まん・ず【満ず】
〔自サ変〕
①願い事が叶う。古今著聞集13「我願すでに―・ずとてぞ…をどりおりさせ給ひける」
②期限が満ちる。期限が来る。平家物語1「七日に―・ずる夜」
まん‐すい【満水】
水がいっぱいになること。河水などが増水して、あふれんばかりになること。
まん‐すう【満数】
定数に達すること。「―次第締切」
マンズー【Giacomo Manzù】
イタリア、現代具象派彫刻の代表者。素描家としても著名。(1908〜1991)
まん‐すじ【万筋】‥スヂ
2本ずつ色のちがった経糸たていとを配列した竪縞たてじま。→縞織物(図)
マンスフィールド【Katherine Mansfield】
イギリスの女性作家。ニュー‐ジーランド出身。繊細な感覚と優雅な文体で多くの短編小説を書いた。代表作「園遊会」。(1888〜1923)
マンスリー【monthly】
(「月ごと」の意)月刊雑誌。
まん・ずる【慢ずる】
〔自サ変〕[文]慢ず(サ変)
①あなどる。軽んじる。天草本伊曾保物語「この難に遇ふこと最も道理ぢや、…仇となるものを―・じた故ぢや」
②自慢する。ほこる。慢心する。日葡辞書「ワレ(我)トミ(身)ヲマンゼザレ」
まん‐せい【慢性】
①症状が激しくなく経過の長びくような病気の性質。↔急性。
②比喩的に、好ましくない現象・状態が長く続くこと。「―のインフレ」
⇒まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】
⇒まんせい‐しっかん【慢性疾患】
⇒まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
⇒まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】
⇒まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】
まん‐せい【蔓生】
茎が蔓つるとなって生えること。つるだち。
まん‐せい【蔓菁】
〔植〕カブラの漢名。
まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】‥シヤウ
感染してから発症するまでの時間が長く緩慢な経過をとる伝染性疾患の総称。エイズ・結核・ハンセン病など。慢性伝染病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせい‐しっかん【慢性疾患】‥クワン
徐々に発病し、または急性期から移行して長期間経過する病気。慢性病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんぜい‐しゃみ【満誓沙弥】
沙弥満誓さみまんぜいのこと。
まんせい‐しょくぶつ【蔓性植物】
(→)蔓つる植物に同じ。
まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
毒物が長時間持続的に作用することによって徐々に生理的機能に異常を生じること。麻薬など一部の薬品やアルコール飲料などの嗜好品では耐性と依存性を招く。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】‥ラウシヤウ‥
(chronic fatigue syndrome)健康に生活していた人に突然発症し、極度の疲労感が長く続いて活動能力が低下する状態。ウイルス病原説があるが原因不明。CFS
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】‥クワン
慢性の気道・肺の炎症のために肺胞組織が破壊され、呼吸困難・閉塞性換気障害を起こす病態。空気中の有害物質によると考えられ、患者は喫煙者が大多数を占める。
⇒まん‐せい【慢性】
マンセー【万歳】
(朝鮮語manse)祝いの意を表す語。ばんざい。
まん‐せき【満席】
乗物・劇場などで、すべての客席がふさがること。満員。
マンセル‐ひょうしょくけい【マンセル表色系】‥ヘウ‥
アメリカの画家マンセル(A. H. Munsell1858〜1918)が考案した色の表示体系。個々の色を色相・明度・彩度の3次元座標軸内の点として記述する。
まん‐せん【満線】
駅構内の線路に列車が停車中で、後続列車の入れない状態。
まん‐ぜん【万善】
あらゆる善行・善事。
まん‐ぜん【漫然】
心にとめて深く考えず、またはっきりとした目的や意識を持たないさま。とりとめのないさま。しまりのないさま。「―と日を過ごす」
まん‐そう【万草】‥サウ
よろずの草。すべての草。
まん‐そう【蔓草】‥サウ
茎が蔓つるとなって生える草。つるくさ。
まんぞう‐くじ【万雑公事】‥ザフ‥
荘園における種々の雑税や夫役。狂言、餅酒「―を御免なさるる」
マンゾーニ【Alessandro Manzoni】
イタリアのロマン主義の小説家・劇作家。大部の歴史小説「いいなずけ」で名声を得、晩年は歴史や言語への省察に傾いた。他に悲劇「カルマニョーラ伯爵」「アデルキ」など。(1785〜1873)
まん‐ぞく【満足】
①十分なこと。完全なこと。「挨拶も―にできない」
②望みが満ち足りて不平のないこと。今昔物語集6「霊幹りょうかん、其の上に坐して願ふ所―しぬと」。「予は―じゃ」「好奇心を―させる」
③〔数〕方程式の未知数に適当なある値を代入した時、等式が成立すれば、この値はこの方程式を満足する、あるいは満たすという。
⇒まんぞく‐かん【満足感】
まんぞく‐かん【満足感】
満ち足りたという感じ。
⇒まん‐ぞく【満足】
まんた【茨田】
河内国(大阪府)の旧郡名。
⇒まんた‐の‐いけ【茨田の池】
⇒まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
マンタ【manta】
イトマキエイ科の海産の軟骨魚。オニイトマキエイの別称。体盤長5メートル以上に達するものもある。頭の前端に一対の耳状の頭びれがある。全世界の熱帯海域に分布。マンタエイ。
マンタ
 マンタ
提供:NHK
まん‐だい【万代】
⇒ばんだい
まんだいわかしゅう【万代和歌集】‥シフ
私撰集。20巻6冊。3820首余を収める。撰者は初撰本は藤原光俊(真観)、精撰本は藤原(衣笠)家良か。成立は初撰本1248年(宝治2)、精撰本は1249年(建長1)か。
まんた‐の‐いけ【茨田の池】
茨田の地にあった池。今の寝屋川市の西部に当たる。
⇒まんた【茨田】
まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
古代、淀川の下流の左岸、茨田郡の側にあった堤防。伝承では仁徳天皇時代の築堤という。
⇒まんた【茨田】
マンダメント【mandamento ポルトガル】
(キリシタン用語)戒律。おきて。マダメント。どちりなきりしたん「―とは御掟の事也」→十戒2
まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
〔仏〕(梵語maṇḍala 輪円具足・道場・壇・本質などと訳す)諸尊の悟りの世界を象徴するものとして、一定の方式に基づいて、諸仏・菩薩および神々を網羅して描いた図。四種曼荼羅・両界曼荼羅など多くの種類がある。もともと密教のものであるが、浄土曼荼羅や垂迹すいじゃく曼荼羅、日蓮宗の十界じっかい曼荼羅のように、他にも転用される。おまんだら。
両界曼荼羅
マンタ
提供:NHK
まん‐だい【万代】
⇒ばんだい
まんだいわかしゅう【万代和歌集】‥シフ
私撰集。20巻6冊。3820首余を収める。撰者は初撰本は藤原光俊(真観)、精撰本は藤原(衣笠)家良か。成立は初撰本1248年(宝治2)、精撰本は1249年(建長1)か。
まんた‐の‐いけ【茨田の池】
茨田の地にあった池。今の寝屋川市の西部に当たる。
⇒まんた【茨田】
まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
古代、淀川の下流の左岸、茨田郡の側にあった堤防。伝承では仁徳天皇時代の築堤という。
⇒まんた【茨田】
マンダメント【mandamento ポルトガル】
(キリシタン用語)戒律。おきて。マダメント。どちりなきりしたん「―とは御掟の事也」→十戒2
まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
〔仏〕(梵語maṇḍala 輪円具足・道場・壇・本質などと訳す)諸尊の悟りの世界を象徴するものとして、一定の方式に基づいて、諸仏・菩薩および神々を網羅して描いた図。四種曼荼羅・両界曼荼羅など多くの種類がある。もともと密教のものであるが、浄土曼荼羅や垂迹すいじゃく曼荼羅、日蓮宗の十界じっかい曼荼羅のように、他にも転用される。おまんだら。
両界曼荼羅
 中台八葉院
胎蔵曼荼羅
金剛界曼荼羅
⇒まんだら‐く【曼荼羅供】
⇒まんだら‐どう【曼荼羅堂】
まんだら‐く【曼荼羅供】
密教で曼荼羅を作製し供養すること。また、その法会ほうえ。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
まんだらげ【曼陀羅華】
①〔仏〕(梵語māndārava)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を喜ばせるという。
②〔植〕チョウセンアサガオ・ムラサキケマンの別称。
まんだら‐どう【曼荼羅堂】‥ダウ
(いわゆる当麻たいま曼荼羅を本尊として祀るからいう)当麻寺本堂の別名。平安初期の創建で1161年(応保1)ほぼ現在の形に再建。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
マンタリテ【mentalité フランス】
心性。フランスのアナール学派が用いた社会史の基本概念で、ある時代のある社会の成員に共有されている、ものの感じ方や思考様式。
マンダリン【mandarin】
①中国、清朝の高等官吏。
②(Mandarin)中国の公用語。官話。
③中国原産の蜜柑。
⇒マンダリン‐カラー【mandarin collar】
マンダリン‐カラー【mandarin collar】
(清朝の官吏の服に用いたからいう)スタンド‐カラーの一種。首に沿った幅の狭い立ち襟の総称。チャイニーズ‐カラー。
⇒マンダリン【mandarin】
マンダレー【Mandalay】
ミャンマーの中央部にある古都。1857年、ミンドン王が都城を築き、翌年完成。旧跡が多い。人口53万3千(1983)。
まん‐タン【満タン】
(タンはタンクの略)燃料や水などが容器いっぱいに入っていること。満杯。
まん‐だん【漫談】
①とりとめもない話。
②演芸の一種。滑稽を主とし、世相・人情の批評・諷刺をも取り入れた話術。1924年(大正13)頃から徳川夢声・大辻司郎らが始めた。
まん‐ち【満地】
地上一面。
まん‐ち【満池】
水が池いっぱいに満ちていること。
マンチェスター【Manchester】
イギリス、イングランド北西部のランカシャー地方にある商工業都市。産業革命の発祥地で、かつては綿工業の中心地。人口43万1千(1996)。
⇒マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
⇒マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
「ガーディアン」参照。
⇒マンチェスター【Manchester】
マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
1838年頃から、マンチェスターを中心に、コブデン・ブライトら、穀物法廃止運動を推進し自由貿易思想の普及に努力した人々とその流派。
⇒マンチェスター【Manchester】
まん‐ちゃく【瞞着】
あざむくこと。ごまかすこと。人の目をくらますこと。「世人を―する」
まん‐ちゅういん【満中陰】
〔仏〕(→)四十九日しじゅうくにち2に同じ。
マンチュリ【満洲里】
(Manzhouli)中国、内モンゴル自治区の北東部にある都市。ロシアとの国境付近に当たり、中国東北部と外モンゴルを結ぶ重要地点。人口18万1千(2000)。
まん‐ちょう【満潮】‥テウ
潮が満ちて海水面が最高に達した状態。みちしお。↔干潮
まんちょうほう【万朝報】‥テウ‥
⇒よろずちょうほう
マン‐ツー‐マン【man-to-man】
一人に一人が応対すること。1対1。「―で指導する」
⇒マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
球技などで、相手側競技者の誰には味方の誰が当たるというように、あらかじめ守備の責任分担をきめて行う防御法。対人防御法。↔ゾーン‐ディフェンス
⇒マン‐ツー‐マン【man-to-man】
まん‐てい【満廷】
朝廷または法廷などに人が満ちること。また、そこに列するすべての人。
まん‐てい【満庭】
庭に満ちること。また、庭全体。
マンテイカ【manteiga ポルトガル】
猪などの脂肪。膏薬に加え、また、器械の錆さびどめに用いる。豬膏ちょこう。
マンデー【mandi マレー】
インドネシア地方の水浴。
マンテーニャ【Andrea Mantegna】
イタリア、ルネサンスの画家。パドヴァ公の宮廷画家となる。作「死せるキリスト」など。(1431〜1506)
「死せるキリスト」
提供:Maxppp/APL
中台八葉院
胎蔵曼荼羅
金剛界曼荼羅
⇒まんだら‐く【曼荼羅供】
⇒まんだら‐どう【曼荼羅堂】
まんだら‐く【曼荼羅供】
密教で曼荼羅を作製し供養すること。また、その法会ほうえ。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
まんだらげ【曼陀羅華】
①〔仏〕(梵語māndārava)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を喜ばせるという。
②〔植〕チョウセンアサガオ・ムラサキケマンの別称。
まんだら‐どう【曼荼羅堂】‥ダウ
(いわゆる当麻たいま曼荼羅を本尊として祀るからいう)当麻寺本堂の別名。平安初期の創建で1161年(応保1)ほぼ現在の形に再建。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
マンタリテ【mentalité フランス】
心性。フランスのアナール学派が用いた社会史の基本概念で、ある時代のある社会の成員に共有されている、ものの感じ方や思考様式。
マンダリン【mandarin】
①中国、清朝の高等官吏。
②(Mandarin)中国の公用語。官話。
③中国原産の蜜柑。
⇒マンダリン‐カラー【mandarin collar】
マンダリン‐カラー【mandarin collar】
(清朝の官吏の服に用いたからいう)スタンド‐カラーの一種。首に沿った幅の狭い立ち襟の総称。チャイニーズ‐カラー。
⇒マンダリン【mandarin】
マンダレー【Mandalay】
ミャンマーの中央部にある古都。1857年、ミンドン王が都城を築き、翌年完成。旧跡が多い。人口53万3千(1983)。
まん‐タン【満タン】
(タンはタンクの略)燃料や水などが容器いっぱいに入っていること。満杯。
まん‐だん【漫談】
①とりとめもない話。
②演芸の一種。滑稽を主とし、世相・人情の批評・諷刺をも取り入れた話術。1924年(大正13)頃から徳川夢声・大辻司郎らが始めた。
まん‐ち【満地】
地上一面。
まん‐ち【満池】
水が池いっぱいに満ちていること。
マンチェスター【Manchester】
イギリス、イングランド北西部のランカシャー地方にある商工業都市。産業革命の発祥地で、かつては綿工業の中心地。人口43万1千(1996)。
⇒マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
⇒マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
「ガーディアン」参照。
⇒マンチェスター【Manchester】
マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
1838年頃から、マンチェスターを中心に、コブデン・ブライトら、穀物法廃止運動を推進し自由貿易思想の普及に努力した人々とその流派。
⇒マンチェスター【Manchester】
まん‐ちゃく【瞞着】
あざむくこと。ごまかすこと。人の目をくらますこと。「世人を―する」
まん‐ちゅういん【満中陰】
〔仏〕(→)四十九日しじゅうくにち2に同じ。
マンチュリ【満洲里】
(Manzhouli)中国、内モンゴル自治区の北東部にある都市。ロシアとの国境付近に当たり、中国東北部と外モンゴルを結ぶ重要地点。人口18万1千(2000)。
まん‐ちょう【満潮】‥テウ
潮が満ちて海水面が最高に達した状態。みちしお。↔干潮
まんちょうほう【万朝報】‥テウ‥
⇒よろずちょうほう
マン‐ツー‐マン【man-to-man】
一人に一人が応対すること。1対1。「―で指導する」
⇒マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
球技などで、相手側競技者の誰には味方の誰が当たるというように、あらかじめ守備の責任分担をきめて行う防御法。対人防御法。↔ゾーン‐ディフェンス
⇒マン‐ツー‐マン【man-to-man】
まん‐てい【満廷】
朝廷または法廷などに人が満ちること。また、そこに列するすべての人。
まん‐てい【満庭】
庭に満ちること。また、庭全体。
マンテイカ【manteiga ポルトガル】
猪などの脂肪。膏薬に加え、また、器械の錆さびどめに用いる。豬膏ちょこう。
マンデー【mandi マレー】
インドネシア地方の水浴。
マンテーニャ【Andrea Mantegna】
イタリア、ルネサンスの画家。パドヴァ公の宮廷画家となる。作「死せるキリスト」など。(1431〜1506)
「死せるキリスト」
提供:Maxppp/APL
 まん‐てつ【満鉄】
南満州鉄道(株式会社)の略称。
⇒まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】
まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】‥テウ‥
満鉄が設置した調査研究機関。1907年(明治40)発足。中国・ソ連などの総合的調査・研究、満州国・華北の経済開発計画の立案などを行なった。日中戦争時には2000人をこえたが、太平洋戦争時の左翼グループ検挙(満鉄事件)で打撃をうけ、敗戦により解体。
⇒まん‐てつ【満鉄】
マンデラ【Nelson Mandela】
南アフリカ共和国の政治家。反アパルトヘイト運動の指導者。27年間の獄中生活ののち1990年釈放。94年、初の全人種による選挙で大統領に当選。ノーベル賞。(1918〜)
マンデラ
提供:ullstein bild/APL
まん‐てつ【満鉄】
南満州鉄道(株式会社)の略称。
⇒まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】
まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】‥テウ‥
満鉄が設置した調査研究機関。1907年(明治40)発足。中国・ソ連などの総合的調査・研究、満州国・華北の経済開発計画の立案などを行なった。日中戦争時には2000人をこえたが、太平洋戦争時の左翼グループ検挙(満鉄事件)で打撃をうけ、敗戦により解体。
⇒まん‐てつ【満鉄】
マンデラ【Nelson Mandela】
南アフリカ共和国の政治家。反アパルトヘイト運動の指導者。27年間の獄中生活ののち1990年釈放。94年、初の全人種による選挙で大統領に当選。ノーベル賞。(1918〜)
マンデラ
提供:ullstein bild/APL
 マンデリシターム【Osip E. Mandel'shtam】
ロシア(ソ連)の詩人。ユダヤ系。明晰な美を追求するアクメイズムの詩人として出発し、彫琢された形式と音楽性で際立った哲学的抒情詩を書く。スターリン諷刺の詩ゆえに逮捕され、獄死。詩集「石」「トリスチア」など。(1891〜1938)
マンデリン【Mandheling】
①インドネシア、スマトラ島北部の地方。
②1で産するアラビカ種のコーヒー。
マンテル【mantel オランダ】
マント。外套。
マンテルピース【mantelpiece】
⇒マントルピース
まん‐てん【万天】
天全体。また、天下四方。
まん‐てん【満天】
空全体。一天。「―の星」
⇒まんてん‐せい【満天星】
まん‐てん【満点】
規定された点の最高。また、それに達すること。百パーセントの成績。転じて、申し分のないこと。「サービス―」
まん‐てんか【満天下】
天下全体。全世界。
まんてん‐せい【満天星】
〔植〕
①ハクチョウゲ(白丁花)の別称。
②ドウダンツツジの漢名。
⇒まん‐てん【満天】
まん‐と【満都】
みやこのうち全体。
マント【manteau フランス】
ゆったりとした外套。日本では特に袖なしのものをいう。幕末、軍隊用としてとり入れられ、一般にも広く用いられるようになった。
⇒マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
⇒マント‐ひひ【マント狒狒】
まん‐と
〔副〕
(江戸後期の流行語)たくさん。どっさり。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「市に売り出す手桶を―拵へんと手間取りを多く入れて」
まん‐ど【万度・万灯】
四角い箱に、某社御祭礼などと大書、その下に町名を、また氏子中・子供中などと書き、これに灯火をともし、また花などを飾って祭礼に出すもの。まんどう。
⇒まんど‐ばらい【万度祓】
マン‐とう【マン島】‥タウ
(Isle of Man)イギリス、グレート‐ブリテン島と北アイルランドとの間のアイリッシュ海にある島。ケルト文化地域で、独自の法律・議会を有する。中心都市ダグラス。
まん‐どう【万灯】
①仏前にともす多くの灯火。御伽草子、梵天国「毎日―を三年ともして」
②(→)万度に同じ。
③(東北地方で)非常に明るいさま。
⇒まんどう‐え【万灯会】
まん‐どう【満堂】‥ダウ
堂の中に満ちること。堂いっぱい。堂の中の人全部。満場。
マンドヴィル【Bernard Mandeville】
フランス人の医師・思想家。オランダに生まれ、イギリスに移住。我欲・浪費等の個人の悪徳が仕事・雇用等を生み、社会の繁栄を導くことを暴露し、当時の倫理観の偽善を指摘。著「蜂の寓話」。(1670〜1733)
まんどう‐え【万灯会】‥ヱ
懺悔・滅罪のために仏・菩薩に一万の灯明を供養する法会。東大寺・高野山・北野天満宮などで行われた。万灯供養。
⇒まん‐どう【万灯】
マントー【饅頭】
(中国語)小麦粉を練って発酵させ、蒸した丸いパン。
マントー‐はんのう【マントー反応】‥オウ
(→)ツベルクリン反応に同じ。フランスの医師マントー(C. Mantoux1877〜1947)が創始。
まん‐とく【万徳】
(マンドクとも)多くの徳行。多くの善行。
まん‐どころ【政所】
①政務・庶務をつかさどる所。
②平安時代以後、親王や公卿の家政機関。特に所領荘園の事務をつかさどった。
③鎌倉・室町幕府の財政および一部の民事訴訟をつかさどった機関。
④「北の政所」の略。
マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
女子宮廷礼装の一種。洋式大礼服。君主国の宮廷儀式参内に着用。→ローブ‐デコルテ→ローブ‐モンタント。
⇒マント【manteau フランス】
まんど‐ばらい【万度祓】‥バラヒ
①中臣なかとみの祓の詞を神前で一万度(度数の多い意)読んで罪をはらいきよめること。一万度祓。
②万度の祓をした祓串を白紙貼の祓箱に入れて家々に配るもの。万度。
⇒まん‐ど【万度・万灯】
マント‐ひひ【マント狒狒】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長90センチメートルほど、肩から背にかけて長い毛のマントをもつが、雌は体長50センチメートルほどで、たてがみはない。尾はともに長い。毛色は子供は黒で、成長すると茶色となり、マントは銀白色となる。アラビア半島からエチオピアの岩山に、群れをつくって生息。古代エジプトでは神として尊ばれた。
マントひひ
マンデリシターム【Osip E. Mandel'shtam】
ロシア(ソ連)の詩人。ユダヤ系。明晰な美を追求するアクメイズムの詩人として出発し、彫琢された形式と音楽性で際立った哲学的抒情詩を書く。スターリン諷刺の詩ゆえに逮捕され、獄死。詩集「石」「トリスチア」など。(1891〜1938)
マンデリン【Mandheling】
①インドネシア、スマトラ島北部の地方。
②1で産するアラビカ種のコーヒー。
マンテル【mantel オランダ】
マント。外套。
マンテルピース【mantelpiece】
⇒マントルピース
まん‐てん【万天】
天全体。また、天下四方。
まん‐てん【満天】
空全体。一天。「―の星」
⇒まんてん‐せい【満天星】
まん‐てん【満点】
規定された点の最高。また、それに達すること。百パーセントの成績。転じて、申し分のないこと。「サービス―」
まん‐てんか【満天下】
天下全体。全世界。
まんてん‐せい【満天星】
〔植〕
①ハクチョウゲ(白丁花)の別称。
②ドウダンツツジの漢名。
⇒まん‐てん【満天】
まん‐と【満都】
みやこのうち全体。
マント【manteau フランス】
ゆったりとした外套。日本では特に袖なしのものをいう。幕末、軍隊用としてとり入れられ、一般にも広く用いられるようになった。
⇒マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
⇒マント‐ひひ【マント狒狒】
まん‐と
〔副〕
(江戸後期の流行語)たくさん。どっさり。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「市に売り出す手桶を―拵へんと手間取りを多く入れて」
まん‐ど【万度・万灯】
四角い箱に、某社御祭礼などと大書、その下に町名を、また氏子中・子供中などと書き、これに灯火をともし、また花などを飾って祭礼に出すもの。まんどう。
⇒まんど‐ばらい【万度祓】
マン‐とう【マン島】‥タウ
(Isle of Man)イギリス、グレート‐ブリテン島と北アイルランドとの間のアイリッシュ海にある島。ケルト文化地域で、独自の法律・議会を有する。中心都市ダグラス。
まん‐どう【万灯】
①仏前にともす多くの灯火。御伽草子、梵天国「毎日―を三年ともして」
②(→)万度に同じ。
③(東北地方で)非常に明るいさま。
⇒まんどう‐え【万灯会】
まん‐どう【満堂】‥ダウ
堂の中に満ちること。堂いっぱい。堂の中の人全部。満場。
マンドヴィル【Bernard Mandeville】
フランス人の医師・思想家。オランダに生まれ、イギリスに移住。我欲・浪費等の個人の悪徳が仕事・雇用等を生み、社会の繁栄を導くことを暴露し、当時の倫理観の偽善を指摘。著「蜂の寓話」。(1670〜1733)
まんどう‐え【万灯会】‥ヱ
懺悔・滅罪のために仏・菩薩に一万の灯明を供養する法会。東大寺・高野山・北野天満宮などで行われた。万灯供養。
⇒まん‐どう【万灯】
マントー【饅頭】
(中国語)小麦粉を練って発酵させ、蒸した丸いパン。
マントー‐はんのう【マントー反応】‥オウ
(→)ツベルクリン反応に同じ。フランスの医師マントー(C. Mantoux1877〜1947)が創始。
まん‐とく【万徳】
(マンドクとも)多くの徳行。多くの善行。
まん‐どころ【政所】
①政務・庶務をつかさどる所。
②平安時代以後、親王や公卿の家政機関。特に所領荘園の事務をつかさどった。
③鎌倉・室町幕府の財政および一部の民事訴訟をつかさどった機関。
④「北の政所」の略。
マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
女子宮廷礼装の一種。洋式大礼服。君主国の宮廷儀式参内に着用。→ローブ‐デコルテ→ローブ‐モンタント。
⇒マント【manteau フランス】
まんど‐ばらい【万度祓】‥バラヒ
①中臣なかとみの祓の詞を神前で一万度(度数の多い意)読んで罪をはらいきよめること。一万度祓。
②万度の祓をした祓串を白紙貼の祓箱に入れて家々に配るもの。万度。
⇒まん‐ど【万度・万灯】
マント‐ひひ【マント狒狒】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長90センチメートルほど、肩から背にかけて長い毛のマントをもつが、雌は体長50センチメートルほどで、たてがみはない。尾はともに長い。毛色は子供は黒で、成長すると茶色となり、マントは銀白色となる。アラビア半島からエチオピアの岩山に、群れをつくって生息。古代エジプトでは神として尊ばれた。
マントひひ
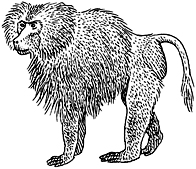 マントヒヒ
提供:東京動物園協会
マントヒヒ
提供:東京動物園協会
 ⇒マント【manteau フランス】
マントラ【mantra 梵】
(→)真言しんごんのこと。
マンドリル【mandrill】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長80センチメートル、雌は50センチメートルほどで、尾はともに短い。毛色は褐色。雄は成長すると鼻筋が赤くなり、周りに青い隆起を持つ。コンゴ・カメルーンなどの山地に小さい群れで生息。類似種にドリルがある。
マンドリル
提供:東京動物園協会
⇒マント【manteau フランス】
マントラ【mantra 梵】
(→)真言しんごんのこと。
マンドリル【mandrill】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長80センチメートル、雌は50センチメートルほどで、尾はともに短い。毛色は褐色。雄は成長すると鼻筋が赤くなり、周りに青い隆起を持つ。コンゴ・カメルーンなどの山地に小さい群れで生息。類似種にドリルがある。
マンドリル
提供:東京動物園協会
 マンドリン【mandolin(e)】
弦楽器。背面が円い卵形の胴にスチール製の複弦を4対(8本)張り、鼈甲べっこうまたはセルロイド製の爪で弾奏。調弦はバイオリンと同一。
マンドリン
マンドリン【mandolin(e)】
弦楽器。背面が円い卵形の胴にスチール製の複弦を4対(8本)張り、鼈甲べっこうまたはセルロイド製の爪で弾奏。調弦はバイオリンと同一。
マンドリン
 マントル【mantle】
①(→)ガス‐マントルに同じ。
②地球の地殻と核との間の層。地球の体積の80パーセント以上を占める。地殻のすぐ下から深さ約2900キロメートルまでの部分。→モホロヴィチッチ不連続面。
⇒マントル‐たいりゅう【マントル対流】
⇒マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントル‐たいりゅう【マントル対流】‥リウ
地球内部の熱が外へ運ばれる一つの過程として考えられた熱対流。20世紀前半には、これがマントル内だけで起こり、それにひきずられて地殻に大陸移動などの変動が起こるという説が広まったが、現在考えられている熱対流は、大洋底リソスフェアとその下のアセノスフェアとの間で行われる物質循環やプルームによる大規模なものを指す。
⇒マントル【mantle】
マントルピース【mantelpiece】
暖炉の前飾り。壁付暖炉の上に設けた飾り棚。マンテルピース。
マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントルを構成する岩石。深さ900キロメートルまでは、橄欖岩かんらんがんや柘榴石ざくろいし橄欖岩が主体であり、柘榴石輝岩やエクロジャイトは少量。深さ900キロメートル以深では、橄欖石が高密度の鉱物に変化する。
⇒マントル【mantle】
まん‐どろ
(青森県で)非常に明るいこと。
まん‐な【真名・真字】
マナの撥音化。枕草子82「たどたどしき―に書きたらんも、いと見ぐるしと」
⇒まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
まん‐なおし【間直し・真直し】‥ナホシ
①運の悪いのをよくするためにある事を行うこと。
②不漁の際、好漁を祈願する酒宴。げん直し。船霊ふなだま遊ばせ。
まん‐なか【真ん中】
(マナカの撥音化)中心。中央。ただなか。もなか。「会場の―に座る」「三人姉妹の―です」「ひもを―で結ぶ」
まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
真名すなわち漢字で書いてある書。漢籍。紫式部日記「なでふ女が―は読む」
⇒まん‐な【真名・真字】
まんなり‐いし【万成石】
岡山市万成付近に産出する花崗岩。淡紅色で美しい。建築・土木用。万成みかげ。
マンナン【mannan】
マンノースをおもな構成成分とする多糖の総称。植物や微生物に含まれる。こんにゃくの主成分であるコンニャク‐マンナンはマンノースのほかにグルコースを構成成分とする。
まん‐にち【万日】
(新潟県などで)女の祈祷師。まんち。
まん‐にょう【万葉】‥エフ
(マンヨウの連声)
⇒まんよう。
⇒まんにょう‐しゅう【万葉集】
まんにょう‐しゅう【万葉集】‥エフシフ
⇒まんようしゅう
⇒まん‐にょう【万葉】
まん‐にん【万人】
よろずの人。多くの人。ばんじん。ばんにん。
⇒まんにん‐むき【万人向き】
まんにん‐むき【万人向き】
誰にでも向くこと。一般向き。ばんにんむき。
⇒まん‐にん【万人】
マンネリ
マンネリズムの略。
マンネリズム【mannerism】
一定の技法や形式を反復慣用し、固定した型にはまって独創性や新鮮さを失うようになる傾向。マナリズム。→マニエリスム
まん‐ねん【万年】
①万の年。非常に長い年月。「鶴は千年、亀は―」
②ある語に冠して、「いつまでも変わらない」「長くつづく」などの意を表す語。「―青年」
⇒まんねん‐がみ【万年紙】
⇒まんねん‐ぐさ【万年草】
⇒まんねん‐ごよみ【万年暦】
⇒まんねん‐しんぞ【万年新造】
⇒まんねん‐ず【万年酢】
⇒まんねん‐すぎ【万年杉】
⇒まんねん‐せい【万年青】
⇒まんねん‐たけ【万年茸】
⇒まんねん‐つうほう【万年通宝】
⇒まんねん‐どこ【万年床】
⇒まんねん‐ひつ【万年筆】
⇒まんねん‐ふで【万年筆】
⇒まんねん‐べい【万年塀】
⇒まんねん‐むすめ【万年娘】
⇒まんねん‐ゆき【万年雪】
まんねん‐がみ【万年紙】
厚紙に漆を塗った紙。墨で文字などを書いた後、湿った布で拭い去れば何回でも使えるもの。まんねんし。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ぐさ【万年草】
①ベンケイソウ科の多年草。山地に群生し、高さ20センチメートル、全体多肉。葉は線形で3葉が輪生。初夏、茎上に黄色、5弁の小花を散房状に密生。オノマンネングサ。イチゲソウ。タカノツメ。
マンネングサ
撮影:関戸 勇
マントル【mantle】
①(→)ガス‐マントルに同じ。
②地球の地殻と核との間の層。地球の体積の80パーセント以上を占める。地殻のすぐ下から深さ約2900キロメートルまでの部分。→モホロヴィチッチ不連続面。
⇒マントル‐たいりゅう【マントル対流】
⇒マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントル‐たいりゅう【マントル対流】‥リウ
地球内部の熱が外へ運ばれる一つの過程として考えられた熱対流。20世紀前半には、これがマントル内だけで起こり、それにひきずられて地殻に大陸移動などの変動が起こるという説が広まったが、現在考えられている熱対流は、大洋底リソスフェアとその下のアセノスフェアとの間で行われる物質循環やプルームによる大規模なものを指す。
⇒マントル【mantle】
マントルピース【mantelpiece】
暖炉の前飾り。壁付暖炉の上に設けた飾り棚。マンテルピース。
マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントルを構成する岩石。深さ900キロメートルまでは、橄欖岩かんらんがんや柘榴石ざくろいし橄欖岩が主体であり、柘榴石輝岩やエクロジャイトは少量。深さ900キロメートル以深では、橄欖石が高密度の鉱物に変化する。
⇒マントル【mantle】
まん‐どろ
(青森県で)非常に明るいこと。
まん‐な【真名・真字】
マナの撥音化。枕草子82「たどたどしき―に書きたらんも、いと見ぐるしと」
⇒まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
まん‐なおし【間直し・真直し】‥ナホシ
①運の悪いのをよくするためにある事を行うこと。
②不漁の際、好漁を祈願する酒宴。げん直し。船霊ふなだま遊ばせ。
まん‐なか【真ん中】
(マナカの撥音化)中心。中央。ただなか。もなか。「会場の―に座る」「三人姉妹の―です」「ひもを―で結ぶ」
まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
真名すなわち漢字で書いてある書。漢籍。紫式部日記「なでふ女が―は読む」
⇒まん‐な【真名・真字】
まんなり‐いし【万成石】
岡山市万成付近に産出する花崗岩。淡紅色で美しい。建築・土木用。万成みかげ。
マンナン【mannan】
マンノースをおもな構成成分とする多糖の総称。植物や微生物に含まれる。こんにゃくの主成分であるコンニャク‐マンナンはマンノースのほかにグルコースを構成成分とする。
まん‐にち【万日】
(新潟県などで)女の祈祷師。まんち。
まん‐にょう【万葉】‥エフ
(マンヨウの連声)
⇒まんよう。
⇒まんにょう‐しゅう【万葉集】
まんにょう‐しゅう【万葉集】‥エフシフ
⇒まんようしゅう
⇒まん‐にょう【万葉】
まん‐にん【万人】
よろずの人。多くの人。ばんじん。ばんにん。
⇒まんにん‐むき【万人向き】
まんにん‐むき【万人向き】
誰にでも向くこと。一般向き。ばんにんむき。
⇒まん‐にん【万人】
マンネリ
マンネリズムの略。
マンネリズム【mannerism】
一定の技法や形式を反復慣用し、固定した型にはまって独創性や新鮮さを失うようになる傾向。マナリズム。→マニエリスム
まん‐ねん【万年】
①万の年。非常に長い年月。「鶴は千年、亀は―」
②ある語に冠して、「いつまでも変わらない」「長くつづく」などの意を表す語。「―青年」
⇒まんねん‐がみ【万年紙】
⇒まんねん‐ぐさ【万年草】
⇒まんねん‐ごよみ【万年暦】
⇒まんねん‐しんぞ【万年新造】
⇒まんねん‐ず【万年酢】
⇒まんねん‐すぎ【万年杉】
⇒まんねん‐せい【万年青】
⇒まんねん‐たけ【万年茸】
⇒まんねん‐つうほう【万年通宝】
⇒まんねん‐どこ【万年床】
⇒まんねん‐ひつ【万年筆】
⇒まんねん‐ふで【万年筆】
⇒まんねん‐べい【万年塀】
⇒まんねん‐むすめ【万年娘】
⇒まんねん‐ゆき【万年雪】
まんねん‐がみ【万年紙】
厚紙に漆を塗った紙。墨で文字などを書いた後、湿った布で拭い去れば何回でも使えるもの。まんねんし。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ぐさ【万年草】
①ベンケイソウ科の多年草。山地に群生し、高さ20センチメートル、全体多肉。葉は線形で3葉が輪生。初夏、茎上に黄色、5弁の小花を散房状に密生。オノマンネングサ。イチゲソウ。タカノツメ。
マンネングサ
撮影:関戸 勇
 ②メノマンネングサの別称。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ごよみ【万年暦】
(1年だけの用に終わらない暦の意)暦日について、開運・相性などを記し集めた書。雑書。日本永代蔵5「―の合ふも不思議」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐しんぞ【万年新造】
いつまでも変わらない若々しい婦人。万年娘。まんねんしんぞう。人情本、春色辰巳園「―といはれたる花の盛りも永くは保たず」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ず【万年酢】
酒と酢と水とを合わせて密封し、数十日で成る酢。使った場合にはその分だけ酒と水を加えて置いて、常にその量が減らないようにして使用する。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐すぎ【万年杉】
ヒカゲノカズラ科のシダ植物。地中にのびた根茎から所々に茎を直立。高さ約15センチメートル。多くの枝を分け、茎・枝ともに鱗片状の小葉を密生し、スギの芽生えに似る。夏、茎頭に、円柱状で長さ2〜3センチメートルの胞子嚢穂を生ずる。アリマスギ。漢名、玉柏。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐せい【万年青】
〔植〕オモトの漢名。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐たけ【万年茸】
担子菌類のきのこ。広葉樹の枯木の根元に生える。腎臓形、傘・軸ともに赤褐色・赤紫色または暗紫色を呈し、漆のような光沢があり堅い。古来、乾して霊芝れいしと称し、床飾りとして愛玩する。サイワイタケ。芝草。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐つうほう【万年通宝】
760年(天平宝字4)、開基勝宝(金銭)・大平元宝(銀銭)とともに発行された銅銭。皇朝十二銭の一つ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐どこ【万年床】
常に敷きっぱなしにして、片付けたことのない寝床。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ひつ【万年筆】
(fountain pen)中空のペン軸にインクを入れ、その先に金または合金のペン先を取り付け、使用するにしたがって、インクがペン先に伝わり出るように装置したペン。万年ペン。夏目漱石、書簡「時さんの呉れた―は船中にて…打ち壊し申候」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ふで【万年筆】
明治期、「まんねんひつ」が一般化する前に用いた語。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐べい【万年塀】
プレキャスト‐コンクリート造りの組立塀。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐むすめ【万年娘】
(→)万年新造まんねんしんぞに同じ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ゆき【万年雪】
山地で雪線以上の所に年々降り積もる雪が、その重みによる圧縮その他の原因により、性質が変化して次第に粒状構造の氷塊になったもの。
⇒まん‐ねん【万年】
まん‐ねんれい【満年齢】
誕生日ごとに1歳ふえる年齢の数え方。また、それで数えた年齢。
まんねんろう
〔植〕(→)ローズマリーに同じ。
まん‐のう【万能】
①さまざまの物事にたくみなこと。ばんのう。狂言、八幡の前「こなたは―な人でござるによつて」
②除草に用いる農具。10センチメートル位の扁平または円くとがった刃に柄をはめたもの。
⇒まんのう‐こう【万能膏】
まんのう‐いけ【満濃池】
8世紀に造築され、821年(弘仁12)から3年をかけて空海らが修築した日本最大の灌漑用溜池。香川県仲多度郡まんのう町にあり、丸亀平野を灌漑。満水面積1.4平方キロメートル。周囲約20キロメートル。万農池。十千池とちのいけ。
満濃池
撮影:佐藤 尚
②メノマンネングサの別称。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ごよみ【万年暦】
(1年だけの用に終わらない暦の意)暦日について、開運・相性などを記し集めた書。雑書。日本永代蔵5「―の合ふも不思議」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐しんぞ【万年新造】
いつまでも変わらない若々しい婦人。万年娘。まんねんしんぞう。人情本、春色辰巳園「―といはれたる花の盛りも永くは保たず」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ず【万年酢】
酒と酢と水とを合わせて密封し、数十日で成る酢。使った場合にはその分だけ酒と水を加えて置いて、常にその量が減らないようにして使用する。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐すぎ【万年杉】
ヒカゲノカズラ科のシダ植物。地中にのびた根茎から所々に茎を直立。高さ約15センチメートル。多くの枝を分け、茎・枝ともに鱗片状の小葉を密生し、スギの芽生えに似る。夏、茎頭に、円柱状で長さ2〜3センチメートルの胞子嚢穂を生ずる。アリマスギ。漢名、玉柏。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐せい【万年青】
〔植〕オモトの漢名。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐たけ【万年茸】
担子菌類のきのこ。広葉樹の枯木の根元に生える。腎臓形、傘・軸ともに赤褐色・赤紫色または暗紫色を呈し、漆のような光沢があり堅い。古来、乾して霊芝れいしと称し、床飾りとして愛玩する。サイワイタケ。芝草。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐つうほう【万年通宝】
760年(天平宝字4)、開基勝宝(金銭)・大平元宝(銀銭)とともに発行された銅銭。皇朝十二銭の一つ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐どこ【万年床】
常に敷きっぱなしにして、片付けたことのない寝床。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ひつ【万年筆】
(fountain pen)中空のペン軸にインクを入れ、その先に金または合金のペン先を取り付け、使用するにしたがって、インクがペン先に伝わり出るように装置したペン。万年ペン。夏目漱石、書簡「時さんの呉れた―は船中にて…打ち壊し申候」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ふで【万年筆】
明治期、「まんねんひつ」が一般化する前に用いた語。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐べい【万年塀】
プレキャスト‐コンクリート造りの組立塀。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐むすめ【万年娘】
(→)万年新造まんねんしんぞに同じ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ゆき【万年雪】
山地で雪線以上の所に年々降り積もる雪が、その重みによる圧縮その他の原因により、性質が変化して次第に粒状構造の氷塊になったもの。
⇒まん‐ねん【万年】
まん‐ねんれい【満年齢】
誕生日ごとに1歳ふえる年齢の数え方。また、それで数えた年齢。
まんねんろう
〔植〕(→)ローズマリーに同じ。
まん‐のう【万能】
①さまざまの物事にたくみなこと。ばんのう。狂言、八幡の前「こなたは―な人でござるによつて」
②除草に用いる農具。10センチメートル位の扁平または円くとがった刃に柄をはめたもの。
⇒まんのう‐こう【万能膏】
まんのう‐いけ【満濃池】
8世紀に造築され、821年(弘仁12)から3年をかけて空海らが修築した日本最大の灌漑用溜池。香川県仲多度郡まんのう町にあり、丸亀平野を灌漑。満水面積1.4平方キロメートル。周囲約20キロメートル。万農池。十千池とちのいけ。
満濃池
撮影:佐藤 尚
 まんのう‐こう【万能膏】‥カウ
傷・腫物などの一切に効能があるという膏薬。
⇒まん‐のう【万能】
マンノース【mannose】
分子式C6H12O6 ヘキソースの一つ。甘味と苦味のある白色結晶性物質。還元性をもつ。マンナン・コンニャク‐マンナン・糖蛋白質・配糖体などの構成成分として天然に広く存在。
まん‐ば【慢罵】
あなどりののしること。
まん‐ば【漫罵】
みだりにののしること。
マンバ【mamba】
コブラ科のヘビ。アフリカに4種が分布。有毒で、毒は主に神経毒。動きが速く危険。ブラック‐マンバは全長約3メートルに達する。
まん‐ぱ【万波】
幾重にも寄せて来る波。多くの波。ばんぱ。「千波―」
まん‐ぱい【満杯】
容器が中身で一杯であること。予定した数量に達していること。
マンハイム【Mannheim】
ドイツ南部、バーデン‐ヴュルテンベルク州の都市。ネッカー川がライン川に合流する地点に位置し、もとファルツ選帝侯の本拠地。18世紀以後、音楽の一中心地。機械・精密工業が盛ん。人口30万8千(1999)。
マンハイム【Karl Mannheim】
ハンガリー生れの社会学者。知識社会学の創始者として、知識の存在被拘束性を指摘。時代診断学としての社会学を企て「自由のための社会計画」を提唱。著「イデオロギーとユートピア」「変革期における人間と社会」など。(1893〜1947)
まん‐ばけん【万馬券】
競馬で、配当が100円につき1万円以上となる馬券。
まんのう‐こう【万能膏】‥カウ
傷・腫物などの一切に効能があるという膏薬。
⇒まん‐のう【万能】
マンノース【mannose】
分子式C6H12O6 ヘキソースの一つ。甘味と苦味のある白色結晶性物質。還元性をもつ。マンナン・コンニャク‐マンナン・糖蛋白質・配糖体などの構成成分として天然に広く存在。
まん‐ば【慢罵】
あなどりののしること。
まん‐ば【漫罵】
みだりにののしること。
マンバ【mamba】
コブラ科のヘビ。アフリカに4種が分布。有毒で、毒は主に神経毒。動きが速く危険。ブラック‐マンバは全長約3メートルに達する。
まん‐ぱ【万波】
幾重にも寄せて来る波。多くの波。ばんぱ。「千波―」
まん‐ぱい【満杯】
容器が中身で一杯であること。予定した数量に達していること。
マンハイム【Mannheim】
ドイツ南部、バーデン‐ヴュルテンベルク州の都市。ネッカー川がライン川に合流する地点に位置し、もとファルツ選帝侯の本拠地。18世紀以後、音楽の一中心地。機械・精密工業が盛ん。人口30万8千(1999)。
マンハイム【Karl Mannheim】
ハンガリー生れの社会学者。知識社会学の創始者として、知識の存在被拘束性を指摘。時代診断学としての社会学を企て「自由のための社会計画」を提唱。著「イデオロギーとユートピア」「変革期における人間と社会」など。(1893〜1947)
まん‐ばけん【万馬券】
競馬で、配当が100円につき1万円以上となる馬券。
 ⇒まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】
⇒まんじ‐ともえ【卍巴】
まんじ【万治】‥ヂ
[史記]江戸前期、後西天皇朝の年号。明暦4年7月23日(1658年8月21日)改元、万治4年4月25日(1661年5月23日)寛文に改元。
まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】‥クヅシ‥
卍を崩した形を連続させた組子。法隆寺の金堂・中門・五重塔などの上層の高欄の地覆じふくと平桁との間にある。
卍崩し組子
⇒まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】
⇒まんじ‐ともえ【卍巴】
まんじ【万治】‥ヂ
[史記]江戸前期、後西天皇朝の年号。明暦4年7月23日(1658年8月21日)改元、万治4年4月25日(1661年5月23日)寛文に改元。
まんじくずし‐くみこ【卍崩し組子】‥クヅシ‥
卍を崩した形を連続させた組子。法隆寺の金堂・中門・五重塔などの上層の高欄の地覆じふくと平桁との間にある。
卍崩し組子
 ⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐くす・む【慢じくすむ】
〔自四〕
高慢顔ですましこむ。もっともらしい顔つきをする。醒睡笑「われとわが名を畠山の右兵衛佐とつき、―・み」
まん‐しつ【満室】
旅館やホテルなどで、全室がふさがっていること。
まんじ‐ともえ【卍巴】‥トモヱ
(マンジドモエとも)卍や巴の模様のように、追いかけあうように入り乱れるさま。
⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐まんざぶろう【万次万三郎】‥ラウ
磐次磐三郎ばんじばんざぶろうのこと。
まん‐しゃ【満車】
駐車場が車両でいっぱいでこれ以上駐車できる余地のないこと。
まんじゅ【万寿】
[詩経「万寿無疆」]平安中期、後一条天皇朝の年号。甲子革令により治安4年7月13日(1024年8月19日)改元、万寿5年7月25日(1028年8月18日)長元に改元。
まん‐じゅ【満珠】
(→)「しおみちのたま」に同じ。太平記39「竜宮城に宝とする干珠・―を借り召さる」↔干珠
まんしゅ‐いん【曼殊院】‥ヰン
(マンジュインとも)京都市左京区にある天台宗の門跡寺院。もと北野天満宮の別当寺。延暦(782〜806)年間最澄の創めた比叡山中の一宇に始まり、15世紀から宮門跡となり竹内門跡と称す。1656年(明暦2)現在地に移転。黄不動尊絵像や古典籍などを所蔵。
まんしゅう【満州・満洲】‥シウ
中国の東北一帯の俗称。もと民族名。行政上は東北三省(遼寧・吉林・黒竜江)と内モンゴル自治区の一部にわたり、中国では東北と呼ぶ。
⇒まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】
⇒まんしゅう‐ご【満州語】
⇒まんしゅう‐こく【満州国】
⇒まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】
⇒まんしゅう‐じへん【満州事変】
⇒まんしゅう‐ぞく【満州族】
⇒まんしゅう‐もじ【満州文字】
まん‐じゅう【饅頭】‥ヂユウ
(ジュウは唐音)
①小麦粉・米粉・そば粉などでつくった皮で餡あんを包んで蒸して作る菓子。暦応(1338〜1342)年間、中国から帰化した林浄因が奈良で始めた奈良饅頭を始めとする。狂言、栗焼「―羊羹などではござりませぬか」
②饅頭金物の略。
⇒まんじゅう‐がさ【饅頭笠】
⇒まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】
⇒まんじゅう‐がに【饅頭蟹】
⇒まんじゅう‐じころ【饅頭錏】
⇒まんじゅう‐はだ【饅頭肌】
⇒まんじゅう‐ぼん【饅頭本】
まんじゅう‐がさ【饅頭笠】‥ヂユウ‥
頂はまるく浅く、饅頭を横に半分に切ったような形につくったかぶり笠。
饅頭笠
⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐くす・む【慢じくすむ】
〔自四〕
高慢顔ですましこむ。もっともらしい顔つきをする。醒睡笑「われとわが名を畠山の右兵衛佐とつき、―・み」
まん‐しつ【満室】
旅館やホテルなどで、全室がふさがっていること。
まんじ‐ともえ【卍巴】‥トモヱ
(マンジドモエとも)卍や巴の模様のように、追いかけあうように入り乱れるさま。
⇒まん‐じ【卍・卐】
まんじ‐まんざぶろう【万次万三郎】‥ラウ
磐次磐三郎ばんじばんざぶろうのこと。
まん‐しゃ【満車】
駐車場が車両でいっぱいでこれ以上駐車できる余地のないこと。
まんじゅ【万寿】
[詩経「万寿無疆」]平安中期、後一条天皇朝の年号。甲子革令により治安4年7月13日(1024年8月19日)改元、万寿5年7月25日(1028年8月18日)長元に改元。
まん‐じゅ【満珠】
(→)「しおみちのたま」に同じ。太平記39「竜宮城に宝とする干珠・―を借り召さる」↔干珠
まんしゅ‐いん【曼殊院】‥ヰン
(マンジュインとも)京都市左京区にある天台宗の門跡寺院。もと北野天満宮の別当寺。延暦(782〜806)年間最澄の創めた比叡山中の一宇に始まり、15世紀から宮門跡となり竹内門跡と称す。1656年(明暦2)現在地に移転。黄不動尊絵像や古典籍などを所蔵。
まんしゅう【満州・満洲】‥シウ
中国の東北一帯の俗称。もと民族名。行政上は東北三省(遼寧・吉林・黒竜江)と内モンゴル自治区の一部にわたり、中国では東北と呼ぶ。
⇒まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】
⇒まんしゅう‐ご【満州語】
⇒まんしゅう‐こく【満州国】
⇒まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】
⇒まんしゅう‐じへん【満州事変】
⇒まんしゅう‐ぞく【満州族】
⇒まんしゅう‐もじ【満州文字】
まん‐じゅう【饅頭】‥ヂユウ
(ジュウは唐音)
①小麦粉・米粉・そば粉などでつくった皮で餡あんを包んで蒸して作る菓子。暦応(1338〜1342)年間、中国から帰化した林浄因が奈良で始めた奈良饅頭を始めとする。狂言、栗焼「―羊羹などではござりませぬか」
②饅頭金物の略。
⇒まんじゅう‐がさ【饅頭笠】
⇒まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】
⇒まんじゅう‐がに【饅頭蟹】
⇒まんじゅう‐じころ【饅頭錏】
⇒まんじゅう‐はだ【饅頭肌】
⇒まんじゅう‐ぼん【饅頭本】
まんじゅう‐がさ【饅頭笠】‥ヂユウ‥
頂はまるく浅く、饅頭を横に半分に切ったような形につくったかぶり笠。
饅頭笠
 ⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】‥ヂユウ‥
扉に打つ半球形の装飾金物。元来は釘の頭を隠すもの。乳金物ちかなもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐がに【饅頭蟹】‥ヂユウ‥
オウギガニ科マンジュウガニ属のカニの総称。甲は左右に長い楕円形で、歩脚は短く、全体にずんぐりした形。その一種スベスベマンジュウガニは房総半島以南の磯に普通。食うと有毒。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】‥シウ‥リウカウ
古来中国東北部(満州)に興亡した諸族および風俗・地理などに関する地誌。20巻。清の阿桂・于敏中らが奉勅撰。1778年成る。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ご【満州語】‥シウ‥
満州族の用いる言語。アルタイ語族ツングース語派に属する。特に17世紀後半以降、清朝の興隆とともに中国語の影響を受け、語彙および文法の面で変化。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐こく【満州国】‥シウ‥
日本が満州事変により、中国の東北三省および東部内モンゴル(熱河省)をもって作りあげた傀儡かいらい国家。1932年、もと清の宣統帝であった溥儀ふぎを執政として建国、34年に溥儀が皇帝に即位。首都は新京(長春)。45年日本の敗戦に伴い消滅。中国では偽満州国と称。
満州国建国
提供:NHK
→資料:日満議定書
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】‥シウ‥ケフ‥クワイ
満州国の住民を組織し動員するための官製団体。満州国や関東軍の高官を幹部として1932年(昭和7)発足。当初は宣撫工作を主としたが、36年住民動員組織に改組。満州国崩壊とともに解体。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうこわい【饅頭怖い】‥ヂユウコハイ
落語。若い連中が自分の怖いものを白状し合っていると、仲間内の嫌われ者が「饅頭が怖い」というので、皆で饅頭を与えるが、すっかり食われてしまう話。
まんじゅう‐じころ【饅頭錏】‥ヂユウ‥
兜かぶとの錏しころの一種。笠錏や日根野ひねの錏に対して、一の板から裾板すそいたまで勾配に曲線をつけて縅おどし下げたもの。江戸時代の復古的作品に多い。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐じへん【満州事変】‥シウ‥
1931年(昭和6)9月18日、奉天(今の瀋陽)北方の柳条湖の鉄道爆破事件を契機とする日本の中国東北侵略戦争。十五年戦争の第1段階。翌32年には、満州国を樹立。華北分離工作を経て、日中戦争へ発展。→柳条湖事件。
現場検証するリットン調査団
提供:毎日新聞社
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐かなもの【饅頭金物】‥ヂユウ‥
扉に打つ半球形の装飾金物。元来は釘の頭を隠すもの。乳金物ちかなもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐がに【饅頭蟹】‥ヂユウ‥
オウギガニ科マンジュウガニ属のカニの総称。甲は左右に長い楕円形で、歩脚は短く、全体にずんぐりした形。その一種スベスベマンジュウガニは房総半島以南の磯に普通。食うと有毒。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐げんりゅうこう【満洲源流考】‥シウ‥リウカウ
古来中国東北部(満州)に興亡した諸族および風俗・地理などに関する地誌。20巻。清の阿桂・于敏中らが奉勅撰。1778年成る。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ご【満州語】‥シウ‥
満州族の用いる言語。アルタイ語族ツングース語派に属する。特に17世紀後半以降、清朝の興隆とともに中国語の影響を受け、語彙および文法の面で変化。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐こく【満州国】‥シウ‥
日本が満州事変により、中国の東北三省および東部内モンゴル(熱河省)をもって作りあげた傀儡かいらい国家。1932年、もと清の宣統帝であった溥儀ふぎを執政として建国、34年に溥儀が皇帝に即位。首都は新京(長春)。45年日本の敗戦に伴い消滅。中国では偽満州国と称。
満州国建国
提供:NHK
→資料:日満議定書
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅうこく‐きょうわかい【満州国協和会】‥シウ‥ケフ‥クワイ
満州国の住民を組織し動員するための官製団体。満州国や関東軍の高官を幹部として1932年(昭和7)発足。当初は宣撫工作を主としたが、36年住民動員組織に改組。満州国崩壊とともに解体。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうこわい【饅頭怖い】‥ヂユウコハイ
落語。若い連中が自分の怖いものを白状し合っていると、仲間内の嫌われ者が「饅頭が怖い」というので、皆で饅頭を与えるが、すっかり食われてしまう話。
まんじゅう‐じころ【饅頭錏】‥ヂユウ‥
兜かぶとの錏しころの一種。笠錏や日根野ひねの錏に対して、一の板から裾板すそいたまで勾配に曲線をつけて縅おどし下げたもの。江戸時代の復古的作品に多い。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐じへん【満州事変】‥シウ‥
1931年(昭和6)9月18日、奉天(今の瀋陽)北方の柳条湖の鉄道爆破事件を契機とする日本の中国東北侵略戦争。十五年戦争の第1段階。翌32年には、満州国を樹立。華北分離工作を経て、日中戦争へ発展。→柳条湖事件。
現場検証するリットン調査団
提供:毎日新聞社
 満州事変
提供:NHK
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ぞく【満州族】‥シウ‥
中国東北地方の東北部から南部一帯にかけて分布した民族。南方ツングース系で、渤海国を建てた靺鞨まっかつ、金を建てた女真、清を建てた女直はともにこれに属する。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅう‐はだ【饅頭肌】‥ヂユウ‥
饅頭のように滑らかにつやつやした肌。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐ぼん【饅頭本】‥ヂユウ‥
亡くなった人の遺した文章やその人を偲ぶ文章などを本にして、近親やゆかりの人々に配るもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐もじ【満州文字】‥シウ‥
満州語を表記するための文字。モンゴル文字を基本とし、点または圏を加えて満州語の音を示すに至ったもので、別にまた、字体を定めて中国語をも記し得るようになっている。1599年清の太祖ヌルハチの制定に始まり、太宗の時に成った。満州字。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうや‐ぼん【饅頭屋本】‥ヂユウ‥
室町末期、奈良の歌人・歌学者で菓子商(塩瀬の祖)の饅頭屋宗二(林逸1498〜1581)が刊行した本。饅頭屋本節用集のほか、漢籍がある。
まんじゅう‐らく【万秋楽】‥ジウ‥
⇒まんじゅらく
まんしゅうり【満洲里】‥シウ‥
⇒マンチュリ
まんじゅ‐ぎく【万寿菊】
マリーゴールドの和名。
まんじゅ‐さん【万寿山】
中国北京、頤和園いわえんにある山丘。清朝の離宮が残り、山水・楼閣の美に富む。
まんじゅ‐じ【万寿寺】
京都市東山区の東福寺内にある臨済宗の寺。京都五山の一つ。1097年(承徳1)白河上皇の御願により建立され六条御堂と称す。正嘉(1257〜1259)年中円爾えんにに帰依して禅宗となり、万寿禅寺と改称。天正(1573〜1592)年中現在地に移る。
まんじゅしゃげ【曼殊沙華・曼珠沙華】
①〔仏〕(梵語mañjūṣaka)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を柔軟にするという。
②〔植〕ヒガンバナの別称。〈[季]秋〉。日葡辞書「マンジュシャケ」
まんじゅ‐らく【万秋楽】
雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの大曲。六人または四人舞。736年(天平8)天竺僧仙那・林邑僧仏哲が来日して伝えたともいう。慈尊楽。まんずらく。まんじゅうらく。
まん‐しょ【万庶】
すべての人民。ばんしょ。
まん‐しょう【満床】‥シヤウ
病院で、入院患者用のベッドがすべてふさがっていること。
まん‐じょう【満場】‥ヂヤウ
その場所にいる人全体。会場全体。「―の諸君」
⇒まんじょう‐いっち【満場一致】
まんじょう‐いっち【満場一致】‥ヂヤウ‥
その場にいる全員の意見が一致すること。「―で可決する」
⇒まん‐じょう【満場】
まんじょう‐かんぼ【満城漢墓】‥ジヤウ‥
中国河北省満城県にある前漢代の墓。中山国初代の中山靖王劉勝とその妻の墓。遺骸を包んだ金縷玉衣きんるぎょくいなどで有名。
マンジョーカ【manjoca ポルトガル】
キャッサバのこと。ブラジルの日本移民が沖縄などにこの名で持ち帰った。
マンション【mansion】
(大邸宅の意)中高層の集合住宅。1960年代後半から急速に普及。
⇒マンション‐ほう【マンション法】
マンション‐ほう【マンション法】‥ハフ
建物区分所有法の通称。マンションの権利関係・管理・集会・建替えなどについて定める。
⇒マンション【mansion】
まんじり
〔副〕
①(多く、打消の語を伴う)ちょっと眠るさま。まどろむさま。「―ともせず一夜を明かす」
②じっと。まじまじと。「―と見る」
まん・じる【慢じる】
〔自上一〕
(→)「慢ずる」に同じ。
まん‐しん【満身】
からだじゅう。全身。「―の力をこめる」
⇒まんしん‐そうい【満身創痍】
まん‐しん【慢心】
おごりたかぶること。また、その心。
まんしん‐そうい【満身創痍】‥サウ‥
全身傷だらけであること。転じて、手ひどく痛めつけられていること。
⇒まん‐しん【満身】
まん・ず【満ず】
〔自サ変〕
①願い事が叶う。古今著聞集13「我願すでに―・ずとてぞ…をどりおりさせ給ひける」
②期限が満ちる。期限が来る。平家物語1「七日に―・ずる夜」
まん‐すい【満水】
水がいっぱいになること。河水などが増水して、あふれんばかりになること。
まん‐すう【満数】
定数に達すること。「―次第締切」
マンズー【Giacomo Manzù】
イタリア、現代具象派彫刻の代表者。素描家としても著名。(1908〜1991)
まん‐すじ【万筋】‥スヂ
2本ずつ色のちがった経糸たていとを配列した竪縞たてじま。→縞織物(図)
マンスフィールド【Katherine Mansfield】
イギリスの女性作家。ニュー‐ジーランド出身。繊細な感覚と優雅な文体で多くの短編小説を書いた。代表作「園遊会」。(1888〜1923)
マンスリー【monthly】
(「月ごと」の意)月刊雑誌。
まん・ずる【慢ずる】
〔自サ変〕[文]慢ず(サ変)
①あなどる。軽んじる。天草本伊曾保物語「この難に遇ふこと最も道理ぢや、…仇となるものを―・じた故ぢや」
②自慢する。ほこる。慢心する。日葡辞書「ワレ(我)トミ(身)ヲマンゼザレ」
まん‐せい【慢性】
①症状が激しくなく経過の長びくような病気の性質。↔急性。
②比喩的に、好ましくない現象・状態が長く続くこと。「―のインフレ」
⇒まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】
⇒まんせい‐しっかん【慢性疾患】
⇒まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
⇒まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】
⇒まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】
まん‐せい【蔓生】
茎が蔓つるとなって生えること。つるだち。
まん‐せい【蔓菁】
〔植〕カブラの漢名。
まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】‥シヤウ
感染してから発症するまでの時間が長く緩慢な経過をとる伝染性疾患の総称。エイズ・結核・ハンセン病など。慢性伝染病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせい‐しっかん【慢性疾患】‥クワン
徐々に発病し、または急性期から移行して長期間経過する病気。慢性病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんぜい‐しゃみ【満誓沙弥】
沙弥満誓さみまんぜいのこと。
まんせい‐しょくぶつ【蔓性植物】
(→)蔓つる植物に同じ。
まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
毒物が長時間持続的に作用することによって徐々に生理的機能に異常を生じること。麻薬など一部の薬品やアルコール飲料などの嗜好品では耐性と依存性を招く。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】‥ラウシヤウ‥
(chronic fatigue syndrome)健康に生活していた人に突然発症し、極度の疲労感が長く続いて活動能力が低下する状態。ウイルス病原説があるが原因不明。CFS
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】‥クワン
慢性の気道・肺の炎症のために肺胞組織が破壊され、呼吸困難・閉塞性換気障害を起こす病態。空気中の有害物質によると考えられ、患者は喫煙者が大多数を占める。
⇒まん‐せい【慢性】
マンセー【万歳】
(朝鮮語manse)祝いの意を表す語。ばんざい。
まん‐せき【満席】
乗物・劇場などで、すべての客席がふさがること。満員。
マンセル‐ひょうしょくけい【マンセル表色系】‥ヘウ‥
アメリカの画家マンセル(A. H. Munsell1858〜1918)が考案した色の表示体系。個々の色を色相・明度・彩度の3次元座標軸内の点として記述する。
まん‐せん【満線】
駅構内の線路に列車が停車中で、後続列車の入れない状態。
まん‐ぜん【万善】
あらゆる善行・善事。
まん‐ぜん【漫然】
心にとめて深く考えず、またはっきりとした目的や意識を持たないさま。とりとめのないさま。しまりのないさま。「―と日を過ごす」
まん‐そう【万草】‥サウ
よろずの草。すべての草。
まん‐そう【蔓草】‥サウ
茎が蔓つるとなって生える草。つるくさ。
まんぞう‐くじ【万雑公事】‥ザフ‥
荘園における種々の雑税や夫役。狂言、餅酒「―を御免なさるる」
マンゾーニ【Alessandro Manzoni】
イタリアのロマン主義の小説家・劇作家。大部の歴史小説「いいなずけ」で名声を得、晩年は歴史や言語への省察に傾いた。他に悲劇「カルマニョーラ伯爵」「アデルキ」など。(1785〜1873)
まん‐ぞく【満足】
①十分なこと。完全なこと。「挨拶も―にできない」
②望みが満ち足りて不平のないこと。今昔物語集6「霊幹りょうかん、其の上に坐して願ふ所―しぬと」。「予は―じゃ」「好奇心を―させる」
③〔数〕方程式の未知数に適当なある値を代入した時、等式が成立すれば、この値はこの方程式を満足する、あるいは満たすという。
⇒まんぞく‐かん【満足感】
まんぞく‐かん【満足感】
満ち足りたという感じ。
⇒まん‐ぞく【満足】
まんた【茨田】
河内国(大阪府)の旧郡名。
⇒まんた‐の‐いけ【茨田の池】
⇒まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
マンタ【manta】
イトマキエイ科の海産の軟骨魚。オニイトマキエイの別称。体盤長5メートル以上に達するものもある。頭の前端に一対の耳状の頭びれがある。全世界の熱帯海域に分布。マンタエイ。
マンタ
満州事変
提供:NHK
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんしゅう‐ぞく【満州族】‥シウ‥
中国東北地方の東北部から南部一帯にかけて分布した民族。南方ツングース系で、渤海国を建てた靺鞨まっかつ、金を建てた女真、清を建てた女直はともにこれに属する。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅう‐はだ【饅頭肌】‥ヂユウ‥
饅頭のように滑らかにつやつやした肌。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんじゅう‐ぼん【饅頭本】‥ヂユウ‥
亡くなった人の遺した文章やその人を偲ぶ文章などを本にして、近親やゆかりの人々に配るもの。
⇒まん‐じゅう【饅頭】
まんしゅう‐もじ【満州文字】‥シウ‥
満州語を表記するための文字。モンゴル文字を基本とし、点または圏を加えて満州語の音を示すに至ったもので、別にまた、字体を定めて中国語をも記し得るようになっている。1599年清の太祖ヌルハチの制定に始まり、太宗の時に成った。満州字。
⇒まんしゅう【満州・満洲】
まんじゅうや‐ぼん【饅頭屋本】‥ヂユウ‥
室町末期、奈良の歌人・歌学者で菓子商(塩瀬の祖)の饅頭屋宗二(林逸1498〜1581)が刊行した本。饅頭屋本節用集のほか、漢籍がある。
まんじゅう‐らく【万秋楽】‥ジウ‥
⇒まんじゅらく
まんしゅうり【満洲里】‥シウ‥
⇒マンチュリ
まんじゅ‐ぎく【万寿菊】
マリーゴールドの和名。
まんじゅ‐さん【万寿山】
中国北京、頤和園いわえんにある山丘。清朝の離宮が残り、山水・楼閣の美に富む。
まんじゅ‐じ【万寿寺】
京都市東山区の東福寺内にある臨済宗の寺。京都五山の一つ。1097年(承徳1)白河上皇の御願により建立され六条御堂と称す。正嘉(1257〜1259)年中円爾えんにに帰依して禅宗となり、万寿禅寺と改称。天正(1573〜1592)年中現在地に移る。
まんじゅしゃげ【曼殊沙華・曼珠沙華】
①〔仏〕(梵語mañjūṣaka)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を柔軟にするという。
②〔植〕ヒガンバナの別称。〈[季]秋〉。日葡辞書「マンジュシャケ」
まんじゅ‐らく【万秋楽】
雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの大曲。六人または四人舞。736年(天平8)天竺僧仙那・林邑僧仏哲が来日して伝えたともいう。慈尊楽。まんずらく。まんじゅうらく。
まん‐しょ【万庶】
すべての人民。ばんしょ。
まん‐しょう【満床】‥シヤウ
病院で、入院患者用のベッドがすべてふさがっていること。
まん‐じょう【満場】‥ヂヤウ
その場所にいる人全体。会場全体。「―の諸君」
⇒まんじょう‐いっち【満場一致】
まんじょう‐いっち【満場一致】‥ヂヤウ‥
その場にいる全員の意見が一致すること。「―で可決する」
⇒まん‐じょう【満場】
まんじょう‐かんぼ【満城漢墓】‥ジヤウ‥
中国河北省満城県にある前漢代の墓。中山国初代の中山靖王劉勝とその妻の墓。遺骸を包んだ金縷玉衣きんるぎょくいなどで有名。
マンジョーカ【manjoca ポルトガル】
キャッサバのこと。ブラジルの日本移民が沖縄などにこの名で持ち帰った。
マンション【mansion】
(大邸宅の意)中高層の集合住宅。1960年代後半から急速に普及。
⇒マンション‐ほう【マンション法】
マンション‐ほう【マンション法】‥ハフ
建物区分所有法の通称。マンションの権利関係・管理・集会・建替えなどについて定める。
⇒マンション【mansion】
まんじり
〔副〕
①(多く、打消の語を伴う)ちょっと眠るさま。まどろむさま。「―ともせず一夜を明かす」
②じっと。まじまじと。「―と見る」
まん・じる【慢じる】
〔自上一〕
(→)「慢ずる」に同じ。
まん‐しん【満身】
からだじゅう。全身。「―の力をこめる」
⇒まんしん‐そうい【満身創痍】
まん‐しん【慢心】
おごりたかぶること。また、その心。
まんしん‐そうい【満身創痍】‥サウ‥
全身傷だらけであること。転じて、手ひどく痛めつけられていること。
⇒まん‐しん【満身】
まん・ず【満ず】
〔自サ変〕
①願い事が叶う。古今著聞集13「我願すでに―・ずとてぞ…をどりおりさせ給ひける」
②期限が満ちる。期限が来る。平家物語1「七日に―・ずる夜」
まん‐すい【満水】
水がいっぱいになること。河水などが増水して、あふれんばかりになること。
まん‐すう【満数】
定数に達すること。「―次第締切」
マンズー【Giacomo Manzù】
イタリア、現代具象派彫刻の代表者。素描家としても著名。(1908〜1991)
まん‐すじ【万筋】‥スヂ
2本ずつ色のちがった経糸たていとを配列した竪縞たてじま。→縞織物(図)
マンスフィールド【Katherine Mansfield】
イギリスの女性作家。ニュー‐ジーランド出身。繊細な感覚と優雅な文体で多くの短編小説を書いた。代表作「園遊会」。(1888〜1923)
マンスリー【monthly】
(「月ごと」の意)月刊雑誌。
まん・ずる【慢ずる】
〔自サ変〕[文]慢ず(サ変)
①あなどる。軽んじる。天草本伊曾保物語「この難に遇ふこと最も道理ぢや、…仇となるものを―・じた故ぢや」
②自慢する。ほこる。慢心する。日葡辞書「ワレ(我)トミ(身)ヲマンゼザレ」
まん‐せい【慢性】
①症状が激しくなく経過の長びくような病気の性質。↔急性。
②比喩的に、好ましくない現象・状態が長く続くこと。「―のインフレ」
⇒まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】
⇒まんせい‐しっかん【慢性疾患】
⇒まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
⇒まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】
⇒まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】
まん‐せい【蔓生】
茎が蔓つるとなって生えること。つるだち。
まん‐せい【蔓菁】
〔植〕カブラの漢名。
まんせい‐かんせんしょう【慢性感染症】‥シヤウ
感染してから発症するまでの時間が長く緩慢な経過をとる伝染性疾患の総称。エイズ・結核・ハンセン病など。慢性伝染病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせい‐しっかん【慢性疾患】‥クワン
徐々に発病し、または急性期から移行して長期間経過する病気。慢性病。
⇒まん‐せい【慢性】
まんぜい‐しゃみ【満誓沙弥】
沙弥満誓さみまんぜいのこと。
まんせい‐しょくぶつ【蔓性植物】
(→)蔓つる植物に同じ。
まんせい‐ちゅうどく【慢性中毒】
毒物が長時間持続的に作用することによって徐々に生理的機能に異常を生じること。麻薬など一部の薬品やアルコール飲料などの嗜好品では耐性と依存性を招く。
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいひろう‐しょうこうぐん【慢性疲労症候群】‥ラウシヤウ‥
(chronic fatigue syndrome)健康に生活していた人に突然発症し、極度の疲労感が長く続いて活動能力が低下する状態。ウイルス病原説があるが原因不明。CFS
⇒まん‐せい【慢性】
まんせいへいそくせい‐はいしっかん【慢性閉塞性肺疾患】‥クワン
慢性の気道・肺の炎症のために肺胞組織が破壊され、呼吸困難・閉塞性換気障害を起こす病態。空気中の有害物質によると考えられ、患者は喫煙者が大多数を占める。
⇒まん‐せい【慢性】
マンセー【万歳】
(朝鮮語manse)祝いの意を表す語。ばんざい。
まん‐せき【満席】
乗物・劇場などで、すべての客席がふさがること。満員。
マンセル‐ひょうしょくけい【マンセル表色系】‥ヘウ‥
アメリカの画家マンセル(A. H. Munsell1858〜1918)が考案した色の表示体系。個々の色を色相・明度・彩度の3次元座標軸内の点として記述する。
まん‐せん【満線】
駅構内の線路に列車が停車中で、後続列車の入れない状態。
まん‐ぜん【万善】
あらゆる善行・善事。
まん‐ぜん【漫然】
心にとめて深く考えず、またはっきりとした目的や意識を持たないさま。とりとめのないさま。しまりのないさま。「―と日を過ごす」
まん‐そう【万草】‥サウ
よろずの草。すべての草。
まん‐そう【蔓草】‥サウ
茎が蔓つるとなって生える草。つるくさ。
まんぞう‐くじ【万雑公事】‥ザフ‥
荘園における種々の雑税や夫役。狂言、餅酒「―を御免なさるる」
マンゾーニ【Alessandro Manzoni】
イタリアのロマン主義の小説家・劇作家。大部の歴史小説「いいなずけ」で名声を得、晩年は歴史や言語への省察に傾いた。他に悲劇「カルマニョーラ伯爵」「アデルキ」など。(1785〜1873)
まん‐ぞく【満足】
①十分なこと。完全なこと。「挨拶も―にできない」
②望みが満ち足りて不平のないこと。今昔物語集6「霊幹りょうかん、其の上に坐して願ふ所―しぬと」。「予は―じゃ」「好奇心を―させる」
③〔数〕方程式の未知数に適当なある値を代入した時、等式が成立すれば、この値はこの方程式を満足する、あるいは満たすという。
⇒まんぞく‐かん【満足感】
まんぞく‐かん【満足感】
満ち足りたという感じ。
⇒まん‐ぞく【満足】
まんた【茨田】
河内国(大阪府)の旧郡名。
⇒まんた‐の‐いけ【茨田の池】
⇒まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
マンタ【manta】
イトマキエイ科の海産の軟骨魚。オニイトマキエイの別称。体盤長5メートル以上に達するものもある。頭の前端に一対の耳状の頭びれがある。全世界の熱帯海域に分布。マンタエイ。
マンタ
 マンタ
提供:NHK
まん‐だい【万代】
⇒ばんだい
まんだいわかしゅう【万代和歌集】‥シフ
私撰集。20巻6冊。3820首余を収める。撰者は初撰本は藤原光俊(真観)、精撰本は藤原(衣笠)家良か。成立は初撰本1248年(宝治2)、精撰本は1249年(建長1)か。
まんた‐の‐いけ【茨田の池】
茨田の地にあった池。今の寝屋川市の西部に当たる。
⇒まんた【茨田】
まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
古代、淀川の下流の左岸、茨田郡の側にあった堤防。伝承では仁徳天皇時代の築堤という。
⇒まんた【茨田】
マンダメント【mandamento ポルトガル】
(キリシタン用語)戒律。おきて。マダメント。どちりなきりしたん「―とは御掟の事也」→十戒2
まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
〔仏〕(梵語maṇḍala 輪円具足・道場・壇・本質などと訳す)諸尊の悟りの世界を象徴するものとして、一定の方式に基づいて、諸仏・菩薩および神々を網羅して描いた図。四種曼荼羅・両界曼荼羅など多くの種類がある。もともと密教のものであるが、浄土曼荼羅や垂迹すいじゃく曼荼羅、日蓮宗の十界じっかい曼荼羅のように、他にも転用される。おまんだら。
両界曼荼羅
マンタ
提供:NHK
まん‐だい【万代】
⇒ばんだい
まんだいわかしゅう【万代和歌集】‥シフ
私撰集。20巻6冊。3820首余を収める。撰者は初撰本は藤原光俊(真観)、精撰本は藤原(衣笠)家良か。成立は初撰本1248年(宝治2)、精撰本は1249年(建長1)か。
まんた‐の‐いけ【茨田の池】
茨田の地にあった池。今の寝屋川市の西部に当たる。
⇒まんた【茨田】
まんた‐の‐つつみ【茨田の堤】
古代、淀川の下流の左岸、茨田郡の側にあった堤防。伝承では仁徳天皇時代の築堤という。
⇒まんた【茨田】
マンダメント【mandamento ポルトガル】
(キリシタン用語)戒律。おきて。マダメント。どちりなきりしたん「―とは御掟の事也」→十戒2
まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
〔仏〕(梵語maṇḍala 輪円具足・道場・壇・本質などと訳す)諸尊の悟りの世界を象徴するものとして、一定の方式に基づいて、諸仏・菩薩および神々を網羅して描いた図。四種曼荼羅・両界曼荼羅など多くの種類がある。もともと密教のものであるが、浄土曼荼羅や垂迹すいじゃく曼荼羅、日蓮宗の十界じっかい曼荼羅のように、他にも転用される。おまんだら。
両界曼荼羅
 中台八葉院
胎蔵曼荼羅
金剛界曼荼羅
⇒まんだら‐く【曼荼羅供】
⇒まんだら‐どう【曼荼羅堂】
まんだら‐く【曼荼羅供】
密教で曼荼羅を作製し供養すること。また、その法会ほうえ。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
まんだらげ【曼陀羅華】
①〔仏〕(梵語māndārava)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を喜ばせるという。
②〔植〕チョウセンアサガオ・ムラサキケマンの別称。
まんだら‐どう【曼荼羅堂】‥ダウ
(いわゆる当麻たいま曼荼羅を本尊として祀るからいう)当麻寺本堂の別名。平安初期の創建で1161年(応保1)ほぼ現在の形に再建。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
マンタリテ【mentalité フランス】
心性。フランスのアナール学派が用いた社会史の基本概念で、ある時代のある社会の成員に共有されている、ものの感じ方や思考様式。
マンダリン【mandarin】
①中国、清朝の高等官吏。
②(Mandarin)中国の公用語。官話。
③中国原産の蜜柑。
⇒マンダリン‐カラー【mandarin collar】
マンダリン‐カラー【mandarin collar】
(清朝の官吏の服に用いたからいう)スタンド‐カラーの一種。首に沿った幅の狭い立ち襟の総称。チャイニーズ‐カラー。
⇒マンダリン【mandarin】
マンダレー【Mandalay】
ミャンマーの中央部にある古都。1857年、ミンドン王が都城を築き、翌年完成。旧跡が多い。人口53万3千(1983)。
まん‐タン【満タン】
(タンはタンクの略)燃料や水などが容器いっぱいに入っていること。満杯。
まん‐だん【漫談】
①とりとめもない話。
②演芸の一種。滑稽を主とし、世相・人情の批評・諷刺をも取り入れた話術。1924年(大正13)頃から徳川夢声・大辻司郎らが始めた。
まん‐ち【満地】
地上一面。
まん‐ち【満池】
水が池いっぱいに満ちていること。
マンチェスター【Manchester】
イギリス、イングランド北西部のランカシャー地方にある商工業都市。産業革命の発祥地で、かつては綿工業の中心地。人口43万1千(1996)。
⇒マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
⇒マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
「ガーディアン」参照。
⇒マンチェスター【Manchester】
マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
1838年頃から、マンチェスターを中心に、コブデン・ブライトら、穀物法廃止運動を推進し自由貿易思想の普及に努力した人々とその流派。
⇒マンチェスター【Manchester】
まん‐ちゃく【瞞着】
あざむくこと。ごまかすこと。人の目をくらますこと。「世人を―する」
まん‐ちゅういん【満中陰】
〔仏〕(→)四十九日しじゅうくにち2に同じ。
マンチュリ【満洲里】
(Manzhouli)中国、内モンゴル自治区の北東部にある都市。ロシアとの国境付近に当たり、中国東北部と外モンゴルを結ぶ重要地点。人口18万1千(2000)。
まん‐ちょう【満潮】‥テウ
潮が満ちて海水面が最高に達した状態。みちしお。↔干潮
まんちょうほう【万朝報】‥テウ‥
⇒よろずちょうほう
マン‐ツー‐マン【man-to-man】
一人に一人が応対すること。1対1。「―で指導する」
⇒マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
球技などで、相手側競技者の誰には味方の誰が当たるというように、あらかじめ守備の責任分担をきめて行う防御法。対人防御法。↔ゾーン‐ディフェンス
⇒マン‐ツー‐マン【man-to-man】
まん‐てい【満廷】
朝廷または法廷などに人が満ちること。また、そこに列するすべての人。
まん‐てい【満庭】
庭に満ちること。また、庭全体。
マンテイカ【manteiga ポルトガル】
猪などの脂肪。膏薬に加え、また、器械の錆さびどめに用いる。豬膏ちょこう。
マンデー【mandi マレー】
インドネシア地方の水浴。
マンテーニャ【Andrea Mantegna】
イタリア、ルネサンスの画家。パドヴァ公の宮廷画家となる。作「死せるキリスト」など。(1431〜1506)
「死せるキリスト」
提供:Maxppp/APL
中台八葉院
胎蔵曼荼羅
金剛界曼荼羅
⇒まんだら‐く【曼荼羅供】
⇒まんだら‐どう【曼荼羅堂】
まんだら‐く【曼荼羅供】
密教で曼荼羅を作製し供養すること。また、その法会ほうえ。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
まんだらげ【曼陀羅華】
①〔仏〕(梵語māndārava)天上に咲くという花の名。四華の一種で、見る者の心を喜ばせるという。
②〔植〕チョウセンアサガオ・ムラサキケマンの別称。
まんだら‐どう【曼荼羅堂】‥ダウ
(いわゆる当麻たいま曼荼羅を本尊として祀るからいう)当麻寺本堂の別名。平安初期の創建で1161年(応保1)ほぼ現在の形に再建。
⇒まんだら【曼荼羅・曼陀羅】
マンタリテ【mentalité フランス】
心性。フランスのアナール学派が用いた社会史の基本概念で、ある時代のある社会の成員に共有されている、ものの感じ方や思考様式。
マンダリン【mandarin】
①中国、清朝の高等官吏。
②(Mandarin)中国の公用語。官話。
③中国原産の蜜柑。
⇒マンダリン‐カラー【mandarin collar】
マンダリン‐カラー【mandarin collar】
(清朝の官吏の服に用いたからいう)スタンド‐カラーの一種。首に沿った幅の狭い立ち襟の総称。チャイニーズ‐カラー。
⇒マンダリン【mandarin】
マンダレー【Mandalay】
ミャンマーの中央部にある古都。1857年、ミンドン王が都城を築き、翌年完成。旧跡が多い。人口53万3千(1983)。
まん‐タン【満タン】
(タンはタンクの略)燃料や水などが容器いっぱいに入っていること。満杯。
まん‐だん【漫談】
①とりとめもない話。
②演芸の一種。滑稽を主とし、世相・人情の批評・諷刺をも取り入れた話術。1924年(大正13)頃から徳川夢声・大辻司郎らが始めた。
まん‐ち【満地】
地上一面。
まん‐ち【満池】
水が池いっぱいに満ちていること。
マンチェスター【Manchester】
イギリス、イングランド北西部のランカシャー地方にある商工業都市。産業革命の発祥地で、かつては綿工業の中心地。人口43万1千(1996)。
⇒マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
⇒マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
マンチェスター‐ガーディアン【Manchester Guardian】
「ガーディアン」参照。
⇒マンチェスター【Manchester】
マンチェスター‐がくは【マンチェスター学派】
1838年頃から、マンチェスターを中心に、コブデン・ブライトら、穀物法廃止運動を推進し自由貿易思想の普及に努力した人々とその流派。
⇒マンチェスター【Manchester】
まん‐ちゃく【瞞着】
あざむくこと。ごまかすこと。人の目をくらますこと。「世人を―する」
まん‐ちゅういん【満中陰】
〔仏〕(→)四十九日しじゅうくにち2に同じ。
マンチュリ【満洲里】
(Manzhouli)中国、内モンゴル自治区の北東部にある都市。ロシアとの国境付近に当たり、中国東北部と外モンゴルを結ぶ重要地点。人口18万1千(2000)。
まん‐ちょう【満潮】‥テウ
潮が満ちて海水面が最高に達した状態。みちしお。↔干潮
まんちょうほう【万朝報】‥テウ‥
⇒よろずちょうほう
マン‐ツー‐マン【man-to-man】
一人に一人が応対すること。1対1。「―で指導する」
⇒マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
マンツーマン‐ディフェンス【man-to-man defense】
球技などで、相手側競技者の誰には味方の誰が当たるというように、あらかじめ守備の責任分担をきめて行う防御法。対人防御法。↔ゾーン‐ディフェンス
⇒マン‐ツー‐マン【man-to-man】
まん‐てい【満廷】
朝廷または法廷などに人が満ちること。また、そこに列するすべての人。
まん‐てい【満庭】
庭に満ちること。また、庭全体。
マンテイカ【manteiga ポルトガル】
猪などの脂肪。膏薬に加え、また、器械の錆さびどめに用いる。豬膏ちょこう。
マンデー【mandi マレー】
インドネシア地方の水浴。
マンテーニャ【Andrea Mantegna】
イタリア、ルネサンスの画家。パドヴァ公の宮廷画家となる。作「死せるキリスト」など。(1431〜1506)
「死せるキリスト」
提供:Maxppp/APL
 まん‐てつ【満鉄】
南満州鉄道(株式会社)の略称。
⇒まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】
まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】‥テウ‥
満鉄が設置した調査研究機関。1907年(明治40)発足。中国・ソ連などの総合的調査・研究、満州国・華北の経済開発計画の立案などを行なった。日中戦争時には2000人をこえたが、太平洋戦争時の左翼グループ検挙(満鉄事件)で打撃をうけ、敗戦により解体。
⇒まん‐てつ【満鉄】
マンデラ【Nelson Mandela】
南アフリカ共和国の政治家。反アパルトヘイト運動の指導者。27年間の獄中生活ののち1990年釈放。94年、初の全人種による選挙で大統領に当選。ノーベル賞。(1918〜)
マンデラ
提供:ullstein bild/APL
まん‐てつ【満鉄】
南満州鉄道(株式会社)の略称。
⇒まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】
まんてつ‐ちょうさぶ【満鉄調査部】‥テウ‥
満鉄が設置した調査研究機関。1907年(明治40)発足。中国・ソ連などの総合的調査・研究、満州国・華北の経済開発計画の立案などを行なった。日中戦争時には2000人をこえたが、太平洋戦争時の左翼グループ検挙(満鉄事件)で打撃をうけ、敗戦により解体。
⇒まん‐てつ【満鉄】
マンデラ【Nelson Mandela】
南アフリカ共和国の政治家。反アパルトヘイト運動の指導者。27年間の獄中生活ののち1990年釈放。94年、初の全人種による選挙で大統領に当選。ノーベル賞。(1918〜)
マンデラ
提供:ullstein bild/APL
 マンデリシターム【Osip E. Mandel'shtam】
ロシア(ソ連)の詩人。ユダヤ系。明晰な美を追求するアクメイズムの詩人として出発し、彫琢された形式と音楽性で際立った哲学的抒情詩を書く。スターリン諷刺の詩ゆえに逮捕され、獄死。詩集「石」「トリスチア」など。(1891〜1938)
マンデリン【Mandheling】
①インドネシア、スマトラ島北部の地方。
②1で産するアラビカ種のコーヒー。
マンテル【mantel オランダ】
マント。外套。
マンテルピース【mantelpiece】
⇒マントルピース
まん‐てん【万天】
天全体。また、天下四方。
まん‐てん【満天】
空全体。一天。「―の星」
⇒まんてん‐せい【満天星】
まん‐てん【満点】
規定された点の最高。また、それに達すること。百パーセントの成績。転じて、申し分のないこと。「サービス―」
まん‐てんか【満天下】
天下全体。全世界。
まんてん‐せい【満天星】
〔植〕
①ハクチョウゲ(白丁花)の別称。
②ドウダンツツジの漢名。
⇒まん‐てん【満天】
まん‐と【満都】
みやこのうち全体。
マント【manteau フランス】
ゆったりとした外套。日本では特に袖なしのものをいう。幕末、軍隊用としてとり入れられ、一般にも広く用いられるようになった。
⇒マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
⇒マント‐ひひ【マント狒狒】
まん‐と
〔副〕
(江戸後期の流行語)たくさん。どっさり。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「市に売り出す手桶を―拵へんと手間取りを多く入れて」
まん‐ど【万度・万灯】
四角い箱に、某社御祭礼などと大書、その下に町名を、また氏子中・子供中などと書き、これに灯火をともし、また花などを飾って祭礼に出すもの。まんどう。
⇒まんど‐ばらい【万度祓】
マン‐とう【マン島】‥タウ
(Isle of Man)イギリス、グレート‐ブリテン島と北アイルランドとの間のアイリッシュ海にある島。ケルト文化地域で、独自の法律・議会を有する。中心都市ダグラス。
まん‐どう【万灯】
①仏前にともす多くの灯火。御伽草子、梵天国「毎日―を三年ともして」
②(→)万度に同じ。
③(東北地方で)非常に明るいさま。
⇒まんどう‐え【万灯会】
まん‐どう【満堂】‥ダウ
堂の中に満ちること。堂いっぱい。堂の中の人全部。満場。
マンドヴィル【Bernard Mandeville】
フランス人の医師・思想家。オランダに生まれ、イギリスに移住。我欲・浪費等の個人の悪徳が仕事・雇用等を生み、社会の繁栄を導くことを暴露し、当時の倫理観の偽善を指摘。著「蜂の寓話」。(1670〜1733)
まんどう‐え【万灯会】‥ヱ
懺悔・滅罪のために仏・菩薩に一万の灯明を供養する法会。東大寺・高野山・北野天満宮などで行われた。万灯供養。
⇒まん‐どう【万灯】
マントー【饅頭】
(中国語)小麦粉を練って発酵させ、蒸した丸いパン。
マントー‐はんのう【マントー反応】‥オウ
(→)ツベルクリン反応に同じ。フランスの医師マントー(C. Mantoux1877〜1947)が創始。
まん‐とく【万徳】
(マンドクとも)多くの徳行。多くの善行。
まん‐どころ【政所】
①政務・庶務をつかさどる所。
②平安時代以後、親王や公卿の家政機関。特に所領荘園の事務をつかさどった。
③鎌倉・室町幕府の財政および一部の民事訴訟をつかさどった機関。
④「北の政所」の略。
マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
女子宮廷礼装の一種。洋式大礼服。君主国の宮廷儀式参内に着用。→ローブ‐デコルテ→ローブ‐モンタント。
⇒マント【manteau フランス】
まんど‐ばらい【万度祓】‥バラヒ
①中臣なかとみの祓の詞を神前で一万度(度数の多い意)読んで罪をはらいきよめること。一万度祓。
②万度の祓をした祓串を白紙貼の祓箱に入れて家々に配るもの。万度。
⇒まん‐ど【万度・万灯】
マント‐ひひ【マント狒狒】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長90センチメートルほど、肩から背にかけて長い毛のマントをもつが、雌は体長50センチメートルほどで、たてがみはない。尾はともに長い。毛色は子供は黒で、成長すると茶色となり、マントは銀白色となる。アラビア半島からエチオピアの岩山に、群れをつくって生息。古代エジプトでは神として尊ばれた。
マントひひ
マンデリシターム【Osip E. Mandel'shtam】
ロシア(ソ連)の詩人。ユダヤ系。明晰な美を追求するアクメイズムの詩人として出発し、彫琢された形式と音楽性で際立った哲学的抒情詩を書く。スターリン諷刺の詩ゆえに逮捕され、獄死。詩集「石」「トリスチア」など。(1891〜1938)
マンデリン【Mandheling】
①インドネシア、スマトラ島北部の地方。
②1で産するアラビカ種のコーヒー。
マンテル【mantel オランダ】
マント。外套。
マンテルピース【mantelpiece】
⇒マントルピース
まん‐てん【万天】
天全体。また、天下四方。
まん‐てん【満天】
空全体。一天。「―の星」
⇒まんてん‐せい【満天星】
まん‐てん【満点】
規定された点の最高。また、それに達すること。百パーセントの成績。転じて、申し分のないこと。「サービス―」
まん‐てんか【満天下】
天下全体。全世界。
まんてん‐せい【満天星】
〔植〕
①ハクチョウゲ(白丁花)の別称。
②ドウダンツツジの漢名。
⇒まん‐てん【満天】
まん‐と【満都】
みやこのうち全体。
マント【manteau フランス】
ゆったりとした外套。日本では特に袖なしのものをいう。幕末、軍隊用としてとり入れられ、一般にも広く用いられるようになった。
⇒マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
⇒マント‐ひひ【マント狒狒】
まん‐と
〔副〕
(江戸後期の流行語)たくさん。どっさり。黄表紙、啌多雁取帳うそしっかりがんとりちょう「市に売り出す手桶を―拵へんと手間取りを多く入れて」
まん‐ど【万度・万灯】
四角い箱に、某社御祭礼などと大書、その下に町名を、また氏子中・子供中などと書き、これに灯火をともし、また花などを飾って祭礼に出すもの。まんどう。
⇒まんど‐ばらい【万度祓】
マン‐とう【マン島】‥タウ
(Isle of Man)イギリス、グレート‐ブリテン島と北アイルランドとの間のアイリッシュ海にある島。ケルト文化地域で、独自の法律・議会を有する。中心都市ダグラス。
まん‐どう【万灯】
①仏前にともす多くの灯火。御伽草子、梵天国「毎日―を三年ともして」
②(→)万度に同じ。
③(東北地方で)非常に明るいさま。
⇒まんどう‐え【万灯会】
まん‐どう【満堂】‥ダウ
堂の中に満ちること。堂いっぱい。堂の中の人全部。満場。
マンドヴィル【Bernard Mandeville】
フランス人の医師・思想家。オランダに生まれ、イギリスに移住。我欲・浪費等の個人の悪徳が仕事・雇用等を生み、社会の繁栄を導くことを暴露し、当時の倫理観の偽善を指摘。著「蜂の寓話」。(1670〜1733)
まんどう‐え【万灯会】‥ヱ
懺悔・滅罪のために仏・菩薩に一万の灯明を供養する法会。東大寺・高野山・北野天満宮などで行われた。万灯供養。
⇒まん‐どう【万灯】
マントー【饅頭】
(中国語)小麦粉を練って発酵させ、蒸した丸いパン。
マントー‐はんのう【マントー反応】‥オウ
(→)ツベルクリン反応に同じ。フランスの医師マントー(C. Mantoux1877〜1947)が創始。
まん‐とく【万徳】
(マンドクとも)多くの徳行。多くの善行。
まん‐どころ【政所】
①政務・庶務をつかさどる所。
②平安時代以後、親王や公卿の家政機関。特に所領荘園の事務をつかさどった。
③鎌倉・室町幕府の財政および一部の民事訴訟をつかさどった機関。
④「北の政所」の略。
マント‐ド‐クール【manteau de cour フランス】
女子宮廷礼装の一種。洋式大礼服。君主国の宮廷儀式参内に着用。→ローブ‐デコルテ→ローブ‐モンタント。
⇒マント【manteau フランス】
まんど‐ばらい【万度祓】‥バラヒ
①中臣なかとみの祓の詞を神前で一万度(度数の多い意)読んで罪をはらいきよめること。一万度祓。
②万度の祓をした祓串を白紙貼の祓箱に入れて家々に配るもの。万度。
⇒まん‐ど【万度・万灯】
マント‐ひひ【マント狒狒】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長90センチメートルほど、肩から背にかけて長い毛のマントをもつが、雌は体長50センチメートルほどで、たてがみはない。尾はともに長い。毛色は子供は黒で、成長すると茶色となり、マントは銀白色となる。アラビア半島からエチオピアの岩山に、群れをつくって生息。古代エジプトでは神として尊ばれた。
マントひひ
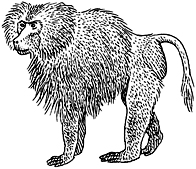 マントヒヒ
提供:東京動物園協会
マントヒヒ
提供:東京動物園協会
 ⇒マント【manteau フランス】
マントラ【mantra 梵】
(→)真言しんごんのこと。
マンドリル【mandrill】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長80センチメートル、雌は50センチメートルほどで、尾はともに短い。毛色は褐色。雄は成長すると鼻筋が赤くなり、周りに青い隆起を持つ。コンゴ・カメルーンなどの山地に小さい群れで生息。類似種にドリルがある。
マンドリル
提供:東京動物園協会
⇒マント【manteau フランス】
マントラ【mantra 梵】
(→)真言しんごんのこと。
マンドリル【mandrill】
オナガザル科のヒヒの一種。雄は体長80センチメートル、雌は50センチメートルほどで、尾はともに短い。毛色は褐色。雄は成長すると鼻筋が赤くなり、周りに青い隆起を持つ。コンゴ・カメルーンなどの山地に小さい群れで生息。類似種にドリルがある。
マンドリル
提供:東京動物園協会
 マンドリン【mandolin(e)】
弦楽器。背面が円い卵形の胴にスチール製の複弦を4対(8本)張り、鼈甲べっこうまたはセルロイド製の爪で弾奏。調弦はバイオリンと同一。
マンドリン
マンドリン【mandolin(e)】
弦楽器。背面が円い卵形の胴にスチール製の複弦を4対(8本)張り、鼈甲べっこうまたはセルロイド製の爪で弾奏。調弦はバイオリンと同一。
マンドリン
 マントル【mantle】
①(→)ガス‐マントルに同じ。
②地球の地殻と核との間の層。地球の体積の80パーセント以上を占める。地殻のすぐ下から深さ約2900キロメートルまでの部分。→モホロヴィチッチ不連続面。
⇒マントル‐たいりゅう【マントル対流】
⇒マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントル‐たいりゅう【マントル対流】‥リウ
地球内部の熱が外へ運ばれる一つの過程として考えられた熱対流。20世紀前半には、これがマントル内だけで起こり、それにひきずられて地殻に大陸移動などの変動が起こるという説が広まったが、現在考えられている熱対流は、大洋底リソスフェアとその下のアセノスフェアとの間で行われる物質循環やプルームによる大規模なものを指す。
⇒マントル【mantle】
マントルピース【mantelpiece】
暖炉の前飾り。壁付暖炉の上に設けた飾り棚。マンテルピース。
マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントルを構成する岩石。深さ900キロメートルまでは、橄欖岩かんらんがんや柘榴石ざくろいし橄欖岩が主体であり、柘榴石輝岩やエクロジャイトは少量。深さ900キロメートル以深では、橄欖石が高密度の鉱物に変化する。
⇒マントル【mantle】
まん‐どろ
(青森県で)非常に明るいこと。
まん‐な【真名・真字】
マナの撥音化。枕草子82「たどたどしき―に書きたらんも、いと見ぐるしと」
⇒まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
まん‐なおし【間直し・真直し】‥ナホシ
①運の悪いのをよくするためにある事を行うこと。
②不漁の際、好漁を祈願する酒宴。げん直し。船霊ふなだま遊ばせ。
まん‐なか【真ん中】
(マナカの撥音化)中心。中央。ただなか。もなか。「会場の―に座る」「三人姉妹の―です」「ひもを―で結ぶ」
まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
真名すなわち漢字で書いてある書。漢籍。紫式部日記「なでふ女が―は読む」
⇒まん‐な【真名・真字】
まんなり‐いし【万成石】
岡山市万成付近に産出する花崗岩。淡紅色で美しい。建築・土木用。万成みかげ。
マンナン【mannan】
マンノースをおもな構成成分とする多糖の総称。植物や微生物に含まれる。こんにゃくの主成分であるコンニャク‐マンナンはマンノースのほかにグルコースを構成成分とする。
まん‐にち【万日】
(新潟県などで)女の祈祷師。まんち。
まん‐にょう【万葉】‥エフ
(マンヨウの連声)
⇒まんよう。
⇒まんにょう‐しゅう【万葉集】
まんにょう‐しゅう【万葉集】‥エフシフ
⇒まんようしゅう
⇒まん‐にょう【万葉】
まん‐にん【万人】
よろずの人。多くの人。ばんじん。ばんにん。
⇒まんにん‐むき【万人向き】
まんにん‐むき【万人向き】
誰にでも向くこと。一般向き。ばんにんむき。
⇒まん‐にん【万人】
マンネリ
マンネリズムの略。
マンネリズム【mannerism】
一定の技法や形式を反復慣用し、固定した型にはまって独創性や新鮮さを失うようになる傾向。マナリズム。→マニエリスム
まん‐ねん【万年】
①万の年。非常に長い年月。「鶴は千年、亀は―」
②ある語に冠して、「いつまでも変わらない」「長くつづく」などの意を表す語。「―青年」
⇒まんねん‐がみ【万年紙】
⇒まんねん‐ぐさ【万年草】
⇒まんねん‐ごよみ【万年暦】
⇒まんねん‐しんぞ【万年新造】
⇒まんねん‐ず【万年酢】
⇒まんねん‐すぎ【万年杉】
⇒まんねん‐せい【万年青】
⇒まんねん‐たけ【万年茸】
⇒まんねん‐つうほう【万年通宝】
⇒まんねん‐どこ【万年床】
⇒まんねん‐ひつ【万年筆】
⇒まんねん‐ふで【万年筆】
⇒まんねん‐べい【万年塀】
⇒まんねん‐むすめ【万年娘】
⇒まんねん‐ゆき【万年雪】
まんねん‐がみ【万年紙】
厚紙に漆を塗った紙。墨で文字などを書いた後、湿った布で拭い去れば何回でも使えるもの。まんねんし。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ぐさ【万年草】
①ベンケイソウ科の多年草。山地に群生し、高さ20センチメートル、全体多肉。葉は線形で3葉が輪生。初夏、茎上に黄色、5弁の小花を散房状に密生。オノマンネングサ。イチゲソウ。タカノツメ。
マンネングサ
撮影:関戸 勇
マントル【mantle】
①(→)ガス‐マントルに同じ。
②地球の地殻と核との間の層。地球の体積の80パーセント以上を占める。地殻のすぐ下から深さ約2900キロメートルまでの部分。→モホロヴィチッチ不連続面。
⇒マントル‐たいりゅう【マントル対流】
⇒マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントル‐たいりゅう【マントル対流】‥リウ
地球内部の熱が外へ運ばれる一つの過程として考えられた熱対流。20世紀前半には、これがマントル内だけで起こり、それにひきずられて地殻に大陸移動などの変動が起こるという説が広まったが、現在考えられている熱対流は、大洋底リソスフェアとその下のアセノスフェアとの間で行われる物質循環やプルームによる大規模なものを指す。
⇒マントル【mantle】
マントルピース【mantelpiece】
暖炉の前飾り。壁付暖炉の上に設けた飾り棚。マンテルピース。
マントル‐ぶっしつ【マントル物質】
マントルを構成する岩石。深さ900キロメートルまでは、橄欖岩かんらんがんや柘榴石ざくろいし橄欖岩が主体であり、柘榴石輝岩やエクロジャイトは少量。深さ900キロメートル以深では、橄欖石が高密度の鉱物に変化する。
⇒マントル【mantle】
まん‐どろ
(青森県で)非常に明るいこと。
まん‐な【真名・真字】
マナの撥音化。枕草子82「たどたどしき―に書きたらんも、いと見ぐるしと」
⇒まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
まん‐なおし【間直し・真直し】‥ナホシ
①運の悪いのをよくするためにある事を行うこと。
②不漁の際、好漁を祈願する酒宴。げん直し。船霊ふなだま遊ばせ。
まん‐なか【真ん中】
(マナカの撥音化)中心。中央。ただなか。もなか。「会場の―に座る」「三人姉妹の―です」「ひもを―で結ぶ」
まんな‐ぶみ【真名書・真字書】
真名すなわち漢字で書いてある書。漢籍。紫式部日記「なでふ女が―は読む」
⇒まん‐な【真名・真字】
まんなり‐いし【万成石】
岡山市万成付近に産出する花崗岩。淡紅色で美しい。建築・土木用。万成みかげ。
マンナン【mannan】
マンノースをおもな構成成分とする多糖の総称。植物や微生物に含まれる。こんにゃくの主成分であるコンニャク‐マンナンはマンノースのほかにグルコースを構成成分とする。
まん‐にち【万日】
(新潟県などで)女の祈祷師。まんち。
まん‐にょう【万葉】‥エフ
(マンヨウの連声)
⇒まんよう。
⇒まんにょう‐しゅう【万葉集】
まんにょう‐しゅう【万葉集】‥エフシフ
⇒まんようしゅう
⇒まん‐にょう【万葉】
まん‐にん【万人】
よろずの人。多くの人。ばんじん。ばんにん。
⇒まんにん‐むき【万人向き】
まんにん‐むき【万人向き】
誰にでも向くこと。一般向き。ばんにんむき。
⇒まん‐にん【万人】
マンネリ
マンネリズムの略。
マンネリズム【mannerism】
一定の技法や形式を反復慣用し、固定した型にはまって独創性や新鮮さを失うようになる傾向。マナリズム。→マニエリスム
まん‐ねん【万年】
①万の年。非常に長い年月。「鶴は千年、亀は―」
②ある語に冠して、「いつまでも変わらない」「長くつづく」などの意を表す語。「―青年」
⇒まんねん‐がみ【万年紙】
⇒まんねん‐ぐさ【万年草】
⇒まんねん‐ごよみ【万年暦】
⇒まんねん‐しんぞ【万年新造】
⇒まんねん‐ず【万年酢】
⇒まんねん‐すぎ【万年杉】
⇒まんねん‐せい【万年青】
⇒まんねん‐たけ【万年茸】
⇒まんねん‐つうほう【万年通宝】
⇒まんねん‐どこ【万年床】
⇒まんねん‐ひつ【万年筆】
⇒まんねん‐ふで【万年筆】
⇒まんねん‐べい【万年塀】
⇒まんねん‐むすめ【万年娘】
⇒まんねん‐ゆき【万年雪】
まんねん‐がみ【万年紙】
厚紙に漆を塗った紙。墨で文字などを書いた後、湿った布で拭い去れば何回でも使えるもの。まんねんし。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ぐさ【万年草】
①ベンケイソウ科の多年草。山地に群生し、高さ20センチメートル、全体多肉。葉は線形で3葉が輪生。初夏、茎上に黄色、5弁の小花を散房状に密生。オノマンネングサ。イチゲソウ。タカノツメ。
マンネングサ
撮影:関戸 勇
 ②メノマンネングサの別称。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ごよみ【万年暦】
(1年だけの用に終わらない暦の意)暦日について、開運・相性などを記し集めた書。雑書。日本永代蔵5「―の合ふも不思議」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐しんぞ【万年新造】
いつまでも変わらない若々しい婦人。万年娘。まんねんしんぞう。人情本、春色辰巳園「―といはれたる花の盛りも永くは保たず」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ず【万年酢】
酒と酢と水とを合わせて密封し、数十日で成る酢。使った場合にはその分だけ酒と水を加えて置いて、常にその量が減らないようにして使用する。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐すぎ【万年杉】
ヒカゲノカズラ科のシダ植物。地中にのびた根茎から所々に茎を直立。高さ約15センチメートル。多くの枝を分け、茎・枝ともに鱗片状の小葉を密生し、スギの芽生えに似る。夏、茎頭に、円柱状で長さ2〜3センチメートルの胞子嚢穂を生ずる。アリマスギ。漢名、玉柏。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐せい【万年青】
〔植〕オモトの漢名。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐たけ【万年茸】
担子菌類のきのこ。広葉樹の枯木の根元に生える。腎臓形、傘・軸ともに赤褐色・赤紫色または暗紫色を呈し、漆のような光沢があり堅い。古来、乾して霊芝れいしと称し、床飾りとして愛玩する。サイワイタケ。芝草。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐つうほう【万年通宝】
760年(天平宝字4)、開基勝宝(金銭)・大平元宝(銀銭)とともに発行された銅銭。皇朝十二銭の一つ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐どこ【万年床】
常に敷きっぱなしにして、片付けたことのない寝床。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ひつ【万年筆】
(fountain pen)中空のペン軸にインクを入れ、その先に金または合金のペン先を取り付け、使用するにしたがって、インクがペン先に伝わり出るように装置したペン。万年ペン。夏目漱石、書簡「時さんの呉れた―は船中にて…打ち壊し申候」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ふで【万年筆】
明治期、「まんねんひつ」が一般化する前に用いた語。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐べい【万年塀】
プレキャスト‐コンクリート造りの組立塀。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐むすめ【万年娘】
(→)万年新造まんねんしんぞに同じ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ゆき【万年雪】
山地で雪線以上の所に年々降り積もる雪が、その重みによる圧縮その他の原因により、性質が変化して次第に粒状構造の氷塊になったもの。
⇒まん‐ねん【万年】
まん‐ねんれい【満年齢】
誕生日ごとに1歳ふえる年齢の数え方。また、それで数えた年齢。
まんねんろう
〔植〕(→)ローズマリーに同じ。
まん‐のう【万能】
①さまざまの物事にたくみなこと。ばんのう。狂言、八幡の前「こなたは―な人でござるによつて」
②除草に用いる農具。10センチメートル位の扁平または円くとがった刃に柄をはめたもの。
⇒まんのう‐こう【万能膏】
まんのう‐いけ【満濃池】
8世紀に造築され、821年(弘仁12)から3年をかけて空海らが修築した日本最大の灌漑用溜池。香川県仲多度郡まんのう町にあり、丸亀平野を灌漑。満水面積1.4平方キロメートル。周囲約20キロメートル。万農池。十千池とちのいけ。
満濃池
撮影:佐藤 尚
②メノマンネングサの別称。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ごよみ【万年暦】
(1年だけの用に終わらない暦の意)暦日について、開運・相性などを記し集めた書。雑書。日本永代蔵5「―の合ふも不思議」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐しんぞ【万年新造】
いつまでも変わらない若々しい婦人。万年娘。まんねんしんぞう。人情本、春色辰巳園「―といはれたる花の盛りも永くは保たず」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ず【万年酢】
酒と酢と水とを合わせて密封し、数十日で成る酢。使った場合にはその分だけ酒と水を加えて置いて、常にその量が減らないようにして使用する。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐すぎ【万年杉】
ヒカゲノカズラ科のシダ植物。地中にのびた根茎から所々に茎を直立。高さ約15センチメートル。多くの枝を分け、茎・枝ともに鱗片状の小葉を密生し、スギの芽生えに似る。夏、茎頭に、円柱状で長さ2〜3センチメートルの胞子嚢穂を生ずる。アリマスギ。漢名、玉柏。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐せい【万年青】
〔植〕オモトの漢名。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐たけ【万年茸】
担子菌類のきのこ。広葉樹の枯木の根元に生える。腎臓形、傘・軸ともに赤褐色・赤紫色または暗紫色を呈し、漆のような光沢があり堅い。古来、乾して霊芝れいしと称し、床飾りとして愛玩する。サイワイタケ。芝草。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐つうほう【万年通宝】
760年(天平宝字4)、開基勝宝(金銭)・大平元宝(銀銭)とともに発行された銅銭。皇朝十二銭の一つ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐どこ【万年床】
常に敷きっぱなしにして、片付けたことのない寝床。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ひつ【万年筆】
(fountain pen)中空のペン軸にインクを入れ、その先に金または合金のペン先を取り付け、使用するにしたがって、インクがペン先に伝わり出るように装置したペン。万年ペン。夏目漱石、書簡「時さんの呉れた―は船中にて…打ち壊し申候」
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ふで【万年筆】
明治期、「まんねんひつ」が一般化する前に用いた語。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐べい【万年塀】
プレキャスト‐コンクリート造りの組立塀。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐むすめ【万年娘】
(→)万年新造まんねんしんぞに同じ。
⇒まん‐ねん【万年】
まんねん‐ゆき【万年雪】
山地で雪線以上の所に年々降り積もる雪が、その重みによる圧縮その他の原因により、性質が変化して次第に粒状構造の氷塊になったもの。
⇒まん‐ねん【万年】
まん‐ねんれい【満年齢】
誕生日ごとに1歳ふえる年齢の数え方。また、それで数えた年齢。
まんねんろう
〔植〕(→)ローズマリーに同じ。
まん‐のう【万能】
①さまざまの物事にたくみなこと。ばんのう。狂言、八幡の前「こなたは―な人でござるによつて」
②除草に用いる農具。10センチメートル位の扁平または円くとがった刃に柄をはめたもの。
⇒まんのう‐こう【万能膏】
まんのう‐いけ【満濃池】
8世紀に造築され、821年(弘仁12)から3年をかけて空海らが修築した日本最大の灌漑用溜池。香川県仲多度郡まんのう町にあり、丸亀平野を灌漑。満水面積1.4平方キロメートル。周囲約20キロメートル。万農池。十千池とちのいけ。
満濃池
撮影:佐藤 尚
 まんのう‐こう【万能膏】‥カウ
傷・腫物などの一切に効能があるという膏薬。
⇒まん‐のう【万能】
マンノース【mannose】
分子式C6H12O6 ヘキソースの一つ。甘味と苦味のある白色結晶性物質。還元性をもつ。マンナン・コンニャク‐マンナン・糖蛋白質・配糖体などの構成成分として天然に広く存在。
まん‐ば【慢罵】
あなどりののしること。
まん‐ば【漫罵】
みだりにののしること。
マンバ【mamba】
コブラ科のヘビ。アフリカに4種が分布。有毒で、毒は主に神経毒。動きが速く危険。ブラック‐マンバは全長約3メートルに達する。
まん‐ぱ【万波】
幾重にも寄せて来る波。多くの波。ばんぱ。「千波―」
まん‐ぱい【満杯】
容器が中身で一杯であること。予定した数量に達していること。
マンハイム【Mannheim】
ドイツ南部、バーデン‐ヴュルテンベルク州の都市。ネッカー川がライン川に合流する地点に位置し、もとファルツ選帝侯の本拠地。18世紀以後、音楽の一中心地。機械・精密工業が盛ん。人口30万8千(1999)。
マンハイム【Karl Mannheim】
ハンガリー生れの社会学者。知識社会学の創始者として、知識の存在被拘束性を指摘。時代診断学としての社会学を企て「自由のための社会計画」を提唱。著「イデオロギーとユートピア」「変革期における人間と社会」など。(1893〜1947)
まん‐ばけん【万馬券】
競馬で、配当が100円につき1万円以上となる馬券。
まんのう‐こう【万能膏】‥カウ
傷・腫物などの一切に効能があるという膏薬。
⇒まん‐のう【万能】
マンノース【mannose】
分子式C6H12O6 ヘキソースの一つ。甘味と苦味のある白色結晶性物質。還元性をもつ。マンナン・コンニャク‐マンナン・糖蛋白質・配糖体などの構成成分として天然に広く存在。
まん‐ば【慢罵】
あなどりののしること。
まん‐ば【漫罵】
みだりにののしること。
マンバ【mamba】
コブラ科のヘビ。アフリカに4種が分布。有毒で、毒は主に神経毒。動きが速く危険。ブラック‐マンバは全長約3メートルに達する。
まん‐ぱ【万波】
幾重にも寄せて来る波。多くの波。ばんぱ。「千波―」
まん‐ぱい【満杯】
容器が中身で一杯であること。予定した数量に達していること。
マンハイム【Mannheim】
ドイツ南部、バーデン‐ヴュルテンベルク州の都市。ネッカー川がライン川に合流する地点に位置し、もとファルツ選帝侯の本拠地。18世紀以後、音楽の一中心地。機械・精密工業が盛ん。人口30万8千(1999)。
マンハイム【Karl Mannheim】
ハンガリー生れの社会学者。知識社会学の創始者として、知識の存在被拘束性を指摘。時代診断学としての社会学を企て「自由のための社会計画」を提唱。著「イデオロギーとユートピア」「変革期における人間と社会」など。(1893〜1947)
まん‐ばけん【万馬券】
競馬で、配当が100円につき1万円以上となる馬券。
広辞苑に「まんざら」で始まるの検索結果 1-2。