複数辞典一括検索+![]()
![]()
すね‐あて【臑当・脛当】🔗⭐🔉
すね‐あて【臑当・脛当】
①小具足の一種。膝から踝くるぶしまでをおおうもの。鉄または皮で作る。鉄板三枚割蝶番ちょうつがい留の丸篠まるしの、細かく分割して鎖でつないだ篠臑当などがある。臑鎧。
臑当
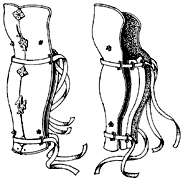 ②(→)シンガードに同じ。
②(→)シンガードに同じ。
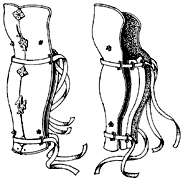 ②(→)シンガードに同じ。
②(→)シンガードに同じ。
スネア‐ドラム【snare drum】🔗⭐🔉
スネア‐ドラム【snare drum】
底面に、副次的な響きを加える細い鎖(響線)を張った小太鼓。
すね‐あらい‐さぶらい【臑洗い侍】‥アラヒサブラヒ🔗⭐🔉
すね‐あらい‐さぶらい【臑洗い侍】‥アラヒサブラヒ
他人の臑を洗うほどの、卑しい侍。成り上りの侍などを卑しめていう語。浄瑠璃、井筒業平河内通「ヤイ―の馬鹿者」
すね・い【拗い】🔗⭐🔉
すね・い【拗い】
〔形〕
すねている。ひねくれている。狂言、腹立てず「そうじて最前から、―・い事をいうた程に」。日葡辞書「スネイヒト」
スネーク【snake】🔗⭐🔉
スネーク【snake】
蛇。「―‐ダンス」
⇒スネーク‐ウッド【snakewood】
スネーク‐ウッド【snakewood】🔗⭐🔉
スネーク‐ウッド【snakewood】
ブラジル産のクワ科の高木。材は重く堅く、蛇のような斑紋がある。ステッキ材として珍重。ほかに、パイプ材・装飾材。
⇒スネーク【snake】
すね‐おし【臑押し】🔗⭐🔉
すね‐おし【臑押し】
互いに腰を下ろして向かい合い、片方の臑で互いの臑を押し合って勝負を決める遊戯。狂言、首引「―を致しませう」
すね‐かじり【臑齧り】🔗⭐🔉
○臑が流れるすねがながれる🔗⭐🔉
○臑が流れるすねがながれる
臑にふみこたえる力がない。足もとが定まらない。狂言、悪坊「臑が流れて使はれぬ」
⇒すね【臑・脛】
○臑から火を取るすねからひをとる🔗⭐🔉
○臑から火を取るすねからひをとる
(火をつける道具もない意)はなはだしく貧しいことのたとえ。「すねより火を出す」とも。元禄大平記「古帷子ふるかたびら一つ召して、―この西鶴同然の御ありさま」
⇒すね【臑・脛】
すね‐き【拗木】
幹のねじ曲がった木。浄瑠璃、絵本太功記「庭先の―の松が枝、踏みしめ踏みしめよぢ登り」
すね‐き【拗ね気】
すねる心のあること。
すね‐くさ【臑瘡】
〔医〕(→)雁瘡がんがさに同じ。
すね‐くろし・い【拗ねくろしい】
〔形〕
すねたようである。ひねくれている。浄瑠璃、栬狩剣本地「お悦びであらうと競ひかかつて戻つたに、さつても当の違うた、あの―・いお顔わい」
すね‐ごと【拗ね言】
すねていう言葉。すねことば。日葡辞書「スネコトヲユウ」
すね‐ことば【拗ね言葉】
(→)「すねごと」に同じ。
すね‐ざんまい【臑三昧】
むやみに臑を出して蹴ったりすること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「武士の前にて―と散々に叱らるる」
すねすね‐し・い【拗ね拗ねしい】
〔形〕
大層すねている。しつこくひがんでいる。浄瑠璃、日本振袖始「心まで―・く」
ず‐ねつ【頭熱】ヅ‥
頭部に熱気のあること。のぼせ。
すねっ‐ぱぎ【臑っ脛】
スネハギの促音化。浄瑠璃、曾我会稽山「徒歩かち―やつこらさ」
すね‐き【拗木】🔗⭐🔉
すね‐き【拗木】
幹のねじ曲がった木。浄瑠璃、絵本太功記「庭先の―の松が枝、踏みしめ踏みしめよぢ登り」
すね‐き【拗ね気】🔗⭐🔉
すね‐き【拗ね気】
すねる心のあること。
すね‐くろし・い【拗ねくろしい】🔗⭐🔉
すね‐くろし・い【拗ねくろしい】
〔形〕
すねたようである。ひねくれている。浄瑠璃、栬狩剣本地「お悦びであらうと競ひかかつて戻つたに、さつても当の違うた、あの―・いお顔わい」
すね‐ごと【拗ね言】🔗⭐🔉
すね‐ごと【拗ね言】
すねていう言葉。すねことば。日葡辞書「スネコトヲユウ」
すね‐ことば【拗ね言葉】🔗⭐🔉
すね‐ことば【拗ね言葉】
(→)「すねごと」に同じ。
すね‐ざんまい【臑三昧】🔗⭐🔉
すね‐ざんまい【臑三昧】
むやみに臑を出して蹴ったりすること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「武士の前にて―と散々に叱らるる」
すねすね‐し・い【拗ね拗ねしい】🔗⭐🔉
すねすね‐し・い【拗ね拗ねしい】
〔形〕
大層すねている。しつこくひがんでいる。浄瑠璃、日本振袖始「心まで―・く」
すねっ‐ぱぎ【臑っ脛】🔗⭐🔉
すねっ‐ぱぎ【臑っ脛】
スネハギの促音化。浄瑠璃、曾我会稽山「徒歩かち―やつこらさ」
○臑に疵持つすねにきずもつ
隠した悪事がある。やましいことがある。うしろぐらいことがある。洒落本、南閨雑話「すねにきずを持つて笹原を走るとやら」。「―身」
⇒すね【臑・脛】
すね‐はぎ【臑脛】🔗⭐🔉
すね‐はぎ【臑脛】
(「すね」と「はぎ」は同義)すね。足。
⇒臑脛の延びた奴
○臑脛の延びた奴すねはぎののびたやつ
いたずらに背丈ばかり高く、物の用に立たない者をののしっていう語。
⇒すね‐はぎ【臑脛】
○臑脛の延びた奴すねはぎののびたやつ🔗⭐🔉
○臑脛の延びた奴すねはぎののびたやつ
いたずらに背丈ばかり高く、物の用に立たない者をののしっていう語。
⇒すね‐はぎ【臑脛】
すねはじかみ【脛薑】
狂言。(→)「芥川あくたがわ」に同じ。
すね‐はたば・る【拗ねはたばる】
〔自四〕
すねて強情を張る。浄瑠璃、傾城酒呑童子「情知らぬ親方と、―・つて」→はたばる
すね‐ふり【脛振り】
①侠客。おとこだて。(和訓栞)
②(長崎・福岡地方で)客が遊郭をひやかして歩くこと。そぞろ歩き。東海道中膝栗毛8「たんだ此の廓ども、―にづらんばいと言ひおつたのじや」
すね‐もの【拗ね者】
すねる人。世をすねた人。つむじまがり。浮世物語「極めたる―」
すね‐よろい【臑鎧】‥ヨロヒ
(→)「すねあて」に同じ。
す・ねる【拗ねる】
〔自下一〕
①ひねくれている。偏屈である。謡曲、鵜飼「まづは―・ねた出家かな」
②ねじけて我意を張る。不平がましく人に従わない。昨日は今日の物語「理非は聞き知る人がござらうとていよいよ―・ねける」。「世を―・ねる」
スネル‐の‐ほうそく【スネルの法則】‥ハフ‥
光の屈折の法則。異なる媒質の境界に光が入射するとき、入射角の正弦と屈折角の正弦との比は、媒質の屈折率の比に等しいという法則。オランダの数学者スネル(W. Snell1591〜1626)が確立。
すねはじかみ【脛薑】🔗⭐🔉
すねはじかみ【脛薑】
狂言。(→)「芥川あくたがわ」に同じ。
すね‐はたば・る【拗ねはたばる】🔗⭐🔉
すね‐はたば・る【拗ねはたばる】
〔自四〕
すねて強情を張る。浄瑠璃、傾城酒呑童子「情知らぬ親方と、―・つて」→はたばる
すね‐ふり【脛振り】🔗⭐🔉
すね‐ふり【脛振り】
①侠客。おとこだて。(和訓栞)
②(長崎・福岡地方で)客が遊郭をひやかして歩くこと。そぞろ歩き。東海道中膝栗毛8「たんだ此の廓ども、―にづらんばいと言ひおつたのじや」
すね‐もの【拗ね者】🔗⭐🔉
すね‐もの【拗ね者】
すねる人。世をすねた人。つむじまがり。浮世物語「極めたる―」
すね‐よろい【臑鎧】‥ヨロヒ🔗⭐🔉
すね‐よろい【臑鎧】‥ヨロヒ
(→)「すねあて」に同じ。
す・ねる【拗ねる】🔗⭐🔉
す・ねる【拗ねる】
〔自下一〕
①ひねくれている。偏屈である。謡曲、鵜飼「まづは―・ねた出家かな」
②ねじけて我意を張る。不平がましく人に従わない。昨日は今日の物語「理非は聞き知る人がござらうとていよいよ―・ねける」。「世を―・ねる」
スネル‐の‐ほうそく【スネルの法則】‥ハフ‥🔗⭐🔉
スネル‐の‐ほうそく【スネルの法則】‥ハフ‥
光の屈折の法則。異なる媒質の境界に光が入射するとき、入射角の正弦と屈折角の正弦との比は、媒質の屈折率の比に等しいという法則。オランダの数学者スネル(W. Snell1591〜1626)が確立。
○臑を齧るすねをかじる
独立して生活できず、親や他人に養ってもらう。
⇒すね【臑・脛】
○臑を齧るすねをかじる🔗⭐🔉
○臑を齧るすねをかじる
独立して生活できず、親や他人に養ってもらう。
⇒すね【臑・脛】
ず‐ねん【頭燃】ヅ‥
〔仏〕頭髪のもえること。危急にたとえた語。太平記2「―を払ふごとくになりぬと覚つて」
す‐のう【収納】‥ナフ
(シュウノウの直音化)
①収穫。また、収穫の最盛期。しゅん。
②収穫物などを入れておく所(小屋)。すのうば。
③小作料を納める日。
⇒すのう‐ば【収納場】
ず‐のう【図嚢】ヅナウ
地図などを入れ、腰にさげる小型かばん。
ず‐のう【頭脳】ヅナウ
①脳。脳髄。頭。
②識別力。判断力。思考力。「―明晰」
③中心となっている人物。首脳。
⇒ずのう‐しゅうだん【頭脳集団】
⇒ずのう‐りゅうしゅつ【頭脳流出】
⇒ずのう‐ろうどう【頭脳労働】
ずのう‐しゅうだん【頭脳集団】ヅナウシフ‥
専門知識を持った人の集まり。シンクタンク。
⇒ず‐のう【頭脳】
すのう‐ば【収納場】‥ナフ‥
物置場。
⇒す‐のう【収納】
ずのう‐りゅうしゅつ【頭脳流出】ヅナウリウ‥
専門的な知識や技術を持つ人が、条件のよい海外に移住すること。
⇒ず‐のう【頭脳】
ずのう‐ろうどう【頭脳労働】ヅナウラウ‥
主として知識や思考力を使って行う仕事。精神労働。
⇒ず‐のう【頭脳】
スノー【snow】
雪。
⇒スノー‐スタイル
⇒スノー‐タイヤ【snow tire】
⇒スノー‐ドロップ【snowdrop】
⇒スノー‐ブーツ【snow boots】
⇒スノー‐ブリッジ【snowbridge】
⇒スノー‐フレーク【snowflake】
⇒スノー‐ボート【snow boat】
⇒スノー‐ボード【snowboard】
⇒スノー‐モービル【snow mobile】
スノー【Charles Percy Snow】
イギリスの小説家。「他人と兄弟」と題する連作小説のほか、論争を呼んだ評論「二つの文化と科学革命」など。(1905〜1980)
スノー【Edgar Parks Snow】
アメリカの新聞記者・著述家。中国共産党・紅軍についてのルポなど、独自の中国報道で知られた。元妻のニム=ウェールズ(Nym Wales1905〜1997)も中国報道で知られた。著「中国の赤い星」など。(1905〜1972)
スノー‐スタイル
(和製語snow style)カクテルを供するスタイルの一つ。グラスの縁をレモンでぬらし、砂糖や塩をまぶす。
⇒スノー【snow】
スノー‐タイヤ【snow tire】
雪の上を走るための特殊タイヤ。滑り止めに深い溝がきざんである。
⇒スノー【snow】
スノー‐ドロップ【snowdrop】
ヒガンバナ科の観賞用植物。地中海西部からカフカスに約20種分布。葉は線形でうすく白粉を帯びる。20センチメートルほどの花茎を出し、先端に数個の白色花を下向きにつける。花被は6弁、早春に開花。秋植の球根類として栽培。ユキノハナ。マツユキソウ。
スノードロップ
提供:OPO
 ⇒スノー【snow】
スノー‐ブーツ【snow boots】
足首まで覆う雪道用の靴。
⇒スノー【snow】
スノー‐ブリッジ【snowbridge】
沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。
⇒スノー【snow】
スノー‐フレーク【snowflake】
(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボート【snow boat】
雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボード【snowboard】
サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。
⇒スノー【snow】
スノー‐モービル【snow mobile】
雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。
⇒スノー【snow】
す‐の‐こ【簀子】
①竹や葦で編んだ簀。
②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。
③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。
④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。
⇒すのこ‐えん【簀子縁】
⇒すのこ‐まき【簀子巻】
すのこ‐えん【簀子縁】
板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。
⇒す‐の‐こ【簀子】
すのこ‐まき【簀子巻】
(→)「すまき」2に同じ。
⇒す‐の‐こ【簀子】
⇒スノー【snow】
スノー‐ブーツ【snow boots】
足首まで覆う雪道用の靴。
⇒スノー【snow】
スノー‐ブリッジ【snowbridge】
沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。
⇒スノー【snow】
スノー‐フレーク【snowflake】
(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボート【snow boat】
雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボード【snowboard】
サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。
⇒スノー【snow】
スノー‐モービル【snow mobile】
雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。
⇒スノー【snow】
す‐の‐こ【簀子】
①竹や葦で編んだ簀。
②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。
③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。
④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。
⇒すのこ‐えん【簀子縁】
⇒すのこ‐まき【簀子巻】
すのこ‐えん【簀子縁】
板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。
⇒す‐の‐こ【簀子】
すのこ‐まき【簀子巻】
(→)「すまき」2に同じ。
⇒す‐の‐こ【簀子】
 ⇒スノー【snow】
スノー‐ブーツ【snow boots】
足首まで覆う雪道用の靴。
⇒スノー【snow】
スノー‐ブリッジ【snowbridge】
沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。
⇒スノー【snow】
スノー‐フレーク【snowflake】
(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボート【snow boat】
雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボード【snowboard】
サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。
⇒スノー【snow】
スノー‐モービル【snow mobile】
雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。
⇒スノー【snow】
す‐の‐こ【簀子】
①竹や葦で編んだ簀。
②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。
③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。
④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。
⇒すのこ‐えん【簀子縁】
⇒すのこ‐まき【簀子巻】
すのこ‐えん【簀子縁】
板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。
⇒す‐の‐こ【簀子】
すのこ‐まき【簀子巻】
(→)「すまき」2に同じ。
⇒す‐の‐こ【簀子】
⇒スノー【snow】
スノー‐ブーツ【snow boots】
足首まで覆う雪道用の靴。
⇒スノー【snow】
スノー‐ブリッジ【snowbridge】
沢または氷河に、橋をかけ渡したように残雪が両岸にまたがってかかっているもの。雪橋。
⇒スノー【snow】
スノー‐フレーク【snowflake】
(雪片の意)ヒガンバナ科の多年草。南ヨーロッパ原産の観賞用植物。スイセンに似た球根があり、根生葉もスイセンに似て幅広の線形。早春、花茎上に鐘形、緑白色の花をスズラン状に垂下する。オオマツユキソウ。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボート【snow boat】
雪の上を荷物や傷病者などを乗せて運ぶボート型のそり。
⇒スノー【snow】
スノー‐ボード【snowboard】
サーフィンのように横向きに乗り、ストックを使わずに雪上を滑り降りる幅広の滑走板。また、それを用いた競技。スノボ。
⇒スノー【snow】
スノー‐モービル【snow mobile】
雪上車の一種。特にキャタピラー付きのオートバイ型のそり。
⇒スノー【snow】
す‐の‐こ【簀子】
①竹や葦で編んだ簀。
②水切りのため竹や板を間をすかせて張った床・縁、または台。浴室や流しに用いる。
③劇場の舞台の天井。ぶどう棚。
④角材をいう。平安時代の規格では方4寸。
⇒すのこ‐えん【簀子縁】
⇒すのこ‐まき【簀子巻】
すのこ‐えん【簀子縁】
板の間をすかして簀子状に張った榑縁くれえん。すのこ。簀子敷。→ひさし1。
⇒す‐の‐こ【簀子】
すのこ‐まき【簀子巻】
(→)「すまき」2に同じ。
⇒す‐の‐こ【簀子】
広辞苑に「スネ」で始まるの検索結果 1-31。