複数辞典一括検索+![]()
![]()
つめ🔗⭐🔉
つめ
文楽人形の首かしらの一つ。男女の雑多な端役に用いるもの。
つめ【爪】🔗⭐🔉
つめ【爪】
①指または趾あしゆびの先端に生じる角質の突起。表皮の堅くなったもの。人の爪は扁爪ひらづめといい、他の動物には鉤爪かぎづめと蹄ひづめがある。また、昆虫では跗節ふせつの末端の小節をいう。万葉集18「馬の―い尽す極み」
②琴爪ことづめ。また、鞍爪くらづめ。
③物をひっかけるために装置した物、すなわち、こはぜ・鉤かぎの類。
④花弁の基部の細まった部分。
⇒爪食う
⇒爪で拾って箕で零す
⇒爪に爪なく瓜に爪あり
⇒爪に火をともす
⇒爪を隠す
⇒爪を銜える
⇒爪を研ぐ
つめ【詰め】🔗⭐🔉
つめ【詰め】
①物をつめること。
②隙間につめこむもの。日葡辞書「ツメヲカ(支)ウ」
③物の端。きわ。特に、橋のたもと。万葉集9「大橋の―に家あらば」
④かぎり。結末。三道「その所の名歌・名句の言葉を取ること、能の破三段の中の―と覚しからん在所に書くべし」
⑤勝負・決着をつけるべき最後の追込み・手順。また、物事の最後の段取り。「―が甘い」
⑥城の最も高い所。日葡辞書「シロノツメ」
⑦(振袖に対する脇つめの衣の意から)年増としまの女。わきつめ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「枕の御伽が御用ならば振袖なりと―なりと」
⑧(→)「おつめ」に同じ。
⑨蹴鞠けまりで、詰め寄せること。狂言、八幡の前「お若い衆の遊ばすに依て―を致いてござる」
⑩牢ろう内の便所。大便。
⑪(「づめ」の形で)
㋐詰めること。また、詰めてあるもの。「瓶―」「氷―」
㋑一定の場所に控えて勤務すること。その場所、また、その人。「警視庁―の記者」
㋒もっぱらそれで通すこと。「理―」「規則―」
㋓(動詞の連用形に付けて)その状態が続くこと。「笑い―」「働き―」
つめ‐あい【詰め合い】‥アヒ🔗⭐🔉
つめ‐あい【詰め合い】‥アヒ
①共に同じ所につめていること。同じ所に勤めていること。また、その人。
②論じあうこと。
つめ‐あ・う【詰め合ふ】‥アフ🔗⭐🔉
つめ‐あ・う【詰め合ふ】‥アフ
〔自四〕
①同じ所に出仕する。同じ所に勤める。
②論じあって互いにつめよる。歌舞伎、傾城壬生大念仏「後に若林と―・ひ、実めきて面白し」
つめ‐あと【爪痕】🔗⭐🔉
つめ‐あと【爪痕】
①物についている爪のかた。
②爪でかいたきずあと。比喩的に、事件・災害が残した被害や影響。「台風の―」
つめ‐あわせ【詰合せ】‥アハセ🔗⭐🔉
つめ‐あわせ【詰合せ】‥アハセ
一つの容器にいろいろの品物を詰めること。また、その詰めたもの。「果物の―」
つめ‐あわ・せる【詰め合わせる】‥アハセル🔗⭐🔉
つめ‐あわ・せる【詰め合わせる】‥アハセル
〔他下一〕[文]つめあは・す(下二)
いろいろの品物を一つの容器に一緒に詰める。
つめ‐いくさ【詰め軍】🔗⭐🔉
つめ‐いくさ【詰め軍】
敵を追いつめて戦ういくさ。義経記4「壇の浦の―までもつひに弱げを見せ給はず」
つめ‐いし【詰め石】🔗⭐🔉
つめ‐いし【詰め石】
積み上げた石。積石。また、いしずえ。栄華物語音楽「大象の―、紫金銀の棟」
つめ‐いん【爪印】🔗⭐🔉
つめ‐いん【爪印】
(ソウインとも)爪先に墨・印肉をつけ、印鑑の代りに押して証とするもの。墨などをつけないで、紙面に爪痕だけをつける場合もある。奈良時代に中国から伝わり江戸時代に盛行。爪判そうはん。つめばん。
つめ‐うた【詰歌】🔗⭐🔉
つめ‐うた【詰歌】
狂歌の一種。故意に名詞・助詞などを省略、要約したもの。天明(1781〜1789)ごろ江戸で流行。
つめ‐えり【詰襟】🔗⭐🔉
つめ‐えり【詰襟】
洋服の襟の立っているもの。また、その洋服。軍服や学生服に多い。
つめ‐かえ【詰め替え】‥カヘ🔗⭐🔉
つめ‐かえ【詰め替え】‥カヘ
つめかえること。また、つめかえたもの。
つめ‐か・える【詰め替える】‥カヘル🔗⭐🔉
つめ‐か・える【詰め替える】‥カヘル
〔他下一〕[文]つめか・ふ(下二)
改めてつめる。つめなおす。「パイプの煙草を―・える」「大瓶から小瓶に―・える」
つめ‐がえる【爪蛙】‥ガヘル🔗⭐🔉
つめ‐がえる【爪蛙】‥ガヘル
カエルの一種。体長約10センチメートル。後肢のみずかきはよく発達し、内側の3本の指先に黒色の爪がある。ほとんど水中生活。舌がないので、前肢を使って餌をとる。オタマジャクシは透きとおっていて、口角にひげがある。アフリカ中部・南部に分布。医学などの実験動物として広く飼育。ペットとしても人気がある。アフリカツメガエル。
つめがえる
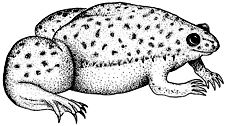 ツメガエル
提供:東京動物園協会
ツメガエル
提供:東京動物園協会

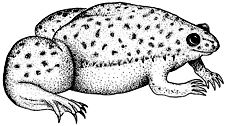 ツメガエル
提供:東京動物園協会
ツメガエル
提供:東京動物園協会

つめ‐か・ける【詰め掛ける】🔗⭐🔉
つめ‐か・ける【詰め掛ける】
〔自下一〕[文]つめか・く(下二)
①大勢の人がひと所に押しよせる。「新聞記者が―・ける」
②間近く迫り寄る。色道大鏡「立たんとするをもすかさず―・けてのますれば」
つめ‐がた【爪形】🔗⭐🔉
つめ‐がた【爪形】
①つめのあと。つめのかた。
②爪印つめいん。
つめ‐かみ【爪髪】🔗⭐🔉
つめ‐かみ【爪髪】
馬のひづめとたてがみ。狂言、富士松「是は―はつたと致いて、たくましいよいお馬ではござれども」
つめ‐かんむり【爪冠】🔗⭐🔉
つめ‐かんむり【爪冠】
漢字の冠かんむりの一つ。「爰」「爵」などの冠の「爫」の称。
つめ‐きり【爪切り】🔗⭐🔉
つめ‐きり【爪切り】
①刃先が爪形に曲がっている、爪を切る具。
②爪切り鋏の略。
⇒つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
つめ‐きり【詰め切り】🔗⭐🔉
つめ‐きり【詰め切り】
たえずそこにいること。つめっきり。「―で看病する」
つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】🔗⭐🔉
つめきり‐ばさみ【爪切り鋏】
手足の爪を切りとるのに使う小さい鋏。つめとりばさみ。
⇒つめ‐きり【爪切り】
つめ‐き・る【詰め切る】🔗⭐🔉
つめ‐き・る【詰め切る】
[一]〔自五〕
その場を離れずに、ずっとそこにいて勤務や待機をする。
[二]〔他五〕
つめこみおわる。いっぱいに詰め込む。
○爪食うつめくう
はずかしがる様子をいう。もじもじする。源氏物語帚木「なま人わろく、爪くはるれど」
⇒つめ【爪】
○爪食うつめくう🔗⭐🔉
○爪食うつめくう
はずかしがる様子をいう。もじもじする。源氏物語帚木「なま人わろく、爪くはるれど」
⇒つめ【爪】
つめ‐くさ【爪草】
ナデシコ科の一年草または越年草。路傍や山野に普通な雑草で、茎は根元から枝分れし、高さ3〜10センチメートル。葉は線形で小さい。春から秋にかけて白色5弁の小花を次々と開き、蒴果さくかを結ぶ。タカノツメ。
つめ‐くさ【詰草】
(梱包の詰物として用いたのでいう)シロツメクサの別称。
つめ‐くそ【爪糞】
爪にたまった垢。爪のあか。
つめ‐ぐみ【詰組】
〔建〕柱上ばかりでなく、柱と柱との間にも組物を配する組み方。唐様建築にみられる。↔阿麻組
つめ‐クラッチ【爪クラッチ】
〔機〕(→)咬合かみあいクラッチに同じ。
つめ‐ぐるま【爪車】
爪と噛み合わせて、間歇かんけつ的な一方向回転運動を伝達し、逆方向回転を防止する一種の歯車。ラチェット。
爪車
 つめ‐ご【詰碁】
碁の部分的な局面を作り、死活を考えさせるもの。
つめ‐ごい【詰乞い】‥ゴヒ
強く、しつこく乞いもとめること。日葡辞書「ツメゴイニコウ」
つめ‐こすり【爪擦り】
切った爪の角かどをこすってなめらかにする具。細長いやすり状のもの。爪みがき。
つめ‐こみ【詰込み】
つめこむこと。
⇒つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
知識の注入や、知識の暗誦・記憶を重視する教育の仕方。
⇒つめ‐こみ【詰込み】
つめ‐こ・む【詰め込む】
〔他五〕
①つめて入れる。つめられるだけ一杯に入れる。「腹一杯―・む」
②知識をむやみに覚える。「英語の単語を―・む」
つめ‐ごろし【詰め殺し】
こっそりと、物を言わせないで殺すこと。〈日葡辞書〉
つめ‐ざ【詰座】
末座。幸若舞曲、和田酒盛「―に、ちやうと直つた」
つめ‐さいそく【詰催促】
きびしい催促。根無草後編「日夜朝暮の―」
つめ‐ざかもり【詰酒盛】
詰座で酒盛をすること。幸若舞曲、和田酒盛「これ程広い座敷にて、―は無用さうぞ」
つめ‐さむらい【詰侍】‥サムラヒ
勤務中の侍。つめている侍。浄瑠璃、平家女護島「荒れに荒れたる有王丸、当番の―」
つめ‐しゅう【詰衆】
⇒おつめしゅう(御詰衆)。
⇒つめしゅう‐なみ【詰衆並】
つめしゅう‐なみ【詰衆並】
(→)詰並つめなみに同じ。
⇒つめ‐しゅう【詰衆】
つめ‐しょ【詰所】
①多くの人の詰めている所。
②官吏・係員などの出勤している所。「警備員の―」
つめ‐しょうぎ【詰将棋】‥シヤウ‥
将棋で、与えられた譜面と駒とを使って、規則に従って王手をつづけて王将を詰めること。詰物。
つめ‐じん【詰陣】‥ヂン
敵に近く接している軍隊の陣。〈日葡辞書〉
つめ‐そで【詰袖】
袖の腋明けを縫い縮めた袖。また、その着物。近世、男は半元服(13、4歳)、女は19歳になると着た。
つめた【冷た】
(ツメタシの語幹)麻布の夜具または綿入れ。布子。おひえ。狂言、比丘貞「鎌倉の上臈は、すす竹の―に織物の手おほひ」
⇒つめた‐もの【冷た物】
つめた・い【冷たい】
〔形〕[文]つめた・し(ク)
①温度が低く、ひややかに感ずる。ひややかである。つべたい。〈[季]冬〉。落窪物語1「単衣もなくていと―・ければ、単衣を脱ぎすべして起き出でたまふ」。「―・い飲み物」
②人情に薄い。冷淡である。「―・い仕打ちを受ける」「―・い目で見る」
⇒冷たくなる
つめたい‐せんそう【冷たい戦争】‥サウ
(cold war)(→)冷戦に同じ。
つめた‐がい【津免多貝】‥ガヒ
タマガイ科の巻貝。殻高約7センチメートル、殻幅約8センチメートル。殻は淡い褐色で底面は黄色。潮間帯の砂の中にすみ、アサリなどの殻に孔を開けて肉を食う。夏、茶碗形の卵塊を産む(すなぢゃわんと呼ばれる)。うつぼがい。虚貝うつせがい。津辺多貝つべたがい。蚜貝。〈書言字考節用集〉
つめたがい
つめ‐ご【詰碁】
碁の部分的な局面を作り、死活を考えさせるもの。
つめ‐ごい【詰乞い】‥ゴヒ
強く、しつこく乞いもとめること。日葡辞書「ツメゴイニコウ」
つめ‐こすり【爪擦り】
切った爪の角かどをこすってなめらかにする具。細長いやすり状のもの。爪みがき。
つめ‐こみ【詰込み】
つめこむこと。
⇒つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
知識の注入や、知識の暗誦・記憶を重視する教育の仕方。
⇒つめ‐こみ【詰込み】
つめ‐こ・む【詰め込む】
〔他五〕
①つめて入れる。つめられるだけ一杯に入れる。「腹一杯―・む」
②知識をむやみに覚える。「英語の単語を―・む」
つめ‐ごろし【詰め殺し】
こっそりと、物を言わせないで殺すこと。〈日葡辞書〉
つめ‐ざ【詰座】
末座。幸若舞曲、和田酒盛「―に、ちやうと直つた」
つめ‐さいそく【詰催促】
きびしい催促。根無草後編「日夜朝暮の―」
つめ‐ざかもり【詰酒盛】
詰座で酒盛をすること。幸若舞曲、和田酒盛「これ程広い座敷にて、―は無用さうぞ」
つめ‐さむらい【詰侍】‥サムラヒ
勤務中の侍。つめている侍。浄瑠璃、平家女護島「荒れに荒れたる有王丸、当番の―」
つめ‐しゅう【詰衆】
⇒おつめしゅう(御詰衆)。
⇒つめしゅう‐なみ【詰衆並】
つめしゅう‐なみ【詰衆並】
(→)詰並つめなみに同じ。
⇒つめ‐しゅう【詰衆】
つめ‐しょ【詰所】
①多くの人の詰めている所。
②官吏・係員などの出勤している所。「警備員の―」
つめ‐しょうぎ【詰将棋】‥シヤウ‥
将棋で、与えられた譜面と駒とを使って、規則に従って王手をつづけて王将を詰めること。詰物。
つめ‐じん【詰陣】‥ヂン
敵に近く接している軍隊の陣。〈日葡辞書〉
つめ‐そで【詰袖】
袖の腋明けを縫い縮めた袖。また、その着物。近世、男は半元服(13、4歳)、女は19歳になると着た。
つめた【冷た】
(ツメタシの語幹)麻布の夜具または綿入れ。布子。おひえ。狂言、比丘貞「鎌倉の上臈は、すす竹の―に織物の手おほひ」
⇒つめた‐もの【冷た物】
つめた・い【冷たい】
〔形〕[文]つめた・し(ク)
①温度が低く、ひややかに感ずる。ひややかである。つべたい。〈[季]冬〉。落窪物語1「単衣もなくていと―・ければ、単衣を脱ぎすべして起き出でたまふ」。「―・い飲み物」
②人情に薄い。冷淡である。「―・い仕打ちを受ける」「―・い目で見る」
⇒冷たくなる
つめたい‐せんそう【冷たい戦争】‥サウ
(cold war)(→)冷戦に同じ。
つめた‐がい【津免多貝】‥ガヒ
タマガイ科の巻貝。殻高約7センチメートル、殻幅約8センチメートル。殻は淡い褐色で底面は黄色。潮間帯の砂の中にすみ、アサリなどの殻に孔を開けて肉を食う。夏、茶碗形の卵塊を産む(すなぢゃわんと呼ばれる)。うつぼがい。虚貝うつせがい。津辺多貝つべたがい。蚜貝。〈書言字考節用集〉
つめたがい
 ツメタガイ
提供:東京動物園協会
ツメタガイ
提供:東京動物園協会

 つめ‐ご【詰碁】
碁の部分的な局面を作り、死活を考えさせるもの。
つめ‐ごい【詰乞い】‥ゴヒ
強く、しつこく乞いもとめること。日葡辞書「ツメゴイニコウ」
つめ‐こすり【爪擦り】
切った爪の角かどをこすってなめらかにする具。細長いやすり状のもの。爪みがき。
つめ‐こみ【詰込み】
つめこむこと。
⇒つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
知識の注入や、知識の暗誦・記憶を重視する教育の仕方。
⇒つめ‐こみ【詰込み】
つめ‐こ・む【詰め込む】
〔他五〕
①つめて入れる。つめられるだけ一杯に入れる。「腹一杯―・む」
②知識をむやみに覚える。「英語の単語を―・む」
つめ‐ごろし【詰め殺し】
こっそりと、物を言わせないで殺すこと。〈日葡辞書〉
つめ‐ざ【詰座】
末座。幸若舞曲、和田酒盛「―に、ちやうと直つた」
つめ‐さいそく【詰催促】
きびしい催促。根無草後編「日夜朝暮の―」
つめ‐ざかもり【詰酒盛】
詰座で酒盛をすること。幸若舞曲、和田酒盛「これ程広い座敷にて、―は無用さうぞ」
つめ‐さむらい【詰侍】‥サムラヒ
勤務中の侍。つめている侍。浄瑠璃、平家女護島「荒れに荒れたる有王丸、当番の―」
つめ‐しゅう【詰衆】
⇒おつめしゅう(御詰衆)。
⇒つめしゅう‐なみ【詰衆並】
つめしゅう‐なみ【詰衆並】
(→)詰並つめなみに同じ。
⇒つめ‐しゅう【詰衆】
つめ‐しょ【詰所】
①多くの人の詰めている所。
②官吏・係員などの出勤している所。「警備員の―」
つめ‐しょうぎ【詰将棋】‥シヤウ‥
将棋で、与えられた譜面と駒とを使って、規則に従って王手をつづけて王将を詰めること。詰物。
つめ‐じん【詰陣】‥ヂン
敵に近く接している軍隊の陣。〈日葡辞書〉
つめ‐そで【詰袖】
袖の腋明けを縫い縮めた袖。また、その着物。近世、男は半元服(13、4歳)、女は19歳になると着た。
つめた【冷た】
(ツメタシの語幹)麻布の夜具または綿入れ。布子。おひえ。狂言、比丘貞「鎌倉の上臈は、すす竹の―に織物の手おほひ」
⇒つめた‐もの【冷た物】
つめた・い【冷たい】
〔形〕[文]つめた・し(ク)
①温度が低く、ひややかに感ずる。ひややかである。つべたい。〈[季]冬〉。落窪物語1「単衣もなくていと―・ければ、単衣を脱ぎすべして起き出でたまふ」。「―・い飲み物」
②人情に薄い。冷淡である。「―・い仕打ちを受ける」「―・い目で見る」
⇒冷たくなる
つめたい‐せんそう【冷たい戦争】‥サウ
(cold war)(→)冷戦に同じ。
つめた‐がい【津免多貝】‥ガヒ
タマガイ科の巻貝。殻高約7センチメートル、殻幅約8センチメートル。殻は淡い褐色で底面は黄色。潮間帯の砂の中にすみ、アサリなどの殻に孔を開けて肉を食う。夏、茶碗形の卵塊を産む(すなぢゃわんと呼ばれる)。うつぼがい。虚貝うつせがい。津辺多貝つべたがい。蚜貝。〈書言字考節用集〉
つめたがい
つめ‐ご【詰碁】
碁の部分的な局面を作り、死活を考えさせるもの。
つめ‐ごい【詰乞い】‥ゴヒ
強く、しつこく乞いもとめること。日葡辞書「ツメゴイニコウ」
つめ‐こすり【爪擦り】
切った爪の角かどをこすってなめらかにする具。細長いやすり状のもの。爪みがき。
つめ‐こみ【詰込み】
つめこむこと。
⇒つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
知識の注入や、知識の暗誦・記憶を重視する教育の仕方。
⇒つめ‐こみ【詰込み】
つめ‐こ・む【詰め込む】
〔他五〕
①つめて入れる。つめられるだけ一杯に入れる。「腹一杯―・む」
②知識をむやみに覚える。「英語の単語を―・む」
つめ‐ごろし【詰め殺し】
こっそりと、物を言わせないで殺すこと。〈日葡辞書〉
つめ‐ざ【詰座】
末座。幸若舞曲、和田酒盛「―に、ちやうと直つた」
つめ‐さいそく【詰催促】
きびしい催促。根無草後編「日夜朝暮の―」
つめ‐ざかもり【詰酒盛】
詰座で酒盛をすること。幸若舞曲、和田酒盛「これ程広い座敷にて、―は無用さうぞ」
つめ‐さむらい【詰侍】‥サムラヒ
勤務中の侍。つめている侍。浄瑠璃、平家女護島「荒れに荒れたる有王丸、当番の―」
つめ‐しゅう【詰衆】
⇒おつめしゅう(御詰衆)。
⇒つめしゅう‐なみ【詰衆並】
つめしゅう‐なみ【詰衆並】
(→)詰並つめなみに同じ。
⇒つめ‐しゅう【詰衆】
つめ‐しょ【詰所】
①多くの人の詰めている所。
②官吏・係員などの出勤している所。「警備員の―」
つめ‐しょうぎ【詰将棋】‥シヤウ‥
将棋で、与えられた譜面と駒とを使って、規則に従って王手をつづけて王将を詰めること。詰物。
つめ‐じん【詰陣】‥ヂン
敵に近く接している軍隊の陣。〈日葡辞書〉
つめ‐そで【詰袖】
袖の腋明けを縫い縮めた袖。また、その着物。近世、男は半元服(13、4歳)、女は19歳になると着た。
つめた【冷た】
(ツメタシの語幹)麻布の夜具または綿入れ。布子。おひえ。狂言、比丘貞「鎌倉の上臈は、すす竹の―に織物の手おほひ」
⇒つめた‐もの【冷た物】
つめた・い【冷たい】
〔形〕[文]つめた・し(ク)
①温度が低く、ひややかに感ずる。ひややかである。つべたい。〈[季]冬〉。落窪物語1「単衣もなくていと―・ければ、単衣を脱ぎすべして起き出でたまふ」。「―・い飲み物」
②人情に薄い。冷淡である。「―・い仕打ちを受ける」「―・い目で見る」
⇒冷たくなる
つめたい‐せんそう【冷たい戦争】‥サウ
(cold war)(→)冷戦に同じ。
つめた‐がい【津免多貝】‥ガヒ
タマガイ科の巻貝。殻高約7センチメートル、殻幅約8センチメートル。殻は淡い褐色で底面は黄色。潮間帯の砂の中にすみ、アサリなどの殻に孔を開けて肉を食う。夏、茶碗形の卵塊を産む(すなぢゃわんと呼ばれる)。うつぼがい。虚貝うつせがい。津辺多貝つべたがい。蚜貝。〈書言字考節用集〉
つめたがい
 ツメタガイ
提供:東京動物園協会
ツメタガイ
提供:東京動物園協会

つめ‐くさ【爪草】🔗⭐🔉
つめ‐くさ【爪草】
ナデシコ科の一年草または越年草。路傍や山野に普通な雑草で、茎は根元から枝分れし、高さ3〜10センチメートル。葉は線形で小さい。春から秋にかけて白色5弁の小花を次々と開き、蒴果さくかを結ぶ。タカノツメ。
つめ‐くさ【詰草】🔗⭐🔉
つめ‐くさ【詰草】
(梱包の詰物として用いたのでいう)シロツメクサの別称。
つめ‐くそ【爪糞】🔗⭐🔉
つめ‐くそ【爪糞】
爪にたまった垢。爪のあか。
つめ‐ぐみ【詰組】🔗⭐🔉
つめ‐ぐみ【詰組】
〔建〕柱上ばかりでなく、柱と柱との間にも組物を配する組み方。唐様建築にみられる。↔阿麻組
つめ‐クラッチ【爪クラッチ】🔗⭐🔉
つめ‐クラッチ【爪クラッチ】
〔機〕(→)咬合かみあいクラッチに同じ。
つめ‐ぐるま【爪車】🔗⭐🔉
つめ‐ぐるま【爪車】
爪と噛み合わせて、間歇かんけつ的な一方向回転運動を伝達し、逆方向回転を防止する一種の歯車。ラチェット。
爪車


つめ‐ご【詰碁】🔗⭐🔉
つめ‐ご【詰碁】
碁の部分的な局面を作り、死活を考えさせるもの。
つめ‐ごい【詰乞い】‥ゴヒ🔗⭐🔉
つめ‐ごい【詰乞い】‥ゴヒ
強く、しつこく乞いもとめること。日葡辞書「ツメゴイニコウ」
つめ‐こすり【爪擦り】🔗⭐🔉
つめ‐こすり【爪擦り】
切った爪の角かどをこすってなめらかにする具。細長いやすり状のもの。爪みがき。
つめ‐こみ【詰込み】🔗⭐🔉
つめ‐こみ【詰込み】
つめこむこと。
⇒つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】🔗⭐🔉
つめこみ‐しゅぎ【詰込み主義】
知識の注入や、知識の暗誦・記憶を重視する教育の仕方。
⇒つめ‐こみ【詰込み】
つめ‐こ・む【詰め込む】🔗⭐🔉
つめ‐こ・む【詰め込む】
〔他五〕
①つめて入れる。つめられるだけ一杯に入れる。「腹一杯―・む」
②知識をむやみに覚える。「英語の単語を―・む」
つめ‐ごろし【詰め殺し】🔗⭐🔉
つめ‐ごろし【詰め殺し】
こっそりと、物を言わせないで殺すこと。〈日葡辞書〉
つめ‐ざ【詰座】🔗⭐🔉
つめ‐ざ【詰座】
末座。幸若舞曲、和田酒盛「―に、ちやうと直つた」
つめ‐さいそく【詰催促】🔗⭐🔉
つめ‐さいそく【詰催促】
きびしい催促。根無草後編「日夜朝暮の―」
つめ‐ざかもり【詰酒盛】🔗⭐🔉
つめ‐ざかもり【詰酒盛】
詰座で酒盛をすること。幸若舞曲、和田酒盛「これ程広い座敷にて、―は無用さうぞ」
つめ‐さむらい【詰侍】‥サムラヒ🔗⭐🔉
つめ‐さむらい【詰侍】‥サムラヒ
勤務中の侍。つめている侍。浄瑠璃、平家女護島「荒れに荒れたる有王丸、当番の―」
つめ‐しゅう【詰衆】🔗⭐🔉
つめ‐しゅう【詰衆】
⇒おつめしゅう(御詰衆)。
⇒つめしゅう‐なみ【詰衆並】
つめしゅう‐なみ【詰衆並】🔗⭐🔉
つめしゅう‐なみ【詰衆並】
(→)詰並つめなみに同じ。
⇒つめ‐しゅう【詰衆】
つめ‐しょ【詰所】🔗⭐🔉
つめ‐しょ【詰所】
①多くの人の詰めている所。
②官吏・係員などの出勤している所。「警備員の―」
つめ‐しょうぎ【詰将棋】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
つめ‐しょうぎ【詰将棋】‥シヤウ‥
将棋で、与えられた譜面と駒とを使って、規則に従って王手をつづけて王将を詰めること。詰物。
つめ‐じん【詰陣】‥ヂン🔗⭐🔉
つめ‐じん【詰陣】‥ヂン
敵に近く接している軍隊の陣。〈日葡辞書〉
つめ‐そで【詰袖】🔗⭐🔉
つめ‐そで【詰袖】
袖の腋明けを縫い縮めた袖。また、その着物。近世、男は半元服(13、4歳)、女は19歳になると着た。
つめた【冷た】🔗⭐🔉
つめた【冷た】
(ツメタシの語幹)麻布の夜具または綿入れ。布子。おひえ。狂言、比丘貞「鎌倉の上臈は、すす竹の―に織物の手おほひ」
⇒つめた‐もの【冷た物】
つめた・い【冷たい】🔗⭐🔉
つめた・い【冷たい】
〔形〕[文]つめた・し(ク)
①温度が低く、ひややかに感ずる。ひややかである。つべたい。〈[季]冬〉。落窪物語1「単衣もなくていと―・ければ、単衣を脱ぎすべして起き出でたまふ」。「―・い飲み物」
②人情に薄い。冷淡である。「―・い仕打ちを受ける」「―・い目で見る」
⇒冷たくなる
広辞苑に「ツメ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む