複数辞典一括検索+![]()
![]()
むな【空】🔗⭐🔉
むな【空】
(ムナシの語幹)名詞に冠して、むなしい、何もない、などの意を添える語。「―言ごと」「―だのみ」
むな【胸】🔗⭐🔉
むな【胸】
「むね(胸)」の古形。多く、複合語に用いる。古事記上「沖つ鳥―見る時」。「―騒ぎ」
むな【棟】🔗⭐🔉
むな【棟】
「むね(棟)」の古形。複合語にのみ用いる。「―瓦」
むな‐あて【胸当】🔗⭐🔉
むな‐あて【胸当】
(→)「むねあて」に同じ。
⇒むなあて‐ぎり【胸当錐】
むなあて‐ぎり【胸当錐】🔗⭐🔉
むなあて‐ぎり【胸当錐】
錐の一種。工作物に直角になるように胸で保持し、片手で支えハンドルを持ち、片手で回転ハンドルを回して穿孔するもの。胸当ドリル。胸ボール。
胸当錐
 ⇒むな‐あて【胸当】
⇒むな‐あて【胸当】
 ⇒むな‐あて【胸当】
⇒むな‐あて【胸当】
ムナーリ【Bruno Munari】🔗⭐🔉
ムナーリ【Bruno Munari】
イタリアのデザイナー・装丁家・児童文学者。遊び心にあふれたデザインをした。代表作は自ら装丁した「霧のなかのサーカス」「本の前の本」。(1907〜1998)
むな‐おち【胸落】🔗⭐🔉
むな‐おち【胸落】
みぞおちのあたり。むなもと。
むな‐がい【胸懸・鞅】🔗⭐🔉
むながい‐づくし【鞅尽し】🔗⭐🔉
むながい‐づくし【鞅尽し】
鞅が馬の胸につくところ。平家物語11「馬の左の―をひやうづばと射て」
⇒むな‐がい【胸懸・鞅】
むなかた【宗像】🔗⭐🔉
むなかた【宗像】
福岡県北部の市。福岡市と北九州市とのほぼ中間に位置する衛星都市。人口9万4千。
⇒むなかた‐じんじゃ【宗像神社】
むなかた【棟方】🔗⭐🔉
むなかた【棟方】
姓氏の一つ。
⇒むなかた‐しこう【棟方志功】
むなかた‐しこう【棟方志功】🔗⭐🔉
むなかた‐しこう【棟方志功】
版画家。青森市生れ。民芸運動家の知遇を得て土俗的ともいえる奔放な作風を確立。自ら「板画」と称し、国際的にも高い評価を得る。文化勲章。(1903〜1975)
棟方志功(1)
撮影:石井幸之助
 棟方志功(2)
撮影:石井幸之助
棟方志功(2)
撮影:石井幸之助
 ⇒むなかた【棟方】
⇒むなかた【棟方】
 棟方志功(2)
撮影:石井幸之助
棟方志功(2)
撮影:石井幸之助
 ⇒むなかた【棟方】
⇒むなかた【棟方】
むなかた‐じんじゃ【宗像神社】🔗⭐🔉
むなかた‐じんじゃ【宗像神社】
福岡県宗像市にある元官幣大社。祭神は田心姫命たごりひめのみこと・湍津姫命たぎつひめのみこと・市杵島姫命いちきしまひめのみことで、玄界灘の沖ノ島にある沖津宮、大島の中津宮、内陸にある辺津へつ宮の三宮に祀る。沖ノ島の祭祀遺跡は著名。宗像大社。
⇒むなかた【宗像】
むな‐かなもの【胸金物】🔗⭐🔉
むな‐かなもの【胸金物】
鎧よろいの胸板に打った金物。
むな‐がらみ【胸搦み】🔗⭐🔉
むな‐がらみ【胸搦み】
(→)「むなぐら」に同じ。
むな‐がわら【棟瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉
むな‐がわら【棟瓦】‥ガハラ
家の棟むねを葺く瓦。むねがわら。
むな‐かんじょう【胸勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
むな‐かんじょう【胸勘定】‥ヂヤウ
(→)胸算用むなざんように同じ。
むなぎ【鰻】🔗⭐🔉
むなぎ【鰻】
「うなぎ」の古形。万葉集16「夏痩せによしといふ物そ―取りめせ」
むな‐ぎ【棟木】🔗⭐🔉
むな‐ぎ【棟木】
棟むねに用いる材木。太平記36「柱立すでに終り、―を揚げんとしけるに」
むな‐くそ【胸糞】🔗⭐🔉
むな‐くそ【胸糞】
「むね(胸)」を、強めまたいやしめていう語。むねくそ。
⇒胸糞が悪い
○胸糞が悪いむなくそがわるい
いまいましい。不愉快である。
⇒むな‐くそ【胸糞】
○胸糞が悪いむなくそがわるい🔗⭐🔉
○胸糞が悪いむなくそがわるい
いまいましい。不愉快である。
⇒むな‐くそ【胸糞】
むな‐くに【空国】
⇒そししのむなくに
むな‐ぐら【胸座・胸倉】
着物の左右の襟の重なり合う辺りの部分。むながらみ。むなづくし。
⇒胸座を取る
むな‐ぐら【胸座・胸倉】🔗⭐🔉
むな‐ぐら【胸座・胸倉】
着物の左右の襟の重なり合う辺りの部分。むながらみ。むなづくし。
⇒胸座を取る
○胸座を取るむなぐらをとる
(怒り、あるいは責めるなどして)相手の着衣の胸倉を握る。浮世物語「そのまゝ喧嘩になり…―」
⇒むな‐ぐら【胸座・胸倉】
○胸座を取るむなぐらをとる🔗⭐🔉
○胸座を取るむなぐらをとる
(怒り、あるいは責めるなどして)相手の着衣の胸倉を握る。浮世物語「そのまゝ喧嘩になり…―」
⇒むな‐ぐら【胸座・胸倉】
むな‐ぐるし・い【胸苦しい】
〔形〕[文]むなぐる・し(シク)
胸に苦痛を感じて呼吸が苦しい。「―・くて目が覚める」「―・げな息づかい」
むな‐ぐるま【空車】
①物や人を乗せていない車。能因本枕草子月夜にむな車「月夜に―のありきたる」
②車蓋しゃがいのない車。今昔物語集12「此の聖人雑役の―を持ちて牛の無きを見て」
むな‐ぐろ【胸黒】
チドリの一種。大きさはハトぐらい。夏羽は額から眉斑・頸側、胸の両側にかけて白く、背面は黒褐色に黄金色と灰白色との斑紋があり、顔と腹面は黒色。冬羽は黒色部が消え、地味な色になる。夏、シベリア・アラスカ西部で繁殖、冬はオーストラリアまで渡り、春秋に日本を通過する。アイグロ。
むなぐろ(夏羽)
 ムナグロ
提供:OPO
ムナグロ
提供:OPO
 むな‐げ【胸毛】
①胸の辺りに生える毛。
②鳥の胸の辺りの羽。
むな‐ごと【虚言・空言】
(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」
むな‐さか【胸坂】
⇒たかむなさか
むな‐さき【胸先・胸前】
胸のあたり。むなもと。
むな‐さわぎ【胸騒ぎ】
心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」
むな‐ざん【胸算】
(→)胸算用に同じ。
むな‐ざんよう【胸算用】
(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」
むな・し【空し・虚し】
〔形シク〕
⇒むなしい
むなし【空し・虚し】
(形容詞の語幹)
⇒むなし‐だのみ【空し頼み】
⇒むなし‐で【空し手】
⇒むなし‐ぶね【空船】
むなし・い【空しい・虚しい】
〔形〕[文]むな・し(シク)
①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」
②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」
③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」
④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」
⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」
⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」
⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」
⇒空しき骸
⇒空しきけぶり
⇒空しき空
⇒空しき名
⇒空しき船
⇒空しくなる
むな‐げ【胸毛】
①胸の辺りに生える毛。
②鳥の胸の辺りの羽。
むな‐ごと【虚言・空言】
(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」
むな‐さか【胸坂】
⇒たかむなさか
むな‐さき【胸先・胸前】
胸のあたり。むなもと。
むな‐さわぎ【胸騒ぎ】
心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」
むな‐ざん【胸算】
(→)胸算用に同じ。
むな‐ざんよう【胸算用】
(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」
むな・し【空し・虚し】
〔形シク〕
⇒むなしい
むなし【空し・虚し】
(形容詞の語幹)
⇒むなし‐だのみ【空し頼み】
⇒むなし‐で【空し手】
⇒むなし‐ぶね【空船】
むなし・い【空しい・虚しい】
〔形〕[文]むな・し(シク)
①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」
②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」
③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」
④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」
⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」
⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」
⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」
⇒空しき骸
⇒空しきけぶり
⇒空しき空
⇒空しき名
⇒空しき船
⇒空しくなる
 ムナグロ
提供:OPO
ムナグロ
提供:OPO
 むな‐げ【胸毛】
①胸の辺りに生える毛。
②鳥の胸の辺りの羽。
むな‐ごと【虚言・空言】
(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」
むな‐さか【胸坂】
⇒たかむなさか
むな‐さき【胸先・胸前】
胸のあたり。むなもと。
むな‐さわぎ【胸騒ぎ】
心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」
むな‐ざん【胸算】
(→)胸算用に同じ。
むな‐ざんよう【胸算用】
(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」
むな・し【空し・虚し】
〔形シク〕
⇒むなしい
むなし【空し・虚し】
(形容詞の語幹)
⇒むなし‐だのみ【空し頼み】
⇒むなし‐で【空し手】
⇒むなし‐ぶね【空船】
むなし・い【空しい・虚しい】
〔形〕[文]むな・し(シク)
①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」
②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」
③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」
④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」
⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」
⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」
⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」
⇒空しき骸
⇒空しきけぶり
⇒空しき空
⇒空しき名
⇒空しき船
⇒空しくなる
むな‐げ【胸毛】
①胸の辺りに生える毛。
②鳥の胸の辺りの羽。
むな‐ごと【虚言・空言】
(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」
むな‐さか【胸坂】
⇒たかむなさか
むな‐さき【胸先・胸前】
胸のあたり。むなもと。
むな‐さわぎ【胸騒ぎ】
心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」
むな‐ざん【胸算】
(→)胸算用に同じ。
むな‐ざんよう【胸算用】
(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」
むな・し【空し・虚し】
〔形シク〕
⇒むなしい
むなし【空し・虚し】
(形容詞の語幹)
⇒むなし‐だのみ【空し頼み】
⇒むなし‐で【空し手】
⇒むなし‐ぶね【空船】
むなし・い【空しい・虚しい】
〔形〕[文]むな・し(シク)
①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」
②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」
③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」
④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」
⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」
⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」
⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」
⇒空しき骸
⇒空しきけぶり
⇒空しき空
⇒空しき名
⇒空しき船
⇒空しくなる
むな‐ぐるし・い【胸苦しい】🔗⭐🔉
むな‐ぐるし・い【胸苦しい】
〔形〕[文]むなぐる・し(シク)
胸に苦痛を感じて呼吸が苦しい。「―・くて目が覚める」「―・げな息づかい」
むな‐ぐるま【空車】🔗⭐🔉
むな‐ぐるま【空車】
①物や人を乗せていない車。能因本枕草子月夜にむな車「月夜に―のありきたる」
②車蓋しゃがいのない車。今昔物語集12「此の聖人雑役の―を持ちて牛の無きを見て」
むな‐ぐろ【胸黒】🔗⭐🔉
むな‐ぐろ【胸黒】
チドリの一種。大きさはハトぐらい。夏羽は額から眉斑・頸側、胸の両側にかけて白く、背面は黒褐色に黄金色と灰白色との斑紋があり、顔と腹面は黒色。冬羽は黒色部が消え、地味な色になる。夏、シベリア・アラスカ西部で繁殖、冬はオーストラリアまで渡り、春秋に日本を通過する。アイグロ。
むなぐろ(夏羽)
 ムナグロ
提供:OPO
ムナグロ
提供:OPO

 ムナグロ
提供:OPO
ムナグロ
提供:OPO

むな‐げ【胸毛】🔗⭐🔉
むな‐げ【胸毛】
①胸の辺りに生える毛。
②鳥の胸の辺りの羽。
むな‐ごと【虚言・空言】🔗⭐🔉
むな‐ごと【虚言・空言】
(上代は清音)うそ。きょげん。そらごと。万葉集20「おぼろかに心思ひて―も親の名断つな」
むな‐さき【胸先・胸前】🔗⭐🔉
むな‐さき【胸先・胸前】
胸のあたり。むなもと。
むな‐さわぎ【胸騒ぎ】🔗⭐🔉
むな‐さわぎ【胸騒ぎ】
心配・驚き・凶事の予感などのために胸がどきどきして心の穏やかでないこと。むねはしり。「―がする」「―を覚える」
むな‐ざんよう【胸算用】🔗⭐🔉
むな‐ざんよう【胸算用】
(江戸中期頃までは多くムネザンヨウ)心の中で見積りを立てること。胸中での計算。むなづもり。風流志道軒伝「其の金つかふ―はすれども、仏の恩さへ思はず」。「―を立てる」
むな・し【空し・虚し】(形シク)🔗⭐🔉
むな・し【空し・虚し】
〔形シク〕
⇒むなしい
むなし・い【空しい・虚しい】🔗⭐🔉
むなし・い【空しい・虚しい】
〔形〕[文]むな・し(シク)
①中に物がない。からである。万葉集3「人もなき―・しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり」。源氏物語椎本「立ち寄らむ蔭とたのみし椎がもと―・しき床とこになりにけるかな」
②内容がない。充実していない。「―・い弁舌」
③事実がない。あとかたがない。源氏物語少女「―・しき事にて人の御名やけがれむ」
④はかない。かりそめである。万葉集5「世の中は―・しきものと知るときしいよよますます悲しかりけり」。「―・い夢」
⑤この世にいない。死んだ。源氏物語夕顔「此の人を―・しくしなしてむ事のいみじく思さるるにそへて」。平家物語3「有王―・しき姿に取りつき、天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき」
⑥無益である。むだである。かいがない。天草本平家物語「平家はむかうの山に陣をとつて―・しう日数をおくらるるに」。「―・く待つ」
⑦欲がない。恬淡てんたんである。垂仁紀「志懐沖むなしく退く」
⇒空しき骸
⇒空しきけぶり
⇒空しき空
⇒空しき名
⇒空しき船
⇒空しくなる
○空しき骸むなしきから
死骸。むなしき屍かばね。源氏物語蜻蛉「―をだに見奉らぬが」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しきけぶりむなしきけぶり
火葬の煙。無常の煙。
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しき空むなしきそら
おおぞら。虚空こくう。古今和歌集恋「わが恋は―に満ちぬらし」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しき名むなしきな
かいのない名。いたずらな評判。
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しき船むなしきふね
(船は君主。位を去ったからいう)上皇(仙洞)の異称。後拾遺和歌集雑「住吉の神はあはれと思ふらむ―をさして来たれば」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しくなるむなしくなる
死ぬ。みまかる。宇津保物語梅花笠「はやく空しくなり給ひにき」。日葡辞書「ムナシュウナル」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しき骸むなしきから🔗⭐🔉
○空しき骸むなしきから
死骸。むなしき屍かばね。源氏物語蜻蛉「―をだに見奉らぬが」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しきけぶりむなしきけぶり🔗⭐🔉
○空しきけぶりむなしきけぶり
火葬の煙。無常の煙。
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しき空むなしきそら🔗⭐🔉
○空しき空むなしきそら
おおぞら。虚空こくう。古今和歌集恋「わが恋は―に満ちぬらし」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しき名むなしきな🔗⭐🔉
○空しき名むなしきな
かいのない名。いたずらな評判。
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しき船むなしきふね🔗⭐🔉
○空しき船むなしきふね
(船は君主。位を去ったからいう)上皇(仙洞)の異称。後拾遺和歌集雑「住吉の神はあはれと思ふらむ―をさして来たれば」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
○空しくなるむなしくなる🔗⭐🔉
○空しくなるむなしくなる
死ぬ。みまかる。宇津保物語梅花笠「はやく空しくなり給ひにき」。日葡辞書「ムナシュウナル」
⇒むなし・い【空しい・虚しい】
むなし‐だのみ【空し頼み】
あてにならない頼み。そらだのみ。古今和歌集六帖3「―によせつくしつつ」
⇒むなし【空し・虚し】
むなし‐で【空し手】
からて。すで。むなで。神代紀(一本)下「―にして来り帰る」
⇒むなし【空し・虚し】
むなし‐ぶね【空船】
からふね。古事記(一本)中「―を攻めむとす」
⇒むなし【空し・虚し】
むな‐じゃくり【胸噦り】
泣く時などに、胸のあたりをしゃくるように動かすこと。
むな‐ずわら・し【胸づはらし】‥ヅハラシ
〔形シク〕
(ヅハラシは詰マラシの転か)心配ごとで胸がつまりそうである。むなつまらし。浄瑠璃、冥途飛脚「梅川いとど―・しく」
むな‐そこ【胸底】
⇒きょうてい
むな‐そろばん【胸算盤】
(→)胸算用に同じ。
むな‐だか【胸高】
帯を高く胸のあたりに締めること。好色一代男7「帯は―にして」
⇒むなだか‐おび【胸高帯】
むなだか‐おび【胸高帯】
高く胸のあたりに締めた帯。
⇒むな‐だか【胸高】
むな‐だのみ【空頼み】
(→)「そらだのみ」に同じ。
むな‐ち【胸乳】
(ムナヂとも)ちぶさ。神代紀下「其の―を露あらわにかきいでて」
むな‐つき【胸突き】
山道や坂などの険しく急なところ。「―坂」
⇒むなつき‐はっちょう【胸突き八丁】
むなつき‐はっちょう【胸突き八丁】‥チヤウ
山道で、登りのきつい難所。転じて、物事をなしとげるのに一番苦しい時期。「―にさしかかる」
⇒むな‐つき【胸突き】
むな‐づくし【胸尽し】
むなぐら。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「返答が聞きたいと―をひつつかむ」
むな‐づもり【胸積り】
心中に見積もること。胸算用。
むな‐で【空手・徒手】
(→)「むなしで」に同じ。古事記中「この山の神は―に直ただに取りてむ」
むな‐ばしら【棟柱】
家の棟木をのせて据える柱。〈日葡辞書〉
むな‐ばせ【空馳せ】
競べ馬で負けること。
むな‐ひげ【胸鬚】
胸に生えた毛。むなげ。
むな‐ひぼ【胸紐】
(ムナヒモの訛)
①着物・羽織などの胸部につけてある紐。
②紐のつけてある着物を着る頃。幼少の頃。浄瑠璃、栬狩剣本地「イヤ舌長し、―からかか様にさへつめられぬ大事の身」
むな‐びれ【胸鰭】
魚類の体の両側にある一対のひれ。ふつう腹びれの前方にある。→魚類(図)
むな‐ふだ【棟札】
棟上げや再建・修理の時、工事の由緒、建築の年月、建築者または工匠の名などを記して棟木に打ち付ける札。頭部は多く山形をなす。また、直接棟木に書いたものを棟木銘という。むねふだ。とうさつ。
むな‐ふね【空船】
からの船。古事記中「喪船もふねに赴きて―を攻めむとしき」
むな‐べつ【棟別】
(→)軒別けんべつに同じ。むねべつ。
むな‐ぼね【胸骨】
胸の骨。
むなもち‐ばしら【棟持柱】
妻側の壁の外にあって、突出した棟木を直接支える柱。小狭柱おさばしら。→神明造しんめいづくり
むな‐もと【胸元】
鳩尾みぞおちの辺り。むなさき。「銃を―に突きつける」「―の開いた服」
むな‐もん【棟門】
本柱2本で控柱がなく、切妻造り・平入りの門。寺院の塔頭たっちゅう、住宅などの門に多く用いられる。むねかど。むねもん。
棟門
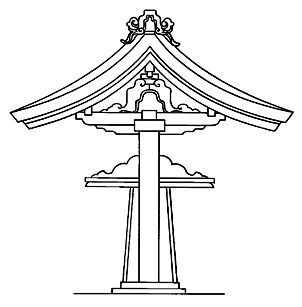 むな‐やけ【胸焼け】
⇒むねやけ
むな‐わ・く【胸分く】
〔自下二〕
(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」
むな‐わけ【胸分け】
①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」
②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」
むに【牟尼・文尼】
〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)
①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。
②釈尊の称。「釈迦―」
む‐に【無二】
二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」
ムニエル【meunière フランス】
魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。
むな‐やけ【胸焼け】
⇒むねやけ
むな‐わ・く【胸分く】
〔自下二〕
(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」
むな‐わけ【胸分け】
①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」
②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」
むに【牟尼・文尼】
〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)
①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。
②釈尊の称。「釈迦―」
む‐に【無二】
二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」
ムニエル【meunière フランス】
魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。
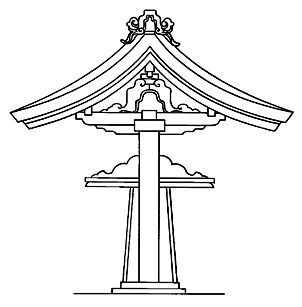 むな‐やけ【胸焼け】
⇒むねやけ
むな‐わ・く【胸分く】
〔自下二〕
(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」
むな‐わけ【胸分け】
①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」
②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」
むに【牟尼・文尼】
〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)
①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。
②釈尊の称。「釈迦―」
む‐に【無二】
二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」
ムニエル【meunière フランス】
魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。
むな‐やけ【胸焼け】
⇒むねやけ
むな‐わ・く【胸分く】
〔自下二〕
(鹿などが)草木の茂っている中などを胸で押し分けて行く。万葉集20「大夫ますらおの呼び立てしかばさを鹿の―・けゆかむ秋野萩原」
むな‐わけ【胸分け】
①胸で草などを押し分けること。むねわけ。万葉集8「さを鹿の―にかも秋萩の散り過ぎにける盛りかもいぬる」
②胸。胸のはば。万葉集9「―の広ゆたけき吾妹わぎも腰細のすがる娘子おとめの」
むに【牟尼・文尼】
〔仏〕(梵語muni 寂黙・聖者・聖仙の意)
①インドで、山林に在って心を修め道を修する者の称。仙人。聖人。
②釈尊の称。「釈迦―」
む‐に【無二】
二つとないこと。かけがえのないこと。無類。唯一。無双。「―の親友」「当代―の声楽家」
ムニエル【meunière フランス】
魚に小麦粉をまぶし、バターで焼いた料理。ムニエール。
むなし‐だのみ【空し頼み】🔗⭐🔉
むなし‐だのみ【空し頼み】
あてにならない頼み。そらだのみ。古今和歌集六帖3「―によせつくしつつ」
⇒むなし【空し・虚し】
むなし‐で【空し手】🔗⭐🔉
むなし‐で【空し手】
からて。すで。むなで。神代紀(一本)下「―にして来り帰る」
⇒むなし【空し・虚し】
むなし‐ぶね【空船】🔗⭐🔉
むなし‐ぶね【空船】
からふね。古事記(一本)中「―を攻めむとす」
⇒むなし【空し・虚し】
むな‐じゃくり【胸噦り】🔗⭐🔉
むな‐じゃくり【胸噦り】
泣く時などに、胸のあたりをしゃくるように動かすこと。
むな‐ずわら・し【胸づはらし】‥ヅハラシ🔗⭐🔉
むな‐ずわら・し【胸づはらし】‥ヅハラシ
〔形シク〕
(ヅハラシは詰マラシの転か)心配ごとで胸がつまりそうである。むなつまらし。浄瑠璃、冥途飛脚「梅川いとど―・しく」
広辞苑に「ムナ」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む