複数辞典一括検索+![]()
![]()
○一の裏は六いちのうらはろく🔗⭐🔉
○一の裏は六いちのうらはろく
賽さいの目の1の裏は6であるので、悪いことの後には善いことがあるの意。
⇒いち【一・壱】
いち‐の‐おとど【一の大臣】
左大臣の異称。いちのかみ。浜松中納言物語1「一の后きさきの父、―」
いち‐の‐おり【一の折】‥ヲリ
連歌・俳諧で、句を記す懐紙(横二つ折)の、最初の一折。初折しょおり。→懐紙2
いち‐の‐かい【一ノ貝】‥カヒ
(「頁」の字を分解してよんだもの)(→)大貝おおがいに同じ。
いち‐の‐かみ【市正】
律令制の市司いちのつかさの長官。
いち‐の‐かみ【市神】
(→)「いちがみ」に同じ。
いち‐の‐かみ【一の上】
(第一の上達部かんだちべの意)左大臣の異称。いちのおとど。一の上卿。「いちのしょう」とも。宇津保物語国譲上「あるは―などになり給ひぬれば」
いち‐の‐きさき【一の后】
皇后の異称。浜松中納言物語1「―の父、一の大臣」
いち‐の‐きど【一の城戸】
最も外側にある城門。
いち‐の‐くらい【一の位】‥クラヰ
①第一等の位階。
②十進法で最初の位。
いちのくら‐さわ【一ノ倉沢】‥サハ
群馬県北部、谷川岳および一ノ倉岳(標高1974メートル)の東斜面にある沢。高さ800メートルの岩壁で知られる。
いち‐の‐ざえ【一の才】
学び得た学芸中で第一のもの。源氏物語絵合「琴ひかせ給ふことなむ―にて」
いちのじ‐つなぎ【一の字繋ぎ】
平行線の間を煉瓦積のように繋いだ文様。
一の字繋ぎ
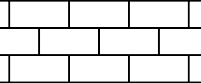 いちのじ‐てん【一の字点】
(点は「しるし」の意)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「ゝ」「ヽ」。「しのゝめ」「アラヽギ」など。現在では仮名の反復に用いる。→踊り字
いち‐の‐しょうけい【一上卿】‥シヤウ‥
(上卿中、最も有力なものの意)普通は左大臣の称。一上いちのしょう・いちのかみ。
いちのせき【一関】
岩手県南部、北上盆地南端の市。陸羽街道の要地。もと仙台藩の支藩田村氏3万石の城下町。県南の中心都市として商工業が発達。人口12万6千。
厳美渓
撮影:山梨勝弘
いちのじ‐てん【一の字点】
(点は「しるし」の意)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「ゝ」「ヽ」。「しのゝめ」「アラヽギ」など。現在では仮名の反復に用いる。→踊り字
いち‐の‐しょうけい【一上卿】‥シヤウ‥
(上卿中、最も有力なものの意)普通は左大臣の称。一上いちのしょう・いちのかみ。
いちのせき【一関】
岩手県南部、北上盆地南端の市。陸羽街道の要地。もと仙台藩の支藩田村氏3万石の城下町。県南の中心都市として商工業が発達。人口12万6千。
厳美渓
撮影:山梨勝弘
 いち‐の‐ぜん【一の膳】
本膳料理で出す第一の食膳。本膳。→二の膳→三の膳
いち‐の‐たい【一の対】
①寝殿造の東の対あるいは西の対。東北対・西北対に対していう。対屋たいのやのうち主な方。宇津保物語国譲上「東の―の北面」→二の対。
②第一夫人、すなわち、妻妾中の頭立った人。〈日葡辞書〉
いち‐の‐だいじん【一の大臣】
⇒いちのおとど
いちのたに【一谷】
神戸市須磨区の、鉄枴てっかい・鉢伏はちぶせの両山が海岸に迫る地域。北に鵯越ひよどりごえがある。1184年(寿永3)源義経が平家の軍を攻めた古戦場。
一谷
撮影:的場 啓
いち‐の‐ぜん【一の膳】
本膳料理で出す第一の食膳。本膳。→二の膳→三の膳
いち‐の‐たい【一の対】
①寝殿造の東の対あるいは西の対。東北対・西北対に対していう。対屋たいのやのうち主な方。宇津保物語国譲上「東の―の北面」→二の対。
②第一夫人、すなわち、妻妾中の頭立った人。〈日葡辞書〉
いち‐の‐だいじん【一の大臣】
⇒いちのおとど
いちのたに【一谷】
神戸市須磨区の、鉄枴てっかい・鉢伏はちぶせの両山が海岸に迫る地域。北に鵯越ひよどりごえがある。1184年(寿永3)源義経が平家の軍を攻めた古戦場。
一谷
撮影:的場 啓
 ⇒いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1751年(宝暦1)初演。一谷の戦に、熊谷次郎直実が平敦盛を討って遁世し、また、岡部六弥太が平忠度を討ったことを脚色。「熊谷陣屋」の段が有名。後に歌舞伎化。
→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]
⇒いちのたに【一谷】
いち‐の‐つかさ【市司】
律令制で、都の市(市場)を監督した役所。平城京・平安京で、左京(東)・右京(西)のそれぞれに東市ひがしのいち・西市にしのいちが公設され、東市司・西市司がこれを管理した。
いち‐の‐て【一の手】
第一になすべき手段。または、最もすぐれた手段。
いち‐の‐どう【一の胴】
胴体の上部で両腋わきより少し下の所。浄瑠璃、傾城反魂香「試して見たい新刃あらみはないか、―か二の胴か望んで置け」→二の胴
いち‐の‐ところ【一の所】
(→)「いちのひと」に同じ。
いち‐の‐とり【一の酉】
11月の最初の酉の日。また、この日行われる酉の市。初酉。〈[季]冬〉。→酉の市
いち‐の‐とりい【一の鳥居】‥ヰ
神社の一番外側にある鳥居。
いち‐の‐ないし【一の内侍】
内侍(掌侍)の首席。勾当内侍こうとうのないし。
いち‐の‐ひじり【市聖】
空也くうやの通称。天慶(938〜947)年間、京都市中で阿弥陀仏の名号を唱えて民衆を勧化かんげしたことによる。市の上人。いちひじり。
いち‐の‐ひと【一の人】
(第一の席につくからいう)摂政・関白、また太政大臣の異称。いちのところ。一の家。枕草子88「―の御ありき」
いち‐の‐ふで【一の筆】
①戦場で一番首を取ったことを首帳くびちょうの初めに記されたこと。また、奉加帳などに第一に書きしるすこと。平家物語9「高名の―にぞ付きにける」
②年頭にする書きぞめ。
いち‐の‐まい【一の舞】‥マヒ
舞の中で、最初に舞う舞。また、その舞い手。枕草子142「―のいとうるはしく袖を合はせて」
いち‐の‐まつ【一の松】
能舞台の橋掛りの前面に植える3本の松のうち、舞台に最も近い松。→能舞台(図)
いち‐の‐みこ【一の御子】
1番目の皇子。一の宮。源氏物語桐壺「―は右大臣の女御の御腹にて」
いち‐の‐みだい【一の御台】
(「台」は台盤の略)第一に奉る食膳。
いち‐の‐みや【一の宮】
①(→)「いちのみこ」に同じ。源氏物語桐壺「―を見たてまつらせ給ふにも若宮の御恋しさのみ思ほし出でつつ」
②各国の由緒あり信仰の篤い神社で、その国の第1位のもの。大宮市の氷川神社を武蔵国の一の宮とした類。今、各地に地名としても存続している。(「うつのみや」もその転訛)
いちのみや【一宮】
愛知県北西部の市。尾張の一宮真清田ますみだ神社の門前町として発展。毛織物工業の中心。人口37万2千。尾張一の宮。
いち‐の‐もの【一の物・一の者】
①すぐれた物。すぐれた人。
②楽所の楽人の筆頭。
いち‐の‐や【一の矢】
手に持った2本の矢のうち、第一に放つ矢。
いち‐ば【市場・市庭】
①毎日または定期に商人が集まって、商品の売買を行う場所。市いち。「魚うお―」
市場
撮影:関戸 勇
⇒いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1751年(宝暦1)初演。一谷の戦に、熊谷次郎直実が平敦盛を討って遁世し、また、岡部六弥太が平忠度を討ったことを脚色。「熊谷陣屋」の段が有名。後に歌舞伎化。
→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]
⇒いちのたに【一谷】
いち‐の‐つかさ【市司】
律令制で、都の市(市場)を監督した役所。平城京・平安京で、左京(東)・右京(西)のそれぞれに東市ひがしのいち・西市にしのいちが公設され、東市司・西市司がこれを管理した。
いち‐の‐て【一の手】
第一になすべき手段。または、最もすぐれた手段。
いち‐の‐どう【一の胴】
胴体の上部で両腋わきより少し下の所。浄瑠璃、傾城反魂香「試して見たい新刃あらみはないか、―か二の胴か望んで置け」→二の胴
いち‐の‐ところ【一の所】
(→)「いちのひと」に同じ。
いち‐の‐とり【一の酉】
11月の最初の酉の日。また、この日行われる酉の市。初酉。〈[季]冬〉。→酉の市
いち‐の‐とりい【一の鳥居】‥ヰ
神社の一番外側にある鳥居。
いち‐の‐ないし【一の内侍】
内侍(掌侍)の首席。勾当内侍こうとうのないし。
いち‐の‐ひじり【市聖】
空也くうやの通称。天慶(938〜947)年間、京都市中で阿弥陀仏の名号を唱えて民衆を勧化かんげしたことによる。市の上人。いちひじり。
いち‐の‐ひと【一の人】
(第一の席につくからいう)摂政・関白、また太政大臣の異称。いちのところ。一の家。枕草子88「―の御ありき」
いち‐の‐ふで【一の筆】
①戦場で一番首を取ったことを首帳くびちょうの初めに記されたこと。また、奉加帳などに第一に書きしるすこと。平家物語9「高名の―にぞ付きにける」
②年頭にする書きぞめ。
いち‐の‐まい【一の舞】‥マヒ
舞の中で、最初に舞う舞。また、その舞い手。枕草子142「―のいとうるはしく袖を合はせて」
いち‐の‐まつ【一の松】
能舞台の橋掛りの前面に植える3本の松のうち、舞台に最も近い松。→能舞台(図)
いち‐の‐みこ【一の御子】
1番目の皇子。一の宮。源氏物語桐壺「―は右大臣の女御の御腹にて」
いち‐の‐みだい【一の御台】
(「台」は台盤の略)第一に奉る食膳。
いち‐の‐みや【一の宮】
①(→)「いちのみこ」に同じ。源氏物語桐壺「―を見たてまつらせ給ふにも若宮の御恋しさのみ思ほし出でつつ」
②各国の由緒あり信仰の篤い神社で、その国の第1位のもの。大宮市の氷川神社を武蔵国の一の宮とした類。今、各地に地名としても存続している。(「うつのみや」もその転訛)
いちのみや【一宮】
愛知県北西部の市。尾張の一宮真清田ますみだ神社の門前町として発展。毛織物工業の中心。人口37万2千。尾張一の宮。
いち‐の‐もの【一の物・一の者】
①すぐれた物。すぐれた人。
②楽所の楽人の筆頭。
いち‐の‐や【一の矢】
手に持った2本の矢のうち、第一に放つ矢。
いち‐ば【市場・市庭】
①毎日または定期に商人が集まって、商品の売買を行う場所。市いち。「魚うお―」
市場
撮影:関戸 勇
 ②常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。しじょう。マーケット。
⇒いちば‐せん【市庭銭】
⇒いちば‐まち【市場町】
いち‐ばい【一倍】
①ある数量と同じ数量。「―半」
②ある数量を二つ合わせた数量。倍。2倍。日本永代蔵1「一年―の算用につもり」
③(副詞的に)いっそう。ひとしお。浄瑠璃、近江源氏先陣館「聞分けよい程助けたさは、胸―に迫れども」。「人―喜ぶ」
いちばく‐じっかん【一暴十寒】
[孟子告子上]1日だけ日光に当てて暖めても、10日寒くしたままでは、良い種子も成長することはできない。たまに好い条件を与えても、普段の条件が悪ければなんにもならない。
いちば‐せん【市庭銭】
中世、荘園内の市場に課した税金。江戸時代には市場運上を徴収。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はつ【鳶尾・一八】
アヤメ科の多年草。中国の原産。高さ約30センチメートル。葉は剣状で、中央脈が隆起。5月頃、紫花または白花を開く。花被は6枚で、外花被に白色の突起がつく。観賞用。火災を防ぐという俗信から、わら屋の上に植えることがある。コヤスグサ。〈[季]夏〉
いちはつ
②常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。しじょう。マーケット。
⇒いちば‐せん【市庭銭】
⇒いちば‐まち【市場町】
いち‐ばい【一倍】
①ある数量と同じ数量。「―半」
②ある数量を二つ合わせた数量。倍。2倍。日本永代蔵1「一年―の算用につもり」
③(副詞的に)いっそう。ひとしお。浄瑠璃、近江源氏先陣館「聞分けよい程助けたさは、胸―に迫れども」。「人―喜ぶ」
いちばく‐じっかん【一暴十寒】
[孟子告子上]1日だけ日光に当てて暖めても、10日寒くしたままでは、良い種子も成長することはできない。たまに好い条件を与えても、普段の条件が悪ければなんにもならない。
いちば‐せん【市庭銭】
中世、荘園内の市場に課した税金。江戸時代には市場運上を徴収。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はつ【鳶尾・一八】
アヤメ科の多年草。中国の原産。高さ約30センチメートル。葉は剣状で、中央脈が隆起。5月頃、紫花または白花を開く。花被は6枚で、外花被に白色の突起がつく。観賞用。火災を防ぐという俗信から、わら屋の上に植えることがある。コヤスグサ。〈[季]夏〉
いちはつ
 いちばつ‐ひゃっかい【一罰百戒】‥ヒヤク‥
一人を罰して、多くの人の戒めとすること。
いちはな‐か・く【一端駆く】
〔自下二〕
一番最初に駆ける。一番駆けをする。堀河百首題狂歌集「鶯の―・けて咲く梅に」
いちはな‐がけ【一端駆け】
一番最初にすること。一番先。浮世風呂前「死んだら―に泣くだらう」
いちはな‐だ・つ【一端立つ】
〔自四〕
一番先に立つ。東海道中膝栗毛5「ゑどぐみの御師の手代、―・ちておくより出」
いちば‐まち【市場町】
市場から発達した集落。室町後期に広く成立。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はやく【逸速く】
⇒いちはやし5
いち‐はや・し【逸速し】
〔形ク〕
(イチに「逸」は当て字。一説に、「厳」の意)
①霊威がいちじるしい。欽明紀「浦の神―・し」
②容赦しない。手きびしい。源氏物語須磨「―・き世のいとおそろしう侍るなり」
③はげしい。強烈である。切実である。伊勢物語「昔人はかく―・きみやびをなんしける」
④気が早い。性急である。蜻蛉日記下「なほここにはいと―・き心ちすれば、思ひかくることもなきを」
⑤(連用形を副詞的に用いて)他にさきがけてすばやく。「現場に―・くかけつける」
いち‐はや・ぶ【逸速ぶ】
〔自上二〕
するどくなる。はげしくなる。祝詞、鎮火祭「御心―・び給はじとして」
いちはら【市原】
千葉県中部、京葉工業地帯の中心都市。東京湾に面し、工業港をもつ。古代、上総国の要地で、国府跡・国分寺跡がある。人口28万。
いちはらの【市原野】
歌舞伎舞踊。常磐津。富本からの改作。3世桜田治助作詞。1875年(明治8)4世岸沢古式部作曲。本名題「笛澄月白浪ふえにすむつきのしらなみ」。袴垂保輔が京都の市原野に源頼光を襲うが討てず、小蝶の前がからんで3人のだんまり。のち長唄にも移された。
いちはら‐の‐おおきみ【市原王】‥オホ‥
天智天皇の曾孫安貴王の王子。万葉歌人。生没年未詳。
いち‐ばん【一番】
[一]〔名〕
①二つが一組となったもの。ひとつがい。
②最初。第一。
③同種のものの中で最もすぐれたもの。また、最大のもの。東海道中膝栗毛6「―の桶」
④一度。一回。特に、歌舞などの一曲。碁・将棋などの一局。相撲の一勝負。「結びの―」
[二]〔副〕
①こころみに。まず一度。「承知するかしないか―あたってみよう」
②最も。甚だしく。この上もなく。「―悪い」「―早く起きる」
⇒いちばん‐うけ【一番受】
⇒いちばん‐がい【一番貝】
⇒いちばん‐がけ【一番駆け】
⇒いちばん‐きり【一番切】
⇒いちばん‐ぐさ【一番草】
⇒いちばん‐くび【一番首】
⇒いちばん‐こ【一番子】
⇒いちばん‐しゅっせ【一番出世】
⇒いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
⇒いちばん‐せんじ【一番煎じ】
⇒いちばん‐ぞなえ【一番備え】
⇒いちばん‐だいこ【一番太鼓】
⇒いちばん‐だし【一番出し】
⇒いちばん‐ちゃ【一番茶】
⇒いちばん‐て【一番手】
⇒いちばん‐ていとう【一番抵当】
⇒いちばん‐でし【一番弟子】
⇒いちばん‐どり【一番鶏】
⇒いちばん‐なり【一番成り】
⇒いちばん‐にょうぼう【一番女房】
⇒いちばん‐のり【一番乗り】
⇒いちばん‐ぶろ【一番風呂】
⇒いちばん‐ぼし【一番星】
⇒いちばん‐め【一番目】
⇒いちばん‐やり【一番槍】
⇒いちばん‐れっしゃ【一番列車】
いちばん‐うけ【一番受】
武家時代、敵の来襲に備えて先頭にいること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がい【一番貝】‥ガヒ
軍陣で最初に吹く陣貝。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がけ【一番駆け】
①戦場で第一番に敵陣に駆け入って戦うこと。
②転じて、人に先んじて事をなすこと。一端いちはな駆け。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐きり【一番切】
(→)「いちばんしょうぶ」に同じ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「数ばかりの勝負づく、―に突いて見て」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぐさ【一番草】
稲田除草の第1回目。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐くび【一番首】
戦場で第一番に討ち取った敵の首級。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐こ【一番子】
①最初に生まれた子。
②その家でもっともできのよい子。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しゅっせ【一番出世】
大相撲の前相撲で、新弟子が定められた日までに規定の勝星をあげ、翌場所序の口に上がる資格を得ること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
ただ1番だけで決する勝負。また、ただ1回だけ試みること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐せんじ【一番煎じ】
茶または薬の、第一番に煎じ出したもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぞなえ【一番備え】‥ゾナヘ
敵陣にもっとも近く、第一番に備えた軍隊。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だいこ【一番太鼓】
①大坂新町の遊郭で、門限を知らせるための太鼓。3回に及ぶがそのうち夜10時頃打つ最初の太鼓。→三番太鼓。
②歌舞伎劇場の開場を知らせるために毎早暁に打つ大太鼓。顔見世狂言の初日の暁の八つ時に打ったのが始まり。根無草後編「―は八声に先立ち、三番叟さんばそうは明けるを待たず」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だし【一番出し】
出し汁用の材料から最初にうまみを引き出した汁。一般的には昆布と鰹節かつおぶしの出し汁。吸い物や茶碗蒸しなどに用いる。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ちゃ【一番茶】
春に最初に摘みとった茶。〈[季]春〉
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐て【一番手】
①第一番に敵陣に討って出る軍勢。
②最初に物事にあたる人。
③競争者の中で最も優位にある人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ていとう【一番抵当】‥タウ
同一の物件上に設定された抵当権のうち最優先の順位にあるもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐でし【一番弟子】
弟子のなかで、最もすぐれたもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐どり【一番鶏】
暁に最初に鳴くニワトリ。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐なり【一番成り】
その年一番最初に実った果実。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐にょうぼう【一番女房】‥バウ
最も働きのある女奉公人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐のり【一番乗り】
第一番に敵陣や敵城に馬を乗り入れること。転じて、ある場所に最初に乗りこむこと。また、その人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぶろ【一番風呂】
沸かしたばかりで、その日初めて人が入る風呂。新湯。↔仕舞風呂。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぼし【一番星】
夕方、一番はじめに輝き出す星。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐め【一番目】
①順番の第一番。
②時代物の歌舞伎狂言。多くは演目中の最初に演ずるからいう。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐やり【一番槍】
第一番に敵陣に槍を突き入れること。また、その人。転じて、最初に功名をたてること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐れっしゃ【一番列車】
その日最初に運転される列車。
⇒いち‐ばん【一番】
いち‐び【市日】
定期的に市の立つ日。市の開かれる日。
いちび【莔麻】
アオイ科の一年草。インド・西アジア原産。高さ約1メートル。全体に軟毛が密生。夏、黄色5弁の花を開く。茎の繊維で綱・糸・粗布を製し、暖地で稀に栽培。きり麻。白麻。漢名、莔麻ぼうま。
いちび
いちばつ‐ひゃっかい【一罰百戒】‥ヒヤク‥
一人を罰して、多くの人の戒めとすること。
いちはな‐か・く【一端駆く】
〔自下二〕
一番最初に駆ける。一番駆けをする。堀河百首題狂歌集「鶯の―・けて咲く梅に」
いちはな‐がけ【一端駆け】
一番最初にすること。一番先。浮世風呂前「死んだら―に泣くだらう」
いちはな‐だ・つ【一端立つ】
〔自四〕
一番先に立つ。東海道中膝栗毛5「ゑどぐみの御師の手代、―・ちておくより出」
いちば‐まち【市場町】
市場から発達した集落。室町後期に広く成立。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はやく【逸速く】
⇒いちはやし5
いち‐はや・し【逸速し】
〔形ク〕
(イチに「逸」は当て字。一説に、「厳」の意)
①霊威がいちじるしい。欽明紀「浦の神―・し」
②容赦しない。手きびしい。源氏物語須磨「―・き世のいとおそろしう侍るなり」
③はげしい。強烈である。切実である。伊勢物語「昔人はかく―・きみやびをなんしける」
④気が早い。性急である。蜻蛉日記下「なほここにはいと―・き心ちすれば、思ひかくることもなきを」
⑤(連用形を副詞的に用いて)他にさきがけてすばやく。「現場に―・くかけつける」
いち‐はや・ぶ【逸速ぶ】
〔自上二〕
するどくなる。はげしくなる。祝詞、鎮火祭「御心―・び給はじとして」
いちはら【市原】
千葉県中部、京葉工業地帯の中心都市。東京湾に面し、工業港をもつ。古代、上総国の要地で、国府跡・国分寺跡がある。人口28万。
いちはらの【市原野】
歌舞伎舞踊。常磐津。富本からの改作。3世桜田治助作詞。1875年(明治8)4世岸沢古式部作曲。本名題「笛澄月白浪ふえにすむつきのしらなみ」。袴垂保輔が京都の市原野に源頼光を襲うが討てず、小蝶の前がからんで3人のだんまり。のち長唄にも移された。
いちはら‐の‐おおきみ【市原王】‥オホ‥
天智天皇の曾孫安貴王の王子。万葉歌人。生没年未詳。
いち‐ばん【一番】
[一]〔名〕
①二つが一組となったもの。ひとつがい。
②最初。第一。
③同種のものの中で最もすぐれたもの。また、最大のもの。東海道中膝栗毛6「―の桶」
④一度。一回。特に、歌舞などの一曲。碁・将棋などの一局。相撲の一勝負。「結びの―」
[二]〔副〕
①こころみに。まず一度。「承知するかしないか―あたってみよう」
②最も。甚だしく。この上もなく。「―悪い」「―早く起きる」
⇒いちばん‐うけ【一番受】
⇒いちばん‐がい【一番貝】
⇒いちばん‐がけ【一番駆け】
⇒いちばん‐きり【一番切】
⇒いちばん‐ぐさ【一番草】
⇒いちばん‐くび【一番首】
⇒いちばん‐こ【一番子】
⇒いちばん‐しゅっせ【一番出世】
⇒いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
⇒いちばん‐せんじ【一番煎じ】
⇒いちばん‐ぞなえ【一番備え】
⇒いちばん‐だいこ【一番太鼓】
⇒いちばん‐だし【一番出し】
⇒いちばん‐ちゃ【一番茶】
⇒いちばん‐て【一番手】
⇒いちばん‐ていとう【一番抵当】
⇒いちばん‐でし【一番弟子】
⇒いちばん‐どり【一番鶏】
⇒いちばん‐なり【一番成り】
⇒いちばん‐にょうぼう【一番女房】
⇒いちばん‐のり【一番乗り】
⇒いちばん‐ぶろ【一番風呂】
⇒いちばん‐ぼし【一番星】
⇒いちばん‐め【一番目】
⇒いちばん‐やり【一番槍】
⇒いちばん‐れっしゃ【一番列車】
いちばん‐うけ【一番受】
武家時代、敵の来襲に備えて先頭にいること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がい【一番貝】‥ガヒ
軍陣で最初に吹く陣貝。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がけ【一番駆け】
①戦場で第一番に敵陣に駆け入って戦うこと。
②転じて、人に先んじて事をなすこと。一端いちはな駆け。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐きり【一番切】
(→)「いちばんしょうぶ」に同じ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「数ばかりの勝負づく、―に突いて見て」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぐさ【一番草】
稲田除草の第1回目。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐くび【一番首】
戦場で第一番に討ち取った敵の首級。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐こ【一番子】
①最初に生まれた子。
②その家でもっともできのよい子。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しゅっせ【一番出世】
大相撲の前相撲で、新弟子が定められた日までに規定の勝星をあげ、翌場所序の口に上がる資格を得ること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
ただ1番だけで決する勝負。また、ただ1回だけ試みること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐せんじ【一番煎じ】
茶または薬の、第一番に煎じ出したもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぞなえ【一番備え】‥ゾナヘ
敵陣にもっとも近く、第一番に備えた軍隊。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だいこ【一番太鼓】
①大坂新町の遊郭で、門限を知らせるための太鼓。3回に及ぶがそのうち夜10時頃打つ最初の太鼓。→三番太鼓。
②歌舞伎劇場の開場を知らせるために毎早暁に打つ大太鼓。顔見世狂言の初日の暁の八つ時に打ったのが始まり。根無草後編「―は八声に先立ち、三番叟さんばそうは明けるを待たず」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だし【一番出し】
出し汁用の材料から最初にうまみを引き出した汁。一般的には昆布と鰹節かつおぶしの出し汁。吸い物や茶碗蒸しなどに用いる。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ちゃ【一番茶】
春に最初に摘みとった茶。〈[季]春〉
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐て【一番手】
①第一番に敵陣に討って出る軍勢。
②最初に物事にあたる人。
③競争者の中で最も優位にある人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ていとう【一番抵当】‥タウ
同一の物件上に設定された抵当権のうち最優先の順位にあるもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐でし【一番弟子】
弟子のなかで、最もすぐれたもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐どり【一番鶏】
暁に最初に鳴くニワトリ。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐なり【一番成り】
その年一番最初に実った果実。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐にょうぼう【一番女房】‥バウ
最も働きのある女奉公人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐のり【一番乗り】
第一番に敵陣や敵城に馬を乗り入れること。転じて、ある場所に最初に乗りこむこと。また、その人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぶろ【一番風呂】
沸かしたばかりで、その日初めて人が入る風呂。新湯。↔仕舞風呂。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぼし【一番星】
夕方、一番はじめに輝き出す星。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐め【一番目】
①順番の第一番。
②時代物の歌舞伎狂言。多くは演目中の最初に演ずるからいう。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐やり【一番槍】
第一番に敵陣に槍を突き入れること。また、その人。転じて、最初に功名をたてること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐れっしゃ【一番列車】
その日最初に運転される列車。
⇒いち‐ばん【一番】
いち‐び【市日】
定期的に市の立つ日。市の開かれる日。
いちび【莔麻】
アオイ科の一年草。インド・西アジア原産。高さ約1メートル。全体に軟毛が密生。夏、黄色5弁の花を開く。茎の繊維で綱・糸・粗布を製し、暖地で稀に栽培。きり麻。白麻。漢名、莔麻ぼうま。
いちび
 ⇒いちび‐がら【莔麻稈】
⇒いちび‐ずさ【莔麻苆】
⇒いちび‐はばき【莔麻脛巾】
いちび‐がら【莔麻稈】
イチビの茎の皮を剥いだもの。焼いて炭とし、火口ほくちを作る。
⇒いちび【莔麻】
いちび‐ずさ【莔麻苆】
イチビの繊維から作った綱などの廃物を利用した苆すさ。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひと【一人】
第一人者。もっともすぐれた人。狂言、法師が母「―の、眉目のよいは、田中権頭のまま娘」
いち‐びと【市人】
市で物を売る人。商人。夫木和歌抄9「かきくらし思ひもあへぬ夕立に―騒ぐ三輪の山もと」
いちび‐はばき【莔麻脛巾】
イチビの皮で編んだはばき。衛府の随身などが用いた。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひめ【市姫】
市神である女神。市杵島姫命いちきしまひめのみこと、また橋姫のことという。為頼集「―の神のいがきのいかなれや」
⇒いちび‐がら【莔麻稈】
⇒いちび‐ずさ【莔麻苆】
⇒いちび‐はばき【莔麻脛巾】
いちび‐がら【莔麻稈】
イチビの茎の皮を剥いだもの。焼いて炭とし、火口ほくちを作る。
⇒いちび【莔麻】
いちび‐ずさ【莔麻苆】
イチビの繊維から作った綱などの廃物を利用した苆すさ。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひと【一人】
第一人者。もっともすぐれた人。狂言、法師が母「―の、眉目のよいは、田中権頭のまま娘」
いち‐びと【市人】
市で物を売る人。商人。夫木和歌抄9「かきくらし思ひもあへぬ夕立に―騒ぐ三輪の山もと」
いちび‐はばき【莔麻脛巾】
イチビの皮で編んだはばき。衛府の随身などが用いた。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひめ【市姫】
市神である女神。市杵島姫命いちきしまひめのみこと、また橋姫のことという。為頼集「―の神のいがきのいかなれや」
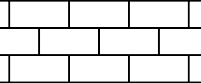 いちのじ‐てん【一の字点】
(点は「しるし」の意)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「ゝ」「ヽ」。「しのゝめ」「アラヽギ」など。現在では仮名の反復に用いる。→踊り字
いち‐の‐しょうけい【一上卿】‥シヤウ‥
(上卿中、最も有力なものの意)普通は左大臣の称。一上いちのしょう・いちのかみ。
いちのせき【一関】
岩手県南部、北上盆地南端の市。陸羽街道の要地。もと仙台藩の支藩田村氏3万石の城下町。県南の中心都市として商工業が発達。人口12万6千。
厳美渓
撮影:山梨勝弘
いちのじ‐てん【一の字点】
(点は「しるし」の意)踊り字の一つ。同じ字を繰り返すことをあらわす符号。「ゝ」「ヽ」。「しのゝめ」「アラヽギ」など。現在では仮名の反復に用いる。→踊り字
いち‐の‐しょうけい【一上卿】‥シヤウ‥
(上卿中、最も有力なものの意)普通は左大臣の称。一上いちのしょう・いちのかみ。
いちのせき【一関】
岩手県南部、北上盆地南端の市。陸羽街道の要地。もと仙台藩の支藩田村氏3万石の城下町。県南の中心都市として商工業が発達。人口12万6千。
厳美渓
撮影:山梨勝弘
 いち‐の‐ぜん【一の膳】
本膳料理で出す第一の食膳。本膳。→二の膳→三の膳
いち‐の‐たい【一の対】
①寝殿造の東の対あるいは西の対。東北対・西北対に対していう。対屋たいのやのうち主な方。宇津保物語国譲上「東の―の北面」→二の対。
②第一夫人、すなわち、妻妾中の頭立った人。〈日葡辞書〉
いち‐の‐だいじん【一の大臣】
⇒いちのおとど
いちのたに【一谷】
神戸市須磨区の、鉄枴てっかい・鉢伏はちぶせの両山が海岸に迫る地域。北に鵯越ひよどりごえがある。1184年(寿永3)源義経が平家の軍を攻めた古戦場。
一谷
撮影:的場 啓
いち‐の‐ぜん【一の膳】
本膳料理で出す第一の食膳。本膳。→二の膳→三の膳
いち‐の‐たい【一の対】
①寝殿造の東の対あるいは西の対。東北対・西北対に対していう。対屋たいのやのうち主な方。宇津保物語国譲上「東の―の北面」→二の対。
②第一夫人、すなわち、妻妾中の頭立った人。〈日葡辞書〉
いち‐の‐だいじん【一の大臣】
⇒いちのおとど
いちのたに【一谷】
神戸市須磨区の、鉄枴てっかい・鉢伏はちぶせの両山が海岸に迫る地域。北に鵯越ひよどりごえがある。1184年(寿永3)源義経が平家の軍を攻めた古戦場。
一谷
撮影:的場 啓
 ⇒いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1751年(宝暦1)初演。一谷の戦に、熊谷次郎直実が平敦盛を討って遁世し、また、岡部六弥太が平忠度を討ったことを脚色。「熊谷陣屋」の段が有名。後に歌舞伎化。
→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]
⇒いちのたに【一谷】
いち‐の‐つかさ【市司】
律令制で、都の市(市場)を監督した役所。平城京・平安京で、左京(東)・右京(西)のそれぞれに東市ひがしのいち・西市にしのいちが公設され、東市司・西市司がこれを管理した。
いち‐の‐て【一の手】
第一になすべき手段。または、最もすぐれた手段。
いち‐の‐どう【一の胴】
胴体の上部で両腋わきより少し下の所。浄瑠璃、傾城反魂香「試して見たい新刃あらみはないか、―か二の胴か望んで置け」→二の胴
いち‐の‐ところ【一の所】
(→)「いちのひと」に同じ。
いち‐の‐とり【一の酉】
11月の最初の酉の日。また、この日行われる酉の市。初酉。〈[季]冬〉。→酉の市
いち‐の‐とりい【一の鳥居】‥ヰ
神社の一番外側にある鳥居。
いち‐の‐ないし【一の内侍】
内侍(掌侍)の首席。勾当内侍こうとうのないし。
いち‐の‐ひじり【市聖】
空也くうやの通称。天慶(938〜947)年間、京都市中で阿弥陀仏の名号を唱えて民衆を勧化かんげしたことによる。市の上人。いちひじり。
いち‐の‐ひと【一の人】
(第一の席につくからいう)摂政・関白、また太政大臣の異称。いちのところ。一の家。枕草子88「―の御ありき」
いち‐の‐ふで【一の筆】
①戦場で一番首を取ったことを首帳くびちょうの初めに記されたこと。また、奉加帳などに第一に書きしるすこと。平家物語9「高名の―にぞ付きにける」
②年頭にする書きぞめ。
いち‐の‐まい【一の舞】‥マヒ
舞の中で、最初に舞う舞。また、その舞い手。枕草子142「―のいとうるはしく袖を合はせて」
いち‐の‐まつ【一の松】
能舞台の橋掛りの前面に植える3本の松のうち、舞台に最も近い松。→能舞台(図)
いち‐の‐みこ【一の御子】
1番目の皇子。一の宮。源氏物語桐壺「―は右大臣の女御の御腹にて」
いち‐の‐みだい【一の御台】
(「台」は台盤の略)第一に奉る食膳。
いち‐の‐みや【一の宮】
①(→)「いちのみこ」に同じ。源氏物語桐壺「―を見たてまつらせ給ふにも若宮の御恋しさのみ思ほし出でつつ」
②各国の由緒あり信仰の篤い神社で、その国の第1位のもの。大宮市の氷川神社を武蔵国の一の宮とした類。今、各地に地名としても存続している。(「うつのみや」もその転訛)
いちのみや【一宮】
愛知県北西部の市。尾張の一宮真清田ますみだ神社の門前町として発展。毛織物工業の中心。人口37万2千。尾張一の宮。
いち‐の‐もの【一の物・一の者】
①すぐれた物。すぐれた人。
②楽所の楽人の筆頭。
いち‐の‐や【一の矢】
手に持った2本の矢のうち、第一に放つ矢。
いち‐ば【市場・市庭】
①毎日または定期に商人が集まって、商品の売買を行う場所。市いち。「魚うお―」
市場
撮影:関戸 勇
⇒いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
いちのたに‐ふたばぐんき【一谷嫩軍記】
浄瑠璃。並木宗輔ほか合作の時代物。1751年(宝暦1)初演。一谷の戦に、熊谷次郎直実が平敦盛を討って遁世し、また、岡部六弥太が平忠度を討ったことを脚色。「熊谷陣屋」の段が有名。後に歌舞伎化。
→文献資料[一谷嫩軍記(熊谷陣屋の段)]
⇒いちのたに【一谷】
いち‐の‐つかさ【市司】
律令制で、都の市(市場)を監督した役所。平城京・平安京で、左京(東)・右京(西)のそれぞれに東市ひがしのいち・西市にしのいちが公設され、東市司・西市司がこれを管理した。
いち‐の‐て【一の手】
第一になすべき手段。または、最もすぐれた手段。
いち‐の‐どう【一の胴】
胴体の上部で両腋わきより少し下の所。浄瑠璃、傾城反魂香「試して見たい新刃あらみはないか、―か二の胴か望んで置け」→二の胴
いち‐の‐ところ【一の所】
(→)「いちのひと」に同じ。
いち‐の‐とり【一の酉】
11月の最初の酉の日。また、この日行われる酉の市。初酉。〈[季]冬〉。→酉の市
いち‐の‐とりい【一の鳥居】‥ヰ
神社の一番外側にある鳥居。
いち‐の‐ないし【一の内侍】
内侍(掌侍)の首席。勾当内侍こうとうのないし。
いち‐の‐ひじり【市聖】
空也くうやの通称。天慶(938〜947)年間、京都市中で阿弥陀仏の名号を唱えて民衆を勧化かんげしたことによる。市の上人。いちひじり。
いち‐の‐ひと【一の人】
(第一の席につくからいう)摂政・関白、また太政大臣の異称。いちのところ。一の家。枕草子88「―の御ありき」
いち‐の‐ふで【一の筆】
①戦場で一番首を取ったことを首帳くびちょうの初めに記されたこと。また、奉加帳などに第一に書きしるすこと。平家物語9「高名の―にぞ付きにける」
②年頭にする書きぞめ。
いち‐の‐まい【一の舞】‥マヒ
舞の中で、最初に舞う舞。また、その舞い手。枕草子142「―のいとうるはしく袖を合はせて」
いち‐の‐まつ【一の松】
能舞台の橋掛りの前面に植える3本の松のうち、舞台に最も近い松。→能舞台(図)
いち‐の‐みこ【一の御子】
1番目の皇子。一の宮。源氏物語桐壺「―は右大臣の女御の御腹にて」
いち‐の‐みだい【一の御台】
(「台」は台盤の略)第一に奉る食膳。
いち‐の‐みや【一の宮】
①(→)「いちのみこ」に同じ。源氏物語桐壺「―を見たてまつらせ給ふにも若宮の御恋しさのみ思ほし出でつつ」
②各国の由緒あり信仰の篤い神社で、その国の第1位のもの。大宮市の氷川神社を武蔵国の一の宮とした類。今、各地に地名としても存続している。(「うつのみや」もその転訛)
いちのみや【一宮】
愛知県北西部の市。尾張の一宮真清田ますみだ神社の門前町として発展。毛織物工業の中心。人口37万2千。尾張一の宮。
いち‐の‐もの【一の物・一の者】
①すぐれた物。すぐれた人。
②楽所の楽人の筆頭。
いち‐の‐や【一の矢】
手に持った2本の矢のうち、第一に放つ矢。
いち‐ば【市場・市庭】
①毎日または定期に商人が集まって、商品の売買を行う場所。市いち。「魚うお―」
市場
撮影:関戸 勇
 ②常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。しじょう。マーケット。
⇒いちば‐せん【市庭銭】
⇒いちば‐まち【市場町】
いち‐ばい【一倍】
①ある数量と同じ数量。「―半」
②ある数量を二つ合わせた数量。倍。2倍。日本永代蔵1「一年―の算用につもり」
③(副詞的に)いっそう。ひとしお。浄瑠璃、近江源氏先陣館「聞分けよい程助けたさは、胸―に迫れども」。「人―喜ぶ」
いちばく‐じっかん【一暴十寒】
[孟子告子上]1日だけ日光に当てて暖めても、10日寒くしたままでは、良い種子も成長することはできない。たまに好い条件を与えても、普段の条件が悪ければなんにもならない。
いちば‐せん【市庭銭】
中世、荘園内の市場に課した税金。江戸時代には市場運上を徴収。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はつ【鳶尾・一八】
アヤメ科の多年草。中国の原産。高さ約30センチメートル。葉は剣状で、中央脈が隆起。5月頃、紫花または白花を開く。花被は6枚で、外花被に白色の突起がつく。観賞用。火災を防ぐという俗信から、わら屋の上に植えることがある。コヤスグサ。〈[季]夏〉
いちはつ
②常設の設備があって、おもに日用品・食料品を販売する所。しじょう。マーケット。
⇒いちば‐せん【市庭銭】
⇒いちば‐まち【市場町】
いち‐ばい【一倍】
①ある数量と同じ数量。「―半」
②ある数量を二つ合わせた数量。倍。2倍。日本永代蔵1「一年―の算用につもり」
③(副詞的に)いっそう。ひとしお。浄瑠璃、近江源氏先陣館「聞分けよい程助けたさは、胸―に迫れども」。「人―喜ぶ」
いちばく‐じっかん【一暴十寒】
[孟子告子上]1日だけ日光に当てて暖めても、10日寒くしたままでは、良い種子も成長することはできない。たまに好い条件を与えても、普段の条件が悪ければなんにもならない。
いちば‐せん【市庭銭】
中世、荘園内の市場に課した税金。江戸時代には市場運上を徴収。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はつ【鳶尾・一八】
アヤメ科の多年草。中国の原産。高さ約30センチメートル。葉は剣状で、中央脈が隆起。5月頃、紫花または白花を開く。花被は6枚で、外花被に白色の突起がつく。観賞用。火災を防ぐという俗信から、わら屋の上に植えることがある。コヤスグサ。〈[季]夏〉
いちはつ
 いちばつ‐ひゃっかい【一罰百戒】‥ヒヤク‥
一人を罰して、多くの人の戒めとすること。
いちはな‐か・く【一端駆く】
〔自下二〕
一番最初に駆ける。一番駆けをする。堀河百首題狂歌集「鶯の―・けて咲く梅に」
いちはな‐がけ【一端駆け】
一番最初にすること。一番先。浮世風呂前「死んだら―に泣くだらう」
いちはな‐だ・つ【一端立つ】
〔自四〕
一番先に立つ。東海道中膝栗毛5「ゑどぐみの御師の手代、―・ちておくより出」
いちば‐まち【市場町】
市場から発達した集落。室町後期に広く成立。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はやく【逸速く】
⇒いちはやし5
いち‐はや・し【逸速し】
〔形ク〕
(イチに「逸」は当て字。一説に、「厳」の意)
①霊威がいちじるしい。欽明紀「浦の神―・し」
②容赦しない。手きびしい。源氏物語須磨「―・き世のいとおそろしう侍るなり」
③はげしい。強烈である。切実である。伊勢物語「昔人はかく―・きみやびをなんしける」
④気が早い。性急である。蜻蛉日記下「なほここにはいと―・き心ちすれば、思ひかくることもなきを」
⑤(連用形を副詞的に用いて)他にさきがけてすばやく。「現場に―・くかけつける」
いち‐はや・ぶ【逸速ぶ】
〔自上二〕
するどくなる。はげしくなる。祝詞、鎮火祭「御心―・び給はじとして」
いちはら【市原】
千葉県中部、京葉工業地帯の中心都市。東京湾に面し、工業港をもつ。古代、上総国の要地で、国府跡・国分寺跡がある。人口28万。
いちはらの【市原野】
歌舞伎舞踊。常磐津。富本からの改作。3世桜田治助作詞。1875年(明治8)4世岸沢古式部作曲。本名題「笛澄月白浪ふえにすむつきのしらなみ」。袴垂保輔が京都の市原野に源頼光を襲うが討てず、小蝶の前がからんで3人のだんまり。のち長唄にも移された。
いちはら‐の‐おおきみ【市原王】‥オホ‥
天智天皇の曾孫安貴王の王子。万葉歌人。生没年未詳。
いち‐ばん【一番】
[一]〔名〕
①二つが一組となったもの。ひとつがい。
②最初。第一。
③同種のものの中で最もすぐれたもの。また、最大のもの。東海道中膝栗毛6「―の桶」
④一度。一回。特に、歌舞などの一曲。碁・将棋などの一局。相撲の一勝負。「結びの―」
[二]〔副〕
①こころみに。まず一度。「承知するかしないか―あたってみよう」
②最も。甚だしく。この上もなく。「―悪い」「―早く起きる」
⇒いちばん‐うけ【一番受】
⇒いちばん‐がい【一番貝】
⇒いちばん‐がけ【一番駆け】
⇒いちばん‐きり【一番切】
⇒いちばん‐ぐさ【一番草】
⇒いちばん‐くび【一番首】
⇒いちばん‐こ【一番子】
⇒いちばん‐しゅっせ【一番出世】
⇒いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
⇒いちばん‐せんじ【一番煎じ】
⇒いちばん‐ぞなえ【一番備え】
⇒いちばん‐だいこ【一番太鼓】
⇒いちばん‐だし【一番出し】
⇒いちばん‐ちゃ【一番茶】
⇒いちばん‐て【一番手】
⇒いちばん‐ていとう【一番抵当】
⇒いちばん‐でし【一番弟子】
⇒いちばん‐どり【一番鶏】
⇒いちばん‐なり【一番成り】
⇒いちばん‐にょうぼう【一番女房】
⇒いちばん‐のり【一番乗り】
⇒いちばん‐ぶろ【一番風呂】
⇒いちばん‐ぼし【一番星】
⇒いちばん‐め【一番目】
⇒いちばん‐やり【一番槍】
⇒いちばん‐れっしゃ【一番列車】
いちばん‐うけ【一番受】
武家時代、敵の来襲に備えて先頭にいること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がい【一番貝】‥ガヒ
軍陣で最初に吹く陣貝。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がけ【一番駆け】
①戦場で第一番に敵陣に駆け入って戦うこと。
②転じて、人に先んじて事をなすこと。一端いちはな駆け。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐きり【一番切】
(→)「いちばんしょうぶ」に同じ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「数ばかりの勝負づく、―に突いて見て」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぐさ【一番草】
稲田除草の第1回目。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐くび【一番首】
戦場で第一番に討ち取った敵の首級。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐こ【一番子】
①最初に生まれた子。
②その家でもっともできのよい子。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しゅっせ【一番出世】
大相撲の前相撲で、新弟子が定められた日までに規定の勝星をあげ、翌場所序の口に上がる資格を得ること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
ただ1番だけで決する勝負。また、ただ1回だけ試みること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐せんじ【一番煎じ】
茶または薬の、第一番に煎じ出したもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぞなえ【一番備え】‥ゾナヘ
敵陣にもっとも近く、第一番に備えた軍隊。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だいこ【一番太鼓】
①大坂新町の遊郭で、門限を知らせるための太鼓。3回に及ぶがそのうち夜10時頃打つ最初の太鼓。→三番太鼓。
②歌舞伎劇場の開場を知らせるために毎早暁に打つ大太鼓。顔見世狂言の初日の暁の八つ時に打ったのが始まり。根無草後編「―は八声に先立ち、三番叟さんばそうは明けるを待たず」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だし【一番出し】
出し汁用の材料から最初にうまみを引き出した汁。一般的には昆布と鰹節かつおぶしの出し汁。吸い物や茶碗蒸しなどに用いる。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ちゃ【一番茶】
春に最初に摘みとった茶。〈[季]春〉
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐て【一番手】
①第一番に敵陣に討って出る軍勢。
②最初に物事にあたる人。
③競争者の中で最も優位にある人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ていとう【一番抵当】‥タウ
同一の物件上に設定された抵当権のうち最優先の順位にあるもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐でし【一番弟子】
弟子のなかで、最もすぐれたもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐どり【一番鶏】
暁に最初に鳴くニワトリ。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐なり【一番成り】
その年一番最初に実った果実。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐にょうぼう【一番女房】‥バウ
最も働きのある女奉公人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐のり【一番乗り】
第一番に敵陣や敵城に馬を乗り入れること。転じて、ある場所に最初に乗りこむこと。また、その人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぶろ【一番風呂】
沸かしたばかりで、その日初めて人が入る風呂。新湯。↔仕舞風呂。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぼし【一番星】
夕方、一番はじめに輝き出す星。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐め【一番目】
①順番の第一番。
②時代物の歌舞伎狂言。多くは演目中の最初に演ずるからいう。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐やり【一番槍】
第一番に敵陣に槍を突き入れること。また、その人。転じて、最初に功名をたてること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐れっしゃ【一番列車】
その日最初に運転される列車。
⇒いち‐ばん【一番】
いち‐び【市日】
定期的に市の立つ日。市の開かれる日。
いちび【莔麻】
アオイ科の一年草。インド・西アジア原産。高さ約1メートル。全体に軟毛が密生。夏、黄色5弁の花を開く。茎の繊維で綱・糸・粗布を製し、暖地で稀に栽培。きり麻。白麻。漢名、莔麻ぼうま。
いちび
いちばつ‐ひゃっかい【一罰百戒】‥ヒヤク‥
一人を罰して、多くの人の戒めとすること。
いちはな‐か・く【一端駆く】
〔自下二〕
一番最初に駆ける。一番駆けをする。堀河百首題狂歌集「鶯の―・けて咲く梅に」
いちはな‐がけ【一端駆け】
一番最初にすること。一番先。浮世風呂前「死んだら―に泣くだらう」
いちはな‐だ・つ【一端立つ】
〔自四〕
一番先に立つ。東海道中膝栗毛5「ゑどぐみの御師の手代、―・ちておくより出」
いちば‐まち【市場町】
市場から発達した集落。室町後期に広く成立。
⇒いち‐ば【市場・市庭】
いち‐はやく【逸速く】
⇒いちはやし5
いち‐はや・し【逸速し】
〔形ク〕
(イチに「逸」は当て字。一説に、「厳」の意)
①霊威がいちじるしい。欽明紀「浦の神―・し」
②容赦しない。手きびしい。源氏物語須磨「―・き世のいとおそろしう侍るなり」
③はげしい。強烈である。切実である。伊勢物語「昔人はかく―・きみやびをなんしける」
④気が早い。性急である。蜻蛉日記下「なほここにはいと―・き心ちすれば、思ひかくることもなきを」
⑤(連用形を副詞的に用いて)他にさきがけてすばやく。「現場に―・くかけつける」
いち‐はや・ぶ【逸速ぶ】
〔自上二〕
するどくなる。はげしくなる。祝詞、鎮火祭「御心―・び給はじとして」
いちはら【市原】
千葉県中部、京葉工業地帯の中心都市。東京湾に面し、工業港をもつ。古代、上総国の要地で、国府跡・国分寺跡がある。人口28万。
いちはらの【市原野】
歌舞伎舞踊。常磐津。富本からの改作。3世桜田治助作詞。1875年(明治8)4世岸沢古式部作曲。本名題「笛澄月白浪ふえにすむつきのしらなみ」。袴垂保輔が京都の市原野に源頼光を襲うが討てず、小蝶の前がからんで3人のだんまり。のち長唄にも移された。
いちはら‐の‐おおきみ【市原王】‥オホ‥
天智天皇の曾孫安貴王の王子。万葉歌人。生没年未詳。
いち‐ばん【一番】
[一]〔名〕
①二つが一組となったもの。ひとつがい。
②最初。第一。
③同種のものの中で最もすぐれたもの。また、最大のもの。東海道中膝栗毛6「―の桶」
④一度。一回。特に、歌舞などの一曲。碁・将棋などの一局。相撲の一勝負。「結びの―」
[二]〔副〕
①こころみに。まず一度。「承知するかしないか―あたってみよう」
②最も。甚だしく。この上もなく。「―悪い」「―早く起きる」
⇒いちばん‐うけ【一番受】
⇒いちばん‐がい【一番貝】
⇒いちばん‐がけ【一番駆け】
⇒いちばん‐きり【一番切】
⇒いちばん‐ぐさ【一番草】
⇒いちばん‐くび【一番首】
⇒いちばん‐こ【一番子】
⇒いちばん‐しゅっせ【一番出世】
⇒いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
⇒いちばん‐せんじ【一番煎じ】
⇒いちばん‐ぞなえ【一番備え】
⇒いちばん‐だいこ【一番太鼓】
⇒いちばん‐だし【一番出し】
⇒いちばん‐ちゃ【一番茶】
⇒いちばん‐て【一番手】
⇒いちばん‐ていとう【一番抵当】
⇒いちばん‐でし【一番弟子】
⇒いちばん‐どり【一番鶏】
⇒いちばん‐なり【一番成り】
⇒いちばん‐にょうぼう【一番女房】
⇒いちばん‐のり【一番乗り】
⇒いちばん‐ぶろ【一番風呂】
⇒いちばん‐ぼし【一番星】
⇒いちばん‐め【一番目】
⇒いちばん‐やり【一番槍】
⇒いちばん‐れっしゃ【一番列車】
いちばん‐うけ【一番受】
武家時代、敵の来襲に備えて先頭にいること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がい【一番貝】‥ガヒ
軍陣で最初に吹く陣貝。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐がけ【一番駆け】
①戦場で第一番に敵陣に駆け入って戦うこと。
②転じて、人に先んじて事をなすこと。一端いちはな駆け。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐きり【一番切】
(→)「いちばんしょうぶ」に同じ。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「数ばかりの勝負づく、―に突いて見て」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぐさ【一番草】
稲田除草の第1回目。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐くび【一番首】
戦場で第一番に討ち取った敵の首級。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐こ【一番子】
①最初に生まれた子。
②その家でもっともできのよい子。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しゅっせ【一番出世】
大相撲の前相撲で、新弟子が定められた日までに規定の勝星をあげ、翌場所序の口に上がる資格を得ること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐しょうぶ【一番勝負】
ただ1番だけで決する勝負。また、ただ1回だけ試みること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐せんじ【一番煎じ】
茶または薬の、第一番に煎じ出したもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぞなえ【一番備え】‥ゾナヘ
敵陣にもっとも近く、第一番に備えた軍隊。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だいこ【一番太鼓】
①大坂新町の遊郭で、門限を知らせるための太鼓。3回に及ぶがそのうち夜10時頃打つ最初の太鼓。→三番太鼓。
②歌舞伎劇場の開場を知らせるために毎早暁に打つ大太鼓。顔見世狂言の初日の暁の八つ時に打ったのが始まり。根無草後編「―は八声に先立ち、三番叟さんばそうは明けるを待たず」
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐だし【一番出し】
出し汁用の材料から最初にうまみを引き出した汁。一般的には昆布と鰹節かつおぶしの出し汁。吸い物や茶碗蒸しなどに用いる。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ちゃ【一番茶】
春に最初に摘みとった茶。〈[季]春〉
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐て【一番手】
①第一番に敵陣に討って出る軍勢。
②最初に物事にあたる人。
③競争者の中で最も優位にある人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ていとう【一番抵当】‥タウ
同一の物件上に設定された抵当権のうち最優先の順位にあるもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐でし【一番弟子】
弟子のなかで、最もすぐれたもの。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐どり【一番鶏】
暁に最初に鳴くニワトリ。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐なり【一番成り】
その年一番最初に実った果実。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐にょうぼう【一番女房】‥バウ
最も働きのある女奉公人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐のり【一番乗り】
第一番に敵陣や敵城に馬を乗り入れること。転じて、ある場所に最初に乗りこむこと。また、その人。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぶろ【一番風呂】
沸かしたばかりで、その日初めて人が入る風呂。新湯。↔仕舞風呂。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐ぼし【一番星】
夕方、一番はじめに輝き出す星。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐め【一番目】
①順番の第一番。
②時代物の歌舞伎狂言。多くは演目中の最初に演ずるからいう。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐やり【一番槍】
第一番に敵陣に槍を突き入れること。また、その人。転じて、最初に功名をたてること。
⇒いち‐ばん【一番】
いちばん‐れっしゃ【一番列車】
その日最初に運転される列車。
⇒いち‐ばん【一番】
いち‐び【市日】
定期的に市の立つ日。市の開かれる日。
いちび【莔麻】
アオイ科の一年草。インド・西アジア原産。高さ約1メートル。全体に軟毛が密生。夏、黄色5弁の花を開く。茎の繊維で綱・糸・粗布を製し、暖地で稀に栽培。きり麻。白麻。漢名、莔麻ぼうま。
いちび
 ⇒いちび‐がら【莔麻稈】
⇒いちび‐ずさ【莔麻苆】
⇒いちび‐はばき【莔麻脛巾】
いちび‐がら【莔麻稈】
イチビの茎の皮を剥いだもの。焼いて炭とし、火口ほくちを作る。
⇒いちび【莔麻】
いちび‐ずさ【莔麻苆】
イチビの繊維から作った綱などの廃物を利用した苆すさ。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひと【一人】
第一人者。もっともすぐれた人。狂言、法師が母「―の、眉目のよいは、田中権頭のまま娘」
いち‐びと【市人】
市で物を売る人。商人。夫木和歌抄9「かきくらし思ひもあへぬ夕立に―騒ぐ三輪の山もと」
いちび‐はばき【莔麻脛巾】
イチビの皮で編んだはばき。衛府の随身などが用いた。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひめ【市姫】
市神である女神。市杵島姫命いちきしまひめのみこと、また橋姫のことという。為頼集「―の神のいがきのいかなれや」
⇒いちび‐がら【莔麻稈】
⇒いちび‐ずさ【莔麻苆】
⇒いちび‐はばき【莔麻脛巾】
いちび‐がら【莔麻稈】
イチビの茎の皮を剥いだもの。焼いて炭とし、火口ほくちを作る。
⇒いちび【莔麻】
いちび‐ずさ【莔麻苆】
イチビの繊維から作った綱などの廃物を利用した苆すさ。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひと【一人】
第一人者。もっともすぐれた人。狂言、法師が母「―の、眉目のよいは、田中権頭のまま娘」
いち‐びと【市人】
市で物を売る人。商人。夫木和歌抄9「かきくらし思ひもあへぬ夕立に―騒ぐ三輪の山もと」
いちび‐はばき【莔麻脛巾】
イチビの皮で編んだはばき。衛府の随身などが用いた。
⇒いちび【莔麻】
いち‐ひめ【市姫】
市神である女神。市杵島姫命いちきしまひめのみこと、また橋姫のことという。為頼集「―の神のいがきのいかなれや」
広辞苑に「一の裏は六」で始まるの検索結果 1-1。