複数辞典一括検索+![]()
![]()
中 うち🔗⭐🔉
【中】
 4画 |部 [一年]
区点=3570 16進=4366 シフトJIS=9286
《常用音訓》チュウ/なか
《音読み》 チュウ
4画 |部 [一年]
区点=3570 16進=4366 シフトJIS=9286
《常用音訓》チュウ/なか
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh ng・zh
ng・zh ng〉
《訓読み》 なか/うち/あたる
《名付け》 あたる・あつ・うち・かなめ・ただ・ただし・な・なか・なかち・なかば・のり・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 なか/うち/あたる
《名付け》 あたる・あつ・うち・かなめ・ただ・ただし・な・なか・なかち・なかば・のり・よし
《意味》
 {名}なか。ものの内側。〈対語〉→外。「中外」「中身」
{名}なか。ものの内側。〈対語〉→外。「中外」「中身」
 {名}なか。もののまんなか。また、程度のなかほど。「中央」「中庸」
{名}なか。もののまんなか。また、程度のなかほど。「中央」「中庸」
 {名・形}進行している物事のなかば。なかばであるさま。「中途」「中旬」
{名・形}進行している物事のなかば。なかばであるさま。「中途」「中旬」
 {名}在野ザイヤに対する宮中を略していうことば。
{名}在野ザイヤに対する宮中を略していうことば。
 {名}なか。うち。ある地区や時期の範囲のうち。〈類義語〉→内。「蜀中ショクチュウ(四川シセン省のうち)」「寒中」
{名}なか。うち。ある地区や時期の範囲のうち。〈類義語〉→内。「蜀中ショクチュウ(四川シセン省のうち)」「寒中」
 {名・形}子や兄弟で、上下の間にいる。また、その人。▽仲に当てた用法。「中兄」
{名・形}子や兄弟で、上下の間にいる。また、その人。▽仲に当てた用法。「中兄」
 {名}心のなか。▽衷チュウに当てた用法。「中情怯耳=中情ハ怯ナルノミ」〔→史記〕
{名}心のなか。▽衷チュウに当てた用法。「中情怯耳=中情ハ怯ナルノミ」〔→史記〕
 チュウス{動}まんなかにくる。▽去声に読む。「中天=天ニ中ス」
チュウス{動}まんなかにくる。▽去声に読む。「中天=天ニ中ス」
 {動}あたる。ずばりとかなめを突き通す。▽去声に読む。「命中」「中風チュウフウ・チュウブ(風などの外界の刺激にまともにあてられた病気)」「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕
《解字》
{動}あたる。ずばりとかなめを突き通す。▽去声に読む。「命中」「中風チュウフウ・チュウブ(風などの外界の刺激にまともにあてられた病気)」「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕
《解字》
 象形。もとの字は、旗ざおをわくのまんなかにつき通した姿を描いたもので、まんなかの意をあらわす。また、まんなかを突き通すの意をも含む。仲チュウ・衷チュウの音符となる。
《単語家族》
通トウ・ツウ
象形。もとの字は、旗ざおをわくのまんなかにつき通した姿を描いたもので、まんなかの意をあらわす。また、まんなかを突き通すの意をも含む。仲チュウ・衷チュウの音符となる。
《単語家族》
通トウ・ツウ 筒トウと同系。
《類義》
→衝
《異字同訓》
なか。中「箱の中。両者の中に入る」仲「仲がいい。仲を取り持つ。仲働き」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
筒トウと同系。
《類義》
→衝
《異字同訓》
なか。中「箱の中。両者の中に入る」仲「仲がいい。仲を取り持つ。仲働き」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
 4画 |部 [一年]
区点=3570 16進=4366 シフトJIS=9286
《常用音訓》チュウ/なか
《音読み》 チュウ
4画 |部 [一年]
区点=3570 16進=4366 シフトJIS=9286
《常用音訓》チュウ/なか
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh ng・zh
ng・zh ng〉
《訓読み》 なか/うち/あたる
《名付け》 あたる・あつ・うち・かなめ・ただ・ただし・な・なか・なかち・なかば・のり・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 なか/うち/あたる
《名付け》 あたる・あつ・うち・かなめ・ただ・ただし・な・なか・なかち・なかば・のり・よし
《意味》
 {名}なか。ものの内側。〈対語〉→外。「中外」「中身」
{名}なか。ものの内側。〈対語〉→外。「中外」「中身」
 {名}なか。もののまんなか。また、程度のなかほど。「中央」「中庸」
{名}なか。もののまんなか。また、程度のなかほど。「中央」「中庸」
 {名・形}進行している物事のなかば。なかばであるさま。「中途」「中旬」
{名・形}進行している物事のなかば。なかばであるさま。「中途」「中旬」
 {名}在野ザイヤに対する宮中を略していうことば。
{名}在野ザイヤに対する宮中を略していうことば。
 {名}なか。うち。ある地区や時期の範囲のうち。〈類義語〉→内。「蜀中ショクチュウ(四川シセン省のうち)」「寒中」
{名}なか。うち。ある地区や時期の範囲のうち。〈類義語〉→内。「蜀中ショクチュウ(四川シセン省のうち)」「寒中」
 {名・形}子や兄弟で、上下の間にいる。また、その人。▽仲に当てた用法。「中兄」
{名・形}子や兄弟で、上下の間にいる。また、その人。▽仲に当てた用法。「中兄」
 {名}心のなか。▽衷チュウに当てた用法。「中情怯耳=中情ハ怯ナルノミ」〔→史記〕
{名}心のなか。▽衷チュウに当てた用法。「中情怯耳=中情ハ怯ナルノミ」〔→史記〕
 チュウス{動}まんなかにくる。▽去声に読む。「中天=天ニ中ス」
チュウス{動}まんなかにくる。▽去声に読む。「中天=天ニ中ス」
 {動}あたる。ずばりとかなめを突き通す。▽去声に読む。「命中」「中風チュウフウ・チュウブ(風などの外界の刺激にまともにあてられた病気)」「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕
《解字》
{動}あたる。ずばりとかなめを突き通す。▽去声に読む。「命中」「中風チュウフウ・チュウブ(風などの外界の刺激にまともにあてられた病気)」「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕
《解字》
 象形。もとの字は、旗ざおをわくのまんなかにつき通した姿を描いたもので、まんなかの意をあらわす。また、まんなかを突き通すの意をも含む。仲チュウ・衷チュウの音符となる。
《単語家族》
通トウ・ツウ
象形。もとの字は、旗ざおをわくのまんなかにつき通した姿を描いたもので、まんなかの意をあらわす。また、まんなかを突き通すの意をも含む。仲チュウ・衷チュウの音符となる。
《単語家族》
通トウ・ツウ 筒トウと同系。
《類義》
→衝
《異字同訓》
なか。中「箱の中。両者の中に入る」仲「仲がいい。仲を取り持つ。仲働き」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
筒トウと同系。
《類義》
→衝
《異字同訓》
なか。中「箱の中。両者の中に入る」仲「仲がいい。仲を取り持つ。仲働き」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要書物
→主要人名
内 うち🔗⭐🔉
【内】
 4画 冂部 [二年]
区点=3866 16進=4662 シフトJIS=93E0
《常用音訓》ダイ/ナイ/うち
《音読み》 ナイ
4画 冂部 [二年]
区点=3866 16進=4662 シフトJIS=93E0
《常用音訓》ダイ/ナイ/うち
《音読み》 ナイ /ダイ
/ダイ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)/いれる(いる)
《名付け》 うち・うつ・ただ・ちか・のぶ・はる・まさ・みつ
《意味》
i〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)/いれる(いる)
《名付け》 うち・うつ・ただ・ちか・のぶ・はる・まさ・みつ
《意味》
 {名}うち。ある範囲の中。〈対語〉→外。〈類義語〉→中。「以内」「四海之内、皆兄弟ナリ」〔→論語〕
{名}うち。ある範囲の中。〈対語〉→外。〈類義語〉→中。「以内」「四海之内、皆兄弟ナリ」〔→論語〕
 {名}うち。家庭の中。〈対語〉→外(家の外)。「内有余帛、外有贏財=内ニ余帛有リ、外ニ贏財有リ」〔→蜀志〕
{名}うち。家庭の中。〈対語〉→外(家の外)。「内有余帛、外有贏財=内ニ余帛有リ、外ニ贏財有リ」〔→蜀志〕
 {名}うち。中央の朝廷。〈対語〉→外(地方の任地)。「侍衛之臣、不懈於内、忠志之士、忘身於外=侍衛ノ臣、内ニ懈ラズ、忠志ノ士、身ヲ外ニ忘ル」〔→諸葛亮〕
{名}うち。中央の朝廷。〈対語〉→外(地方の任地)。「侍衛之臣、不懈於内、忠志之士、忘身於外=侍衛ノ臣、内ニ懈ラズ、忠志ノ士、身ヲ外ニ忘ル」〔→諸葛亮〕
 {名}妻。「内室」「内兄弟(妻の兄弟)」
{名}妻。「内室」「内兄弟(妻の兄弟)」
 {形}ないしょであるさま。「内密」「内諾」
{形}ないしょであるさま。「内密」「内諾」
 {動}うちにする(ウチニス)。たいせつにする。〈対語〉→疏・→外。「外本内末=本ヲ外ニシ末ヲ内ニス」〔→大学〕
{動}うちにする(ウチニス)。たいせつにする。〈対語〉→疏・→外。「外本内末=本ヲ外ニシ末ヲ内ニス」〔→大学〕
 {動}いれる(イル)。うちに入る。中にいれる。〈同義語〉→納・→入。「交戟之衛士欲止不内=交戟ノ衛士止メテ内レザラント欲ス」〔→史記〕
《解字》
{動}いれる(イル)。うちに入る。中にいれる。〈同義語〉→納・→入。「交戟之衛士欲止不内=交戟ノ衛士止メテ内レザラント欲ス」〔→史記〕
《解字》
 会意。屋根の形と入とをあわせたもので、おおいの中にいれることを示す。
《単語家族》
入
会意。屋根の形と入とをあわせたもので、おおいの中にいれることを示す。
《単語家族》
入 納と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
納と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 4画 冂部 [二年]
区点=3866 16進=4662 シフトJIS=93E0
《常用音訓》ダイ/ナイ/うち
《音読み》 ナイ
4画 冂部 [二年]
区点=3866 16進=4662 シフトJIS=93E0
《常用音訓》ダイ/ナイ/うち
《音読み》 ナイ /ダイ
/ダイ 〈n
〈n i〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)/いれる(いる)
《名付け》 うち・うつ・ただ・ちか・のぶ・はる・まさ・みつ
《意味》
i〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)/いれる(いる)
《名付け》 うち・うつ・ただ・ちか・のぶ・はる・まさ・みつ
《意味》
 {名}うち。ある範囲の中。〈対語〉→外。〈類義語〉→中。「以内」「四海之内、皆兄弟ナリ」〔→論語〕
{名}うち。ある範囲の中。〈対語〉→外。〈類義語〉→中。「以内」「四海之内、皆兄弟ナリ」〔→論語〕
 {名}うち。家庭の中。〈対語〉→外(家の外)。「内有余帛、外有贏財=内ニ余帛有リ、外ニ贏財有リ」〔→蜀志〕
{名}うち。家庭の中。〈対語〉→外(家の外)。「内有余帛、外有贏財=内ニ余帛有リ、外ニ贏財有リ」〔→蜀志〕
 {名}うち。中央の朝廷。〈対語〉→外(地方の任地)。「侍衛之臣、不懈於内、忠志之士、忘身於外=侍衛ノ臣、内ニ懈ラズ、忠志ノ士、身ヲ外ニ忘ル」〔→諸葛亮〕
{名}うち。中央の朝廷。〈対語〉→外(地方の任地)。「侍衛之臣、不懈於内、忠志之士、忘身於外=侍衛ノ臣、内ニ懈ラズ、忠志ノ士、身ヲ外ニ忘ル」〔→諸葛亮〕
 {名}妻。「内室」「内兄弟(妻の兄弟)」
{名}妻。「内室」「内兄弟(妻の兄弟)」
 {形}ないしょであるさま。「内密」「内諾」
{形}ないしょであるさま。「内密」「内諾」
 {動}うちにする(ウチニス)。たいせつにする。〈対語〉→疏・→外。「外本内末=本ヲ外ニシ末ヲ内ニス」〔→大学〕
{動}うちにする(ウチニス)。たいせつにする。〈対語〉→疏・→外。「外本内末=本ヲ外ニシ末ヲ内ニス」〔→大学〕
 {動}いれる(イル)。うちに入る。中にいれる。〈同義語〉→納・→入。「交戟之衛士欲止不内=交戟ノ衛士止メテ内レザラント欲ス」〔→史記〕
《解字》
{動}いれる(イル)。うちに入る。中にいれる。〈同義語〉→納・→入。「交戟之衛士欲止不内=交戟ノ衛士止メテ内レザラント欲ス」〔→史記〕
《解字》
 会意。屋根の形と入とをあわせたもので、おおいの中にいれることを示す。
《単語家族》
入
会意。屋根の形と入とをあわせたもので、おおいの中にいれることを示す。
《単語家族》
入 納と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
納と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
家 うち🔗⭐🔉
【家】
 10画 宀部 [二年]
区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6
《常用音訓》カ/ケ/いえ/や
《音読み》
10画 宀部 [二年]
区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6
《常用音訓》カ/ケ/いえ/や
《音読み》  カ
カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉/
〉/ ク
ク /コ
/コ 《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)
《名付け》 いえ・え・お・や・やか
《意味》
《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)
《名付け》 いえ・え・お・や・やか
《意味》

 {名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕
{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕
 {名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」
{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」
 {名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」
{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」
 {名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」
{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」
 {動}いえす(イヘス)。家
{動}いえす(イヘス)。家 を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕
を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕
 {名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」
{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」
 {名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
 {名}いえがら。「名家」
{名}いえがら。「名家」
 {名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」
〔国〕一氏族全体。「平家」
《解字》
会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。
《単語家族》
廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる)
{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」
〔国〕一氏族全体。「平家」
《解字》
会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。
《単語家族》
廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる) 胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。
《類義》
房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。
《異字同訓》
や。 →屋
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。
《類義》
房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。
《異字同訓》
や。 →屋
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
 10画 宀部 [二年]
区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6
《常用音訓》カ/ケ/いえ/や
《音読み》
10画 宀部 [二年]
区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6
《常用音訓》カ/ケ/いえ/や
《音読み》  カ
カ /ケ
/ケ 〈ji
〈ji 〉/
〉/ ク
ク /コ
/コ 《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)
《名付け》 いえ・え・お・や・やか
《意味》
《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)
《名付け》 いえ・え・お・や・やか
《意味》

 {名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕
{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕
 {名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」
{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」
 {名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」
{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」
 {名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」
{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」
 {動}いえす(イヘス)。家
{動}いえす(イヘス)。家 を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕
を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕
 {名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」
{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」
 {名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕
 {名}いえがら。「名家」
{名}いえがら。「名家」
 {名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」
〔国〕一氏族全体。「平家」
《解字》
会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。
《単語家族》
廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる)
{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」
〔国〕一氏族全体。「平家」
《解字》
会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。
《単語家族》
廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる) 胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。
《類義》
房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。
《異字同訓》
や。 →屋
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。
《類義》
房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。
《異字同訓》
や。 →屋
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
衷 うち🔗⭐🔉
【衷】
 9画 衣部 [常用漢字]
区点=3579 16進=436F シフトJIS=928F
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
9画 衣部 [常用漢字]
区点=3579 16進=436F シフトJIS=928F
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)
《名付け》 あつ・ただ・ただし・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)
《名付け》 あつ・ただ・ただし・よし
《意味》
 {名}うち。衣につつまれたそのなか。広く、なか。また、なかみ。〈同義語〉→中。
{名}うち。衣につつまれたそのなか。広く、なか。また、なかみ。〈同義語〉→中。
 {動}うちにする(ウチニス)。中に着こむ。「衷甲」「皆衷其衵服、以戯于朝=ミナソノ衵服ヲ衷ニシ、モッテ朝ニ戯ル」〔→左伝〕
{動}うちにする(ウチニス)。中に着こむ。「衷甲」「皆衷其衵服、以戯于朝=ミナソノ衵服ヲ衷ニシ、モッテ朝ニ戯ル」〔→左伝〕
 {名}心の中。また、まごころ。「衷情」「愚衷(私の本心)」
{名}心の中。また、まごころ。「衷情」「愚衷(私の本心)」
 {名}極端ではないほどの程度。また、ほどよい程度。▽去声に読む。〈同義語〉→中。「折衷」
{名}極端ではないほどの程度。また、ほどよい程度。▽去声に読む。〈同義語〉→中。「折衷」
 {動}あたる。かなう。適当する。▽中に当てた用法。去声に読む。
《解字》
会意兼形声。中は、なかほど、充実したなかみ、の二つの意味を含む。衷は「衣+音符中」で、衣でつつんだそのなかみ。中とほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}あたる。かなう。適当する。▽中に当てた用法。去声に読む。
《解字》
会意兼形声。中は、なかほど、充実したなかみ、の二つの意味を含む。衷は「衣+音符中」で、衣でつつんだそのなかみ。中とほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 9画 衣部 [常用漢字]
区点=3579 16進=436F シフトJIS=928F
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
9画 衣部 [常用漢字]
区点=3579 16進=436F シフトJIS=928F
《常用音訓》チュウ
《音読み》 チュウ
 〈zh
〈zh ng〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)
《名付け》 あつ・ただ・ただし・よし
《意味》
ng〉
《訓読み》 うち/うちにする(うちにす)
《名付け》 あつ・ただ・ただし・よし
《意味》
 {名}うち。衣につつまれたそのなか。広く、なか。また、なかみ。〈同義語〉→中。
{名}うち。衣につつまれたそのなか。広く、なか。また、なかみ。〈同義語〉→中。
 {動}うちにする(ウチニス)。中に着こむ。「衷甲」「皆衷其衵服、以戯于朝=ミナソノ衵服ヲ衷ニシ、モッテ朝ニ戯ル」〔→左伝〕
{動}うちにする(ウチニス)。中に着こむ。「衷甲」「皆衷其衵服、以戯于朝=ミナソノ衵服ヲ衷ニシ、モッテ朝ニ戯ル」〔→左伝〕
 {名}心の中。また、まごころ。「衷情」「愚衷(私の本心)」
{名}心の中。また、まごころ。「衷情」「愚衷(私の本心)」
 {名}極端ではないほどの程度。また、ほどよい程度。▽去声に読む。〈同義語〉→中。「折衷」
{名}極端ではないほどの程度。また、ほどよい程度。▽去声に読む。〈同義語〉→中。「折衷」
 {動}あたる。かなう。適当する。▽中に当てた用法。去声に読む。
《解字》
会意兼形声。中は、なかほど、充実したなかみ、の二つの意味を含む。衷は「衣+音符中」で、衣でつつんだそのなかみ。中とほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{動}あたる。かなう。適当する。▽中に当てた用法。去声に読む。
《解字》
会意兼形声。中は、なかほど、充実したなかみ、の二つの意味を含む。衷は「衣+音符中」で、衣でつつんだそのなかみ。中とほとんど同じ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
裏 うち🔗⭐🔉
【裏】
 13画 衣部 [六年]
区点=4602 16進=4E22 シフトJIS=97A0
【裡】異体字異体字
13画 衣部 [六年]
区点=4602 16進=4E22 シフトJIS=97A0
【裡】異体字異体字
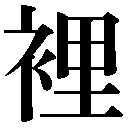 12画 衣部
区点=4603 16進=4E23 シフトJIS=97A1
《常用音訓》リ/うら
《音読み》 リ
12画 衣部
区点=4603 16進=4E23 シフトJIS=97A1
《常用音訓》リ/うら
《音読み》 リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 うら/うち
《名付け》 うら
《意味》
〉
《訓読み》 うら/うち
《名付け》 うら
《意味》
 {名}うら。すじもようのついた、衣のうら地。転じて、衣服のうら地。また、物の表面の反対側。うらがわ。〈対語〉→表。「表裏」「緑衣黄裏コウリ(緑の表地、黄色のうら地)」〔→詩経〕
{名}うら。すじもようのついた、衣のうら地。転じて、衣服のうら地。また、物の表面の反対側。うらがわ。〈対語〉→表。「表裏」「緑衣黄裏コウリ(緑の表地、黄色のうら地)」〔→詩経〕
 {名}うち。物のうちがわ。ふところ。〈対語〉→表・→外。〈類義語〉→内。「内裏ダイリ(宮中)」「心裏(心のなか)」
{名}うち。物のうちがわ。ふところ。〈対語〉→表・→外。〈類義語〉→内。「内裏ダイリ(宮中)」「心裏(心のなか)」
 {助}〔俗〕場所をあらわす接尾辞。「家裏チアリイ(いえ)」「那裏ナアリイ(そこ)」
〔国〕
{助}〔俗〕場所をあらわす接尾辞。「家裏チアリイ(いえ)」「那裏ナアリイ(そこ)」
〔国〕 うら。物事の表面にあらわれないこと。また、そのようなもの。「裏話」「裏方ウラカタ」
うら。物事の表面にあらわれないこと。また、そのようなもの。「裏話」「裏方ウラカタ」 …のうちに。「暗暗裏アンアンリ」「盛会裏」
《解字》
会意兼形声。里リは、すじめのついた田畑。裏は「衣+音符里」で、もと、たてよこのすじめの模様(しま模様)の布地。しま模様の布地は、衣服のうら地に用いた。▽裹カは、別字。
《単語家族》
理リ(玉のすじめ)
…のうちに。「暗暗裏アンアンリ」「盛会裏」
《解字》
会意兼形声。里リは、すじめのついた田畑。裏は「衣+音符里」で、もと、たてよこのすじめの模様(しま模様)の布地。しま模様の布地は、衣服のうら地に用いた。▽裹カは、別字。
《単語家族》
理リ(玉のすじめ) 吏リ(物事のすじめをつける人)
吏リ(物事のすじめをつける人) 鯉リ(すじもようのついた魚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鯉リ(すじもようのついた魚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 13画 衣部 [六年]
区点=4602 16進=4E22 シフトJIS=97A0
【裡】異体字異体字
13画 衣部 [六年]
区点=4602 16進=4E22 シフトJIS=97A0
【裡】異体字異体字
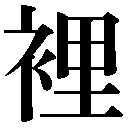 12画 衣部
区点=4603 16進=4E23 シフトJIS=97A1
《常用音訓》リ/うら
《音読み》 リ
12画 衣部
区点=4603 16進=4E23 シフトJIS=97A1
《常用音訓》リ/うら
《音読み》 リ
 〈l
〈l 〉
《訓読み》 うら/うち
《名付け》 うら
《意味》
〉
《訓読み》 うら/うち
《名付け》 うら
《意味》
 {名}うら。すじもようのついた、衣のうら地。転じて、衣服のうら地。また、物の表面の反対側。うらがわ。〈対語〉→表。「表裏」「緑衣黄裏コウリ(緑の表地、黄色のうら地)」〔→詩経〕
{名}うら。すじもようのついた、衣のうら地。転じて、衣服のうら地。また、物の表面の反対側。うらがわ。〈対語〉→表。「表裏」「緑衣黄裏コウリ(緑の表地、黄色のうら地)」〔→詩経〕
 {名}うち。物のうちがわ。ふところ。〈対語〉→表・→外。〈類義語〉→内。「内裏ダイリ(宮中)」「心裏(心のなか)」
{名}うち。物のうちがわ。ふところ。〈対語〉→表・→外。〈類義語〉→内。「内裏ダイリ(宮中)」「心裏(心のなか)」
 {助}〔俗〕場所をあらわす接尾辞。「家裏チアリイ(いえ)」「那裏ナアリイ(そこ)」
〔国〕
{助}〔俗〕場所をあらわす接尾辞。「家裏チアリイ(いえ)」「那裏ナアリイ(そこ)」
〔国〕 うら。物事の表面にあらわれないこと。また、そのようなもの。「裏話」「裏方ウラカタ」
うら。物事の表面にあらわれないこと。また、そのようなもの。「裏話」「裏方ウラカタ」 …のうちに。「暗暗裏アンアンリ」「盛会裏」
《解字》
会意兼形声。里リは、すじめのついた田畑。裏は「衣+音符里」で、もと、たてよこのすじめの模様(しま模様)の布地。しま模様の布地は、衣服のうら地に用いた。▽裹カは、別字。
《単語家族》
理リ(玉のすじめ)
…のうちに。「暗暗裏アンアンリ」「盛会裏」
《解字》
会意兼形声。里リは、すじめのついた田畑。裏は「衣+音符里」で、もと、たてよこのすじめの模様(しま模様)の布地。しま模様の布地は、衣服のうら地に用いた。▽裹カは、別字。
《単語家族》
理リ(玉のすじめ) 吏リ(物事のすじめをつける人)
吏リ(物事のすじめをつける人) 鯉リ(すじもようのついた魚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
鯉リ(すじもようのついた魚)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源に「うち」で完全一致するの検索結果 1-5。