複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (4)
じゅん‐さい【蓴菜】🔗⭐🔉
じゅん‐さい【蓴菜】
スイレン科の多年生水草。日本各地の池沼に自生し、中部以北に多い。地下茎は泥中を伸び、節ごとに根を下ろす。葉は楕円状楯形、長い葉柄で水面に浮かぶ。茎と葉の背面には寒天様の粘液を分泌し、新葉には殊に多い。夏、水面に紫紅色の花を開き、のち卵形の果実を結ぶ。若芽・若葉は食用として珍重。古名、ぬなわ(蓴)。〈[季]夏〉。〈伊呂波字類抄〉
じゅんさい


ぬ‐なわ【沼縄・蓴】‥ナハ🔗⭐🔉
ぬ‐なわ【沼縄・蓴】‥ナハ
〔植〕ジュンサイの別名。〈[季]夏〉。万葉集7「あが心ゆたにたゆたにうき―」
⇒ぬなわ‐くり【蓴繰】
⇒沼縄生う
○沼縄生うぬなわおう
春になってヌナワの根茎から新しい芽が生える。〈[季]春〉
⇒ぬ‐なわ【沼縄・蓴】
ぬなわ‐くり【蓴繰】‥ナハ‥🔗⭐🔉
ぬなわ‐くり【蓴繰】‥ナハ‥
(→)「ぬなわ」に同じ。古事記中「―延へけく知らに」
⇒ぬ‐なわ【沼縄・蓴】
[漢]蓴🔗⭐🔉
蓴 字形
 〔艹部11画/14画/7283・6873〕
〔音〕ジュン(呉)
〔訓〕ぬなわ
[意味]
水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」
▷[
〔艹部11画/14画/7283・6873〕
〔音〕ジュン(呉)
〔訓〕ぬなわ
[意味]
水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」
▷[ ]は異体字。
]は異体字。
 〔艹部11画/14画/7283・6873〕
〔音〕ジュン(呉)
〔訓〕ぬなわ
[意味]
水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」
▷[
〔艹部11画/14画/7283・6873〕
〔音〕ジュン(呉)
〔訓〕ぬなわ
[意味]
水草の名。ぬなわ。「蓴菜・蓴羹鱸膾じゅんこうろかい」
▷[ ]は異体字。
]は異体字。
大辞林の検索結果 (3)
じゅん-さい【蓴菜】🔗⭐🔉
じゅん-さい [0] 【蓴菜】
(1)スイレン科の多年生水草。池沼に自生。茎は泥中の根茎から長く伸び,楕円形の葉を互生。夏,水上に花柄を出して暗紅紫色の花を開く。茎・葉にぬめりがあり,若い芽・葉を食用にする。蓴。古名ヌナワ。[季]夏。
(2)〔ぬめりをもつことから,それにたとえていう。近世上方語〕
ぬらりくらりと,どっちつかずであること。「こなさんがた―とはなぜに言ふえ。はておまへ追従ばかり言ふて,あちらでもこちらでもぬらりぬらりといふ心じやわいのう/浮世草子・旦那気質」
蓴菜(1)
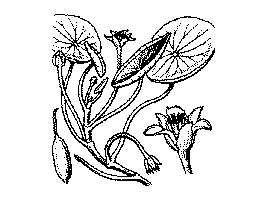 [図]
[図]
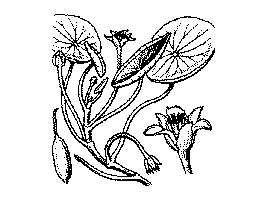 [図]
[図]
ぬ-なわ【沼縄・蓴】🔗⭐🔉
ぬ-なわ ―ナハ [0] 【沼縄・蓴】
蓴菜(ジユンサイ)の別名。[季]夏。《―とる小舟にうたはなかりけり/蕪村》
じゅんさい【蓴菜】(和英)🔗⭐🔉
じゅんさい【蓴菜】
《植》a water shield.
広辞苑+大辞林に「蓴」で始まるの検索結果。