複数辞典一括検索+![]()
![]()
い-たけ  ― 【居丈】🔗⭐🔉
― 【居丈】🔗⭐🔉
い-たけ  ― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
 ― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
― 【居丈】
〔「いだけ」とも〕
座っている時の背の高さ。「御髪は―にて,いとけ高う清らなり/宇津保(国譲下)」
いたけ-だか  ― [0][3] 【居丈高】 (形動)[文]ナリ🔗⭐🔉
― [0][3] 【居丈高】 (形動)[文]ナリ🔗⭐🔉
いたけ-だか  ― [0][3] 【居丈高】 (形動)[文]ナリ
〔「いだけだか」とも〕
(1)(「威丈高」とも書く)人を威圧するような態度をとるさま。「―にものを言う」
(2)座った時の背が高いこと。「―に髪少なにて倚子のおましにのぼり給はんは/栄花(根合)」
(3)座ったまま体を反らせて,相手を威圧しようとするさま。「―になりて申しける/義経記 3」
― [0][3] 【居丈高】 (形動)[文]ナリ
〔「いだけだか」とも〕
(1)(「威丈高」とも書く)人を威圧するような態度をとるさま。「―にものを言う」
(2)座った時の背が高いこと。「―に髪少なにて倚子のおましにのぼり給はんは/栄花(根合)」
(3)座ったまま体を反らせて,相手を威圧しようとするさま。「―になりて申しける/義経記 3」
 ― [0][3] 【居丈高】 (形動)[文]ナリ
〔「いだけだか」とも〕
(1)(「威丈高」とも書く)人を威圧するような態度をとるさま。「―にものを言う」
(2)座った時の背が高いこと。「―に髪少なにて倚子のおましにのぼり給はんは/栄花(根合)」
(3)座ったまま体を反らせて,相手を威圧しようとするさま。「―になりて申しける/義経記 3」
― [0][3] 【居丈高】 (形動)[文]ナリ
〔「いだけだか」とも〕
(1)(「威丈高」とも書く)人を威圧するような態度をとるさま。「―にものを言う」
(2)座った時の背が高いこと。「―に髪少なにて倚子のおましにのぼり給はんは/栄花(根合)」
(3)座ったまま体を反らせて,相手を威圧しようとするさま。「―になりて申しける/義経記 3」
いたける-の-みこと 【五十猛命】🔗⭐🔉
いたける-の-みこと 【五十猛命】
日本書紀の神話の神。素戔嗚尊(スサノオノミコト)の子。新羅(シラギ)から樹種を持ち帰り,大八洲(オオヤシマ)国全土に植えた。
いたこ [0]🔗⭐🔉
いたこ [0]
(主に東北地方で)
(1)霊界と人間との間にたって神おろしや死霊の口寄せをする巫女(ミコ)。家々を回っておしら様の祭りなども行う。盲目の女性が多く,幼少のうちから修行する。みこ。いちこ。口寄せ。青森県恐山(オソレザン)の地蔵講に集まる者がよく知られる。
(2)旅芸人の一種。三味線を弾いて門付(カドヅケ)をする盲目の女性。ごぜ。
いたこ 【潮来】🔗⭐🔉
いたこ 【潮来】
茨城県行方(ナメガタ)郡の町。霞ヶ浦と北浦とを結ぶ北利根川に面した水郷地帯の中心地。
いたこ-ぶし 【潮来節】🔗⭐🔉
いたこ-ぶし 【潮来節】
俗謡。潮来の船唄に由来。江戸の花柳界から各地に広まり,盆踊り唄・お座敷唄・仕事唄などとして唄われた。
いた-ご [0] 【板子】🔗⭐🔉
いた-ご [0] 【板子】
(1)和船の底に敷く揚げ板。
(2)江戸時代の材種の一。主にヒノキ・スギ・ケヤキなどの,厚く挽(ヒ)いた板。挽き割って天井板や建具材料とする。
――一枚下は地獄🔗⭐🔉
――一枚下は地獄
船乗りの仕事は危険が多いことをいう。
いた-ごし [2] 【板輿】🔗⭐🔉
いた-ごし [2] 【板輿】
屋形を板で張り,一方または二方に簾(スダレ)をかけた軽装の輿。木輿。室町時代には上皇・摂関・僧侶が遠出に用いた。はんよ。
板輿
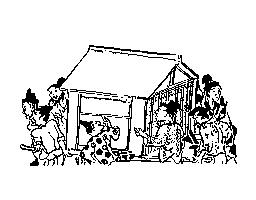 [図]
[図]
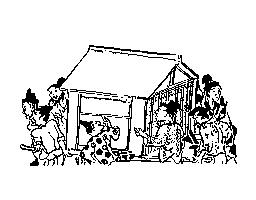 [図]
[図]
大辞林 ページ 138745。