複数辞典一括検索+![]()
![]()
うた-びくに [3] 【歌比丘尼】🔗⭐🔉
うた-びくに [3] 【歌比丘尼】
歌念仏やはやり歌などを歌い,施し物を求めた尼。のちには売春する者も現れた。
歌比丘尼
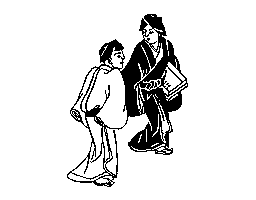 [図]
[図]
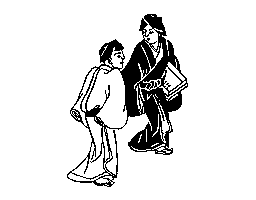 [図]
[図]
うた-ひこう ―ヒカウ [3][4] 【歌披講】🔗⭐🔉
うた-ひこう ―ヒカウ [3][4] 【歌披講】
歌会で,一定の形式に従って節づけして披露すること。二条流・冷泉(レイゼイ)流がある。新年の歌御会始めなどに残る。
うた-びと [0][2] 【歌人】🔗⭐🔉
うた-びと [0][2] 【歌人】
(1)和歌を詠む人。うたよみ。かじん。
(2)詩人。
(3)雅楽寮に属し,舞楽のとき,歌をうたうことにあたった者。
(4)歌をうたうのが巧みな人。うたいて。「明らけくわが知ることを―と我(ワ)を召すらめや/万葉 3886」
うた-ひめ [2][0] 【歌姫】🔗⭐🔉
うた-ひめ [2][0] 【歌姫】
女性歌手。女流声楽家。
うた-ぶえ [3] 【歌笛】🔗⭐🔉
うた-ぶえ [3] 【歌笛】
古く東遊(アズマアソ)びに用いた横笛。高麗笛(コマブエ)に似てやや大形。のちには高麗笛で代用することが一般化して,用いられなくなった。中管。
うた-ぶくろ [3] 【歌袋】🔗⭐🔉
うた-ぶくろ [3] 【歌袋】
(1)和歌の草稿を入れておく袋。檀紙(ダンシ)・錦(ニシキ)・綾(アヤ)などで作り,水引を通し座敷の柱にかけて飾りにする。
(2)カエルののどにある器官で,鳴くときにふくらませる。鳴嚢(メイノウ)。
うたぶくろ 【歌袋】🔗⭐🔉
うたぶくろ 【歌袋】
歌論書。六巻。富士谷御杖(ミツエ)著。1793年刊。歌論のほか,勅撰集の作者索引,および作例などを収める。父成章(ナリアキラ)の見解の祖述もうかがえ,富士谷派の歌論としてのまとまりを示す。
うた-まい ―マヒ [2] 【歌舞】🔗⭐🔉
うた-まい ―マヒ [2] 【歌舞】
歌うことと舞うこと。歌い舞うこと。「種々(クサグサ)の―を奏(オコ)す/日本書紀(天武下訓)」
うたまい-どころ ―マヒ― 【歌舞所】🔗⭐🔉
うたまい-どころ ―マヒ― 【歌舞所】
歌舞をつかさどる役所。雅楽寮と同じか。「―の諸王臣子等/万葉(一〇一一詞)」
うたまい-の-つかさ ―マヒ― 【楽官】🔗⭐🔉
うたまい-の-つかさ ―マヒ― 【楽官】
(1)古代,朝廷で歌舞のことをつかさどる官司の総称。また,それに属する人。「―うたまひつかうまつる/日本書紀(持統訓)」
(2)「雅楽寮(ガガクリヨウ)」に同じ。
大辞林 ページ 139350。