複数辞典一括検索+![]()
![]()
え-ほん  ― [0] 【会本】🔗⭐🔉
― [0] 【会本】🔗⭐🔉
え-ほん  ― [0] 【会本】
〔仏〕 元本とは独立して流布している注釈書を,元本の本文に相当する各部分に配置して合本としたもの。
― [0] 【会本】
〔仏〕 元本とは独立して流布している注釈書を,元本の本文に相当する各部分に配置して合本としたもの。
 ― [0] 【会本】
〔仏〕 元本とは独立して流布している注釈書を,元本の本文に相当する各部分に配置して合本としたもの。
― [0] 【会本】
〔仏〕 元本とは独立して流布している注釈書を,元本の本文に相当する各部分に配置して合本としたもの。
え-ほん  ― [2] 【絵本】🔗⭐🔉
― [2] 【絵本】🔗⭐🔉
え-ほん  ― [2] 【絵本】
(1)絵を中心にして簡単な文をつけた本。主として子供向けの本をいう。
(2)絵の手本。「本朝名木の松の―を集めらる/浄瑠璃・反魂香」
(3)江戸時代,絵を主とした読み物。「此間三馬が作で,早がはり胸のからくりといふおかしい―が出たがの/滑稽本・浮世風呂 2」
― [2] 【絵本】
(1)絵を中心にして簡単な文をつけた本。主として子供向けの本をいう。
(2)絵の手本。「本朝名木の松の―を集めらる/浄瑠璃・反魂香」
(3)江戸時代,絵を主とした読み物。「此間三馬が作で,早がはり胸のからくりといふおかしい―が出たがの/滑稽本・浮世風呂 2」
 ― [2] 【絵本】
(1)絵を中心にして簡単な文をつけた本。主として子供向けの本をいう。
(2)絵の手本。「本朝名木の松の―を集めらる/浄瑠璃・反魂香」
(3)江戸時代,絵を主とした読み物。「此間三馬が作で,早がはり胸のからくりといふおかしい―が出たがの/滑稽本・浮世風呂 2」
― [2] 【絵本】
(1)絵を中心にして簡単な文をつけた本。主として子供向けの本をいう。
(2)絵の手本。「本朝名木の松の―を集めらる/浄瑠璃・反魂香」
(3)江戸時代,絵を主とした読み物。「此間三馬が作で,早がはり胸のからくりといふおかしい―が出たがの/滑稽本・浮世風呂 2」
えほん-ばんづけ  ― [4] 【絵本番付】🔗⭐🔉
― [4] 【絵本番付】🔗⭐🔉
えほん-ばんづけ  ― [4] 【絵本番付】
芝居番付の一。狂言の一幕一幕を絵で表し,傍らに役名と俳優名を記した小冊子で,表紙にはその脚本の外題(ゲダイ)を,裏表紙にその作者名を記した。芝居絵本。芝居絵草紙。絵番付。絵草紙番付。
― [4] 【絵本番付】
芝居番付の一。狂言の一幕一幕を絵で表し,傍らに役名と俳優名を記した小冊子で,表紙にはその脚本の外題(ゲダイ)を,裏表紙にその作者名を記した。芝居絵本。芝居絵草紙。絵番付。絵草紙番付。
 ― [4] 【絵本番付】
芝居番付の一。狂言の一幕一幕を絵で表し,傍らに役名と俳優名を記した小冊子で,表紙にはその脚本の外題(ゲダイ)を,裏表紙にその作者名を記した。芝居絵本。芝居絵草紙。絵番付。絵草紙番付。
― [4] 【絵本番付】
芝居番付の一。狂言の一幕一幕を絵で表し,傍らに役名と俳優名を記した小冊子で,表紙にはその脚本の外題(ゲダイ)を,裏表紙にその作者名を記した。芝居絵本。芝居絵草紙。絵番付。絵草紙番付。
えほんたいこうき  ホン― 【絵本太功記】🔗⭐🔉
ホン― 【絵本太功記】🔗⭐🔉
えほんたいこうき  ホン― 【絵本太功記】
人形浄瑠璃。時代物。近松柳・近松湖水軒・近松千葉軒の合作。1799年初演。一三段。「絵本太閤記」により,明智光秀の謀反から滅亡までの一三日間を一日一段に構成。一〇段目「尼ヶ崎(アマガサキ)の段」(通称「太十(タイジユウ)」)は有名。
ホン― 【絵本太功記】
人形浄瑠璃。時代物。近松柳・近松湖水軒・近松千葉軒の合作。1799年初演。一三段。「絵本太閤記」により,明智光秀の謀反から滅亡までの一三日間を一日一段に構成。一〇段目「尼ヶ崎(アマガサキ)の段」(通称「太十(タイジユウ)」)は有名。
 ホン― 【絵本太功記】
人形浄瑠璃。時代物。近松柳・近松湖水軒・近松千葉軒の合作。1799年初演。一三段。「絵本太閤記」により,明智光秀の謀反から滅亡までの一三日間を一日一段に構成。一〇段目「尼ヶ崎(アマガサキ)の段」(通称「太十(タイジユウ)」)は有名。
ホン― 【絵本太功記】
人形浄瑠璃。時代物。近松柳・近松湖水軒・近松千葉軒の合作。1799年初演。一三段。「絵本太閤記」により,明智光秀の謀反から滅亡までの一三日間を一日一段に構成。一〇段目「尼ヶ崎(アマガサキ)の段」(通称「太十(タイジユウ)」)は有名。
えほんたいこうき  ホンタイカフキ 【絵本太閤記】🔗⭐🔉
ホンタイカフキ 【絵本太閤記】🔗⭐🔉
えほんたいこうき  ホンタイカフキ 【絵本太閤記】
読本(ヨミホン)。七編八四冊。武内確斎作,岡田玉山画。1797〜1802年刊。「織豊二記」に基づいて脚色した豊臣秀吉の一代記。
ホンタイカフキ 【絵本太閤記】
読本(ヨミホン)。七編八四冊。武内確斎作,岡田玉山画。1797〜1802年刊。「織豊二記」に基づいて脚色した豊臣秀吉の一代記。
 ホンタイカフキ 【絵本太閤記】
読本(ヨミホン)。七編八四冊。武内確斎作,岡田玉山画。1797〜1802年刊。「織豊二記」に基づいて脚色した豊臣秀吉の一代記。
ホンタイカフキ 【絵本太閤記】
読本(ヨミホン)。七編八四冊。武内確斎作,岡田玉山画。1797〜1802年刊。「織豊二記」に基づいて脚色した豊臣秀吉の一代記。
え-ま  ― [1] 【絵馬】🔗⭐🔉
― [1] 【絵馬】🔗⭐🔉
え-ま  ― [1] 【絵馬】
(1)祈願または報謝のため社寺に奉納する絵入りの額や板絵。生きた馬を奉納する代用として馬の絵が描かれたものが多い。上部が屋根形になっており,額絵馬・小絵馬などの種類がある。
(2)能の一。脇能(ワキノウ)物。伊勢神宮で節分の夜,白・黒の絵馬を斎宮の扉に掛けて農作を占うことに,天の岩屋戸の神話を結びつけたもの。喜多流では「えんま」と呼ぶ。
絵馬(1)
― [1] 【絵馬】
(1)祈願または報謝のため社寺に奉納する絵入りの額や板絵。生きた馬を奉納する代用として馬の絵が描かれたものが多い。上部が屋根形になっており,額絵馬・小絵馬などの種類がある。
(2)能の一。脇能(ワキノウ)物。伊勢神宮で節分の夜,白・黒の絵馬を斎宮の扉に掛けて農作を占うことに,天の岩屋戸の神話を結びつけたもの。喜多流では「えんま」と呼ぶ。
絵馬(1)
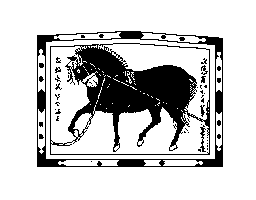 [図]
[図]
 ― [1] 【絵馬】
(1)祈願または報謝のため社寺に奉納する絵入りの額や板絵。生きた馬を奉納する代用として馬の絵が描かれたものが多い。上部が屋根形になっており,額絵馬・小絵馬などの種類がある。
(2)能の一。脇能(ワキノウ)物。伊勢神宮で節分の夜,白・黒の絵馬を斎宮の扉に掛けて農作を占うことに,天の岩屋戸の神話を結びつけたもの。喜多流では「えんま」と呼ぶ。
絵馬(1)
― [1] 【絵馬】
(1)祈願または報謝のため社寺に奉納する絵入りの額や板絵。生きた馬を奉納する代用として馬の絵が描かれたものが多い。上部が屋根形になっており,額絵馬・小絵馬などの種類がある。
(2)能の一。脇能(ワキノウ)物。伊勢神宮で節分の夜,白・黒の絵馬を斎宮の扉に掛けて農作を占うことに,天の岩屋戸の神話を結びつけたもの。喜多流では「えんま」と呼ぶ。
絵馬(1)
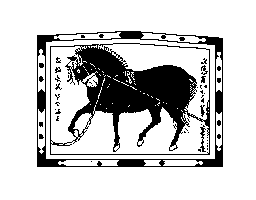 [図]
[図]
えま 【江馬】🔗⭐🔉
えま 【江馬】
姓氏の一。
えま-こしろう ―コシラウ 【江馬小四郎】🔗⭐🔉
えま-こしろう ―コシラウ 【江馬小四郎】
北条義時(ホウジヨウヨシトキ)の通称。
大辞林 ページ 139775。