複数辞典一括検索+![]()
![]()
けい-は 【慶派】🔗⭐🔉
けい-は 【慶派】
仏師の系統の一。平安末期に始まる。運慶・快慶など慶の字を用い,鎌倉時代には院派(インパ)・円派を圧して勢い盛んであった。七条仏所を形成し,江戸時代に至る。
→院派
けい-ば [0] 【競馬】🔗⭐🔉
けい-ば [0] 【競馬】
(1)競走馬に一定の距離を走らせ順位を競う競技。また,その勝馬や着順などを当てる賭け。競馬法による競馬では,前もって馬券(勝馬投票券)を発売し,的中した者には配当金が支払われる。「―場」
(2)「競馬香」に同じ。「千本の蘭鉢・―の香箱/評判記・難波の顔」
(3)「競(クラ)べ馬(ウマ)」に同じ。[季]夏。
けいば-ぐみ 【競馬組】🔗⭐🔉
けいば-ぐみ 【競馬組】
平安時代,賀茂の祭などの競馬に出場した組の人。
けいば-こう ―カウ [0] 【競馬香】🔗⭐🔉
けいば-こう ―カウ [0] 【競馬香】
組香の一。賀茂の競(クラ)べ馬を題材にした盤物。二方に分かれ,四種の香木一〇 (チユウ)を
(チユウ)を (タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一
(タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一 開きで聞く。
競馬香
開きで聞く。
競馬香
 [図]
[図]
 (チユウ)を
(チユウ)を (タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一
(タ)き,聞き当てた人の数に従って盤上の人形を進ませる。人形が早く決勝点を通過した方を勝ちとする。一 開きで聞く。
競馬香
開きで聞く。
競馬香
 [図]
[図]
けいば-ほう ―ハフ 【競馬法】🔗⭐🔉
けいば-ほう ―ハフ 【競馬法】
国営の中央競馬および地方公共団体の行う地方競馬(公営競馬)について,その運営や投票方法などについて規定する法律。1948年(昭和23)制定。
げい-は [1] 【鯨波・鯢波】🔗⭐🔉
げい-は [1] 【鯨波・鯢波】
(1)大波。鯨浪。
(2)戦場であげる,ときの声。「敵の軍勢が戦を挑む―の第一声であつたのだ/思出の記(蘆花)」
ケイパー [1]  caper
caper 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ケイパー [1]  caper
caper フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。
ケイパー
フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。
ケイパー
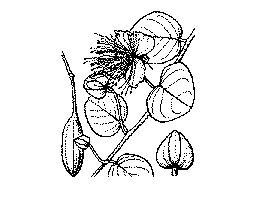 [図]
[図]
 caper
caper フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。
ケイパー
フウチョウソウ科の落葉低木。南ヨーロッパ原産。高さ1メートルほどで,春から夏に,多数の紫色の雄しべをもつ白い花が咲く。つぼみはピクルスにすると独特の風味があり,香料などに用いられる。ケッパー。
ケイパー
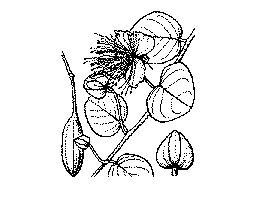 [図]
[図]
大辞林 ページ 143304。