複数辞典一括検索+![]()
![]()
げき-ぶん [0] 【檄文】🔗⭐🔉
げき-ぶん [0] 【檄文】
檄を書いた文章。檄。
げき-ぶんがく [3] 【劇文学】🔗⭐🔉
げき-ぶんがく [3] 【劇文学】
戯曲の形式によって書かれた文学。また,戯曲を文学として着目した場合の称。
げき-へん [0] 【激変・劇変】 (名)スル🔗⭐🔉
げき-へん [0] 【激変・劇変】 (名)スル
急激に変化すること。普通,悪くなる場合に用いる。「天候が―する」
げき-む [1] 【激務・劇務】🔗⭐🔉
げき-む [1] 【激務・劇務】
非常に忙しいつとめ。激しい仕事。「―に倒れる」「―に耐える」
げき-めつ [0] 【撃滅】 (名)スル🔗⭐🔉
げき-めつ [0] 【撃滅】 (名)スル
攻撃して滅ぼすこと。「唯一戦に之を―せんものと/此一戦(広徳)」
げき-やく [0] 【劇薬】🔗⭐🔉
げき-やく [0] 【劇薬】
激しい薬理作用をもち,使用量をあやまると生命にかかわる薬物。厚生大臣により指定される。
→毒薬
げ-ぎょ 【下御】🔗⭐🔉
げ-ぎょ 【下御】
天皇や三后が乗り物から降りることを敬っていう語。「常のごとく―なりて/建武年中行事」
げ-ぎょ [1] 【懸魚】🔗⭐🔉
げ-ぎょ [1] 【懸魚】
屋根の破風に取りつけて,棟木(ムナギ)や桁(ケタ)の木口を隠す装飾。破風の拝み(=合掌の合わせ目)の部分にあるものを本(オモ)懸魚,左右の下部のものを降(クダリ)懸魚または桁隠し懸魚という。また,その形によって猪目(イノメ)懸魚・蕪(カブラ)懸魚・梅鉢懸魚などがある。
懸魚
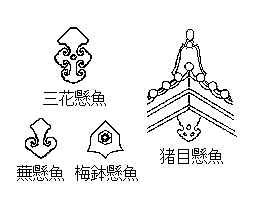 [図]
[図]
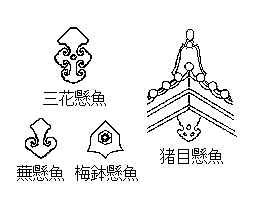 [図]
[図]
け-きょう ―ケウ [0] 【化教】🔗⭐🔉
け-きょう ―ケウ [0] 【化教】
律宗で,衆生(シユジヨウ)をその精神的素質に応じて教化する教え。制教の説く戒律に対し,定(ジヨウ)と慧(エ)をいう。
⇔制教
け-ぎょう ―ギヤウ [0] 【加行】🔗⭐🔉
け-ぎょう ―ギヤウ [0] 【加行】
〔仏〕 中心的な修行の準備段階として行われる修行。多くは密教で灌頂(カンジヨウ)などの前段階の修行を言う。
→四度加行
げ-きょう ―ケウ [0][1] 【外教】🔗⭐🔉
げ-きょう ―ケウ [0][1] 【外教】
仏教で,仏教以外の教え。
⇔内教
げ-ぎょう ―ギヤウ [0] 【夏行】🔗⭐🔉
げ-ぎょう ―ギヤウ [0] 【夏行】
「夏安居(ゲアンゴ)」に同じ。[季]夏。《一貫目うつし身減りし―かな/青木月斗》
大辞林 ページ 143349。