複数辞典一括検索+![]()
![]()
さい-ちょう ―テウ [0] 【犀鳥】🔗⭐🔉
さい-ちょう ―テウ [0] 【犀鳥】
ブッポウソウ目サイチョウ科の鳥の総称。種により,カラス大から全長1.5メートルに及ぶ。長大なくちばしの上に大きな板状突起がある。森林にすみ,果実を主食にする。アフリカ・熱帯アジアに分布。
犀鳥
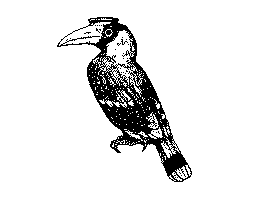 [図]
[図]
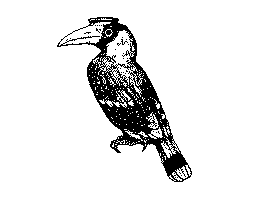 [図]
[図]
さいちょう 【最澄】🔗⭐🔉
さいちょう 【最澄】
(767-822) 日本天台宗の開祖。姓は三津首(ミツノオビト)。近江の人。比叡山に入り法華一乗思想に傾倒し,根本中堂を創建。804年入唐,翌年帰国し,天台宗を開創。「山家学生式(サンゲガクシヨウシキ)」をつくって大乗戒壇設立を請願したが,南都の反対にあい,死後七日目に勅許がおりた。日本最初の大師号伝教大師を勅諡(チヨクシ)される。書状「久隔帖(キユウカクジヨウ)」は名筆として知られる。著「顕戒論」「守護国界章」など。叡山大師。山家大師。根本大師。
ざい-ちょう ―チヤウ [0] 【在庁】 (名)スル🔗⭐🔉
ざい-ちょう ―チヤウ [0] 【在庁】 (名)スル
(1)「庁」と名のつく役所に在職していること。また,出勤して官庁にいること。
(2)「在庁官人」の略。「師光は阿波国の―/平家 1」
ざいちょう-かんにん ―チヤウクワン― 【在庁官人】🔗⭐🔉
ざいちょう-かんにん ―チヤウクワン― 【在庁官人】
平安中期以降,国衙(コクガ)にあって実務に携わった下級役人。多くは土着の豪族で,その職を世襲した。のち武士化して,鎌倉幕府の御家人に組み入れられていった。在庁。在庁人。ざいちょうかんじん。
ざい-ちょう ―テウ [0] 【在朝】🔗⭐🔉
ざい-ちょう ―テウ [0] 【在朝】
朝廷に仕えていること。官途についていること。
⇔在野
さいちょう-がた サイチヤウ― [0] 【細長型】🔗⭐🔉
さいちょう-がた サイチヤウ― [0] 【細長型】
クレッチマーの分類による体型の一。身体がやせて細長いタイプで,分裂気質と関連があるとされる。やせ型。
さいちょう-ほたん サイチヤウ― [0][5] 【採長補短】🔗⭐🔉
さいちょう-ほたん サイチヤウ― [0][5] 【採長補短】
人の長所を取り入れ,自分の短所を補うこと。
さい-づか [0] 【采柄】🔗⭐🔉
さい-づか [0] 【采柄】
采配のつかの部分。
――を握・る🔗⭐🔉
――を握・る
指図をする。指揮する。采配を振る。
大辞林 ページ 144758。