複数辞典一括検索+![]()
![]()
てい 【亭】🔗⭐🔉
てい 【亭】
■一■ [1] (名)
(1)あずまや。ちん。
(2)屋敷。住居。「御使に西八条の―に向かふ/平家 3」
(3)家のあるじ。亭主。「主の―,呼びて風呂へ入れ参らす/仮名草子・仁勢物語」
■二■ (接尾)
(1)料亭・寄席などの屋号に添える語。「末広―」
(2)雅人の居室・あずまや・楼などの号に添える語。「観月―」
(3)芸人・文人などの号に添える語。「古今―」「式―三馬」
てい [1] 【貞】🔗⭐🔉
てい [1] 【貞】
(1)節操を守り貫くこと。
(2)女性が操(ミサオ)を守ること。貞節。
てい 【悌】🔗⭐🔉
てい 【悌】
兄や年長者によく従うこと。また,兄弟の仲が良いこと。「兄は―に弟は敬し/仮名草子・浮世物語」
てい [1] 【艇】🔗⭐🔉
てい [1] 【艇】
小舟。はしけ。ボート。「湖に―を浮かべる」
てい [1] 【鼎】🔗⭐🔉
てい [1] 【鼎】
古代中国の煮炊き用の器の一。一般に円形で三足,また長方形で四足,両耳があり,殷周時代の青銅製の祭器が有名。伝説に夏の禹(ウ)王が九鼎をつくり王位継承の宝器としたという。
→かなえ
鼎
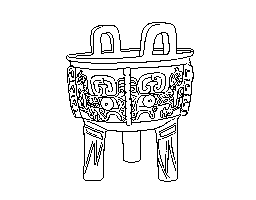 [図]
[図]
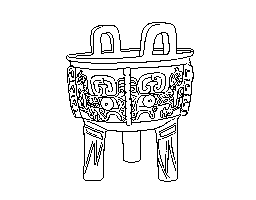 [図]
[図]
てい [1] 【 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
てい [1] 【 】
中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。
】
中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。
 】
中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。
】
中国で,天子が帝(上帝・天帝)をまつる大祭。また,天帝を中心に祖先神を配して執り行う大祭。
てい 【鄭】🔗⭐🔉
てい 【鄭】
中国,春秋時代の諸侯国の一((前806-前375))。周の宣王の弟,桓公友を祖とする姫(キ)姓の国。子産が宰相のとき,国力は充実したが,その死後衰え,戦国時代の初めに韓に滅ぼされた。
てい (副)🔗⭐🔉
てい (副)
硬い物が当たって出る音を表す語。「栗原を通れば―と落つる栗あり/田植草紙」
大辞林 ページ 149887。