複数辞典一括検索+![]()
![]()
○腹も身の内はらもみのうち🔗⭐🔉
○腹も身の内はらもみのうち
腹も身体の一部であるから、暴飲暴食をつつしめという戒め。
⇒はら【腹・肚】
バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】
(浄行と訳す)
①インドの四種姓(ヴァルナ)制中の最高位である僧侶・祭司階級。梵天の裔で、その口から出たものとされ、もっぱら祭祀・教法をつかさどり、他の三姓の尊敬を受けた。ブラーマン。→ヴァルナ。
②バラモン教。また、その僧侶。
⇒バラモン‐きょう【婆羅門教】
⇒バラモン‐じん【婆羅門参】
⇒バラモン‐そうじょう【婆羅門僧正】
バラモン‐きょう【婆羅門教】‥ケウ
(Brahmanism)仏教以前からバラモン1を中心に行われたインドの民族宗教。ヒンドゥー教の前身。ヴェーダ聖典を権威とし、自然神をまつり祭式を重視した。宇宙の本体である梵天を中心とする。また、ヴァルナ制度を思想的に支えた。→ヒンドゥー教。
⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】
バラモン‐じん【婆羅門参】
キク科の越年草。南欧原産の根菜。高さ60〜90センチメートル。ゴボウに似た白色の根がある。7月頃紫色の頭状花を開く。根は食用、花は切花とする。セイヨウゴボウ。ムギナデシコ。
⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】
バラモン‐そうじょう【婆羅門僧正】‥ジヤウ
インドの僧。名は菩提僊那ぼだいせんな。バラモンの出身。文殊菩薩を拝するため中国に渡り、736年(天平8)来日。751年(天平勝宝3)僧正となり、行基の推挙で翌年の東大寺大仏開眼供養の導師となる。菩提仙那。(704〜760)
⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】
はら‐や【軽粉・水銀粉】
塩化第一水銀の白色粉末。伊勢で産出。駆虫剤などに用い、また伊勢白粉おしろいとして販売。〈日葡辞書〉
ばら‐ゆ【薔薇油】
バラの花を水蒸気蒸留して得られる芳香油。400万個の花を使用して1キログラムを得るという。高価な天然香料の一つ。しょうびゆ。
はら‐ようゆうさい【原羊遊斎】‥ヤウイウ‥
江戸後期の蒔絵師。通称、久米次郎。別号、更山。江戸神田に住み、大田南畝をはじめ当時の文化人達と広く交遊。酒井抱一の下絵を用いて制作。(1769〜1845)
⇒はら【原】
はらら
ちりぢりになるさま。ばらばら。万葉集20「あま小舟―に浮きて」
バラライカ【balalaika ロシア】
3弦の撥弦楽器。共鳴胴は三角形で、指先で弾奏。ロシア・ウクライナの民俗音楽に広く使われる。
バラライカ
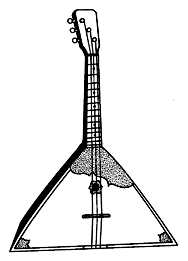 はららか・す【散かす】
〔他四〕
ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」
はらら・く【散く】
〔自四〕
ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉
はらら‐ご【鮞】
魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉
はらら‐じる【はらら汁】
豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。
パララックス【parallax】
〔理〕(→)視差に同じ。
はらり
①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」
②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」
③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」
⇒はらり‐しゃん‐と
ばらり
①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。
②糸や紐の切れるさま。
⇒ばらり‐ずん‐と
ぱらり
①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」
②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」
パラリーガル【paralegal】
弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。
はらり‐しゃん‐と
〔副〕
(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」
⇒はらり
ばらり‐ずん‐と
〔副〕
一刀のもとに斬り落とすさま。
⇒ばらり
パラリンピック【Paralympic】
(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス
ぱら‐ルビ【ぱらルビ】
(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ
ハラレ【Harare】
アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。
パラレル【parallel】
①平行。
②二つの物事が並行するさま。
③〔電〕並列接続。
④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。
⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。
⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】
⇒パラレル‐レース【parallel race】
パラレル‐コンピューター【parallel computer】
複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。
⇒パラレル【parallel】
パラレル‐レース【parallel race】
スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。
⇒パラレル【parallel】
はら‐わた【腸】
①大腸。〈倭名類聚鈔3〉
②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」
③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。
④こころ。性根。
⇒はらわた‐もち【腸餅】
⇒腸が腐る
⇒腸がちぎれる
⇒腸が煮え返る
⇒腸が見え透く
⇒腸に染みる
⇒腸を切る
⇒腸を断つ
はららか・す【散かす】
〔他四〕
ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」
はらら・く【散く】
〔自四〕
ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉
はらら‐ご【鮞】
魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉
はらら‐じる【はらら汁】
豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。
パララックス【parallax】
〔理〕(→)視差に同じ。
はらり
①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」
②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」
③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」
⇒はらり‐しゃん‐と
ばらり
①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。
②糸や紐の切れるさま。
⇒ばらり‐ずん‐と
ぱらり
①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」
②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」
パラリーガル【paralegal】
弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。
はらり‐しゃん‐と
〔副〕
(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」
⇒はらり
ばらり‐ずん‐と
〔副〕
一刀のもとに斬り落とすさま。
⇒ばらり
パラリンピック【Paralympic】
(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス
ぱら‐ルビ【ぱらルビ】
(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ
ハラレ【Harare】
アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。
パラレル【parallel】
①平行。
②二つの物事が並行するさま。
③〔電〕並列接続。
④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。
⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。
⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】
⇒パラレル‐レース【parallel race】
パラレル‐コンピューター【parallel computer】
複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。
⇒パラレル【parallel】
パラレル‐レース【parallel race】
スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。
⇒パラレル【parallel】
はら‐わた【腸】
①大腸。〈倭名類聚鈔3〉
②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」
③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。
④こころ。性根。
⇒はらわた‐もち【腸餅】
⇒腸が腐る
⇒腸がちぎれる
⇒腸が煮え返る
⇒腸が見え透く
⇒腸に染みる
⇒腸を切る
⇒腸を断つ
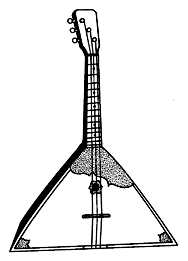 はららか・す【散かす】
〔他四〕
ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」
はらら・く【散く】
〔自四〕
ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉
はらら‐ご【鮞】
魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉
はらら‐じる【はらら汁】
豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。
パララックス【parallax】
〔理〕(→)視差に同じ。
はらり
①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」
②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」
③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」
⇒はらり‐しゃん‐と
ばらり
①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。
②糸や紐の切れるさま。
⇒ばらり‐ずん‐と
ぱらり
①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」
②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」
パラリーガル【paralegal】
弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。
はらり‐しゃん‐と
〔副〕
(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」
⇒はらり
ばらり‐ずん‐と
〔副〕
一刀のもとに斬り落とすさま。
⇒ばらり
パラリンピック【Paralympic】
(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス
ぱら‐ルビ【ぱらルビ】
(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ
ハラレ【Harare】
アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。
パラレル【parallel】
①平行。
②二つの物事が並行するさま。
③〔電〕並列接続。
④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。
⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。
⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】
⇒パラレル‐レース【parallel race】
パラレル‐コンピューター【parallel computer】
複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。
⇒パラレル【parallel】
パラレル‐レース【parallel race】
スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。
⇒パラレル【parallel】
はら‐わた【腸】
①大腸。〈倭名類聚鈔3〉
②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」
③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。
④こころ。性根。
⇒はらわた‐もち【腸餅】
⇒腸が腐る
⇒腸がちぎれる
⇒腸が煮え返る
⇒腸が見え透く
⇒腸に染みる
⇒腸を切る
⇒腸を断つ
はららか・す【散かす】
〔他四〕
ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」
はらら・く【散く】
〔自四〕
ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉
はらら‐ご【鮞】
魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉
はらら‐じる【はらら汁】
豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。
パララックス【parallax】
〔理〕(→)視差に同じ。
はらり
①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」
②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」
③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」
⇒はらり‐しゃん‐と
ばらり
①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。
②糸や紐の切れるさま。
⇒ばらり‐ずん‐と
ぱらり
①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」
②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」
パラリーガル【paralegal】
弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。
はらり‐しゃん‐と
〔副〕
(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」
⇒はらり
ばらり‐ずん‐と
〔副〕
一刀のもとに斬り落とすさま。
⇒ばらり
パラリンピック【Paralympic】
(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス
ぱら‐ルビ【ぱらルビ】
(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ
ハラレ【Harare】
アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。
パラレル【parallel】
①平行。
②二つの物事が並行するさま。
③〔電〕並列接続。
④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。
⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。
⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】
⇒パラレル‐レース【parallel race】
パラレル‐コンピューター【parallel computer】
複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。
⇒パラレル【parallel】
パラレル‐レース【parallel race】
スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。
⇒パラレル【parallel】
はら‐わた【腸】
①大腸。〈倭名類聚鈔3〉
②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」
③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。
④こころ。性根。
⇒はらわた‐もち【腸餅】
⇒腸が腐る
⇒腸がちぎれる
⇒腸が煮え返る
⇒腸が見え透く
⇒腸に染みる
⇒腸を切る
⇒腸を断つ
広辞苑 ページ 16118 での【○腹も身の内】単語。