複数辞典一括検索+![]()
![]()
大凡】🔗⭐🔉
大凡】
おおよそ。あらまし。大略。大概。
たい‐はん【
大半】🔗⭐🔉
大半】
半分以上。過半。大部分。おおかた。「―を占める」「仕事は―片づいた」
たい‐はん【
大藩】🔗⭐🔉
大藩】
①領知の石高の大きい藩。
②1868年(明治1)に、石高で諸藩を3等に分けたものの一つ。草高くさだか40万石以上のもの。70年には改めて物成ものなり15万石以上とした。
たい‐はん【
退帆】🔗⭐🔉
退帆】
(明治期の語)船が帆をあげて帰っていくこと。
たい‐ばん【
胎盤】🔗⭐🔉
胎盤】
哺乳動物が妊娠した時、母体の子宮内壁と胎児との間にあって両者の栄養・呼吸・排泄などの機能を媒介・結合する盤状器官。母体と胎児の血液がこの部で接触し物質交換を行う。胎児とは臍帯さいたいで連絡。胎児の分娩後、胎盤も続いて排出されるが、これを俗に後産あとざん、排出された胎盤を胞衣えなという。
だい‐はん【
台飯】🔗⭐🔉
台飯】
台盤の上にのせてある食物。源平盛衰記7「雀といふ小鳥になりて…―をめしけるこそいとあはれなれ」
だい‐ばん【
代番】🔗⭐🔉
代番】
本人に代わって勤番すること。
だい‐ばん【
台盤】🔗⭐🔉
台盤】
(ダイハンとも)食物を盛った器をのせる台。4脚、横長の机状で、朱または黒の漆塗り、上面は縁が高くなっている。
台盤
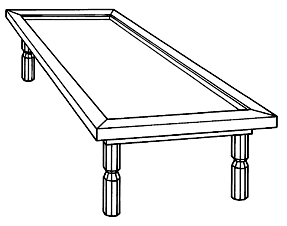 ⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【
⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【
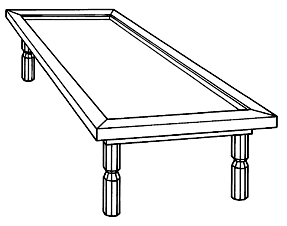 ⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【
⇒だいばん‐どころ【台盤所】
だい‐はんじ【大判事】🔗⭐🔉
大判事】
①律令制の刑部省の上級の判事。
②1869年(明治2)に置いた最上級の判事。
だい‐ばんじゃく【
広辞苑 ページ 11911。