複数辞典一括検索+![]()
![]()
たたら‐づか【栭束】🔗⭐🔉
たたら‐づか【栭束】
〔建〕高欄こうらん1の束柱つかばしらのこと。→斗束とづか
たたら‐はま【多多良浜】🔗⭐🔉
たたら‐はま【多多良浜】
福岡市の北東部、箱崎・香椎間にあった海浜で、蒙古襲来の時の古戦場。また、1336年(建武3)足利尊氏・直義兄弟と菊池武敏とが戦い、1569年(永禄12)毛利・大友両軍が戦った所。
たたら‐ぶき【踏鞴吹き】🔗⭐🔉
たたら‐ぶき【踏鞴吹き】
砂鉄・木炭を原料とし、たたらを用いて行う和鉄製錬法。古代以降中国地方などで行われた。その製錬炉をも鑪たたらと呼ぶ。
⇒たたら【踏鞴・踏韛】
たたら‐ぼし【婁宿】🔗⭐🔉
たたら‐ぼし【婁宿】
〔天〕二十八宿の一つ。牡羊座おひつじざの西部。婁ろう。
たたら‐まつり【踏鞴祭】🔗⭐🔉
たたら‐まつり【踏鞴祭】
(→)鞴祭ふいごまつりに同じ。
⇒たたら【踏鞴・踏韛】
ただら‐め【爛ら目】🔗⭐🔉
ただら‐め【爛ら目】
(→)「ただれめ」に同じ。
○踏鞴を踏むたたらをふむ
①たたらをふんで空気を送る。
②勢い込んで打ちまたは突いた的がはずれたため、力があまって、から足を踏む。
⇒たたら【踏鞴・踏韛】
たたり【祟り】🔗⭐🔉
たたり【祟り】
①たたること。神仏・怨霊などのするわざわい。「あとの―が恐ろしい」
②悪いむくい。
⇒たたり‐め【祟り目】
たたり【絡垜】🔗⭐🔉
たたり【絡垜】
糸のもつれをふせぐため、綛かせを掛ける器具。方形または長方形の台に柱を立てたもの。万葉集12「少女おとめらが績麻うみおの―打麻うちそかけ績うむとき無しに恋ひ渡るかも」
絡垜
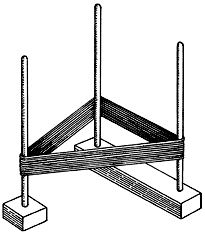
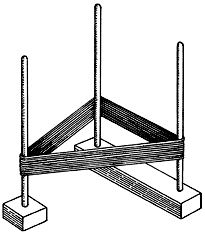
たた‐り【立たり】🔗⭐🔉
たた‐り【立たり】
(「立てり」の上代東国方言)立っている。万葉集20「家人いわびとのわれを見送ると―しもころ」
たたり‐め【祟り目】🔗⭐🔉
たたり‐め【祟り目】
祟りにあう時。災難にあう時。「弱り目に―」
⇒たたり【祟り】
たた・る【祟る】🔗⭐🔉
たた・る【祟る】
〔自五〕
①神仏・怨霊・もののけなどが禍いをする。罰をあたえる。天武紀下「天皇の病を卜うらなふに草薙剣に―・れり」。日葡辞書「カミガタタラルル」
②害をなす。また、したことが悪い結果をもたらす。日葡辞書「コレハフクチュウニタタル」。「飲み過ぎが―・って胃をこわす」「悪天候に―・られて人出が少ない」
広辞苑 ページ 12173。