複数辞典一括検索+![]()
![]()
あか‐まえだれ【赤前垂れ】‥マヘ‥🔗⭐🔉
あか‐まえだれ【赤前垂れ】‥マヘ‥
赤い色の前垂。近世、料理屋・茶屋などの接客の女が用いた。また、それを着用した女。
あかま‐が‐せき【赤間関・赤馬関】🔗⭐🔉
あかま‐が‐せき【赤間関・赤馬関】
下関しものせきの古称。太平記39「門司・―を経て」
⇒あかま【赤間】
あかま‐じんぐう【赤間神宮】🔗⭐🔉
あかま‐じんぐう【赤間神宮】
下関市にある元官幣大社。祭神は安徳天皇。もと阿弥陀寺・赤間宮といった。
⇒あかま【赤間】
あかまた🔗⭐🔉
あかまた
ヘビの一種。全長1〜1.5メートル。無毒。性質はかなり荒く、鼠・鳥・トカゲ・蛇・蛙などを食う。奄美諸島と沖縄諸島にすみ、奄美では「まったぶ」という。
あかまた‐くろまた【赤また黒また】🔗⭐🔉
あかまた‐くろまた【赤また黒また】
沖縄の八重山諸島に残る民俗行事。旧暦6月の豊年祭に、海上の楽土「にらいかない」から訪れる仮面姿の二神を迎える行事。
あか‐まつ【赤松】🔗⭐🔉
あか‐まつ【赤松】
マツ科の常緑高木。樹皮は亀甲状にはげやすく、芽の色と共に赤褐色。山地に多い。クロマツより葉が柔らかい。材は建築用皮付丸太、薪炭用、パルプの原料。雌松めまつ。
アカマツ
撮影:関戸 勇
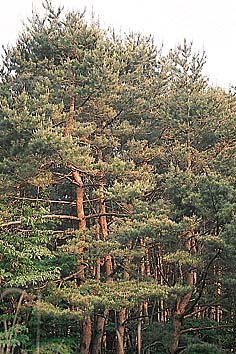
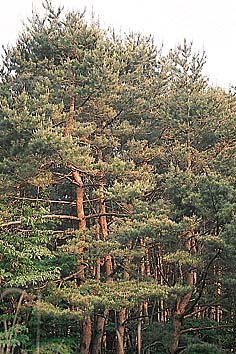
あかまつ【赤松】🔗⭐🔉
あかまつ【赤松】
姓氏の一つ。播磨の豪族。鎌倉時代佐用荘を本拠として興り、南北朝時代以降同国守護。室町幕府四職ししきの一家。
⇒あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
⇒あかまつ‐そくゆう【赤松則祐】
⇒あかまつ‐のりむら【赤松則村】
⇒あかまつ‐みつすけ【赤松満祐】
⇒あかまつ‐よしのり【赤松義則】
あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】🔗⭐🔉
あかまつ‐かつまろ【赤松克麿】
社会運動家。山口県生れ。東大在学中、新人会を結成。日本労働総同盟・日本共産党で活動、のち社会民衆党書記長。満州事変後は国家社会主義に転じ、さらに日本主義を唱え、大政翼賛会などに参加。主著「日本社会運動史」。(1894〜1955)
⇒あかまつ【赤松】
広辞苑 ページ 163。