複数辞典一括検索+![]()
![]()
ふなばら‐そう【船腹草】‥サウ🔗⭐🔉
ふなばら‐そう【船腹草】‥サウ
ガガイモ科の多年草。山野に自生する。高さ約60センチメートル。茎に白毛がある。葉は楕円形。夏、暗紫色の花を数個ずつ開き、船の胴に似た果実をつける。根は漢方生薬の白薇はくびで、解熱・利尿薬。ロクエンソウ。
⇒ふな‐ばら【船腹】
ふな‐ばり【船梁】🔗⭐🔉
ふな‐ばり【船梁】
和船の両舷側間に渡した多くの太い材。横からの水圧を防ぎ支え、船形を維持し、また、船の間仕切とする。〈日葡辞書〉
ふな‐ばんしょ【船番所】🔗⭐🔉
ふな‐ばんしょ【船番所】
(→)番所ばんしょ2に同じ。誹風柳多留11「三味線を握つて通る―」
ふな‐び【船日】🔗⭐🔉
ふな‐び【船日】
①船出するのによい日。浄瑠璃、双生隅田川「今日は三月十五日、上総の浦の―なれど」
②船の着くべき日。
ふな‐ひき【船引き】🔗⭐🔉
ふな‐ひき【船引き】
船を綱で引くこと。また、その人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「網引き―塩焼きあま人」
ふな‐ひじき【舟肘木】‥ヒヂ‥🔗⭐🔉
ふな‐ひじき【舟肘木】‥ヒヂ‥
〔建〕(形が川舟のような感じであるからいう)組物の一形式。柱上に肘木のみをのせて桁けたを支えるもの。
舟肘木
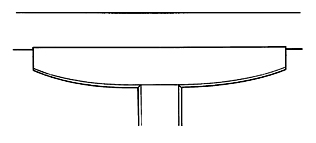
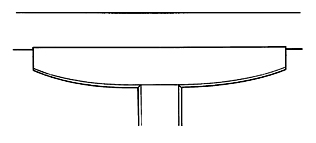
ふな‐びと【船人・舟人】🔗⭐🔉
ふな‐びと【船人・舟人】
①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」
②船客。土佐日記「―のよめる歌」
ふな‐びらき【船開き】🔗⭐🔉
ふな‐びらき【船開き】
船が港から出帆すること。
ふな‐びん【船便】🔗⭐🔉
ふな‐びん【船便】
船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」
ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉
ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ
武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。
フナフティ【Funafuti】🔗⭐🔉
フナフティ【Funafuti】
南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。
ふな‐ふな🔗⭐🔉
ふな‐ふな
ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」
広辞苑 ページ 17329。