複数辞典一括検索+![]()
![]()
斉 字形 筆順🔗⭐🔉
斉 字形
 筆順
筆順
 〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕
[齊] 字形
〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕
[齊] 字形
 〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕
〔音〕セイ(漢) サイ(呉)
〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし
[意味]
①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」
②中国の国名。
㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」
㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。
[解字]
解字
〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕
〔音〕セイ(漢) サイ(呉)
〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし
[意味]
①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」
②中国の国名。
㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」
㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。
[解字]
解字 象形。古字は[
象形。古字は[ ]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。
[下ツキ
一斉・均斉・整斉・不斉
]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。
[下ツキ
一斉・均斉・整斉・不斉
 筆順
筆順
 〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕
[齊] 字形
〔斉(齊)部0画/8画/常用/3238・4046〕
[齊] 字形
 〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕
〔音〕セイ(漢) サイ(呉)
〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし
[意味]
①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」
②中国の国名。
㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」
㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。
[解字]
解字
〔斉(齊)部0画/14画/8378・736E〕
〔音〕セイ(漢) サイ(呉)
〔訓〕ひとしい・ととのえる (名)なり・ただ・とき・ひとし
[意味]
①大小・長短がなくそろっている。ひとしい。均一にそろえる。きちんとととのえる。「斉一・斉唱・斉家・一斉・均斉」
②中国の国名。
㋐周代、春秋戦国時代の諸侯の一つ。今の山東省の地。「斉東野人」
㋑南北朝時代、建康(=今の南京)に都を置いた王朝の名。
[解字]
解字 象形。古字は[
象形。古字は[ ]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。
[下ツキ
一斉・均斉・整斉・不斉
]。穀物の穂がびっしりはえそろっている形。
[下ツキ
一斉・均斉・整斉・不斉
剤 〔斉(齊)部2画〕🔗⭐🔉
剤 〔斉(齊)部2画〕
⇒刀部
斎 字形 筆順🔗⭐🔉
斎 字形
 筆順
筆順
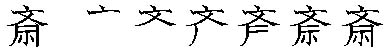 〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕
[齋] 字形
〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕
[齋] 字形
 〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕
〔音〕サイ(漢)
〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし
[意味]
①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」
②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」
③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」
④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。
[解字]
形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[
〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕
〔音〕サイ(漢)
〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし
[意味]
①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」
②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」
③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」
④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。
[解字]
形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[ ]は異体字。
[下ツキ
雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎
]は異体字。
[下ツキ
雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎
 筆順
筆順
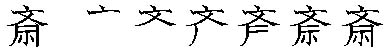 〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕
[齋] 字形
〔斉(齊)部3画/11画/常用/2656・3A58〕
[齋] 字形
 〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕
〔音〕サイ(漢)
〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし
[意味]
①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」
②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」
③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」
④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。
[解字]
形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[
〔斉(齊)部3画/17画/6723・6337〕
〔音〕サイ(漢)
〔訓〕いつく・いむ・とき (名)いつき・ひとし
[意味]
①(神仏をまつる前に)飲食などをつつしんで心身をきよめる。いつく。ものいみ。「斎宮さいぐう・斎場・斎戒・斎日・潔斎」
②ものいみや読書のため心静かにこもる室。「書斎・山斎」
③屋号・雅号・芸名に添える語。「六無斎・一竜斎」
④〔仏〕とき。仏事に僧(または参会者)に供する食事。「斎食さいじき」▶僧は正午以後の食事は非時食ひじじきとして禁じられているが、それに対して、食すべき時(すなわち午前中)にとる食事をいう。
[解字]
形声。「示」(=神をまつる)+音符「齊」(=ととのえる)の省略形。心身をととのえて神に仕える意。[ ]は異体字。
[下ツキ
雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎
]は異体字。
[下ツキ
雲斎・潔斎・定斎・書斎・羅斎
広辞苑 ページ 22778。