複数辞典一括検索+![]()
![]()
ぎり‐ぎり【旋毛】🔗⭐🔉
ぎり‐ぎり【旋毛】
頭部のつむじ。浄瑠璃、心中宵庚申「爪先より―まで打込み」
ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】🔗⭐🔉
ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】
余地のないまでにおしつまること。最後の決着。
⇒ぎり‐ぎり
きりきり‐しゃん‐と🔗⭐🔉
きりきり‐しゃん‐と
〔副〕
きわめてかいがいしく。きりりしゃんと。
⇒きり‐きり
きりぎりす【螽斯・蟋蟀】🔗⭐🔉
きりぎりす【螽斯・蟋蟀】
(鳴き声に基づく語か。スは鳥や虫など飛ぶものにいう語)
①コオロギの古称。古今和歌集雑体「つづりさせてふ―鳴く」
②バッタ目キリギリス科の昆虫。体長約35ミリメートル。畳んだ翅の背面は褐色、側面は褐色斑の多い緑色。盛夏、原野に多い。雄は、「ちょんぎいす」と鳴く。ぎす。ぎっちょ。はたおり。莎さの鶏。〈[季]秋〉
きりぎりす
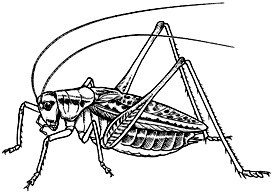 キリギリス
提供:ネイチャー・プロダクション
キリギリス
提供:ネイチャー・プロダクション
 ③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。
③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。
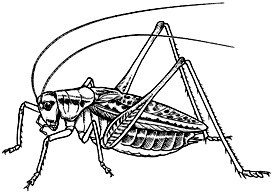 キリギリス
提供:ネイチャー・プロダクション
キリギリス
提供:ネイチャー・プロダクション
 ③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。
③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。
きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ🔗⭐🔉
きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ
①非常な勢いで回ること。せわしく立ち働くさまにいう。「忙しくて―をする」
②相手のはやい動きについて行けず、うろたえて動くさま。「速球に―する」
⇒きり‐きり
広辞苑 ページ 5317。