複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (1)
○学びて思わざれば則ち罔しまなびておもわざればすなわちくらし🔗⭐🔉
○学びて思わざれば則ち罔しまなびておもわざればすなわちくらし
[論語為政]学ぶだけで考えなければ何も分からない。
⇒まな・ぶ【学ぶ】
まなび‐の‐その【学びの園】
学校。がくえん。まなびのにわ。
⇒まなび【学び】
まなび‐の‐にわ【学びの庭】‥ニハ
(→)「まなびのその」に同じ。
⇒まなび【学び】
まなび‐の‐まど【学びの窓】
⇒がくそう(学窓)。
⇒まなび【学び】
まなび‐や【学舎】
学問をするところ。がくしゃ。学校。学窓。まなびのまど。「―を出る」
⇒まなび【学び】
まな・ぶ【学ぶ】
[一]〔他五〕
①まねてする。ならって行う。徒然草「驥を―・ぶは驥のたぐひ、舜を―・ぶは舜の徒なり」
②教えを受ける。業を受ける。習う。源氏物語橋姫「年頃―・び知り給へる事どもの深き心を説き聞かせ奉り」。徒然草「伝へきき、―・びてしるはまことの知にあらず」。天草本平家物語「言葉を―・びがてらに」。「巨匠に油絵を―・ぶ」「この経験から―・んだこと」
③学問をする。「物理学を―・ぶ」→学まねぶ。
[二]〔他上二〕
「まなぶ(五段)」の古活用(漢文訓読体に見られる)。千載和歌集序「此の歌の道を―・ぶる事をいふに、唐国、日本の広きふみの道をも―・びず」。仮名論語「くるしんで―・ぶるは、又そのつぎなり」
⇒学びて思わざれば則ち罔し
ま‐な‐ぶた【瞼】
(「目の蓋ふた」の意)まぶた。万葉集16「婆羅門ばらもんの作れる小田おだを喫はむ烏―腫れて幡幢はたほこに居り」
ま‐な‐ぶち【眼縁】
(「目の縁」の意)(→)「まぶち」に同じ。
まな‐ぶみ【真名文】
漢字の文。漢文。↔仮名文
まなべ【間部】
姓氏の一つ。
⇒まなべ‐あきかつ【間部詮勝】
⇒まなべ‐あきふさ【間部詮房】
まなべ‐あきかつ【間部詮勝】
幕末の幕府老中。越前鯖江藩主。下総守。1858年(安政5)大老井伊直弼の命をうけ、条約調印・将軍継嗣問題で上洛、反幕志士数十人を逮捕した。(1802〜1884)
⇒まなべ【間部】
まなべ‐あきふさ【間部詮房】
江戸幕府6代将軍家宣の側近。越前守。小姓から側用人に累進、権勢をふるった。1710年(宝永7)高崎藩主となり5万石。(1667〜1720)
⇒まなべ【間部】
まな‐ぼん【真名本・真字本】
仮名本に対して、漢字のみで書かれた書物。
ま‐なまこ【真海鼠】
マナマコ目のナマコ。体はほぼ円筒状、背面には多数の小さい角状の突起があり、体長約30センチメートル。背面の暗色斑の色により、同一種をアカコ・アオコ・クロコなどと呼ぶ。九州以北でサハリンまで分布し、浅海底に生息。食用。
まなまこ
 マナマコ
提供:東京動物園協会
マナマコ
提供:東京動物園協会
 まな‐まな
〔副〕
(「まな」の畳語)禁止する語。だめだめ。落窪物語2「君―とそら制止をし給ふ」
まな‐むすめ【愛娘】
(マナは親愛の意を表す接頭語)最愛の娘。宇津保物語藤原君「豊後のすけの―」
まに【摩尼】
〔仏〕
①(梵語maṇi 珠・宝・如意と訳す)宝石。宝玉。濁水を清らかにする不思議な働きがあるとされる。
②如意宝珠。
③(Mani)
⇒マニきょう(摩尼教)
ま‐に【随・任・儘】
〔副〕
(→)「まにまに」に同じ。
マニア【mania】
①熱狂。熱中。夢中。
②一つの事に異常に熱中する人。「切手―」
ま‐に‐あい【間に合い】‥アヒ
①(→)「まにあわせ」に同じ。
②「間に合い紙」の略。
③でまかせ。ごまかし。歌舞伎、お染久松色読販「…ト―を言ふ」
⇒まにあい‐がみ【間に合い紙】
⇒まにあい‐ことば【間に合い言葉】
まにあい‐がみ【間に合い紙】‥アヒ‥
(横幅を長く漉いて半間の間に合うように造った紙の意)古来、兵庫県西宮市名塩と福井県越前市今立の特産。屏風・襖用の鳥の子紙。間似合紙。
間に合い紙
撮影:関戸 勇
まな‐まな
〔副〕
(「まな」の畳語)禁止する語。だめだめ。落窪物語2「君―とそら制止をし給ふ」
まな‐むすめ【愛娘】
(マナは親愛の意を表す接頭語)最愛の娘。宇津保物語藤原君「豊後のすけの―」
まに【摩尼】
〔仏〕
①(梵語maṇi 珠・宝・如意と訳す)宝石。宝玉。濁水を清らかにする不思議な働きがあるとされる。
②如意宝珠。
③(Mani)
⇒マニきょう(摩尼教)
ま‐に【随・任・儘】
〔副〕
(→)「まにまに」に同じ。
マニア【mania】
①熱狂。熱中。夢中。
②一つの事に異常に熱中する人。「切手―」
ま‐に‐あい【間に合い】‥アヒ
①(→)「まにあわせ」に同じ。
②「間に合い紙」の略。
③でまかせ。ごまかし。歌舞伎、お染久松色読販「…ト―を言ふ」
⇒まにあい‐がみ【間に合い紙】
⇒まにあい‐ことば【間に合い言葉】
まにあい‐がみ【間に合い紙】‥アヒ‥
(横幅を長く漉いて半間の間に合うように造った紙の意)古来、兵庫県西宮市名塩と福井県越前市今立の特産。屏風・襖用の鳥の子紙。間似合紙。
間に合い紙
撮影:関戸 勇
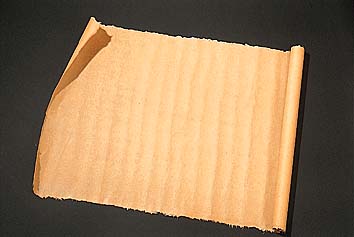 ⇒ま‐に‐あい【間に合い】
まにあい‐ことば【間に合い言葉】‥アヒ‥
口から出まかせの言葉。浄瑠璃、博多小女郎波枕「問ひ詰められて―」
⇒ま‐に‐あい【間に合い】
ま‐に‐あ・う【間に合う】‥アフ
〔自五〕
①その場の役に立つ。用が足りる。「手持ちの品で―・う」「今日は―・っている」
②定めの時刻・期限に遅れない。「終電に―・う」
マニアック【maniac】
一つのことに常軌を逸するほど熱中しているさま。「―な会員が多い」
ま‐に‐あわせ【間に合せ】‥アハセ
急場の用に当てること。一時しのぎ。まにあい。
ま‐に‐あわ・せる【間に合わせる】‥アハセル
〔他下一〕
①とりあえず急場の用に当てる。「借着で―・せる」
②決まった時刻・期限に遅れないようにする。「刊行期日に―・せる」
⇒ま‐に‐あい【間に合い】
まにあい‐ことば【間に合い言葉】‥アヒ‥
口から出まかせの言葉。浄瑠璃、博多小女郎波枕「問ひ詰められて―」
⇒ま‐に‐あい【間に合い】
ま‐に‐あ・う【間に合う】‥アフ
〔自五〕
①その場の役に立つ。用が足りる。「手持ちの品で―・う」「今日は―・っている」
②定めの時刻・期限に遅れない。「終電に―・う」
マニアック【maniac】
一つのことに常軌を逸するほど熱中しているさま。「―な会員が多い」
ま‐に‐あわせ【間に合せ】‥アハセ
急場の用に当てること。一時しのぎ。まにあい。
ま‐に‐あわ・せる【間に合わせる】‥アハセル
〔他下一〕
①とりあえず急場の用に当てる。「借着で―・せる」
②決まった時刻・期限に遅れないようにする。「刊行期日に―・せる」
 マナマコ
提供:東京動物園協会
マナマコ
提供:東京動物園協会
 まな‐まな
〔副〕
(「まな」の畳語)禁止する語。だめだめ。落窪物語2「君―とそら制止をし給ふ」
まな‐むすめ【愛娘】
(マナは親愛の意を表す接頭語)最愛の娘。宇津保物語藤原君「豊後のすけの―」
まに【摩尼】
〔仏〕
①(梵語maṇi 珠・宝・如意と訳す)宝石。宝玉。濁水を清らかにする不思議な働きがあるとされる。
②如意宝珠。
③(Mani)
⇒マニきょう(摩尼教)
ま‐に【随・任・儘】
〔副〕
(→)「まにまに」に同じ。
マニア【mania】
①熱狂。熱中。夢中。
②一つの事に異常に熱中する人。「切手―」
ま‐に‐あい【間に合い】‥アヒ
①(→)「まにあわせ」に同じ。
②「間に合い紙」の略。
③でまかせ。ごまかし。歌舞伎、お染久松色読販「…ト―を言ふ」
⇒まにあい‐がみ【間に合い紙】
⇒まにあい‐ことば【間に合い言葉】
まにあい‐がみ【間に合い紙】‥アヒ‥
(横幅を長く漉いて半間の間に合うように造った紙の意)古来、兵庫県西宮市名塩と福井県越前市今立の特産。屏風・襖用の鳥の子紙。間似合紙。
間に合い紙
撮影:関戸 勇
まな‐まな
〔副〕
(「まな」の畳語)禁止する語。だめだめ。落窪物語2「君―とそら制止をし給ふ」
まな‐むすめ【愛娘】
(マナは親愛の意を表す接頭語)最愛の娘。宇津保物語藤原君「豊後のすけの―」
まに【摩尼】
〔仏〕
①(梵語maṇi 珠・宝・如意と訳す)宝石。宝玉。濁水を清らかにする不思議な働きがあるとされる。
②如意宝珠。
③(Mani)
⇒マニきょう(摩尼教)
ま‐に【随・任・儘】
〔副〕
(→)「まにまに」に同じ。
マニア【mania】
①熱狂。熱中。夢中。
②一つの事に異常に熱中する人。「切手―」
ま‐に‐あい【間に合い】‥アヒ
①(→)「まにあわせ」に同じ。
②「間に合い紙」の略。
③でまかせ。ごまかし。歌舞伎、お染久松色読販「…ト―を言ふ」
⇒まにあい‐がみ【間に合い紙】
⇒まにあい‐ことば【間に合い言葉】
まにあい‐がみ【間に合い紙】‥アヒ‥
(横幅を長く漉いて半間の間に合うように造った紙の意)古来、兵庫県西宮市名塩と福井県越前市今立の特産。屏風・襖用の鳥の子紙。間似合紙。
間に合い紙
撮影:関戸 勇
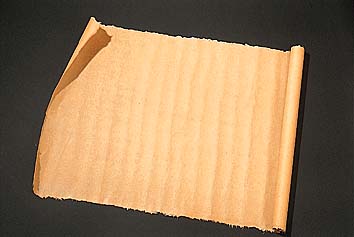 ⇒ま‐に‐あい【間に合い】
まにあい‐ことば【間に合い言葉】‥アヒ‥
口から出まかせの言葉。浄瑠璃、博多小女郎波枕「問ひ詰められて―」
⇒ま‐に‐あい【間に合い】
ま‐に‐あ・う【間に合う】‥アフ
〔自五〕
①その場の役に立つ。用が足りる。「手持ちの品で―・う」「今日は―・っている」
②定めの時刻・期限に遅れない。「終電に―・う」
マニアック【maniac】
一つのことに常軌を逸するほど熱中しているさま。「―な会員が多い」
ま‐に‐あわせ【間に合せ】‥アハセ
急場の用に当てること。一時しのぎ。まにあい。
ま‐に‐あわ・せる【間に合わせる】‥アハセル
〔他下一〕
①とりあえず急場の用に当てる。「借着で―・せる」
②決まった時刻・期限に遅れないようにする。「刊行期日に―・せる」
⇒ま‐に‐あい【間に合い】
まにあい‐ことば【間に合い言葉】‥アヒ‥
口から出まかせの言葉。浄瑠璃、博多小女郎波枕「問ひ詰められて―」
⇒ま‐に‐あい【間に合い】
ま‐に‐あ・う【間に合う】‥アフ
〔自五〕
①その場の役に立つ。用が足りる。「手持ちの品で―・う」「今日は―・っている」
②定めの時刻・期限に遅れない。「終電に―・う」
マニアック【maniac】
一つのことに常軌を逸するほど熱中しているさま。「―な会員が多い」
ま‐に‐あわせ【間に合せ】‥アハセ
急場の用に当てること。一時しのぎ。まにあい。
ま‐に‐あわ・せる【間に合わせる】‥アハセル
〔他下一〕
①とりあえず急場の用に当てる。「借着で―・せる」
②決まった時刻・期限に遅れないようにする。「刊行期日に―・せる」
大辞林の検索結果 (0)
広辞苑+大辞林に「学びて思わざれば則ち罔し」で始まるの検索結果。