複数辞典一括検索+![]()
![]()
【庚庚】🔗⭐🔉
【庚庚】
コウコウ  太いすじの通ったさま。
太いすじの通ったさま。 かたく充実したさま。
かたく充実したさま。
 太いすじの通ったさま。
太いすじの通ったさま。 かたく充実したさま。
かたく充実したさま。
【底】🔗⭐🔉
【底】
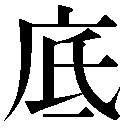 8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ
8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
 {名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
 {名}文書の下書き。「底稿」
{名}文書の下書き。「底稿」
 {動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
 「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
 {疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
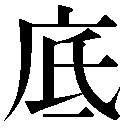 8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ
8画 广部 [四年]
区点=3676 16進=446C シフトJIS=92EA
《常用音訓》テイ/そこ
《音読み》 テイ /タイ
/タイ 〈d
〈d 〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 そこ/とどまる/いたる/なんぞ/なに
《名付け》 さだ・ふか
《意味》
 {名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
{名}そこ。物のいちばん低い所。また、器の下の部分。「水底」
 {名}文書の下書き。「底稿」
{名}文書の下書き。「底稿」
 {動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
{動}とどまる。いたる。ぎりぎりの所までとどく。また、とどいてとどまる。〈同義語〉→淹。「底止(至りとどまる)」
 「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
「…底」とは、…の、という意味をあらわす宋ソウ・元ゲン代の俗語。「自然底事(しぜんのこと)」
 {疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{疑}〔俗〕なんぞ。なに。▽唐・宋ソウの俗語。〈同義語〉→何。「病骨独能在、人間底事無=病骨独リヨク在リ、人間底事カナカラン」〔→李賀〕
《解字》
会意兼形声。下側の字(音テイ)は、積み重ねた物の下部に一印をつけて、低いそこをあらわした指事文字。底はそれを音符とし、广(いえ)を加えた字で、建物の下底のこと。
《単語家族》
低(ひくい)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 1447。