複数辞典一括検索+![]()
![]()
【徴命】🔗⭐🔉
【徴命】
チョウメイ めし出しの命令。
【徴発】🔗⭐🔉
【徴発】
チョウハツ 品物や人夫などを人民から集める。
【徴挙】🔗⭐🔉
【徴挙】
チョウキョ めし出して官職につかせる。
【徴候】🔗⭐🔉
【徴候】
チョウコウ  軍隊で、はっきり見えない敵の動きを前もって知る手がかりのこと。
軍隊で、はっきり見えない敵の動きを前もって知る手がかりのこと。 きざし。前兆。〈同義語〉兆候。『徴兆チョウチョウ』
きざし。前兆。〈同義語〉兆候。『徴兆チョウチョウ』 ききめ。効果。
ききめ。効果。
 軍隊で、はっきり見えない敵の動きを前もって知る手がかりのこと。
軍隊で、はっきり見えない敵の動きを前もって知る手がかりのこと。 きざし。前兆。〈同義語〉兆候。『徴兆チョウチョウ』
きざし。前兆。〈同義語〉兆候。『徴兆チョウチョウ』 ききめ。効果。
ききめ。効果。
【徴祥】🔗⭐🔉
【徴祥】
チョウショウ めでたいことの前兆。よい徴候。『徴瑞チョウズイ』
【徴集】🔗⭐🔉
【徴集】
チョウシュウ  人をめし集める。
人をめし集める。 金品をとりたてる。
金品をとりたてる。
 人をめし集める。
人をめし集める。 金品をとりたてる。
金品をとりたてる。
【徴辟】🔗⭐🔉
【徴辟】
チョウヘキ 身分の低い者をめし出して官職につける。
【徴験】🔗⭐🔉
【徴験】
チョウケン  ききめ。効験。
ききめ。効験。 根拠となるしるし。証拠。『徴証チョウショウ』
根拠となるしるし。証拠。『徴証チョウショウ』
 ききめ。効験。
ききめ。効験。 根拠となるしるし。証拠。『徴証チョウショウ』
根拠となるしるし。証拠。『徴証チョウショウ』
【徳】人名に使える旧字🔗⭐🔉
【徳】
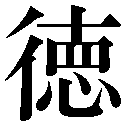 人名に使える旧字
人名に使える旧字
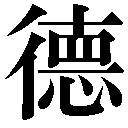 14画 彳部 [五年]
区点=3833 16進=4641 シフトJIS=93BF
【悳】異体字異体字
14画 彳部 [五年]
区点=3833 16進=4641 シフトJIS=93BF
【悳】異体字異体字
 12画 心部
区点=5560 16進=575C シフトJIS=9C7B
《常用音訓》トク
《音読み》 トク
12画 心部
区点=5560 16進=575C シフトJIS=9C7B
《常用音訓》トク
《音読み》 トク
 〈d
〈d 〉
《名付け》 あきら・あつ・あつし・あり・いさお・え・かつ・さと・ただし・とこ・とみ・なり・なる・のぼる・のり・めぐむ・やす・よし
《意味》
〉
《名付け》 あきら・あつ・あつし・あり・いさお・え・かつ・さと・ただし・とこ・とみ・なり・なる・のぼる・のり・めぐむ・やす・よし
《意味》
 {名}本性。うまれつきの人がら。「全徳=徳ヲ全ウス」「君子之徳風、小人之徳草=君子ノ徳ハ風ナリ、小人ノ徳ハ草ナリ」〔→論語〕
{名}本性。うまれつきの人がら。「全徳=徳ヲ全ウス」「君子之徳風、小人之徳草=君子ノ徳ハ風ナリ、小人ノ徳ハ草ナリ」〔→論語〕
 {名}ものに備わった本性。▽五行説では、秦シンは水徳、漢は火徳などといい、また、春の徳は木、夏の徳は火、秋の徳は金、冬の徳は水、中央の徳は土という。
{名}ものに備わった本性。▽五行説では、秦シンは水徳、漢は火徳などといい、また、春の徳は木、夏の徳は火、秋の徳は金、冬の徳は水、中央の徳は土という。
 {名}道徳。「失徳=徳ヲ失フ」
{名}道徳。「失徳=徳ヲ失フ」
 {名}本性の良心をみがきあげたすぐれた人格。「有徳之人」「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕
{名}本性の良心をみがきあげたすぐれた人格。「有徳之人」「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕
 {名}恩恵。〈類義語〉→恵。「記徳=徳ヲ記ス」「何以報徳=何ヲモッテカ徳ニ報イン」〔→論語〕「負戴之徳、何可忘哉=負戴ノ徳、何ゾ忘ルベケンヤ」〔→捜神記〕
{名}恩恵。〈類義語〉→恵。「記徳=徳ヲ記ス」「何以報徳=何ヲモッテカ徳ニ報イン」〔→論語〕「負戴之徳、何可忘哉=負戴ノ徳、何ゾ忘ルベケンヤ」〔→捜神記〕
 トクス{動}恩恵を与える。〈類義語〉→得。「吾為若徳=吾ナンヂノ為ニ徳セン」〔→史記〕
トクス{動}恩恵を与える。〈類義語〉→得。「吾為若徳=吾ナンヂノ為ニ徳セン」〔→史記〕
 トクトス{動}恩を感じる。ありがたく思う。「然則徳我乎=然ラバスナハチ我ヲ徳トスルカ」〔→左伝〕
トクトス{動}恩を感じる。ありがたく思う。「然則徳我乎=然ラバスナハチ我ヲ徳トスルカ」〔→左伝〕
 {形}恵みがこもった。ありがたい。「徳政」
{形}恵みがこもった。ありがたい。「徳政」
 {名}利益。もうけ。▽得に当てた用法。「徳用」
{名}利益。もうけ。▽得に当てた用法。「徳用」
 〔俗〕「徳国トオクオ」とは、ドイツのこと。
《解字》
〔俗〕「徳国トオクオ」とは、ドイツのこと。
《解字》
 会意兼形声。その原字は悳トクと書き「心+音符直」の会意兼形声文字で、もと、本性のままのすなおな心の意。徳はのち、それに彳印を加えて、すなおな本性(良心)に基づく行いを示したもの。
《単語家族》
直(まっすぐ)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
会意兼形声。その原字は悳トクと書き「心+音符直」の会意兼形声文字で、もと、本性のままのすなおな心の意。徳はのち、それに彳印を加えて、すなおな本性(良心)に基づく行いを示したもの。
《単語家族》
直(まっすぐ)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
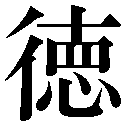 人名に使える旧字
人名に使える旧字
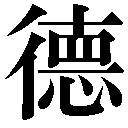 14画 彳部 [五年]
区点=3833 16進=4641 シフトJIS=93BF
【悳】異体字異体字
14画 彳部 [五年]
区点=3833 16進=4641 シフトJIS=93BF
【悳】異体字異体字
 12画 心部
区点=5560 16進=575C シフトJIS=9C7B
《常用音訓》トク
《音読み》 トク
12画 心部
区点=5560 16進=575C シフトJIS=9C7B
《常用音訓》トク
《音読み》 トク
 〈d
〈d 〉
《名付け》 あきら・あつ・あつし・あり・いさお・え・かつ・さと・ただし・とこ・とみ・なり・なる・のぼる・のり・めぐむ・やす・よし
《意味》
〉
《名付け》 あきら・あつ・あつし・あり・いさお・え・かつ・さと・ただし・とこ・とみ・なり・なる・のぼる・のり・めぐむ・やす・よし
《意味》
 {名}本性。うまれつきの人がら。「全徳=徳ヲ全ウス」「君子之徳風、小人之徳草=君子ノ徳ハ風ナリ、小人ノ徳ハ草ナリ」〔→論語〕
{名}本性。うまれつきの人がら。「全徳=徳ヲ全ウス」「君子之徳風、小人之徳草=君子ノ徳ハ風ナリ、小人ノ徳ハ草ナリ」〔→論語〕
 {名}ものに備わった本性。▽五行説では、秦シンは水徳、漢は火徳などといい、また、春の徳は木、夏の徳は火、秋の徳は金、冬の徳は水、中央の徳は土という。
{名}ものに備わった本性。▽五行説では、秦シンは水徳、漢は火徳などといい、また、春の徳は木、夏の徳は火、秋の徳は金、冬の徳は水、中央の徳は土という。
 {名}道徳。「失徳=徳ヲ失フ」
{名}道徳。「失徳=徳ヲ失フ」
 {名}本性の良心をみがきあげたすぐれた人格。「有徳之人」「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕
{名}本性の良心をみがきあげたすぐれた人格。「有徳之人」「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕
 {名}恩恵。〈類義語〉→恵。「記徳=徳ヲ記ス」「何以報徳=何ヲモッテカ徳ニ報イン」〔→論語〕「負戴之徳、何可忘哉=負戴ノ徳、何ゾ忘ルベケンヤ」〔→捜神記〕
{名}恩恵。〈類義語〉→恵。「記徳=徳ヲ記ス」「何以報徳=何ヲモッテカ徳ニ報イン」〔→論語〕「負戴之徳、何可忘哉=負戴ノ徳、何ゾ忘ルベケンヤ」〔→捜神記〕
 トクス{動}恩恵を与える。〈類義語〉→得。「吾為若徳=吾ナンヂノ為ニ徳セン」〔→史記〕
トクス{動}恩恵を与える。〈類義語〉→得。「吾為若徳=吾ナンヂノ為ニ徳セン」〔→史記〕
 トクトス{動}恩を感じる。ありがたく思う。「然則徳我乎=然ラバスナハチ我ヲ徳トスルカ」〔→左伝〕
トクトス{動}恩を感じる。ありがたく思う。「然則徳我乎=然ラバスナハチ我ヲ徳トスルカ」〔→左伝〕
 {形}恵みがこもった。ありがたい。「徳政」
{形}恵みがこもった。ありがたい。「徳政」
 {名}利益。もうけ。▽得に当てた用法。「徳用」
{名}利益。もうけ。▽得に当てた用法。「徳用」
 〔俗〕「徳国トオクオ」とは、ドイツのこと。
《解字》
〔俗〕「徳国トオクオ」とは、ドイツのこと。
《解字》
 会意兼形声。その原字は悳トクと書き「心+音符直」の会意兼形声文字で、もと、本性のままのすなおな心の意。徳はのち、それに彳印を加えて、すなおな本性(良心)に基づく行いを示したもの。
《単語家族》
直(まっすぐ)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
会意兼形声。その原字は悳トクと書き「心+音符直」の会意兼形声文字で、もと、本性のままのすなおな心の意。徳はのち、それに彳印を加えて、すなおな本性(良心)に基づく行いを示したもの。
《単語家族》
直(まっすぐ)と同系。
《参考》
人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
→主要人名
漢字源 ページ 1566。