複数辞典一括検索+![]()
![]()
【詐欺】🔗⭐🔉
【詐欺】
サギ  こけおどしでだます。いつわってあざむく。
こけおどしでだます。いつわってあざむく。 つくりごとで人をだまして、金や品物を自分のものにしたり、また、損害をかけたりする。〈類義語〉欺詐。
つくりごとで人をだまして、金や品物を自分のものにしたり、また、損害をかけたりする。〈類義語〉欺詐。
 こけおどしでだます。いつわってあざむく。
こけおどしでだます。いつわってあざむく。 つくりごとで人をだまして、金や品物を自分のものにしたり、また、損害をかけたりする。〈類義語〉欺詐。
つくりごとで人をだまして、金や品物を自分のものにしたり、また、損害をかけたりする。〈類義語〉欺詐。
【詐誕】🔗⭐🔉
【詐誕】
サタン うそをいったり、おおぼらをふいたりして人をあざむく。〈類義語〉虚誕。
【詐譎】🔗⭐🔉
【詐譎】
サケツ ずるいうそ。いつわり。〈類義語〉譎詐ケッサ。
【詞】🔗⭐🔉
【詞】
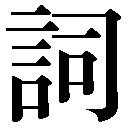 12画 言部 [六年]
区点=2776 16進=3B6C シフトJIS=8E8C
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
12画 言部 [六年]
区点=2776 16進=3B6C シフトJIS=8E8C
《常用音訓》シ
《音読み》 シ /ジ
/ジ 〈c
〈c 〉
《訓読み》 ことば
《名付け》 こと・なり・のり・ふみ
《意味》
〉
《訓読み》 ことば
《名付け》 こと・なり・のり・ふみ
《意味》
 {名}ことば。単語。ワード。▽中国の、特に古代語では一字が一単語を代表する。「単音詞」
{名}ことば。単語。ワード。▽中国の、特に古代語では一字が一単語を代表する。「単音詞」
 {名}ことば。単語を次々とつないでできた文句。また、詩文。〈類義語〉→辞。「答詞(=答辞)」「祝詞シユクシ(=祝辞)」
{名}ことば。単語を次々とつないでできた文句。また、詩文。〈類義語〉→辞。「答詞(=答辞)」「祝詞シユクシ(=祝辞)」
 {名}…乎、…也、…者など、文法的役目や語気をあらわす語。助詞のこと。〈類義語〉→辞。「虚詞(=虚辞。助詞や指示詞、副詞など)」
{名}…乎、…也、…者など、文法的役目や語気をあらわす語。助詞のこと。〈類義語〉→辞。「虚詞(=虚辞。助詞や指示詞、副詞など)」
 {名}単語を意味と文法的な役割から分類したもの。名詞・動詞などの品詞。「詞類(品詞の種類)」
{名}単語を意味と文法的な役割から分類したもの。名詞・動詞などの品詞。「詞類(品詞の種類)」
 {名}韻文の一体。長短の文句をおりまぜたもの。唐代の中ごろから俗謡にならってつくられ、宋ソウ代に最も栄えた。▽「長短句」「詩余」ともいう。「宋詞(宋代の詞)」「詞曲(詞と芝居の戯曲)」
《解字》
形声。「言+音符司シ」で、次々とつないで一連の文句をつくる小さい単位。つまり単語や単語のつながりのこと。
《単語家族》
嗣シ(あとをつぐ小さい子)
{名}韻文の一体。長短の文句をおりまぜたもの。唐代の中ごろから俗謡にならってつくられ、宋ソウ代に最も栄えた。▽「長短句」「詩余」ともいう。「宋詞(宋代の詞)」「詞曲(詞と芝居の戯曲)」
《解字》
形声。「言+音符司シ」で、次々とつないで一連の文句をつくる小さい単位。つまり単語や単語のつながりのこと。
《単語家族》
嗣シ(あとをつぐ小さい子) 孳ジ(小さい子どもがあとからあとからつながってふえる)と同系。
《類義》
辞は、もと裁判でよしあしをいいわけることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
孳ジ(小さい子どもがあとからあとからつながってふえる)と同系。
《類義》
辞は、もと裁判でよしあしをいいわけることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
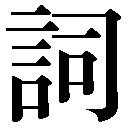 12画 言部 [六年]
区点=2776 16進=3B6C シフトJIS=8E8C
《常用音訓》シ
《音読み》 シ
12画 言部 [六年]
区点=2776 16進=3B6C シフトJIS=8E8C
《常用音訓》シ
《音読み》 シ /ジ
/ジ 〈c
〈c 〉
《訓読み》 ことば
《名付け》 こと・なり・のり・ふみ
《意味》
〉
《訓読み》 ことば
《名付け》 こと・なり・のり・ふみ
《意味》
 {名}ことば。単語。ワード。▽中国の、特に古代語では一字が一単語を代表する。「単音詞」
{名}ことば。単語。ワード。▽中国の、特に古代語では一字が一単語を代表する。「単音詞」
 {名}ことば。単語を次々とつないでできた文句。また、詩文。〈類義語〉→辞。「答詞(=答辞)」「祝詞シユクシ(=祝辞)」
{名}ことば。単語を次々とつないでできた文句。また、詩文。〈類義語〉→辞。「答詞(=答辞)」「祝詞シユクシ(=祝辞)」
 {名}…乎、…也、…者など、文法的役目や語気をあらわす語。助詞のこと。〈類義語〉→辞。「虚詞(=虚辞。助詞や指示詞、副詞など)」
{名}…乎、…也、…者など、文法的役目や語気をあらわす語。助詞のこと。〈類義語〉→辞。「虚詞(=虚辞。助詞や指示詞、副詞など)」
 {名}単語を意味と文法的な役割から分類したもの。名詞・動詞などの品詞。「詞類(品詞の種類)」
{名}単語を意味と文法的な役割から分類したもの。名詞・動詞などの品詞。「詞類(品詞の種類)」
 {名}韻文の一体。長短の文句をおりまぜたもの。唐代の中ごろから俗謡にならってつくられ、宋ソウ代に最も栄えた。▽「長短句」「詩余」ともいう。「宋詞(宋代の詞)」「詞曲(詞と芝居の戯曲)」
《解字》
形声。「言+音符司シ」で、次々とつないで一連の文句をつくる小さい単位。つまり単語や単語のつながりのこと。
《単語家族》
嗣シ(あとをつぐ小さい子)
{名}韻文の一体。長短の文句をおりまぜたもの。唐代の中ごろから俗謡にならってつくられ、宋ソウ代に最も栄えた。▽「長短句」「詩余」ともいう。「宋詞(宋代の詞)」「詞曲(詞と芝居の戯曲)」
《解字》
形声。「言+音符司シ」で、次々とつないで一連の文句をつくる小さい単位。つまり単語や単語のつながりのこと。
《単語家族》
嗣シ(あとをつぐ小さい子) 孳ジ(小さい子どもがあとからあとからつながってふえる)と同系。
《類義》
辞は、もと裁判でよしあしをいいわけることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
孳ジ(小さい子どもがあとからあとからつながってふえる)と同系。
《類義》
辞は、もと裁判でよしあしをいいわけることば。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
【詞兄】🔗⭐🔉
【詞兄】
シケイ 詩人・文人の仲間である友をうやまっていうことば。
【詞曲】🔗⭐🔉
【詞曲】
シキョク 詞と曲(元ゲン代に発達した戯曲)。ともに韻文の形式。
漢字源 ページ 4083。