複数辞典一括検索+![]()
![]()
【農稼】🔗⭐🔉
【農稼】
ノウカ 田畑を耕し穀物をうえる。〈類義語〉耕稼コウカ。
【農政全書】🔗⭐🔉
【農政全書】
ノウセイゼンショ〈書物〉六〇巻。明ミンの徐光啓ジョコウケイ(1562〜1633)の編。1639年に刊行。中国古今の農学を集大成した書。徐光啓は明朝末の政治家だが、農学者・天文学者でもあり、またキリスト教徒でもあった。古来からの農家(農政学中心の政治論を主張した人々)の説を集大成するとともに、自らマテオ=リッチから学んだ水利学・地理学などの西洋の技術を取り入れた自説も加えられている。当時の経済事情を知る上でも重要な資料になる。
【辷】🔗⭐🔉
【辷】
 5画
5画  部 〔国〕
区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788
《訓読み》 すべる
《意味》
すべる。なめらかに進む。
《解字》
指事。いくことをあらわす
部 〔国〕
区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788
《訓読み》 すべる
《意味》
すべる。なめらかに進む。
《解字》
指事。いくことをあらわす に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。
に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。
 5画
5画  部 〔国〕
区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788
《訓読み》 すべる
《意味》
すべる。なめらかに進む。
《解字》
指事。いくことをあらわす
部 〔国〕
区点=7772 16進=6D68 シフトJIS=E788
《訓読み》 すべる
《意味》
すべる。なめらかに進む。
《解字》
指事。いくことをあらわす に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。
に、平らなことをあらわす一印を加えたもの。
【込】🔗⭐🔉
【込】
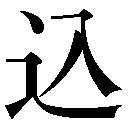 5画
5画  部 [常用漢字] 〔国〕
区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E
《常用音訓》こ…む/こ…める
《訓読み》 こむ/こめる(こむ)
《意味》
部 [常用漢字] 〔国〕
区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E
《常用音訓》こ…む/こ…める
《訓読み》 こむ/こめる(こむ)
《意味》
 こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」
こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」 こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」
こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」 こめる(コム)。集中する。「力を込める」
《解字》
会意。「入+
こめる(コム)。集中する。「力を込める」
《解字》
会意。「入+ 」。
」。
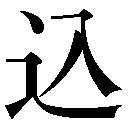 5画
5画  部 [常用漢字] 〔国〕
区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E
《常用音訓》こ…む/こ…める
《訓読み》 こむ/こめる(こむ)
《意味》
部 [常用漢字] 〔国〕
区点=2594 16進=397E シフトJIS=8D9E
《常用音訓》こ…む/こ…める
《訓読み》 こむ/こめる(こむ)
《意味》
 こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」
こむ。こめる(コム)。中へはいる。また、中にいれる。「弾丸を込める」 こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」
こむ。中に人がつまってごたごたしている。また、細工などが複雑である。「手が込んでいる」 こめる(コム)。集中する。「力を込める」
《解字》
会意。「入+
こめる(コム)。集中する。「力を込める」
《解字》
会意。「入+ 」。
」。
【辺】🔗⭐🔉
【辺】
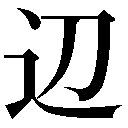 5画
5画  部 [四年]
区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3
【邊】旧字(A)旧字(A)
部 [四年]
区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3
【邊】旧字(A)旧字(A)
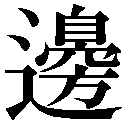 19画
19画  部
区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2
【邉】旧字(B)旧字(B)
部
区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2
【邉】旧字(B)旧字(B)
 17画
17画  部
区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3
《常用音訓》ヘン/あた…り/べ
《音読み》 ヘン
部
区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3
《常用音訓》ヘン/あた…り/べ
《音読み》 ヘン
 〈bi
〈bi n〉
《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり
《名付け》 へ・ほとり
《意味》
n〉
《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり
《名付け》 へ・ほとり
《意味》
 {名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」
{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」
 {名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」
{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」
 {名}国のはて。国境に近い地。「辺境」
{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」
 {名}数学で、多角形の外側の線。
{名}数学で、多角形の外側の線。
 ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕
ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕
 {名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」
{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」
 {名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」
《解字》
{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」
《解字》
 会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、
会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、 (歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。
《類義》
際サイは、すれすれのきわ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
(歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。
《類義》
際サイは、すれすれのきわ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
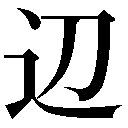 5画
5画  部 [四年]
区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3
【邊】旧字(A)旧字(A)
部 [四年]
区点=4253 16進=4A55 シフトJIS=95D3
【邊】旧字(A)旧字(A)
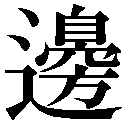 19画
19画  部
区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2
【邉】旧字(B)旧字(B)
部
区点=7820 16進=6E34 シフトJIS=E7B2
【邉】旧字(B)旧字(B)
 17画
17画  部
区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3
《常用音訓》ヘン/あた…り/べ
《音読み》 ヘン
部
区点=7821 16進=6E35 シフトJIS=E7B3
《常用音訓》ヘン/あた…り/べ
《音読み》 ヘン
 〈bi
〈bi n〉
《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり
《名付け》 へ・ほとり
《意味》
n〉
《訓読み》 あたり/べ/はし/はて/へり/ふち/へ/ほとり
《名付け》 へ・ほとり
《意味》
 {名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」
{名・形}はし。はて。いきついた所。また、物の中央に対して、物のはじ。はし近い。「辺際」「無辺=辺無シ」
 {名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」
{名}へり。ふち。へ。「花辺(衣服のふち飾り)」「縁辺(へり)」「江辺(川のきし)」「海辺」「辺幅」
 {名}国のはて。国境に近い地。「辺境」
{名}国のはて。国境に近い地。「辺境」
 {名}数学で、多角形の外側の線。
{名}数学で、多角形の外側の線。
 ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕
ヘンス{動}はしを接する。境と境とが接する。「辺乎斉也=斉ニ辺スルナリ」〔→穀梁〕
 {名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」
{名}ほとり。近くの所。そば。あたり。「身辺」
 {名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」
《解字》
{名}〔俗〕…のほう。「前辺チェンペイエン」「后辺ホウペイエン」
《解字》
 会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、
会意兼形声。邊の右側の字(音ヘン・メン)は「自(鼻)+両側にわかれるしるし+方(両側にはり出る)」の会意文字で、鼻の両わきに出た鼻ぶたのはしをあらわす。邊はそれを音符とし、 (歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。
《類義》
際サイは、すれすれのきわ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
(歩く)を加えた字で、いきづまるはてまで歩いていったそのはしをあらわす。辺は宋ソウ・元ゲンのころ以来の略字。
《類義》
際サイは、すれすれのきわ。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源 ページ 4387。