複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (3)
し‐たく【支度・仕度】🔗⭐🔉
し‐たく【支度・仕度】
①こまかく見積もること。計算すること。続日本紀40「此れを以て―するに、一度の運ぶ所僅かに十一日を支ふ」
②用意。準備。あらかじめ計画すること。また、その計画。竹取物語「石つくりの皇子みこは心の―ある人にて」。「食事の―」
③(外出・接待などの用意の意から)衣服をととのえること。身じたく。
④(近世語)食事をすること。東海道中膝栗毛7「空腹となりたるに、―せんとこの茶屋にはいれば」
⑤支度金の略。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「―が金二百両」
⇒したく‐きん【支度金】
⇒支度違う
したく‐きん【支度金】🔗⭐🔉
したく‐きん【支度金】
就職その他の準備に要する金銭。
⇒し‐たく【支度・仕度】
○支度違うしたくたがう🔗⭐🔉
○支度違うしたくたがう
案に相違する。今昔物語集23「支度違ひて止みにけり」
⇒し‐たく【支度・仕度】
した‐ぐち【下口】
(シタクチとも)
①しもの入口。裏口。太平記12「前さきの陸奥守義家承つて、殿上の―に候こうし」
②馬の口の下側。日葡辞書「シタクチノツヨイウマ」
した‐くちびる【下唇】
下方の唇。「―を噛かむ」↔上唇うわくちびる
した‐ぐつ【襪・下沓】
⇒しとうず。〈倭名類聚鈔12〉
した‐くび【胡】
あごの下に垂れた肉。〈倭名類聚鈔3〉
した‐ぐみ【下組み】
①かねての用意。準備。竹取物語「さしこめて守り戦ふべき―をしたりとも」
②本格的に組み立てる前の仮組み。
した‐ぐも【下雲】
下方にある雲。低い雲。万葉集14「対馬の嶺ねは―あらなふ」
した‐くゆ・る【下燻る】
〔自四〕
火が燃え上がらないでくすぶる。人知れず恋い慕い悩み悶えることにたとえる。増鏡「かの―・る心地にもいとうれしきものから」
した‐ぐら【下鞍・韉】
和鞍の鞍橋くらぼねの下に当てる敷物。2枚重ねを普通とし、上を切付きっつけ、下を肌付という。洋鞍の鞍下に当たる。
下鞍
 した‐ぐる・し【下苦し】
〔形シク〕
(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」
した‐ぐるま【舌車】
しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」
した‐けい【下罫】
文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。
した‐げいこ【下稽古】
晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」
した‐けんぶん【下検分】
前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」
じ‐だこ【字凧】
太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧
字凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
した‐ぐる・し【下苦し】
〔形シク〕
(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」
した‐ぐるま【舌車】
しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」
した‐けい【下罫】
文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。
した‐げいこ【下稽古】
晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」
した‐けんぶん【下検分】
前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」
じ‐だこ【字凧】
太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧
字凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
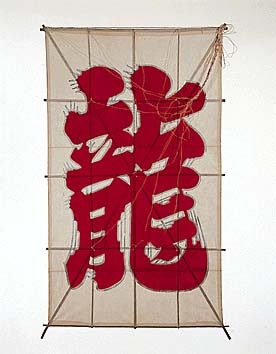 祝凧(島根)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
祝凧(島根)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 字凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
字凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 した‐ごい【下恋】‥ゴヒ
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」
した‐こが・る【下焦る】
〔自下二〕
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」
した‐こき【舌扱き】
(→)「したかき(舌掻)」に同じ。
した‐ごころ【下心】
①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」
②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」
③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉
④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「
した‐ごい【下恋】‥ゴヒ
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」
した‐こが・る【下焦る】
〔自下二〕
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」
した‐こき【舌扱き】
(→)「したかき(舌掻)」に同じ。
した‐ごころ【下心】
①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」
②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」
③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉
④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「 」、「志」「思」などの下の「心」の称。
した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ
①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」
②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」
した‐ごや【下小屋】
大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。
した‐ごろも【下衣】
下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」
した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」
した‐ざいく【下細工】
下ごしらえの細工。また、その職人。
した‐さき【舌先】
①舌のさき。舌端。
②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」
⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】
したさき‐さんずん【舌先三寸】
(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」
⇒した‐さき【舌先】
した‐さく【下作】
(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」
した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ
①下から支えること。また、そのもの。
②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。
した‐ざや【下鞘】
①太刀の鞘袋のこと。
②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや
した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ
食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」
」、「志」「思」などの下の「心」の称。
した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ
①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」
②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」
した‐ごや【下小屋】
大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。
した‐ごろも【下衣】
下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」
した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」
した‐ざいく【下細工】
下ごしらえの細工。また、その職人。
した‐さき【舌先】
①舌のさき。舌端。
②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」
⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】
したさき‐さんずん【舌先三寸】
(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」
⇒した‐さき【舌先】
した‐さく【下作】
(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」
した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ
①下から支えること。また、そのもの。
②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。
した‐ざや【下鞘】
①太刀の鞘袋のこと。
②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや
した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ
食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」
 した‐ぐる・し【下苦し】
〔形シク〕
(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」
した‐ぐるま【舌車】
しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」
した‐けい【下罫】
文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。
した‐げいこ【下稽古】
晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」
した‐けんぶん【下検分】
前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」
じ‐だこ【字凧】
太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧
字凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
した‐ぐる・し【下苦し】
〔形シク〕
(「下」は心の意)心の中で苦しく思う。曾丹集「をし鳥の…―・しとは知るらめや人」
した‐ぐるま【舌車】
しゃべりたてること。弁舌を弄すること。口車。浄瑠璃、聖徳太子絵伝記「おつと自慢の―口にまはせど川勝はしぶい顔」
した‐けい【下罫】
文字を書く時、行ぎょうがよく整うように紙の下に敷いて字配りの標準とする罫。
した‐げいこ【下稽古】
晴れの場でする物事を前もって練習すること。本舞台へ上のぼせる前の予習。前稽古。「―を積む」
した‐けんぶん【下検分】
前もって検査すること。下検査。下見。「会場の―」
じ‐だこ【字凧】
太い文字または籠字かごじで「龍」などの文字を書いた凧。→絵凧
字凧(東京)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
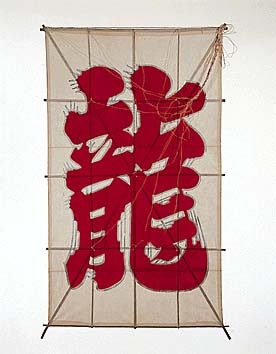 祝凧(島根)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
祝凧(島根)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 字凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
字凧(愛媛)
撮影:薗部 澄(JCII蔵)
 した‐ごい【下恋】‥ゴヒ
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」
した‐こが・る【下焦る】
〔自下二〕
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」
した‐こき【舌扱き】
(→)「したかき(舌掻)」に同じ。
した‐ごころ【下心】
①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」
②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」
③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉
④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「
した‐ごい【下恋】‥ゴヒ
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋うこと。万葉集17「―にいつかもこむと待たすらむ」
した‐こが・る【下焦る】
〔自下二〕
(「下」は心の意)心の中でひそかに恋いこがれる。忠岑集「わび人の心のうちをくらぶるにふじの山とぞ―・れける」
した‐こき【舌扱き】
(→)「したかき(舌掻)」に同じ。
した‐ごころ【下心】
①心のそこ(で考えていること)。本心。万葉集1「あま少女らが焼くしほの思ひそ焼くるわが―」
②かねて心に期すること。かねてのたくらみ。特に、わるだくみ。狂言、水汲新発意「ちと―あつてしたことでござる」。「―が見えている」
③格言などの裏の意味。寓意。〈日葡辞書〉
④漢字の脚あしの一つ。「恭」「慕」などの下の「 」、「志」「思」などの下の「心」の称。
した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ
①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」
②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」
した‐ごや【下小屋】
大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。
した‐ごろも【下衣】
下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」
した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」
した‐ざいく【下細工】
下ごしらえの細工。また、その職人。
した‐さき【舌先】
①舌のさき。舌端。
②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」
⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】
したさき‐さんずん【舌先三寸】
(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」
⇒した‐さき【舌先】
した‐さく【下作】
(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」
した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ
①下から支えること。また、そのもの。
②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。
した‐ざや【下鞘】
①太刀の鞘袋のこと。
②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや
した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ
食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」
」、「志」「思」などの下の「心」の称。
した‐ごしらえ【下拵え】‥ゴシラヘ
①あらかじめ準備すること。下準備。「祭りの―」
②ざっと大まかにこしらえておくこと。「料理の―」
した‐ごや【下小屋】
大工・石工などが下ごしらえをするための、仮に建てた小屋。
した‐ごろも【下衣】
下着。万葉集15「しろたへのあが―失はず」
した‐ごわ・し【舌強し】‥ゴハシ
〔形ク〕
舌がこわばって思うように言えない。源平盛衰記27「―・うして思ふ事をも云ひ置かず」
した‐ざいく【下細工】
下ごしらえの細工。また、その職人。
した‐さき【舌先】
①舌のさき。舌端。
②くちさき。口頭。ことば。「―で言いくるめる」
⇒したさき‐さんずん【舌先三寸】
したさき‐さんずん【舌先三寸】
(3寸ほどの小さい舌の意)くちさきだけで心のこもらない言葉。おしゃべり。「舌三寸」とも。「―で人をまるめこむ」
⇒した‐さき【舌先】
した‐さく【下作】
(→)小作こさくに同じ。浄瑠璃、冥途飛脚「此の藁葺は忠三郎とて―あてた小百姓」
した‐ざさえ【下支え】‥ザサヘ
①下から支えること。また、そのもの。
②相場が一定水準以下には下がらないこと、また、下落しないように買いに出ること。
した‐ざや【下鞘】
①太刀の鞘袋のこと。
②(取引用語)ある物の相場が他の物の相場より安いこと。また中限なかぎりが当限とうぎりより安く、先限さきぎりが中限より安いこと。↔上鞘うわざや
した‐ざわり【舌触り】‥ザハリ
食物などが舌にさわった感じ。「ざらっとした―」「とろけるような―」
大辞林の検索結果 (3)
し-たく【支度・仕度】🔗⭐🔉
し-たく [0] 【支度・仕度】 (名)スル
(1)準備すること。用意すること。「食事の―をする」
(2)外出などのために服装を整えること。身支度。「旅―」
(3)食事をすること。「これから精養軒で―をしようと/うづまき(敏)」
(4)あらかじめ見積もること。計算すること。「石つくりの御子は心の―ある人にて/竹取」
したく-きん【支度金】🔗⭐🔉
したく-きん [0] 【支度金】
準備や用意に必要な金。就職や嫁入りなどの準備に要する金。支度料。
したく【支度】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「支度」で始まるの検索結果。