複数辞典一括検索+![]()
![]()
あじ-な アヂ― [0] 【味な】🔗⭐🔉
あじ-な アヂ― [0] 【味な】
〔形動「あじ(味)」の連体形〕
⇒あじ(味)□二□
あじ-な・い アヂ― 【味無い】 (形)🔗⭐🔉
あじ-な・い アヂ― 【味無い】 (形)
〔近世語〕
(1)「あじけない」に同じ。「我夫(ツマ)よとも我子ともいはれぬやうな,―・い縁が世界に又あらうか/浄瑠璃・彦山権現」
(2)味がない。味がうすい。また,味がわるい。「河漏麪(ソバキリ)の―・いをめで/滑稽本・根無草後編」
あし-なえ ―ナヘ [0][3] 【蹇・跛】🔗⭐🔉
あし-なえ ―ナヘ [0][3] 【蹇・跛】
足が悪く歩行が不自由なこと。また,その人。
あし-なか [0] 【足半】🔗⭐🔉
あし-なか [0] 【足半】
足の裏半ばまでくらいの長さで,かかとの部分のない藁草履(ワラゾウリ)。足半草履。半草履。
足半
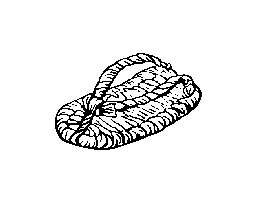 [図]
[図]
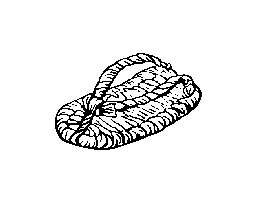 [図]
[図]
あし-なが [0] 【足長】 (名・形動)🔗⭐🔉
あし-なが [0] 【足長】 (名・形動)
(1)足が長いこと。
(2)遠くまで行くこと。(船の)航海距離が長いさま。「―に出たほどに兵糧よろづが大義/蒙求抄 6」
(3)〔山海経(センガイキヨウ)〕
足が非常に長いという想像上の人間。手長(テナガ)とともに清涼殿の荒海の障子に描かれていた。
あしなが-ぐも [5] 【足長蜘蛛】🔗⭐🔉
あしなが-ぐも [5] 【足長蜘蛛】
クモの一種。体も脚も細長く,黄褐色。体長15ミリメートル内外。第一歩脚は特に長い。丸網を水平に張り,昆虫を捕食する。本州・四国・九州に分布。
あしなが-くらげ [5] 【足長水母】🔗⭐🔉
あしなが-くらげ [5] 【足長水母】
アカクラゲの別名。
あしなが-ばち [4] 【足長蜂】🔗⭐🔉
あしなが-ばち [4] 【足長蜂】
〔飛行中,脚を長くのばして下げるのでいう〕
アシナガバチ属のハチの総称。フタモンアシナガバチ・セグロアシナガバチなど。枯れ枝や古い木材をかみくだき,唾液(ダエキ)で練ったものを材料にして,六角柱状の小部屋を並べた巣を軒下や木の枝に作る。[季]春。
大辞林 ページ 138065。