複数辞典一括検索+![]()
![]()
あみだ-ぼとけ 【阿弥陀仏】🔗⭐🔉
あみだ-ぼとけ 【阿弥陀仏】
「阿弥陀{(1)}」に同じ。
あみだ-まんだら [4] 【阿弥陀曼荼羅】🔗⭐🔉
あみだ-まんだら [4] 【阿弥陀曼荼羅】
阿弥陀如来を中心に描いた曼荼羅。阿弥陀法を修する際に用いる。
あみだ-わさん [4] 【阿弥陀和讃】🔗⭐🔉
あみだ-わさん [4] 【阿弥陀和讃】
阿弥陀の功徳をたたえた和讃。
あみだ-わり [0] 【阿弥陀割(り)】🔗⭐🔉
あみだ-わり [0] 【阿弥陀割(り)】
道路の配置を阿弥陀の後光に似せて,中心点から放射状に配する地割りの方法。
⇔碁盤割り
あみ-だいく [3] 【網大工】🔗⭐🔉
あみ-だいく [3] 【網大工】
網を作ったり,修理したりする人。網棟梁(アミトウリヨウ)。
あみだ-が-みね 【阿弥陀ヶ峰】🔗⭐🔉
あみだ-が-みね 【阿弥陀ヶ峰】
京都市東山区,東山三十六峰の一。もと,山腹と山麓に阿弥陀堂があった。山頂に豊臣秀吉の廟(ビヨウ)(豊国廟)がある。
あみ-たけ [2] 【網茸】🔗⭐🔉
あみ-たけ [2] 【網茸】
担子菌類ハラタケ目のきのこ。夏から秋にかけマツ林などに群生する。傘の裏に多数の穴が生じて網状に見えるのでこの名がある。食用。
網茸
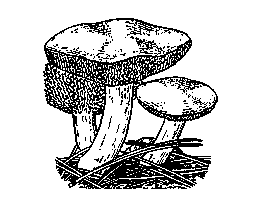 [図]
[図]
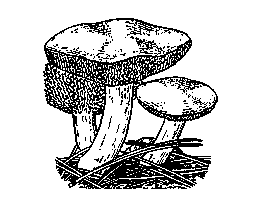 [図]
[図]
あみだ-じ 【阿弥陀寺】🔗⭐🔉
あみだ-じ 【阿弥陀寺】
(1)山口県防府市牟礼(ムレ)にある真言宗御室(オムロ)派の寺。1187年重源(チヨウゲン)の建立。東大寺別所。浄土教発展の一拠点となった。
(2)山口県下関市阿弥陀町にあった寺。中世には浄土宗,近世では真言宗に転じた。安徳天皇鎮魂のため1191年に建立。1875年(明治8)寺を廃して赤間宮となる。
→赤間神宮
あみ-だ・す [3][0] 【編(み)出す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
あみ-だ・す [3][0] 【編(み)出す】 (動サ五[四])
(1)編みはじめる。
(2)工夫して新しい物事や方法を考え出す。「新戦術を―・す」
[可能] あみだせる
あみ-だな [0] 【網棚】🔗⭐🔉
あみ-だな [0] 【網棚】
手荷物をのせるため,電車・バスなどの天井近くに網を張って作った棚。
あみだのむねわり 【阿弥陀胸割】🔗⭐🔉
あみだのむねわり 【阿弥陀胸割】
古浄瑠璃,本地物の一。1614年の上演記録がある。因果応報と仏を信ずる者は大慈悲に浴しうることを説く。
あみつき-りん [4] 【網付き林】🔗⭐🔉
あみつき-りん [4] 【網付き林】
⇒魚付(ウオツ)き林(リン)
大辞林 ページ 138289。