複数辞典一括検索+![]()
![]()
いさり-おぶね ―ヲ― 【漁り小舟】🔗⭐🔉
いさり-おぶね ―ヲ― 【漁り小舟】
漁をする小舟。「浪のよる―の見えつるは/夫木 33」
いさり-び [3][0] 【漁り火】🔗⭐🔉
いさり-び [3][0] 【漁り火】
夜,魚を誘い寄せるため舟の上で焚(タ)く火。ぎょか。
いさり-び-の 【漁り火の】 (枕詞)🔗⭐🔉
いさり-び-の 【漁り火の】 (枕詞)
「ほ」「ほのか」にかかる。「―夜はほのかにかくしつつ/後撰(恋二)」
いさり-ぶね [4] 【漁り船】🔗⭐🔉
いさり-ぶね [4] 【漁り船】
魚をとる船。漁船。
い-ざり  ― [0] 【躄・膝行】🔗⭐🔉
― [0] 【躄・膝行】🔗⭐🔉
い-ざり  ― [0] 【躄・膝行】
〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕
(1)膝や尻をついて移動すること。
(2)足が立たない人。
― [0] 【躄・膝行】
〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕
(1)膝や尻をついて移動すること。
(2)足が立たない人。
 ― [0] 【躄・膝行】
〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕
(1)膝や尻をついて移動すること。
(2)足が立たない人。
― [0] 【躄・膝行】
〔動詞「躄(イザ)る」の連用形から〕
(1)膝や尻をついて移動すること。
(2)足が立たない人。
いざり-うお  ―ウヲ [3] 【躄魚】🔗⭐🔉
―ウヲ [3] 【躄魚】🔗⭐🔉
いざり-うお  ―ウヲ [3] 【躄魚】
アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。
躄魚
―ウヲ [3] 【躄魚】
アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。
躄魚
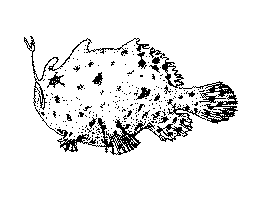 [図]
[図]
 ―ウヲ [3] 【躄魚】
アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。
躄魚
―ウヲ [3] 【躄魚】
アンコウ目の海魚。全長10センチメートルほど。黄褐色に黒い斑紋があり,全身に微細な突起が散在する。アンコウのように小魚をおびき寄せて食い,外敵を威嚇(イカク)するため腹部を大きくふくらませる習性がある。胸びれと腹びれを使って海底を移動する。観賞魚。本州中部以南に分布。
躄魚
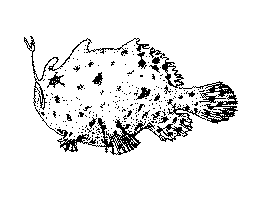 [図]
[図]
いざり-ばた  ― [3][0] 【躄機・居坐機】🔗⭐🔉
― [3][0] 【躄機・居坐機】🔗⭐🔉
いざり-ばた  ― [3][0] 【躄機・居坐機】
手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。
― [3][0] 【躄機・居坐機】
手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。
 ― [3][0] 【躄機・居坐機】
手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。
― [3][0] 【躄機・居坐機】
手織機の一。経(タテ)糸の一端を腰につけて緊張を調節し,足で操作して綜絖(ソウコウ)を上下する。
いざり-まつ  ― [3] 【躄松】🔗⭐🔉
― [3] 【躄松】🔗⭐🔉
いざり-まつ  ― [3] 【躄松】
ハイマツの異名。
― [3] 【躄松】
ハイマツの異名。
 ― [3] 【躄松】
ハイマツの異名。
― [3] 【躄松】
ハイマツの異名。
いざり-かつごろう  ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】🔗⭐🔉
ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】🔗⭐🔉
いざり-かつごろう  ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】
人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。
ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】
人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。
 ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】
人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。
ザリカツゴラウ 【躄勝五郎】
人形浄瑠璃「箱根霊験躄仇討(イザリノアダウチ)」の主人公。
いさ・る 【漁る】 (動ラ四)🔗⭐🔉
いさ・る 【漁る】 (動ラ四)
〔平安時代以前は「いざる」と濁音〕
漁をする。魚や貝をとる。すなどる。「海原の沖辺にともし―・る火は/万葉 3648」
い-ざる 【 ・
・ 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
い-ざる 【 ・
・ 】
竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]
】
竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]
 ・
・ 】
竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]
】
竹を編んで作った器。ざる。[新撰字鏡]
い-ざ・る  ― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉
― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉
い-ざ・る  ― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])
〔「居さる」の意〕
(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」
(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」
(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」
― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])
〔「居さる」の意〕
(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」
(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」
(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」
 ― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])
〔「居さる」の意〕
(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」
(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」
(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」
― [2][0] 【躄る・膝行る】 (動ラ五[四])
〔「居さる」の意〕
(1)座ったまま移動する。足を立てず,膝(ヒザ)をついて前へ進む。「―・って近寄る」
(2)物が置かれた場所からずれ動く。「棚の花瓶が横へ―・る」
(3)舟が浅瀬をのろのろ進む。「川の水なければ,―・りにのみぞ―・る/土左」
大辞林 ページ 138652。