複数辞典一括検索+![]()
![]()
いた-はぎ [0] 【板矧ぎ】🔗⭐🔉
いた-はぎ [0] 【板矧ぎ】
板の幅方向の接合方法の総称。床板や甲板に使用する本実(ホンザネ)矧ぎ,桶や箱組に使用する合釘(アイクギ)矧ぎなどがある。挽合わせ。
いた-ばさみ [3] 【板挟み】🔗⭐🔉
いた-ばさみ [3] 【板挟み】
(1)板と板の間にはさまること。
(2)対立する二者の間で,どちらにもつきかねて苦しむこと。「義理と人情の―」「母と妻との間で―になる」
いた-ばし [0] 【板橋】🔗⭐🔉
いた-ばし [0] 【板橋】
板でつくった橋。板をわたした橋。
いたばし 【板橋】🔗⭐🔉
いたばし 【板橋】
東京都北部,二三区の一。南部は武蔵野台地上に位置し,北部は低地。もと,中山道の第一宿板橋宿があった。
いた-ばね [0] 【板発条】🔗⭐🔉
いた-ばね [0] 【板発条】
板状のばね。数枚重ねたものは重ね板ばねという。
いた-ばめ [0] 【板羽目】🔗⭐🔉
いた-ばめ [0] 【板羽目】
板で張った羽目。板張りの壁・塀。
いた-ばり [0] 【板張(り)】🔗⭐🔉
いた-ばり [0] 【板張(り)】
(1)板を張ること。また,板を張った場所。
(2)和服地を洗い,糊(ノリ)づけして張り板に張り,しわを伸ばし乾かすこと。
いたび [0] 【木蓮子】🔗⭐🔉
いたび [0] 【木蓮子】
(1)イヌビワの別名。
(2)イタビカズラの古名。[新撰字鏡]
いたび-かずら ―カヅラ [4] 【木蓮子葛】🔗⭐🔉
いたび-かずら ―カヅラ [4] 【木蓮子葛】
クワ科の常緑つる性低木。関東以西の暖地に分布する。茎は長く伸び,気根を出して木や石につく。葉は長楕円形で先がとがる。夏,葉腋(ヨウエキ)にイチジク状の花嚢(ノウ)をつけ,秋に紫黒色に熟す。
いた-び [2] 【板碑】🔗⭐🔉
いた-び [2] 【板碑】
死者の供養のための石造りの卒塔婆(ソトバ)。主に緑泥片岩の平たい石でつくる。上部は三角形。仏像・梵字・年月・氏名などを刻む。鎌倉・室町時代にかけて盛んにつくられ,東北・関東地方に多い。秩父青石でつくったものを青石塔婆という。
板碑
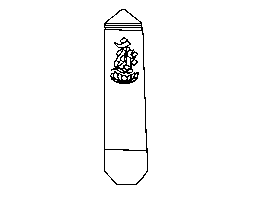 [図]
[図]
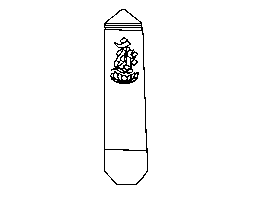 [図]
[図]
いた-ひき [2] 【板挽き】🔗⭐🔉
いた-ひき [2] 【板挽き】
丸太を挽いて板を作ること。また,その職人。
いた-びき [0] 【板引き】🔗⭐🔉
いた-びき [0] 【板引き】
十分に糊(ノリ)づけした絹を漆塗りの板に張り,乾燥後はがす加工法。絹の光沢を増す効果がある。また,そうしてできた絹地。
大辞林 ページ 138757。