複数辞典一括検索+![]()
![]()
いわ-うめ イハ― [2] 【岩梅】🔗⭐🔉
いわ-うめ イハ― [2] 【岩梅】
イワウメ科の常緑小低木。草本状で,多数が集まって高山の岩をおおう。高さ約5センチメートル。葉は革質で狭倒卵形。七月,茎頂に上向きに白色で先の五裂する鐘形花を開く。吹詰草(フキツメソウ)。助六一薬(スケロクイチヤク)。
いわ-えのぐ イハ ノグ [3] 【岩絵の具】🔗⭐🔉
ノグ [3] 【岩絵の具】🔗⭐🔉
いわ-えのぐ イハ ノグ [3] 【岩絵の具】
東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。
ノグ [3] 【岩絵の具】
東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。
 ノグ [3] 【岩絵の具】
東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。
ノグ [3] 【岩絵の具】
東洋画の顔料。天然の鉱物を粉末にし,精製・乾燥させた絵の具。紺青(コンジヨウ)・群青(グンジヨウ)・緑青(ロクシヨウ)など。水に溶けないので,膠(ニカワ)にまぜて用いる。最近は,人工のものもある。岩物(イワモノ)。
いわ・える イハヘル [3][2] 【結える】 (動ア下一)[文]ハ下二 いは・ふ🔗⭐🔉
いわ・える イハヘル [3][2] 【結える】 (動ア下一)[文]ハ下二 いは・ふ
「ゆわえる」の転。「縄で―・える」
いわ-えん ― ン 【頤和園】🔗⭐🔉
ン 【頤和園】🔗⭐🔉
いわ-えん ― ン 【頤和園】
中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。
頤和園
ン 【頤和園】
中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。
頤和園
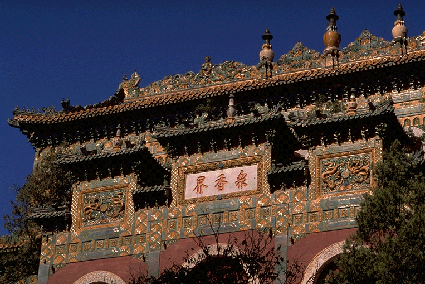 [カラー図版]
[カラー図版]
 ン 【頤和園】
中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。
頤和園
ン 【頤和園】
中国,北京(ペキン)の北西にある清朝の大庭園。乾隆帝以来の離宮が1860年英仏軍に焼き払われたのを,88年西太后が再建し頤和園と名づけた。万寿山と昆明池をめぐる雄大な名園。イーホー-ユワン。
頤和園
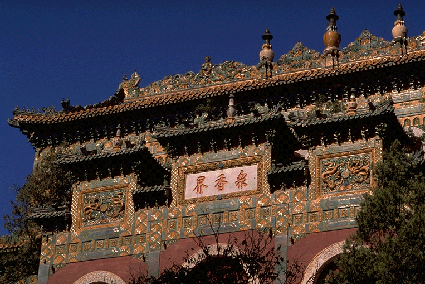 [カラー図版]
[カラー図版]
いわ-お イハホ [0] 【巌】🔗⭐🔉
いわ-お イハホ [0] 【巌】
大きな岩。大盤石。「―のように立ちはだかる」「さざれ石の―となりて苔(コケ)のむすまで」
いわ-おこし イハ― [3][4] 【岩
 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
いわ-おこし イハ― [3][4] 【岩
 】
〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕
粟(アワ)おこしの別名。
】
〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕
粟(アワ)おこしの別名。

 】
〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕
粟(アワ)おこしの別名。
】
〔「おこし」のかたさを「岩」で強調した語〕
粟(アワ)おこしの別名。
いわ-おもだか イハ― [4] 【岩沢瀉】🔗⭐🔉
いわ-おもだか イハ― [4] 【岩沢瀉】
ウラボシ科の常緑シダ。山地の岩上に着生し高さ約20センチメートル。葉は掌状で革質,長い葉柄がある。裏面に粒状の胞子嚢(ノウ)を密生する。
大辞林 ページ 139089。