複数辞典一括検索+![]()
![]()
おくびょう-かぜ ―ビヤウ― [3] 【臆病風】🔗⭐🔉
おくびょう-かぜ ―ビヤウ― [3] 【臆病風】
おじけづくこと。臆病な気持ち。「―に吹かれる」
おくびょう-がね ―ビヤウ― 【臆病金】🔗⭐🔉
おくびょう-がね ―ビヤウ― 【臆病金】
室町時代に盛行した大立挙(オオタテアゲ)の臑当(スネア)ての,後ろのすき間に当てる細長い鉄板。
臆病金
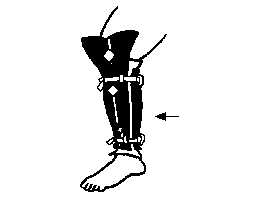 [図]
[図]
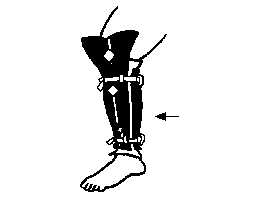 [図]
[図]
おくびょう-がみ ―ビヤウ― [3][0] 【臆病神】🔗⭐🔉
おくびょう-がみ ―ビヤウ― [3][0] 【臆病神】
とりつくと臆病な心を起こさせるという神。「―にとりつかれる」
おくびょう-ぐち ―ビヤウ― [3] 【臆病口】🔗⭐🔉
おくびょう-ぐち ―ビヤウ― [3] 【臆病口】
(1)能舞台正面の鏡板の向かって右わきにある,切り戸口の別称。
→能舞台
(2)歌舞伎で,能舞台を模した装置(松羽目)を施した場合,上手(カミテ)奥にある引き戸の小さい出入り口。古くは上下の大臣柱の後ろの出入り口をいい,黒幕を張ってあった。
おくびょう-まど ―ビヤウ― [5] 【臆病窓】🔗⭐🔉
おくびょう-まど ―ビヤウ― [5] 【臆病窓】
用心のために戸に作りつけてある小窓。開け閉めができ,夜はそこから来客の様子をのぞいたり,商品や金銭の受け渡しをしたりする。
おく-ふか・い [4] 【奥深い】 (形)[文]ク おくふか・し🔗⭐🔉
おく-ふか・い [4] 【奥深い】 (形)[文]ク おくふか・し
〔「おくぶかい」とも〕
(1)入り口から中の方へずっと続いている。奥が深い。奥行がある。奥まっている。「―・い森」
(2)深い意味がある。深遠である。「―・い真理」
[派生] ――さ(名)
おく-ぼうず ―バウズ [3] 【奥坊主】🔗⭐🔉
おく-ぼうず ―バウズ [3] 【奥坊主】
江戸幕府の職名。江戸城の奥向きにいて茶室を管理し,将軍の茶,諸侯の接待・給仕などを担当した坊主。小納戸(コナンド)坊主。
お-くま [0] 【御 ・御供米】🔗⭐🔉
・御供米】🔗⭐🔉
お-くま [0] 【御 ・御供米】
「くましね」に同じ。
・御供米】
「くましね」に同じ。
 ・御供米】
「くましね」に同じ。
・御供米】
「くましね」に同じ。
おぐま ヲグマ 【小熊】🔗⭐🔉
おぐま ヲグマ 【小熊】
姓氏の一。
おぐま-ひでお ヲグマヒデヲ 【小熊秀雄】🔗⭐🔉
おぐま-ひでお ヲグマヒデヲ 【小熊秀雄】
(1901-1940) 詩人。小樽生まれ。プロレタリア詩人として活躍。肺結核で死去。著「飛ぶ橇」「流民詩集」
おく-ま・る [3] 【奥まる】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉
おく-ま・る [3] 【奥まる】 (動ラ五[四])
(1)奥深くなっている。奥深い所に位置している。「―・った座敷」
(2)おくゆかしい心をもっている。「―・りたる人ざまにて/源氏(澪標)」
(3)内気である。引っ込み思案である。「ふるめかしう,―・りたる身なれば/和泉式部日記」
大辞林 ページ 140187。