複数辞典一括検索+![]()
![]()
おもた・い [0] 【重たい】 (形)[文]ク おもた・し🔗⭐🔉
おもた・い [0] 【重たい】 (形)[文]ク おもた・し
(1)目方が多い。「荷物が―・い」
(2)重い感じがする。「まぶたが―・くなる」「―・い足をひきずって帰る」
(3)心がはればれとしない。沈んでいる。「会議室には―・い空気がみなぎっていた」
(4)なみなみでない。重大である。「―・い罪」
〔「重い」とほぼ同義であるが,現在では意味・用法がややせまく,病状などには用いない〕
[派生] ――が・る(動ラ五[四])――げ(形動)――さ(名)
おも-だか [0] 【沢瀉】🔗⭐🔉
おも-だか [0] 【沢瀉】
(1)〔面高の意。葉面の脈が高く隆起しているのでいう〕
オモダカ科の多年草。水田・沼畔などに自生する。葉は鏃(ヤジリ)形で,長い柄がつく。六,七月に高さ約60センチメートルの花茎を立てて,円錐状または総状に白色三弁の単性花をつける。塊茎は食用。野茨菰。ハナグワイ。[季]夏。
→慈姑(クワイ)
(2)家紋の一。オモダカの葉・花の形を図案化したもの。水沢瀉・抱沢瀉など。
(3)模様の名。オモダカの葉を図案化したもの。花を添えたものを花沢瀉という。
沢瀉(2)
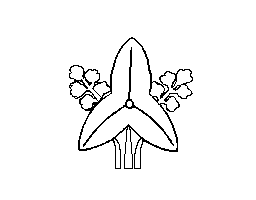 [図]
[図]
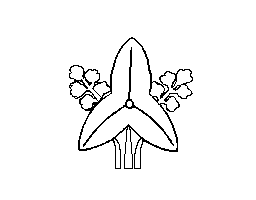 [図]
[図]
おもだか-おどし ―ヲドシ [5] 【沢瀉縅】🔗⭐🔉
おもだか-おどし ―ヲドシ [5] 【沢瀉縅】
鎧(ヨロイ)の縅の名。オモダカの葉の形のように上をせまく下を広く縅したもの。
沢瀉縅
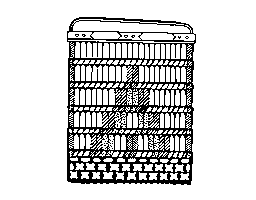 [図]
[図]
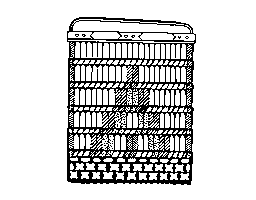 [図]
[図]
おもだか-くわい ―クワ [5] 【沢瀉慈姑】🔗⭐🔉
[5] 【沢瀉慈姑】🔗⭐🔉
おもだか-くわい ―クワ [5] 【沢瀉慈姑】
オモダカの匍匐枝(ホフクシ)の先にできる塊茎。食用。
[5] 【沢瀉慈姑】
オモダカの匍匐枝(ホフクシ)の先にできる塊茎。食用。
 [5] 【沢瀉慈姑】
オモダカの匍匐枝(ホフクシ)の先にできる塊茎。食用。
[5] 【沢瀉慈姑】
オモダカの匍匐枝(ホフクシ)の先にできる塊茎。食用。
おもだか-ずり [0][4] 【沢瀉摺り】🔗⭐🔉
おもだか-ずり [0][4] 【沢瀉摺り】
オモダカの葉・花を図案化した模様を染めたもの。
おもだか-や 【沢瀉屋】🔗⭐🔉
おもだか-や 【沢瀉屋】
歌舞伎俳優市川猿之助一門の屋号。
おもだか 【沢瀉】🔗⭐🔉
おもだか 【沢瀉】
姓氏の一。
おもだか-ひさたか 【沢瀉久孝】🔗⭐🔉
おもだか-ひさたか 【沢瀉久孝】
(1890-1968) 国文学者。三重県生まれ。京大教授。万葉集の訓詁注釈を中心とした精緻な研究を行い,「万葉集注釈」全二〇巻を完成。ほかに著「万葉の作品と時代」「万葉古径」など。
おも-だか [0] 【面高】 (名・形動)[文]ナリ🔗⭐🔉
おも-だか [0] 【面高】 (名・形動)[文]ナリ
顔が骨ばっていて,鼻なども高い・こと(さま)。「蒼白く―に削り成せる彼の顔と/虞美人草(漱石)」
大辞林 ページ 140472。