複数辞典一括検索+![]()
![]()
かざおり-えぼし ―ヲリ― [5] 【風折烏帽子】🔗⭐🔉
かざおり-えぼし ―ヲリ― [5] 【風折烏帽子】
峰の部分を右または左に斜めに折り伏せた形の烏帽子。右折りは上皇が狩衣とともに用い,左折りは地下(ジゲ)が用いた。かざおり。
風折烏帽子
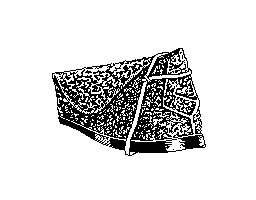 [図]
[図]
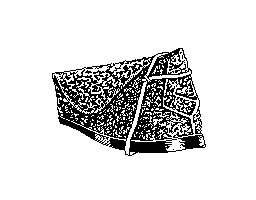 [図]
[図]
かざおり-ちりめん [5] 【風織り縮緬】🔗⭐🔉
かざおり-ちりめん [5] 【風織り縮緬】
緯(ヨコ)糸に強撚糸(ネンシ)と平糸を交互に織り込み横縞状のしぼを表した織物。段縮緬。
かざ-お・る ―ヲル 【風折る】 (動ラ四)🔗⭐🔉
かざ-お・る ―ヲル 【風折る】 (動ラ四)
立烏帽子の峰を風に吹き折られたように折る。「立烏帽子を―・り/謡曲・卒都婆小町」
かざ-おれ ―ヲレ [0] 【風折れ】🔗⭐🔉
かざ-おれ ―ヲレ [0] 【風折れ】
樹木などが風に吹き折られること。かざおり。
かさ-がい ―ガヒ [2] 【笠貝】🔗⭐🔉
かさ-がい ―ガヒ [2] 【笠貝】
(1)海産の巻貝。殻は巻かずに笠を伏せたような形で,殻長8センチメートル,殻高4センチメートル内外。表面は淡黄褐色。小笠原諸島に分布。
(2)殻の形が笠に似ている貝の俗称。ヨメガカサ・カモガイなど。
かさ-かき 【瘡掻き】🔗⭐🔉
かさ-かき 【瘡掻き】
皮膚病にかかっている人。特に,梅毒にかかっている人。かさっかき。
かさ-がけ [0][4] 【笠懸】🔗⭐🔉
かさ-がけ [0][4] 【笠懸】
〔「かさかけ」とも〕
平安時代以来,長く行われた射芸の一。馬に乗って走りながら,2,30メートルの距離から的を射るもの。的は初め笠を用いたが,のちには円板に革を張り,中にわらなどを入れて膨らませたものを用いた。矢は蟇目(ヒキメ)を使う。的間が小笠懸より遠いので,遠笠懸ともいう。
笠懸
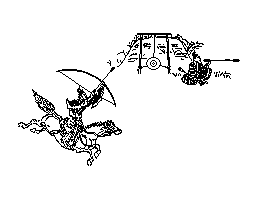 [図]
[図]
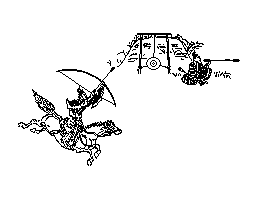 [図]
[図]
かさがけ-ひきめ [5] 【笠懸蟇目】🔗⭐🔉
かさがけ-ひきめ [5] 【笠懸蟇目】
笠懸で用いる蟇目。犬追物(イヌオウモノ)のものよりは小さく,挫目(ヒシギメ)と呼ばれる縦筋が彫ってある。
かさ-かさ🔗⭐🔉
かさ-かさ
■一■ [1] (副)スル
(1)(多く「と」を伴って)乾いたものが触れ合って発する音を表す語。「がさがさ」よりやや軽い感じの音。かさこそ。「枯れ葉が―(と)音を立てる」
(2)湿り気や油気のないさま。「―した肌」
■二■ [0] (形動)
乾いて潤いのないさま。「手が―になる」「―のパン」
大辞林 ページ 141038。