複数辞典一括検索+![]()
![]()
かじ-ばおり クワジ― [3] 【火事羽織】🔗⭐🔉
かじ-ばおり クワジ― [3] 【火事羽織】
江戸時代,火事装束の羽織。大名火消しは革,のちには羅紗(ラシヤ)などで陣羽織のように作り,定紋(ジヨウモン)をつけた。町火消しは組頭が革羽織,一般には刺し子半纏(バンテン)を用いた。
火事羽織
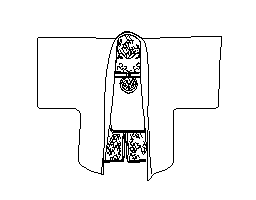 [図]
[図]
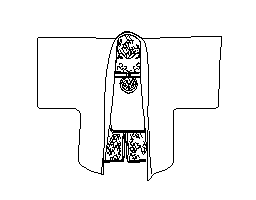 [図]
[図]
かじばし-かのう カヂバシ― 【鍛冶橋狩野】🔗⭐🔉
かじばし-かのう カヂバシ― 【鍛冶橋狩野】
江戸幕府の奥絵師狩野四家の一。また,その流れをくむ画系の名。狩野探幽が鍛冶橋門外に屋敷を与えられたことに由来する。
かし-ばち クワシ― [2] 【菓子鉢】🔗⭐🔉
かし-ばち クワシ― [2] 【菓子鉢】
菓子を入れる,鉢形の器。
かしはら 【橿原】🔗⭐🔉
かしはら 【橿原】
奈良盆地の南部にある市。飛鳥文化の一中心地。大和三山や橿原神宮・藤原京跡・橿原遺跡など,史跡が多い。
かしはら-じんぐう 【橿原神宮】🔗⭐🔉
かしはら-じんぐう 【橿原神宮】
橿原市久米町畝傍(ウネビ)山麓にある神社。祭神は,神武天皇・媛蹈鞴五十鈴媛(ヒメタタライスズヒメ)皇后。1889年(明治22)創建。
かしはら-の-みや 【橿原宮】🔗⭐🔉
かしはら-の-みや 【橿原宮】
神武天皇が即位した宮という。その伝承地に橿原神宮が建てられた。畝傍橿原宮。「―に即帝位(アマツヒツギシロシメ)す。是歳(コトシ)を天皇の元年(ハジメノトシ)とす/日本書紀(神武訓)」
かしはら-りゅう ―リウ 【樫原流】🔗⭐🔉
かしはら-りゅう ―リウ 【樫原流】
槍術の一流派。江戸初期に紀州藩士の樫原五郎左衛門俊重が興した。初め直槍を用い,のち鉤槍(カギヤリ)に転じた。
〔俗に「柏原流」とも書く〕
かし-パン クワシ― [0] 【菓子―】🔗⭐🔉
かし-パン クワシ― [0] 【菓子―】
餡(アン)・ジャム・クリームなどを包みこんだり,甘い味を付けたりして焼いたパン。
かしパン-うに クワシ― [5] 【菓子―海胆】🔗⭐🔉
かしパン-うに クワシ― [5] 【菓子―海胆】
ウニ類のうち,不正形のウニの一群の総称。形が菓子パンに似る。殻は平たく円盤状で,表面に短いとげが密生し,五弁の花びらのような紋をもつ。ハスノハカシパン・スカシカシパンなど。
大辞林 ページ 141084。